ヤツメウナギは、恐竜が出現する前の4億5000万年前に進化した古代の魚類グループである無顎類に属します。

ヤツメウナギの口の構造は、獲物にしがみついて血を吸うのに役立つ。写真:マーリー・ミラー
太平洋ヤツメウナギ( Entosphenus tridentatus )は、カリフォルニアからアラスカ、そしてベーリング海からロシア、日本に至る北太平洋の淡水・海洋生態系に生息しています。Live Scienceによると、 太平洋サケ、ヒラメ、メバル、 タラなどの魚類の血液や体液を餌としています。
ヤツメウナギは、新生代に4億5000万年以上前に進化した顎のない魚の古代のグループです。 オルドビス紀(4億8500万年前~4億4400万年前)。現在でも世界中に約40種のヤツメウナギ類が生息しています。ウナギに似たこの生物は、恐竜や樹木が出現するずっと前から河川を闊歩していました。少なくとも4度の大量絶滅を生き延びました。ヤツメウナギは骨のない魚で、骨格はすべて軟骨でできています。顎の代わりに、歯が詰まった吸盤状の口を持ち、獲物を捕らえて血や体液を吸い取ります。科学者によると、ヤツメウナギは生肉を食べません。
メスは巣に最大20万個の卵を産み、淡水で約3~4週間孵化させます。幼生は孵化すると泥の中に潜り込み、最大10年間そこに留まります。亜成体になると、餌を求めて海へ下流へ移動し、数年後に繁殖のために淡水に戻ります。成体のヤツメウナギは体長最大84cmに成長し、産卵と生育に最適な場所を求めて数百kmも内陸まで移動することができます。
ヤツメウナギは、非常に脂肪分が多く、同じ体重のサケの3~5倍のカロリーを含むため、多くの鳥類、哺乳類、その他の魚類の好物です。そのため、淡水および海洋生態系において重要な役割を果たしています。
アン・カン( Live Scienceによると)
[広告2]
ソースリンク






























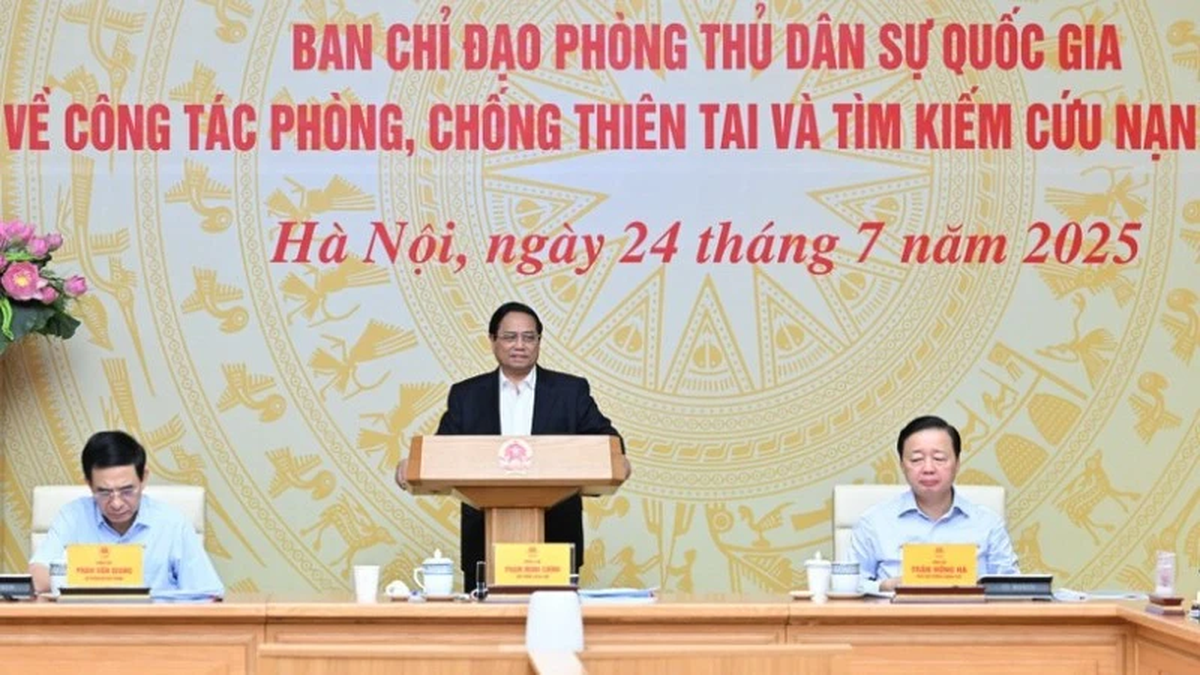































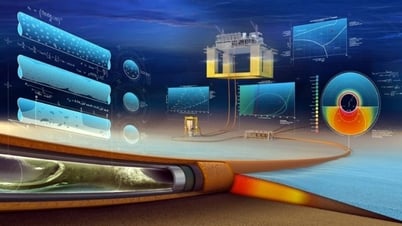




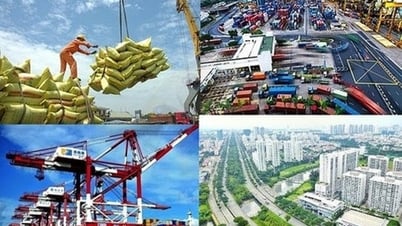



























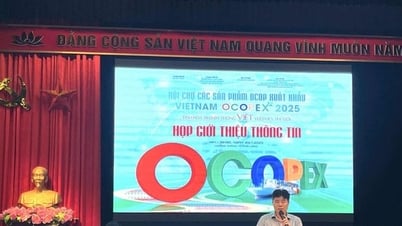






コメント (0)