社会住宅政策に関しては、「住宅法案(改正)」において、社会住宅支援政策の対象となる主体が規定されている。
特に、対象となるのは、都市部の低所得者、工業団地内の企業で働く労働者、幹部、公務員、公務員に関する法律の規定に従った幹部、公務員、公務員の 3 つです。
収入条件を含む社会住宅の購入および割賦購入の条件に関して、法案草案は、上記3者が社会住宅を購入または割賦購入できる資格を得るためには、個人所得税法の規定に従って賃金および給与からの所得に対する所得税が課税されないことが必要であると規定している。
一方、住宅事情については、法案草案では、社会住宅の購入または賃借の資格を有する対象者には、住宅を所有していない、社会住宅を購入または賃借したことがない、居住地または勤務先でいかなる形の住宅支援政策も受けていない、または自ら住宅を所有しているものの、世帯の一人当たり平均居住面積が、 政府が各時期および各地域ごとに定める最低居住面積を下回っていることが規定されている。
法制委員会は、この内容を検討した結果、住宅難に陥っている低所得者層に対する政策の実施を保障するため、「個人所得税法の規定により所得税の課税対象となる所得のある労働者」のグループにはこの政策を適用しないことを検討すべきとの意見もあったと述べた。
この問題に関して、討論グループにおいて、代表のヴァン・ティ・バク・トゥエット氏( ホーチミン市代表団)は、工業団地内の企業で働く労働者は個人所得税の対象とならないことが保証されれば社会住宅の購入を検討される資格があるとする規制を見直すことを提案した。
個人所得税に関する現行の規定を見直す必要がある。多くの労働者や従業員の意見によると、この規定は時代遅れだ。労働者の収入は個人所得税の納税額を超える可能性がある。しかし、その収入でさらに2人の子供を養わなければならない。そして、生活に必要な物資の現在の価格だけでは足りない。この規定が維持されれば、彼らは家を買うお金さえなくなってしまうだろう。
したがって、労働者や労働者が自分の住宅を所有する機会を得られる条件を整備するための適切な調整を検討する必要がある」とトゥエット氏は提案した。
また、この問題に関連して、ホーチミン市代表団のトラン・ホアン・ガン氏は、個人所得税の課税対象となる労働者が社会住宅を購入できる余地を開くことは合理的であると述べた。なぜなら、現在、所得税の課税対象となる労働者は、家族控除(妻と子ども)を支払わなければならないため、社会的に賞賛されるべきであるからだ。
一方、ディエンビエン代表団のタ・ティ・イエン氏は、すべての経済セクターの労働者と給与所得者の枠組み、給与表、収入を構築する際には、社会住宅を購入/雇用/賃貸する能力を計算する必要があると提案した。
「集中型工業団地、クラスター、経済特区のインフラを開発する企業は、非営利目的の労働者に宿泊施設を提供する社会住宅プロジェクトを必ず持つべきだと私は勧告する。
イエン氏は「大規模な工業団地や工業集積地が集中する都市部では、住宅を持たない労働者を多く抱える企業が基金に拠出し、労働者向けの社会住宅を開発できるような社会住宅開発基金を設立することも可能だ」と提案した。
イェン代表はまた、社会住宅政策を実際に容易に実施するためには、特に投資と分配のプロセスと手順に関して、より具体的かつ詳細な規制が必要であると述べた。
さらに、社会住宅に関する基準や技術基準、計画段階からの社会住宅開発のための土地割り当て、土地利用計画、商業住宅プロジェクトに一定の割合の土地面積(現在の法律では 20%)を割り当てる規制、社会住宅建設のための市街地などもあります...
代表団はまた、国が投資・建設していない社会住宅の販売価格、賃貸価格、割賦販売価格の決定に関する第84条の規定にも同意した。投資家の費用を十分に計算し、販売価格における合理的な利益率に基づき、企業の投資資本を回収することで、企業の正当な権益を確保する。
しかし、土地資金の確保状況により、社会住宅プロジェクトに必要な資材や人件費は地域によって大きく異なります。そのため、イエン議員は、社会住宅への財政支援における地域主導の取り組みを強化する法律を支持します。そうすることで初めて、社会住宅の受給者は、適正な面積と建設品質を備えた住宅を手頃な価格で利用・選択できるようになるからです。
社会住宅支援政策の恩恵を受ける対象者を増やす提案
法案草案についてコメントしたブイ・シー・ホアン代表(ハイズオン省代表団)は、社会住宅支援政策の対象となる人々に関して、第73条第6項には工業団地内の企業で働く労働者と労働者は社会住宅支援政策の対象となると規定されていると述べた。
代表団は、現在、多くの産業集積地が出現し、急速に発展し、多くの労働者を惹きつけていると述べた。社会住宅の需要を満たすために必要な条件を確保するためには、産業集積地の企業で働く労働者、労働者、専門家を増やす必要がある。
代表団は、現在、工業団地の労働者の住宅ニーズは満たされており、2014年住宅法に基づく社会住宅建設への投資が誘致されていることを指摘した。企業と労働者の賃貸ニーズを満たすことは非常に重要である。
(VTV)
[広告2]
ソースリンク


![[写真] ファム・ミン・チン首相が、台風11号後の自然災害の影響克服に関する政府常任委員会の会議を主宰した。](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/10/09/1759997894015_dsc-0591-jpg.webp)


![[写真] ファム・ミン・チン首相が、2030年までの麻薬防止・管理に関する国家目標プログラムを展開するための会議を議長として開催](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/10/09/1759990393779_dsc-0495-jpg.webp)
























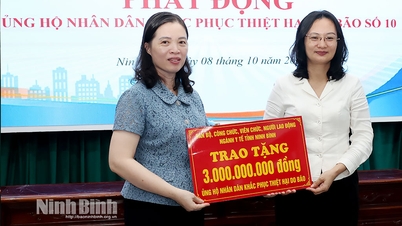






































































コメント (0)