死の祭りでは、参加者は棺桶に横たわり、数分間死を体験して現世に感謝するために料金を支払わなければなりません。
2023年には、日本の死者数は約160万人に達すると予想されており、日本のメディアはこれを「多死時代」と呼んでいます。そこで、日本の人々は死を少しでも怖くないようにと、東京・渋谷で6日間の「死の祭典」を開催しました。
このフェスティバルは、 NGO 、メディア、葬儀専門家など、東京を拠点とする様々な団体によって主催されています。日本語では、数字の「4」は「死」と同音異義語です。そのため、4月14日はフェスティバルの主催者によって「死の日」と定められました。
イベント期間中、来場者は1,100円(約18万2,000ドン)を支払って、約3分間棺桶の中に横たわることができます。時間になると、スタッフが棺桶の蓋を開け、「ようこそ、 この世へ」と声をかけます。
6日間にわたるこの祭りでは、来場者に仮想現実技術を使って死後の世界を探検したり、日本の埋葬の伝統に関する講義に参加したり、死にちなんだ料理を試食したりする機会を提供した。

東京のカフェで棺桶に入る体験。
このフェスティバルは、地域社会の意識を変え、人々が死と向き合いながらも今生と繋がるよう促すことを目指しています。このイベントのメッセージは、死は愛や感謝といった人生の様々な側面を照らし出す助けとなるということです。
このフェスティバルの主催者は、人々が死を体験することで、今この瞬間をどう生きるかを考え直すきっかけを作ることを目指していると語る。「人生の最後の瞬間から振り返ってみると、全く新しい世界が見えてくるでしょう」と、主催者の一人である市川望美さんは語った。
同様の「死の体験」は、上海や瀋陽といった中国の都市でも見られる。広東省出身の男性が、中国のソーシャルメディア「微博(ウェイボー)」で自身の体験を語った。「大学院の入試に失敗して、ひどく落ち込みました。でも、棺桶の中に横たわった後、大したことではないと気づきました」と彼は語った。

日本のお盆に行われる盆踊り。
2012年以来、韓国の首都ソウルでは何万人もの人が「生前葬」に参加しており、棺を閉じた状態で約10分間横たわっている。
日本のお盆は、通常8月中旬に3日間続きますが、盆踊りを通して先祖に敬意を表す行事も行われます。盆踊りは、死者の霊を迎え、提灯を灯し、墓参りをする民間の伝統です。
旧暦7月15日に行われる餓鬼節は、中国、シンガポール、マレーシアの伝統的な祭りで、祖先の霊を慰めるために行われます。人々は食べ物を供え、水に灯籠を流して祖先の霊が無事に帰って来られるように祈ります。
(5月12日ベトナムネット調べ)
ソース










































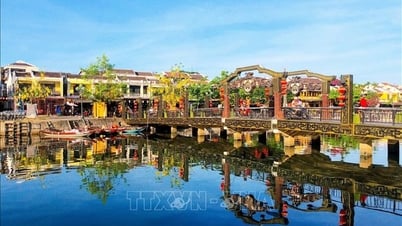



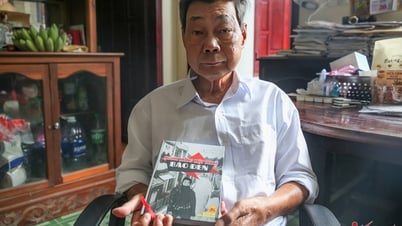





























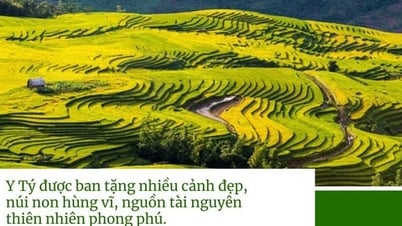























コメント (0)