 NDO -
NDO -日本の福井県鯖江市で食料品店のオーナー兼店長見習いとして働くグエン・チ・タン・ドゥオックさんをはじめとする多くのベトナム人は、10日間近くにわたり、自ら食べ物や飲み物を購入し、車で地震被災者への救援活動に出かけた。
空は暗くなり始め、石川県輪島市へ続く道も通行が困難になってきていた。飲料水とファストフードを満載した1トントラックに座るタン・ドゥオックさん(34歳)は、落ち着かなかった。彼が尋ねた情報によると、1月1日の地震で連絡が取れなくなったベトナム人女性研修生7人が、目の前のコミュニティハウスに仮住まいしているという。エピフォンの中へ…中部地方に15年間住んでいるグエン・チ・タン・ドゥオックさんにとって、
環太平洋火山帯の地震は馴染み深いものだ。しかし、2024年の新年を迎え、彼は初めてこの災害を身近に感じた。1月1日には、予定通り家族で七尾市の和倉温泉に旅行に行く予定だったという。そこは、日本西部を壊滅させたマグニチュード7.6の地震の震源地でもあった。 「幸いにも、当時、家族が隣の省に別のレストランを開いていたので、休暇のスケジュールがずれました。そうでなければ、家族は七尾市に取り残されていたかもしれません」とドゥオックさんはニャンダン新聞の記者に電話で語った。石川県には3つの事業所があり、地震発生直後、ドゥオックさんは被害状況を確認するために西日本へ向かった。メディアからの情報が途切れることなく流れ、彼の焦りはさらに募った。高速鉄道も運行停止となり、数百戸の家屋が倒壊したり、焼け落ちたりした。
石川県の地震により、多くの建物が倒壊した。(写真:タン・ドゥオック)
「当時、危険地域から来た多くのベトナム人研修生も地域社会に助けを求めていました。多くの研修生は親戚と連絡が取れなくなっていました。長年研修生のマネージャーを務めてきた私は、彼らを支援する方法を見つけようと決意しました」とタン・ドゥオック氏は語った。災害の2日後、ドゥオック氏と数人の友人は自宅近くのスーパーマーケットへ車で向かった。約1億ドン(円から換算)を携え、規定に従ってそれぞれ20リットル入りの水樽を3つ購入し、ラーメン、うどん、弁当、割り箸など「できる限りの物資」を集めた。3台の車に「物資」を積み込み、一行は和倉温泉地区へ向かった。そこには10人のベトナム人女性研修生が避難しており、最初の救援活動を開始した。
最初の救援活動では、ドゥオック氏のグループは自宅近くのスーパーマーケットで「買えるものはすべて」買ったという。
1月3日時点では、外部から現場に到着したベトナム人はほとんどいなかった。ドゥオック氏のグループは、道路が常に通行止めになっていたため、「手探りで歩き回った」。「本当に大変でした。地震で多くの高速道路がひび割れ、崩壊し、片側は崖、反対側は長い渓谷になっていました。道路が悪くなってくると、時速20キロ以下に減速しなければなりませんでした」とドゥオック氏は振り返り、車が突然道路の穴に落ちたり、動けなくなったりすることもよくあったと付け加えた。午後7時頃(現地時間)、一行は震源地に近づいた。両側の家屋が倒壊し、傾いていた。車を置き去りにし、一行は建物の奥へと進み、一時的に滞在している最初のベトナム人グループに出会った。一つ一つの救援物資を、胸がいっぱいになるような思いで手渡した。
1月3日の夜、タン・ドゥオックさんのグループがワカル温泉で行った最初の救援旅行の写真。
「その日、最初の荷物を届け終えたのが午前4時近くで、道を探すのに6時間もかかり、ようやく仕事場に戻って休むことができました。道中ずっと揺れが続き、救急車のサイレンが鳴り響いていました」とドゥオックさんは振り返る。その後数日間、ドゥオックさんとグループは、七尾市内各地に避難しているベトナム人のために、数百キロの距離を車で走り続け、生活必需品を届けた。彼はまた、自身のFacebookページで、透明性を確保するため、現金ではなく贈り物のみを受け付けると述べ、地域住民に協力を呼びかけていた。このルートを通じて、各地から数トンもの物資が届けられ、海外在住ベトナム人の思いやりの心と精神が込められていた。
輪島で連絡が取れなくなった7人の女性研修生を捜す旅「1981年生まれの妹NTLを探しています。連絡が取れなくなりました。避難所にいる方、または会ったことがある方は、ご連絡ください。家族が心配しています。石川県で働いていることしか分かりません。皆様のお力添えをお願いします。」これは、1月1日の地震発生後、在日ベトナム人団体や協会に次々と現れた、捜索中のニューススレッドの内容だ。当時、輪島町にいた7人の女性研修生の親族は、彼女たちと全く連絡が取れず、子どもたちの安否も分からなかった。彼女たちは皆、日本に来たばかりの縫製工場の研修生で、まだ携帯電話のSIMカードを登録して連絡を取っていなかった。1月5日の午後早く、私はこの話を聞き、知り合いに詳しい情報を聞き始めた。少女たちがまだ町に取り残されているかもしれないと考え、デュオック一行は同日午前4時に車に乗り込み、小松市から出発した。当時、輪島市は依然として危険地帯であり、頻繁に地震が発生していたため、アクセスは非常に困難だった。
地震により道路が大きな被害を受けたため、石川県を旅行するのは非常に困難です。
以前の旅と比べて、道はさらに困難を極めました。ひび割れが目立ち、家屋は倒壊し、壊れた車が道路沿いに放置されていました。一行は時折道に迷ったり、日本当局の指示に従って立ち止まらざるを得なかったりしました。さらに、携帯電話の電波が頻繁に途絶え、7人の研修生と連絡を取り、情報を得ることはほぼ不可能でした。「電波が通じるたびに輪島市内の各避難所に電話をかけ、情報を尋ねました。幸いにも、同日午後、地元のコミュニティハウスの管理者から、7人のベトナム人グループが仮住まいをしていることが確認されました。この時、一行は決意を新たにし、旅を続けることができました」とドゥオック氏は語りました。
ドゥオック氏が整備した救護所へと続く道。遠くにはひび割れがあり、立ち入り禁止の標識もあった。
その日の午後6時頃、12時間の旅の末、ドゥオックと友人たちは目的地に到着した。目の前には、かなり古びてはいるものの、無傷の3階建ての建物があった。電気系統は遮断されており、周囲には発電機のゴロゴロという音だけが響いていた。2階に上がり、ドアを押して中に入ると、数人の人影が見えたドゥオックは尋ねた。「ここにベトナム人の兄弟姉妹はいますか?」 すると、小さな暖炉のそばに寄り添って座っていた3人の少女がたちまち立ち上がり、泣き崩れた。彼女たちは駆け寄り、同胞たちを抱きしめた。反対側の部屋でも、ドゥオックの目に涙が浮かんでいた。彼は、こんな風に泣いたのは4、5年ぶりだったと語った。「あの瞬間、私たちもインターン生たちも希望を見つけたような気がしました」と彼は回想した。
連絡が取れなくなったベトナム人女性研修生7人のうち3人は1月5日にワジャマ町で救助隊によって救出された。
ドゥオックさんのグループは、災害の6日後、輪島で連絡が取れなくなっていた作業員7名に最初に近づき、彼らを発見したベトナム人でもあった。彼らはすぐに贈り物をし、インターネットを使って、連絡が取れなくなってから1週間近く経った後、故郷に自分たちの安否を報告した… 7人の女性インターンの1人、フォン・ヒエンさんは次のように語った。事件が起こったとき、彼女たちはとてもパニックになりました。町の公民館に逃げて避難した後、最初の数日間はベトナムから持ってきた食べ物を分け合うしかありませんでした。お茶碗も箸もない中で、7人は鍋でインスタントラーメンを茹で、一切れずつ拾い上げて口に入れました。グループはまた、冬の寒さをしのぐために、倒壊した家に戻って毛布や枕など必要な物資を手に入れなければなりませんでした。1月7日正午までに、輪島の震源地に閉じ込められていたベトナム人7名のグループは、救援チームによって安全な場所へ搬送されました。
地震後、コミュニティハウスの暖炉の周りに座るベトナム人女性研修生たち。(写真:VNA)
フォン・ヒエンさんは、「石川県に取り残されたベトナム人7人は、皆さんが危険を恐れながらも助けに来てくれたことにとても感動しました。被災地のベトナム国民を代表して、心から感謝申し上げます」と心境を語りました。グエン・チ・タン・ドゥオックさんは、ニャンダン紙の記者に対し、日本のNHKニュースに出演した時の驚きと喜びを語りました。過去10日間の救援活動について、タン・ドゥオックさんは「ただ、互いに愛し合い、支え合うという精神で、困っている人たちを助けたかっただけです。被災された方々が早く心を落ち着かせ、日常生活に戻れるよう願っています」と語りました。
同胞の精神を広げるタン・ドゥオックさんのグループは、同胞が最も困難に直面している地域へ足を運ぶ先駆的なグループの一つです。1月1日の地震後、日本中のベトナム人コミュニティは、自然災害の被災者を支援するための募金活動を開始しました。在日ベトナム人協会連合会のグエン・ホン・ソン会長によると、石川県には5,000人以上のベトナム人がおり、そのうち約600人(主に実習生)が能登半島地域の企業や工場で働いています。石川県庁の報告によると、同県のベトナム人コミュニティに死傷者はいないとのことです。
ナンダン.vn
ソースリンク  NDO -日本の福井県鯖江市で食料品店のオーナー兼店長見習いとして働くグエン・チ・タン・ドゥオックさんをはじめとする多くのベトナム人は、10日間近くにわたり、自ら食べ物や飲み物を購入し、車で地震被災者への救援活動に出かけた。
NDO -日本の福井県鯖江市で食料品店のオーナー兼店長見習いとして働くグエン・チ・タン・ドゥオックさんをはじめとする多くのベトナム人は、10日間近くにわたり、自ら食べ物や飲み物を購入し、車で地震被災者への救援活動に出かけた。





























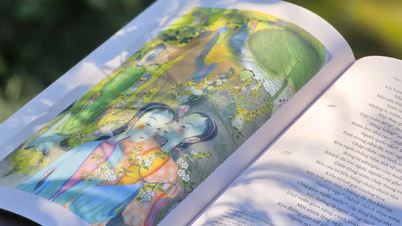

























































![[写真] ト・ラム書記長が第14回党大会小委員会常務委員会と活動中](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/402x226/vietnam/resource/IMAGE/2025/12/09/1765265023554_image.jpeg)







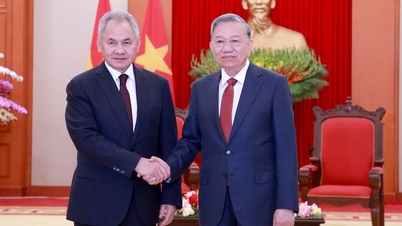


























コメント (0)