桃の枝は、まるで巨大な腕のように、ソン氏とピエンアン村のモン族の家の屋根を覆い尽くしている。朝霧の中、赤い桃の花びらが咲き乱れ、空を染める稀有な美しさを創り出している。高地の道を通って、桃の花は低地へと運ばれていく。
ソン氏はテトがもうすぐ来ることを知っていて、いつもこう言います。
- ああ、大変。私が間違っていたことは分かっていますよ、みんな。
宋さんの家族が桃園をいくつも所有していることは、この辺りの誰もが知っている。桃の木を売ることで、水牛や牛を買うことができ、さらには集落の貧しい人々や孤独な人々を養うお金まで手に入れることができたのだ。ある桃園には、樹齢30年以上の桃の古木が何百本も生えているが、彼は決してそれらを売らない。低地の商人たちが高値で買いたたこうとしても、彼は毎年この時期になると、その桃の古木に腰掛ける。そして、カビの生えた古い桃の木が鮮やかな赤い花を咲かせるのを静かに眺める。脆い花びら、乾いた幹、そして灰色の岩肌の荒涼とした景色のコントラストは、高地特有の野趣あふれる美しさを醸し出し、彼の心の中に、喜びと悲しみの記憶が次々と蘇ってくる。
 |
| (図) |
***
昔々、ソン氏の故郷では、モン族の住む所には必ずケシが咲いていました。9月になると、彼の家族も翌年の3月に収穫するまでケシを植え始めました。ケシの種は丘陵地帯や岩山の谷間に撒かれ、故郷は紫色のケシで満たされました。そして当然のことながら、村のどの家にもアヘンランプがありました。アヘンを吸わずに互いの家を訪ねるのは、楽しいことが台無しになってしまうからです。ソン氏の父親はタバコを吸い、彼も吸い、息子も吸いました。妻がアメンを出産した時、腹痛に襲われたので、痛みを和らげるためにアヘンを少し煎って飲ませました。こうしてアヘンは、彼の家族やピエンアンの人々の生活に深く浸透し、根付いていったのです。
彼の故郷がいつから貧しくなり、後進的になり、ケシのせいで様々な影響を受けたのかは定かではない。薬用原料を加工するために輸入される一部を除けば、村の生活は依然として厳しく、家々は依然として「空っぽ」で、麻薬中毒者の割合は増加していた。彼の小さくぐらぐらした家は、冬になるとまるで柱をもぎ取ろうとするかのように風が唸り声をあげた…
ソン氏は、1990年の初めに娘のア・メンが隣村の青年連合の活動から帰ってきてこう言ったことを今でも覚えている。
- お父さん、もうケシは栽培できないの。政府が禁止したのよ。
彼は叫んだ。
誰から聞いたの?隣村のダンホーっていう奴にそそのかされたの?聞かなかったよ。モン族は何世代にもわたって栽培してきたんだ。慣れているんだ。
実際、彼は村人たちがひそひそと話しているのも聞いていた。「コミューンの幹部が村々に人を送り込み、ケシの栽培をやめるよう説得している。ア・メンの息子もダン・ホーの後をついて村や畑を回り、党と国家の政策に従ってケシの栽培をやめ、他の作物を植えるよう説得していた。しかし、彼と他の多くの人々は、村人たちは耳を傾けないだろうと話し合っていた。」
ア・メンはどこで説明の仕方を学んだのか分からなかったが、ダン・ホーと共に多くの人々の耳を傾けさせることができた。彼自身もダン・ホーや多くのコミューン職員と共に、ケシの栽培地へ赴き、粘り強く説得を繰り返し、畑に赴いてケシを根こそぎ引き抜いた。彼はこう説明した。
「お父さん、アヘン樹脂は犯罪者が麻薬製造の原料として使うものよ。だから、アヘンを栽培するのは犯罪よ。明日は畑のアヘンの苗を根こそぎ抜くわ。」
彼は叫んだ。
- あなたはもう私の息子ではありません。
宋氏はベッドに米を敷き、毛布をかぶって横になった。根こそぎにされたケシ畑のことを思うと、まるで刃物で切られたように胸が痛んだ。数日後、畑へ出てみると、しおれた紫色のケシが目に飛び込んできた。宋氏は岩の上に座り込み、言葉を失った。小川のせせらぎの音を聞きながら、たった三歩しか離れていないこの畑に、阿孟氏は一体何を植えるのだろうと考えた。
***
桃の木はあの日からピエンアン村に存在し続けています。家々の周りや畑には桃の木が植えられ、赤い桃の花が白い杏や梅の花と混ざり合い、山の斜面を覆います。冬が過ぎ春が訪れるたびに、村はまるで花の絨毯のようです。人々はそれを「石桃」「猫桃」と呼んでいます。モン族の古い桃の木、10年以上も畑や農園に植えられている桃の木を指して。
その日、村の党委員会が桃の栽培による経済発展モデルの構築を決議すると、ア・メンと村人たちは熱心にそれを実行に移した。彼女が植えた桃畑は、岩だらけの山腹に丁寧に植えられた土壌と、肌身を切るような寒さに育まれ、若い芽が次々と芽吹いた。毎年春になると、むき出しでカビが生え、荒れた枝から丸い桃の花が咲き、ピエンアン村の人々の夢のように美しく輝いていた。
低地の人々の間では、旧正月の桃の花の需要が日々高まっており、モン族の人々の収入源となっています。そのため、人々は畑の周りに多くの桃林を熱心に植えています。木から美しい枝を一本切るだけで、ヤギや太った豚を買えるほどのお金になります。
しかし、桃の花の森に涼しい風が吹き抜けるたびに、モン族の娘たちが色鮮やかな錦の裾を家の前に干すたびに、宋氏は阿蒙の目が潤んでいるのを見て、悲しみを胸に秘めました。宋氏はダンホが家に入ることを禁じ、桃畑で再び二人に会ったら、全てを切り倒すと言いました。しかし阿蒙は、もしダンホと結婚させてくれなければ、他の家に幽霊として戻ることはないと言いました。宋氏の妻は泣き止むのに唇を噛むことしかできませんでした。阿蒙を気の毒に思いましたが、何も言う勇気がありませんでした。
***
しかし、ソン氏のケシへの「情熱」は、村に毎年咲く桃の花の前で徐々に薄れていった。そのため、ダン・ホーは長年、ソン氏が呪いを解き、美しく才能豊かなア・メン氏との結婚を許してくれたことに、心の中で感謝し続けている。
かつてミスだったア・メンさん、今はミセスとなったア・メンさんは、何十年も夫と共に桃の花を咲かせる村へ通ってきました。しかし毎年テト(旧正月)が近づくと、頬がまだ桃の花で赤く染まっていた頃のように、両親と家族が古くから所有する桃畑を訪ねるのを楽しみにしています。今年は、夫と共に30年間党員として認められ、経済発展を牽引する一家として、地域の飢餓撲滅と貧困削減に貢献できることを、より一層嬉しく思っています。
宋さんは娘のア・メンさんとその夫と共に、桃の古木畑に立ち、下流の道を眺めていた。そこには桃の木を積んだトラックがひしめき合っていた。モン族の桃の枝は、まるで山娘のように森から街へと春を運んでくるようだった。遠くでは、村の若者たちがコミューンの演目「祝宴、祝春」の練習に励む歌声と、美しい笛の音が聞こえ、宋さんは懐かしい気持ちになった。とても幸せな気分だったが、それでも彼は振り返り、毎年口にしていた言葉をア・メンさんとその夫に伝えることを忘れなかった。
- ああ、大変。私が間違っていたことは分かっていますよ、みんな。
それがモン族の哲学です。間違いに気づくのは容易ではありませんが、一度間違いに気づいたら、一生それを認め続けなければなりません。
ソース
































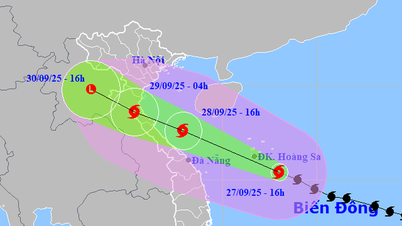







































































コメント (0)