日本円。写真:AFP/TTXVN
「現金がないと言いながらクレジットカードで支払いたいと申し出るお客さんもいました。そこでコンビニに行ってATMで現金を引き出すように伝えました」と植木氏はアルジャジーラに語った。
世界的なキャッシュレス決済の潮流にもかかわらず、植木氏は当面変更する予定はない。「今あるもので十分満足しているので、変更する必要はありません」と彼は述べた。植木氏の考えは、多くの日本人にも共有されている。
日本の経済産業省は2022年、日本におけるキャッシュレス決済が過去10年間で倍増し、36%に達したと発表した。しかし、これはほとんどの取引がキャッシュレスである韓国やシンガポールに比べると依然として低い水準だ。
日本が依然として現金を好んでいることは、東アジアの国である日本がデジタル化への対応が遅れていることの表れです。日本は依然としてハイテク分野で世界をリードしています。しかし、世界第3位の経済大国である日本は、多くの点で過去に囚われています。
日本の行政サービスの多くは依然としてオンラインでは利用できず、紙の申請書や地方自治体への窓口への出頭に頼らざるを得ません。オフィスではメールの代わりにFAXが依然として広く利用されており、電子署名よりも印鑑が好まれています。
日本では多くのオフィスでいまだにファックス機が使われている。写真:ゲッティイメージズ
デジタルトランスフォーメーションを担当する政府機関である日本電子情報技術振興機構(JEA)は、政府間プロセスのうち1,900件が依然としてCDやフロッピーディスクなどの時代遅れのストレージ技術に依存していると推定しています。新型コロナウイルス感染症のパンデミック中、日本の報道機関は、山口県の職員が救援金を配布するために住民の個人情報が入ったフロッピーディスクを地元の銀行に送付した事件を報じました。しかし、ミスが発生し、ある住民が4,630万円(33万1,000ドル)を受け取ってしまいました。
国際経営開発研究所(スイス)が発表した最新の世界デジタル競争力ランキングによると、日本は63カ国中29位にランクされました。
ITサービス企業富士通の経済学者マーティン・シュルツ氏は、日本が老朽化したシステムに依存しているのは、古い技術を使って世界トップクラスの能力を達成することに成功したことが一因だと語る。
「システムを機械のように動作するように訓練する場合、同じくらい効率的だが大きな追加メリットがなく莫大な変換コストがかかる電子システムに置き換えることは、まったく異なる計算だ」と、日本政府の顧問も務めるシュルツ氏は述べた。
東京の現金のみのラーメン店にいる植木隆一さん。写真:アルジャジーラ
日本政府は長年にわたり、日本のデジタル後進性への対応の必要性を認識してきた。経済産業省は2018年の報告書で、企業が電子システムの更新を怠ることで「デジタルの崖」に直面する可能性があり、2025年までに年間12兆円の損失が生じる可能性があると警告した。
岸田文雄首相は、高齢化による人手不足に直面する一部の地域において、デジタルインフラの高度化に5兆7000億円を投じるなど、日本のデジタルトランスフォーメーションを加速させると公約した。一方、河野太郎デジタル担当大臣は、フロッピーディスクに「戦争」を宣言し、「先進社会」に暮らしながらファックス機を所有していると皮肉を言った。
COVID-19パンデミックは日本にとって警鐘です。シュルツ氏は、他の国々がデジタル時代へとより深く移行し、COVID-19パンデミックを通じて新たなビジネス手法を模索している一方で、日本はデジタル時代への「基盤を築いている」に過ぎないことに気づきつつあると述べました。
日本の人口高齢化は、デジタルトランスフォーメーションが困難な課題となる可能性を示唆しています。数十年にわたる低出生率の後、日本政府は2030年までに情報通信技術分野で45万人の人材不足を予測しています。
[広告2]
ソースリンク













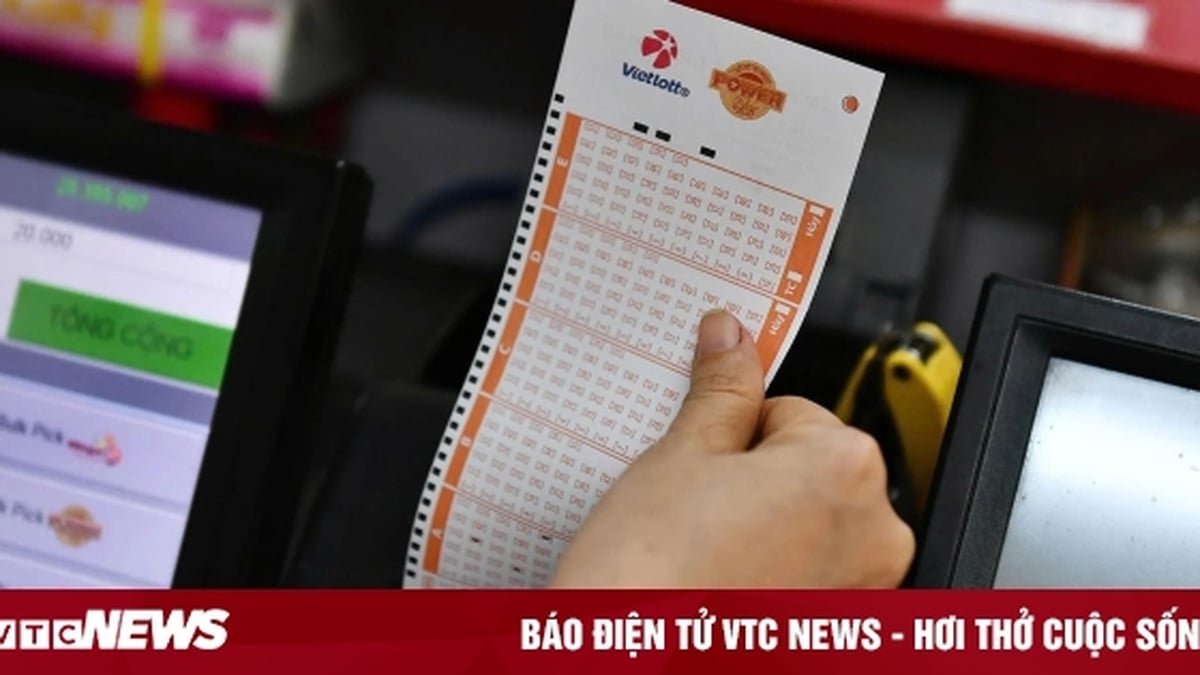


























































































コメント (0)