どこかの本で「一月はパーティの月」という民謡を読んだのですが、母が言っていた「一月は食べて遊ぶ月」という言葉の方が、私の心に深く刻まれているようです。
当時、農作業はのんびりとしていたものの、農民たちの心は安らぎませんでした。田んぼが満開の頃、まだ食べる分に十分な米がある家庭は、収穫の季節が来るのを心待ちにしていました。しかし、部屋の米が毎日少しずつ減り、底をついていくようでは、喜びなど何もありません。収穫の季節はまだまだ遠く、私たち子供は「蚕が残飯を食べる」ように、競って食べ、お腹は底なしの樽のように満腹の意味も知らず、不安な日々が続きました。

今朝、遠い昔の貧しい日々を思い出したのは、偶然ではない。近所の人が最近、あまりにも食が細くてスーパーで買った米を一袋も食べきれないと嘆いている。精米された白米に飽き飽きしているらしく、早く精米が終わって、籾殻がついたままの玄米に切り替えたいと願っているのだ。
あのタイプは健康に良い栄養素がたくさん残っていると聞きました。白米だけが選択肢ではなく、籾殻だけを取り除いた玄米も多くの人が選ぶようになりました。現代の生活は変わり、衣食住の心配がなくなったことを、ふと嬉しく思いました。
今朝、隣人から聞いた話を聞いて、煙の充満した我が家の台所にある重たい精米機を思い出しました。米を精米するのは大変な作業で、白くて柔らかいご飯を一杯いただくには、かなりの力と忍耐力が必要です。
当時の人たちは、まるで模造米を好んで食べていたのではないか、という思いが、稲妻のように脳裏をよぎった。もしそうだったら、姉が米を研ぐたびに着ていたシャツが背中でびしょ濡れになることもなかっただろうし、煙の立ち込める台所の梁に吊るされた、大きな葦でできた「シーリングファン」の存在も知らなかっただろう。両親や兄弟が米を研ぐたびに、私はその葦に紐を結びつけ、前後に引っ張っていた。葦の動きが風となり、黒い煤が舞い上がっていたのだ。
あの巨大な「扇風機」を見て、私は夢想した。「私の家にも、私がよく読んでいた絵本に出てくるラ・マンチャのドン・キホーテが戦っていたような風車があったらいいのに。そうすれば、台所にはいつも涼しい風が吹き、両親や兄弟が「米を糠にする」作業をしなくても、家族全員が食べられるだけの白米が確保できるのに」と。
綿のように白いご飯を椀に盛ることは、長年多くの家族にとっての夢でした。私の家族も例外ではありません。小さな台所で精米機がゆっくりと、重々しく、そして辛抱強く響く音を聞くと、あの頃が蘇ります。米を搗く音は遠く隣の家まで聞こえても、精米機の音は家に着いて初めて聞こえてきます。
普段は米を精米するよりも、米を搗く方が好きです。米を搗くには精米工ほどの柔軟性や器用さは必要ではないからです。正直なところ、私の痩せた体では、精米機を思い通りに動かすほどの力はありません。

当時、私の村は他の多くの村と同じように貧しく、石油精米機が登場してから長い時間が経っていました。精米機が稼働するたびに、濃い黒煙を吐き出していました。精米機を持つには、相当な「裕福」な家庭でなければなりませんでした。精米機は家の繁栄を象徴していました。おそらく、精米機を持つには相当の貯蓄が必要だったのでしょう。一方、農民の生活は日々の苦労であり、一日二日で得られるものではありませんでした。
当時、私たちは隣の村に米を挽くのを手伝いに行く必要がないことを誇りに思っていました。記憶が正しければ、私が子供の頃から大人になるまで、つまり隣村に精米所があった頃まで、我が家は精米所を一つしか使っていませんでした。精米所がすり減ったり壊れたりしても、両親は修理屋を雇って修理してもらうしかありませんでした。新しい精米所を買うお金がなかったのです。
当時、閑散期になると、村の狭い路地裏では「誰かモルタルを作ってくれる人いない?」という声がよく響き渡っていました。熟練の「モルタル職人」は常に求められており、一軒の家が完成する前に、別の家から頼まれて仕事をすることもありました。
彼が持参した道具は、指を何本か合わせたくらいの大きさの木片が詰まった大きな壺が二つありました。中には、粘土を砕いて滑らかでしなやかな塊にこねる、とても大きな土槌が入っていたのを覚えています。少し小さめの槌は、副官が木片を粘土のモルタルに押し込むのに使いました。木片は一定の列に押し込まれ、籾を巧みに米粒へと変えるのに役立ちました。
私たちは副モルタル工の仕事を見るのは楽しかったのですが、彼がいつも持ち歩いている2つの大きな鍋には非常に警戒していました。
友達が教えてくれたのですが、その籠には昔、いつも泣いてすねている子が乗っていたそうです。どうやらその子はいたずらっ子だったらしく、お金のために売られたそうです。あの恐ろしい籠のことを思い出すと、急に意地悪がなくなり、妹も私をいじめなくなりました。
当時、私の近所では、誰かが新しい臼を造ると、近所の皆がそれを知りました。臼を造る日は「良い」日、晴れた日でなければならず、特に農作業が休みで忙しい時期の「三月八日」が選ばれました。熟練した丁寧な職人に出会えれば幸運で、完成した臼は滑らかに、軽く、滑らかに回転し、米粒は「生」や「割れ」がなく、主人と職人の両方が望んでいたものでした。臼が完成した日は同様に重要で、多くの家族が鶏を屠殺し、もち米を作り、それを近所の人々に分け与え、そして助手臼人に丁重に支払いをしました。臼は家族の正式な一員とみなされ、完成するたびにネズミやゴキブリが入り込んで臼を汚さないように念入りに掃除しました。
しかし、長年使っていると、製粉機には何らかのトラブルが発生します。軸が摩耗したり、まな板が壊れたり、くさびが外れたり、製粉機のカバーが外れたりするのです。そうなると、家族全員が市場から帰ってくる母よりも、製粉業者を待ちわびるようになりました。街で製粉業者を見かけたら、すぐに家に連れて帰り、両親に修理を頼むようにしていました。
大人になるまで、精米機は重すぎて誰かの助けなしには動かすことができませんでした。その後、故郷で精米機を使う家庭が増えると、精米機と精米機は役目を終え、煙の立ち込める台所に鎮座しました。
今朝のとりとめのない話がきっかけで、今はもう忘れてしまったあの叫び声を思い出すことになった。「誰か製粉する人いるか…」と、かつての製粉副長が叫んだ言葉だ。深夜や暑い午後の苦労を物語る、あの重々しい製粉所の音は、今や忘却の彼方へと沈んでしまった。
[広告2]
出典: https://daidoanket.vn/ru-ri-coi-xay-lua-10280858.html














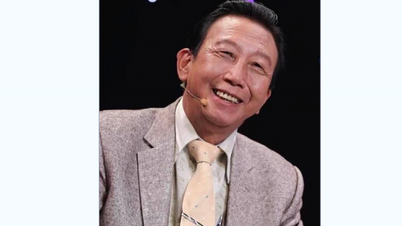









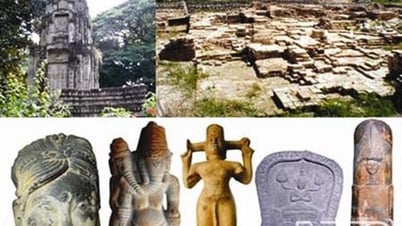


















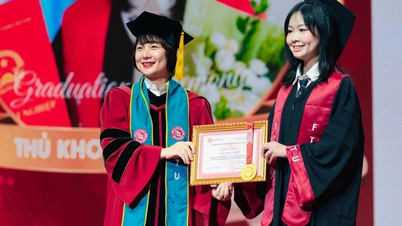



















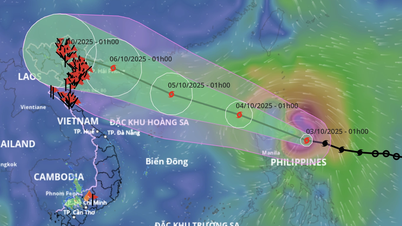




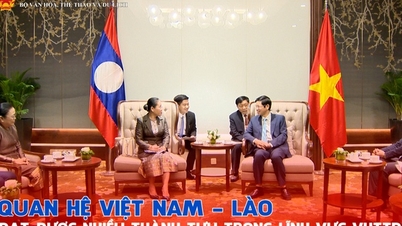


























コメント (0)