世界各国の2桁成長の実績
世界経済がますます不安定で競争が激化する中で、二桁の経済成長、すなわち年間10%を超えるGDP成長率は、多くの国、特に発展途上国にとって戦略的な目標であり、願望となっています。高い成長は、 経済規模の急速な拡大、資本蓄積の促進、教育、医療、インフラ、防衛といった重要分野への投資資源の増加につながるだけでなく、国家の統治能力と国際舞台における競争力の強化にもつながります。人口が多く、発展段階の低い国にとって、二桁成長は発展格差の縮小、「中所得国の罠」からの脱却、そして持続可能な発展の基盤構築のための重要な手段となります。以下の国々の教訓は、共有されるべきです。
まず、日本、韓国、シンガポール、中国といった急成長国においては、経済発展への国家の積極的な指導と介入が重要な要素となっている。これらの国の特徴は、「開発国家」モデルが明確に存在していることである。国家は制度的枠組みを構築するだけでなく、積極的に資源を調整し、長期的な発展戦略を策定し、優先セクターを定め、選択的な保護を実施すると同時に、企業の技術革新と競争力向上を支援している。
日本は、1960年から1973年にかけて平均10%を超えるGDP成長率を維持し、1964年には12.1%、1965年には11.8%という高い成長率を達成しました。これは、政府が産業振興を戦略的に推進したおかげです。国民貯蓄率は30%を超え、公的投資と民間投資のための潤沢な財源が確保されました。日本政府は産業計画に積極的に参加し、主要産業を保護し、新技術開発において企業と連携しました(1) 。
同様に、1960年代半ばから1970年代後半にかけて、韓国は年間9~10%のGDP成長率を達成し、多くの年には12%を超え、1973年には14.9%のピークに達しました。韓国政府は、サムスンや現代などの大企業(財閥)を支援することに重点を置いた優遇融資政策を方向付け、これらの企業が国家の経済発展を主導できる条件を整えました(2) 。
シンガポールも1967年から1978年にかけて10%を超える継続的な成長を記録し、1973年には15.5%に達した典型的な例です。シンガポールの「企業国家」モデルは、外国投資の誘致、貿易・物流インフラの整備、透明で効率的な行政の構築を通じて、その効果を最大限に高めました(3) 。
中国は、経済改革において市場メカニズムを導き、柔軟に適用するという国家の役割のおかげで、1992年から2007年にかけて10%を超えるGDP成長を維持し、1992年と2007年には14.2%に達し、民間部門の発展に好ましい環境を作り出しました(4) 。

したがって、長期的発展戦略の立案、優先産業の選択的保護、技術革新の支援、好ましい制度環境の構築を通じて示される、指導、創造、積極的な介入における国家の役割は、急速かつ持続可能な成長の中核要素です。
第二に、輸出志向型工業化に向けた経済構造の抜本的な転換は、高成長国に共通する特徴です。このプロセスには、農業経済から工業・サービス経済への力強い転換、そして閉鎖的な経済モデルからグローバルな統合への深い移行が含まれます。
韓国は高付加価値製造業の育成に注力し、工業輸出の拡大とGDPに占める工業の割合の向上を目指しています。その好例が財閥系企業の大企業化であり、卓越した輸出力を生み出しています。シンガポールは、開放経済を支えるため、高品質な物流・金融サービスを展開しています。中国は、1978年以来の改革開放政策の下、急速に工業化と都市化を進め、「世界の工場」へと変貌を遂げ、輸出額が急増しました。15年間の平均2桁成長率を達成し、中国は世界第2位の経済大国となっています。
第三に、技術開発とイノベーションは経済成長における重要なブレークスルーです。日本、韓国、中国の経験は、ブレークスルーが「技術的天井を突破する」能力と結びついていることを示しています。高度成長期において、日本は伝統的な機械製造業から第一世代の半導体技術と情報技術の開発へと転換し、エレクトロニクス産業の繁栄の基盤を築きました。韓国と中国は、半導体技術の基礎世代から人工知能(AI)、デジタル化、その他のハイテクを含む第二世代技術へと移行する中で、イノベーションを推進し続けています。これらの進歩は、労働生産性を向上させるだけでなく、急速に変化する世界経済環境において各国が競争優位性を維持する上でも役立ちます。研究開発への積極的な投資、イノベーションを促進する好ましい環境の構築、そして科学技術と生産の緊密な連携は、持続可能な経済成長を確保するために不可欠な要素です。
第4に、人材への投資と質の高い教育機関の構築は、二桁成長の重要な基盤です。人材と教育機関は、生産能力とイノベーション能力の構築において決定的な役割を果たします。日本と韓国は、企業との長期雇用モデルを維持しながら中堅技術系労働力を育成することで際立っており、生産性と生産品質の向上に貢献しています。シンガポールは、質の高い教育システムの構築と厳格な人材選抜政策の実施に重点を置き、公共部門とハイエンドサービス産業の人材育成を統合しています。一方、中国は若く低コストの労働力を活用し、技術教育に多額の投資を行い、大規模で多様な製造業の発展に有利な条件を整えています。教育イノベーション、職業訓練、規律ある専門的な労働文化の構築に関連する人材育成政策は、これらの国の成功に貢献する重要な要素です。
第五に、政治的安定と制度環境の改善は、急成長国にとって重要な要素です。これらの国は高い政治的安定を維持し、制度環境を継続的に改善することで、投資家や企業からの強い信頼を築いています。
ボツワナは、しばしば政情不安に直面するアフリカ地域の典型的な例です。しかし、ボツワナは政情の安定、透明性のある予算管理、そして法の支配の厳格な執行を維持し、1970年代の二桁成長の確固たる基盤を築き、1972年には26.4%という高い経済成長率を達成しました(5) 。
政治の安定は、長期的な経済政策の策定と実施を容易にし、財産権を保護し、民間投資を奨励します。これは、持続可能な経済成長を維持するために不可欠な要素です。
第六に、国際情勢と外部機会の有効活用は、急速な成長を促進する重要な要素です。力強く成長している国は皆、国際環境から得られる条件と機会をいかに活用するかを知っています。日本は戦後、米国の援助と輸出市場の拡大によって急速に復興しました(6) 。韓国は米国との政治軍事同盟の恩恵を受け、資本移転と技術移転を活用しました(7) 。中国はグローバル化の波に乗り、外国投資を誘致し、グローバルバリューチェーンに積極的に参加しました。ボツワナは、透明性の高いガバナンスと持続可能な経済戦略を通じて、ダイヤモンド資源を発展の原動力に変える方法を知っています。国際情勢に柔軟に適応し、外部機会を有効活用する能力は、各国が課題を克服し、長期にわたって高い成長を維持するための重要な要素です。
共通点に加え、急成長を遂げている各国にはそれぞれ独自の特徴がある。日本は「遅れをとりつつも前進する」戦略で際立っており、ハイテク技術の開発と、労働者と経営者を密接に結びつけるビジネスモデルの構築に注力している。中国は、その巨大な人口、柔軟な土地政策、そして地域間で競争する分権型の行政システムによって成功を収めている。韓国は財閥モデルを効果的に推進し、大企業を経済の牽引役として資源を集中させている。シンガポールは、国際物流・金融センターとしての地位を活用し、高品質なサービスを開発の柱としている。ボツワナは、効果的な資源管理によって「資源の呪い」を回避し、アフリカ地域における安定と持続可能な開発を維持している稀有な例である(8) 。
以上の経験から、急速かつ持続可能な経済成長は、幸運や恵まれた環境だけに頼るのではなく、明確な戦略ビジョン、効果的な開発制度、人材への積極的な投資、そして国際情勢への柔軟な適応能力といった要素が調和して組み合わさって初めて実現できると言えるでしょう。特に、労働生産性の向上、イノベーション、そして社会平等の確保を通じて、量的発展から質的発展へと成長を転換させる必要があります。そうでなければ、高い成長率を維持することは困難となり、中期的には社会経済危機に容易に陥る可能性があります。
ベトナムの二桁経済成長の現状と可能性
ベトナムは過去40年近くにわたり、中央計画経済から社会主義志向の市場経済へと、波乱に満ちた経済発展の道のりと大きな変革を経験してきました。この過程は、改革政策の実施、世界的な経済ショックへの対応力、そして国の戦略的発展志向を反映し、様々な成長段階を経てきました。
改革開放後の初期(1985年~1989年)には、経済危機、高インフレ、中央集権的な計画モデルの欠陥の影響で、ベトナムの経済成長率は2.79%から5.14%と、依然としてかなり緩やかでした。しかし、制度改革と市場開放の努力を経て、1990年代には経済は明らかに改善の兆しを見せ始めました。1995年と1996年のGDP成長率はそれぞれ9.54%と9.34%に達し、ベトナムの近代経済史上最高水準を記録しました(9) 。この時期は、制度改革政策と地域貿易統合が初めて成功した時期でもあり、ベトナムは1995年にASEANに加盟し、外国投資の流入を強力に引き寄せました。
1990年から1997年にかけては、経済モデルの転換、貿易開放、投資誘致、工業生産促進といった政策の有効性を反映し、継続的な高成長期であった。しかし、1997年以降、ベトナムはアジア通貨危機の影響を顕著に受け、成長率は低下し、1998年から2007年にかけては6~7%で推移した(10) 。この時期は、ベトナムが制度構築、社会主義志向の市場経済基盤の強化、そして国際統合の拡大に注力した時期でもあった。
2008年から2013年にかけては、ベトナムは世界金融危機の影響を受け、経済回復への課題が続きました。2009年の成長率は5.66%に急落し、ここ数年で最低の水準となりました(11) 。しかしその後、ベトナムはマクロ経済の安定化、公的債務の抑制、経済再建、ビジネス環境の改善に努めました。2015年から2019年にかけては、強力な改革政策、国際統合の深化、デジタル変革プロセスの導入により、ベトナム経済は2018年に7.47%、2019年に7.36%の成長率を記録し、明確な回復を記録しました(12) 。
しかし、2020年以降の新型コロナウイルス感染症(COVID-19)のパンデミックはベトナム経済に深刻な打撃を与え、成長率の大幅な鈍化を引き起こしました。2020年の成長率はわずか2.87%にとどまり、2021年はさらに低下し、2.56%と過去30年以上で最低の水準となりました(13) 。これは、サプライチェーンの混乱、渡航制限、国内外の消費者需要の減少など、多くの悪影響要因の結果です。
2022年は、経済開放政策、金融支援策、そして国内消費需要の伸びにより、8.02%の成長率と力強い回復を記録しました。しかし、2023年には、インフレ圧力、国際市場の変動、そして地政学的緊張により、経済は5.05%の成長率に減速しました(14) 。
2019年から2023年までの四半期成長データを分析すると、多くのショックが連続して発生し、大きな変動が見られた。具体的には、2021年第3四半期は記録的なマイナス成長(-6.02%)を記録した一方、2022年第3四半期はベース効果の低さと効果的な景気回復政策により、13.71%まで急上昇した(15) 。これらの変動は、ベトナム経済が世界的なショックや短期的な経済サイクルの急激な変化に対して高い感受性を持っていることを反映している。
2024年、ベトナムは世界的な景気後退、外国直接投資の減少、エネルギーおよび投入材料価格の激しい変動による生産コストの上昇という状況の中で、多くの課題に直面している。しかし、マクロ経済を柔軟に管理し、インフレを抑制し、消費と公共投資を促進する努力が、成長の勢いを維持するのに役立ってきた。2024年のGDP成長率は5.05%に達し、経済は比較的安定しているものの、期待された回復レベルにはまだ達していないことが示されている(16) 。これは、ベトナム経済が回復後の過渡期にあり、労働生産性の向上、イノベーションの促進、民間部門による持続可能な成長の勢いを促進するための、より長期的かつ構造的な政策の実施が必要であることを示している。

改革プロセスの実施から40年近くを振り返ると、ベトナムのGDP成長率が二桁の節目(それぞれ9.54%と9.34%)に近づいたのは1995年と1996年のわずか2年のみで、この節目を超えることはありませんでした。同時に、平均成長率は10年周期で明らかに低下傾向を示しており、1991~2000年の約7.6%から2011~2020年の約6.2%へと低下しています。この傾向は、ベトナムが近い将来に二桁成長の目標を掲げる上で大きな課題を提起しています。問題は、特に世界経済が困難、変動、リスクに満ちていると予想される中で、ベトナムがどのような根拠で現在の減速傾向を反転させ、今後二桁成長の飛躍を実現できるかということです。
ベトナムは40年近くの改革を経て、世界がテクノロジーの飛躍的進歩とデジタル変革を遂げる中で、根本的な変化を目の当たりにしてきました。第四次産業革命とグローバル化の複雑な変動は、保護主義の高まりの影響を受けて、世界経済を根本的に再構築しました。資源、特に人的資源と資金は大きくシフトし、希少な戦略資源の活用と有効活用をめぐる競争は激化しています。これらの資源の保護と促進は、新時代における各国の重要な課題となっています。
世界はグローバル化と知識経済の時代に入り、経済構造が急速に変化しています。これは、後発国に飛躍的な発展の機会をもたらしています。近代技術の移転はかつてないスピードで進み、ベトナムは「伝統的な発展の順序」を乗り越え、従来の工業化段階を経ることなくハイテク産業に参入し、発展させることができました。古い「産業遺産」をあまり背負う必要がないという利点は、ベトナムが主要な経済分野を容易に受け入れ、迅速に発展させる上で役立っています。
ベトナムは、世界経済との深い融合を通して実証される多くの独自の戦略的優位性を有しており、国家を新たな発展の時代へと導くことに貢献しています。ト・ラム書記長は、新時代において国家を前進させるための7つの戦略的方向性を示しました。それは、党の指導方法の改善、社会主義法治国家の建設における党の精神の強化、組織の合理化、デジタルトランスフォーメーション、無駄の削減、幹部の質の向上と経済発展の促進です(17) 。これは、発展プロセスを正しい方向に導き、設定された目標を達成するための戦略的視点であると同時に、根本的な解決策でもあります。
新たなビジョンに基づく海洋経済発展戦略は、海洋の巨大な潜在力を活用する機会を拡大し、国際舞台におけるベトナムの競争力向上に貢献します。ベトナムは後発国であり、低いスタートラインに立つことで、先進国から科学技術の成果、ハイテク、投資資金、市場、近代的な経営を迅速かつ低コストで獲得できるという優位性を有しています。こうした条件を効果的に活用することは、急速かつ持続可能な経済発展を促進するための重要な前提となります。
しかし、ベトナム経済は依然として潜在能力を下回っており、特に資源の有効活用と配分においてはその限界に達しています。経済プロセスを再編し、国内外の資源をより有効に活用・動員すれば、成長の余地は依然として大きく残されています。これまでの成長プロセスは、主に投入要素の増加に依存していましたが、品質、効率性、イノベーションの向上に基づく成長へと転換することで、包括的かつ持続的な改善がもたらされるでしょう。
人材は、特に知性と創造性に基づく人間中心の現代経済において、ベトナムの根本的かつ長期的な強みです。質の高い人材の育成に重点を置くことで、イノベーションを促進し、労働生産性を向上させる強力な原動力が生まれます。
地政学、地経学、地文化の観点から、ベトナムは東南アジアおよびメコン地域において重要な戦略的地位を占めており、地域間の経済発展の潜在力を拡大し、地域および世界との深い統合を促進しています。これらの優位性を適切に活用すれば、ベトナムは地域における経済発展の「爆発的な」拠点となるための基盤となります。
ベトナムの発展の勢いは、同期的イノベーションと包括的な開発戦略によっても明確に示されています。政治局が採択した4つの重要な決議、すなわち「科学技術開発、イノベーション、国家のデジタル変革における飛躍的進歩について」第57-NQ/TW決議、「新たな情勢における国際統合について」第59-NQ/TW決議、 「新時代の国家発展の要求に応えるための立法・執行におけるイノベーションについて」第66-NQ/TW決議、「民間経済発展について」第68-NQ/TW決議は、発展の飛躍的進歩の基盤を築く「4本の柱」とされています。これらの方針は、制度の改善とイノベーションの促進だけでなく、国家統治能力の向上にもつながり、今後の経済成長の推進力となります。
党の指導方法の革新は、戦略的発展志向を重視し、制度の調和を整備し、権力を効果的に統制することで、国家統治能力を高め、急速かつ複雑な発展の局面において社会の安定を確保するでしょう。人民のための発展を志向し、社会の公平性と福祉を確保するベトナム社会主義体制の優位性は、社会の不均衡や不安定さを招くことなく急速な成長を達成するための確固たる理論的根拠です。これは、経済効率と社会進歩の調和、そして深い統合と戦略的自立を両立させる均衡ある発展モデルの構築の前提となります。
要約すると、適切な開発モデル、ダイナミックな制度、そして強い政治的決意があれば、二桁経済成長という目標は、理論上も実践上も完全に実現可能である。今、最大の課題は、目標を達成できるかどうかではなく、ベトナムの気概、ビジョン、そして機会を持続可能な発展の力へと変える能力である。
ベトナム経済が二桁成長するための解決策
世界各国の二桁経済成長の経験とベトナムの現状及び成長ポテンシャルを検証した結果、二桁成長という目標は喫緊の実際的要件であることが確認された。この目標は、主要国との発展格差を縮小し、内発的能力を高め、自立した経済を構築することで、国際舞台におけるベトナムの地位を強化することを目指している。
このような状況において、「中所得国の罠」に陥ることを回避し、総合的な発展を突破するためには、成長モデルの革新と経済構造の抜本的な改革が重要な課題となっている。その上で、今後の二桁成長という目標を実現するために、いくつかの重要な解決策の実施に注力する必要がある。
まず、成長モデルの抜本的な革新こそが、ベトナムの持続可能な発展の核心的な解決策であると考えられています。この変革には、資本、資源、労働力といった投入要素の量的増加に主に依存する経済から、技術と知的人材が中心的な役割を果たす、質、生産性、革新に基づく成長モデルへの転換が必要です。
これは、人間の知性と創造性が決定的な要因となり、生産と経済発展の全過程を支配することを意味します。日本、韓国、中国といった高成長国からの教訓は、堅固な開発制度、技術革新戦略、そして質の高い労働力が、これらの国が長期にわたって高い持続的な成長率を達成する上で決定的な要因であることを示しています。ベトナムはこれらの教訓を吸収し、効果的に応用することで、内発的能力を徐々に向上させ、自立した自給自足の経済を構築し、世界経済環境の変動に柔軟に対応していく必要があります。
第二に、制度が中心的な役割を果たす新たな成長の原動力を創出する。ト・ラム書記長は、制度は現在「ボトルネック中のボトルネック」 (18 )であり、国家管理の考え方を打破し、「国家統制」モデルから「必要に応じた国家規制」モデルに移行し、市場が開発の主な原動力となる必要があると断言した。ベトナムは、ダイナミックで透明性の高い制度システムを確立し、イノベーションに好ましい環境を創出し、経済主体、特に民間経済部門の力を最大限に引き出す必要がある。さらに、天然資源、海洋資源、非伝統的資源を効果的に評価・管理し、ハイテク加工産業を発展させることは、国の付加価値の割合を高め、原材料輸出への依存を回避するための前提条件である。
第三に、質の高い人材育成は、全体的な開発戦略における重要な軸として位置付けられています。ベトナムは、研修制度を抜本的に改革し、国際基準に沿って研修基準を向上させ、戦略的産業における人材育成に注力する必要があります。同時に、優秀な人材を惹きつけ、創造性とデジタル経済への適応力を促進する環境を構築する必要があります。これは、技術系人材とイノベーションが成長促進において重要な役割を果たす、急成長国から学んだ教訓です。
第四に、サービス指向で透明性の高い行政を構築し、開発ミッションを中核とした適応型ガバナンスへとガバナンスモデルを変革することは、開発管理の有効性、効率性、透明性を向上させるための重要な解決策です。同時に、制度、政策、専門的で柔軟な行政という3つのレベルで国家のガバナンス能力を向上させることは、分断、イノベーションの阻害、既得権益による支配を回避するのに役立ちます。
第五に、緊密な国際統合の利点を効果的に活用し、国際慣行に則って優れた制度を備えたハイテクイノベーションフリーゾーンや専門自由貿易区などの画期的な制度「ポイント」を形成することで、質の高い投資を誘致し、経済構造改革を促進し、新たな産業を育成し、グローバルバリューチェーンにおける国家の競争力を高めることができる。
二桁成長は、知識と技術に基づく加工型経済からイノベーション型経済へと転換するための選択肢であるだけでなく、必要不可欠な要素でもあります。上記の解決策と、党の揺るぎない指導力、そして社会の合意を組み合わせることで、ベトナムが二桁経済成長という目標に向けて前進し、近代的で持続可能な、そして深く統合された経済を構築するために必要な突破口が開かれるでしょう。
------------------------------
(1)参照:チャーマーズ・ジョンソン著『MITIと日本の奇跡:産業政策の成長、1925-1975』スタンフォード大学出版局、1982年、45-90頁;OECD著『OECD経済調査:日本1965年』 OECD出版、1965年、10-25頁;内閣府著『戦後日本の高度成長:経済計画の役割』日本政府、2010年、12-20頁;世界銀行著『世界開発指標:日本経済データ1960-1973』
(2)参照: Alice H. Amsense: Asia's Next Giant : South Korea and late industrialization(アジアの次の巨人:韓国と後期工業化)、Publishing House. Oxford University、1989年、p. 55-110;Kim, Eun Mee: Big Business, Strong State: Collational and Conflict in South Korea Development, 1960 - 1990(大企業、強い国家:韓国の発展過程における衝突と対立、1960-1990)、Publisher. New York State University、1997年、p. 30-75;World Bank: Korea Economic Report 2019 (大企業、強い国家:韓国の発展過程における衝突と対立、1960-1990)World Bank Group、2019年、p. 12-25。 IMF:大韓民国: 選択された問題(大まかに翻訳すると: 韓国: 選択された問題)、IMF 国別報告書、No. 07/327、2007 年、15 - 30 ページ。
(3)参照:リンダ・ロウ著『シンガポールにおける都市・国家:政府・市場関係の政治経済学』 (大まかに訳すと「シンガポールにおける都市・国家:政府・市場関係の政治経済学」)、出版社:大学 Oxford, 1998年、p. 80 - 120; William G. Huff: The Economic Growth of Singapore : Trade and Development in the Twentieth Century (シンガポールの経済成長:20世紀における貿易と開発)、Publishing House. Cambridge University, 1994年、p. 150 - 185; World Bank: Singapore Economic Monitor 2020 (大まかに翻訳すると: Singapore Economic Report 2020)、World Bank Group、2020年、p. 15 - 30。
(4)参照:バリー・ノートン著『中国経済:移行と成長』MITプレス、2007年、200~260頁;世界銀行著『中国2030:近代的で調和のとれた創造的な高所得社会の構築』 「中国2030:現代的で調和のとれた創造的な高所得社会の構築」、世界銀行および国務院開発研究センター、2013年、p. 40 - 65;IMF:中華人民共和国:選択された問題(大まかに翻訳すると:中華人民共和国:選択された問題)、IMFの国別報告書、No. 09/195、2009年、p. 25 - 50。
(5)参照:クリストファー・C・クラップハム著『ボツワナ:南部アフリカの自由民主主義と労働力』 (大まかに訳すと、 ボツワナ:南アフリカの自由民主主義と予備軍)、Modern African Research Magazine、出版社。ケンブリッジ大学、1982年、p. 225 - 250;世界銀行:ボツワナ経済報告1975 (大まかに翻訳すると「ボツワナ経済報告」となる)、 世界銀行グループ、1975年、p. 10 - 30; ロバート・A・ロットバーグ:ボツワナの政治経済学:成長と民主主義の研究(大まかに翻訳: ボツワナの政治経済:成長と民主主義の研究(カリフォルニア大学出版局、1988年、100~140頁)。
(6)マイケル・シャーラー著『アメリカによる日本占領:アジアにおける冷戦の起源』 (オックスフォード大学出版、1985年、100~140頁)を参照。
(7)参照:ビクター・D・ファーザー著『敵対関係にもかかわらず連携:米韓日安全保障トライアングル』 (大まかに訳すと「敵対関係にもかかわらず結論:米韓日安全保障トライアングル」)、スタンフォード大学出版、1999年、45~70頁
(8)参照:ポール・コリアー、アンケ・ホフラー著『資源の呪いと天然資源』 (大まかに訳すと「天然資源の呪い」と「天然資源」)、オックスフォード大学出版、2009年、120-150頁
(9)参照:ベトナム統計総局『 1985年~1996年社会経済報告書』出版社。統計、1997年、45~70頁
(10)ベトナム国家銀行「ベトナム経済報告書 1990-2007 」出版社金融、2009年、30-60頁を参照
(11)ベトナム国家銀行「ベトナム経済報告2008-2013 」出版社金融、2014年、40-70頁を参照
(12)参照:世界銀行「ベトナム経済アップデート2019:現状維持」 (大まかに訳すと: ベトナム経済の最新情報2019:地位維持)、世界銀行グループ、2019年、10~30ページ
(13)参照:ベトナム統計総局: 2021年社会経済報告書、出版社。統計、2022年、15~50頁
(14)参照:世界銀行「ベトナム経済アップデート2023:世界的な不確実性の乗り越え」 (大まかに訳すと「ベトナム経済アップデート2023:世界的な不安定性の克服」)、世界銀行グループ、2023年、10~35ページ
(15) 参照:ベトナム統計総局: 2021年および2022年第3四半期の社会経済状況報告書、出版社。統計、2021-2022年、p.5-15
(16)参照:世界銀行:ベトナム経済アップデート2024:外部ショックと国内課題への対応(概ね更新版ベトナム2024:国内の外部ショックと課題への対応)、世界銀行グループ、2024年、10~35頁
。 1-11-2024、https://www.tapchicongsan.org.vn/media-story/-/asset_publisher/v8hp4dk31gf/content/ky-nguyen-moi-ky-nguyen-vuon -minh-cua-dan-toc-ky-ky-ky-trien-giau-manh-duoi-su-lanh-dao-cam -quy-cua-dan-cong-san-san- santay -ten-thanh-tuoc-viet
(18)Tran Van博士:「ボトルネックの克服、開発機関の建設」、 Nhan Dan Electronic Newspaper 、2025年1月23日、https://nhandan.vn/vuot-qua-diem-nghen-xay-dung-the-che-phat-trien-post857173.html
出典:https://tapchicongsan.org.vn/web/guest/the-gioi-van-de-su-kien/-2018/111702/tang-truong-hai-so--- kinh-nghiem-tu-mot-so-quoc-gia-tren-the-gioi-va-va-phap-a0






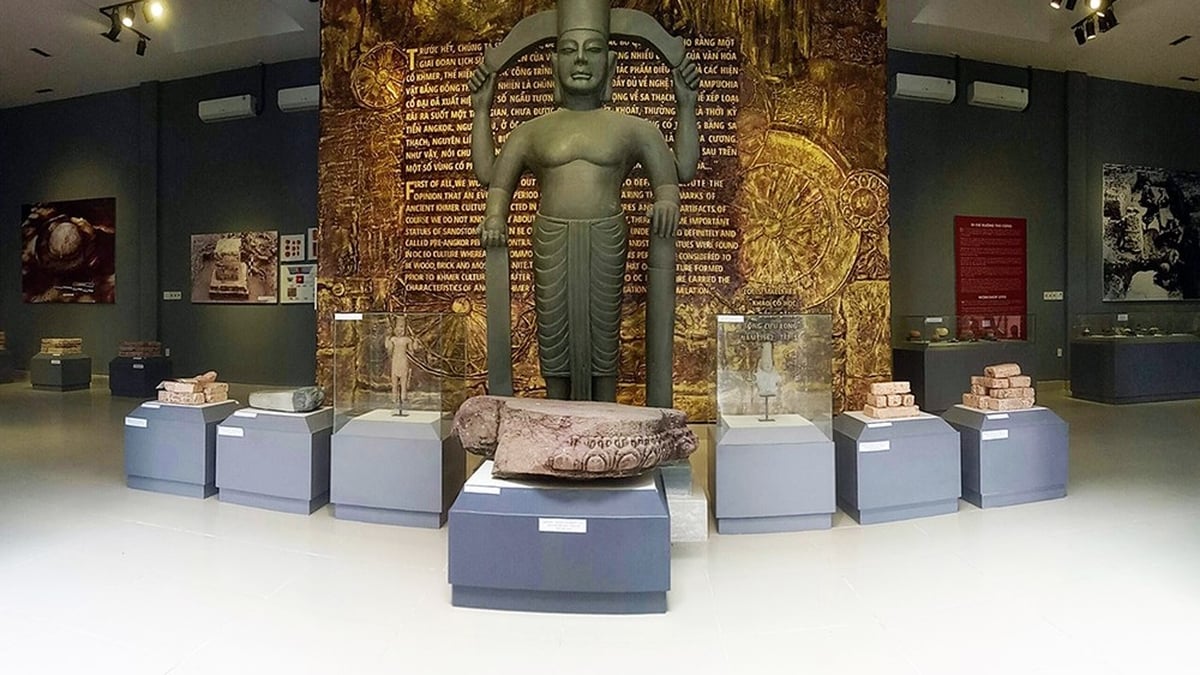




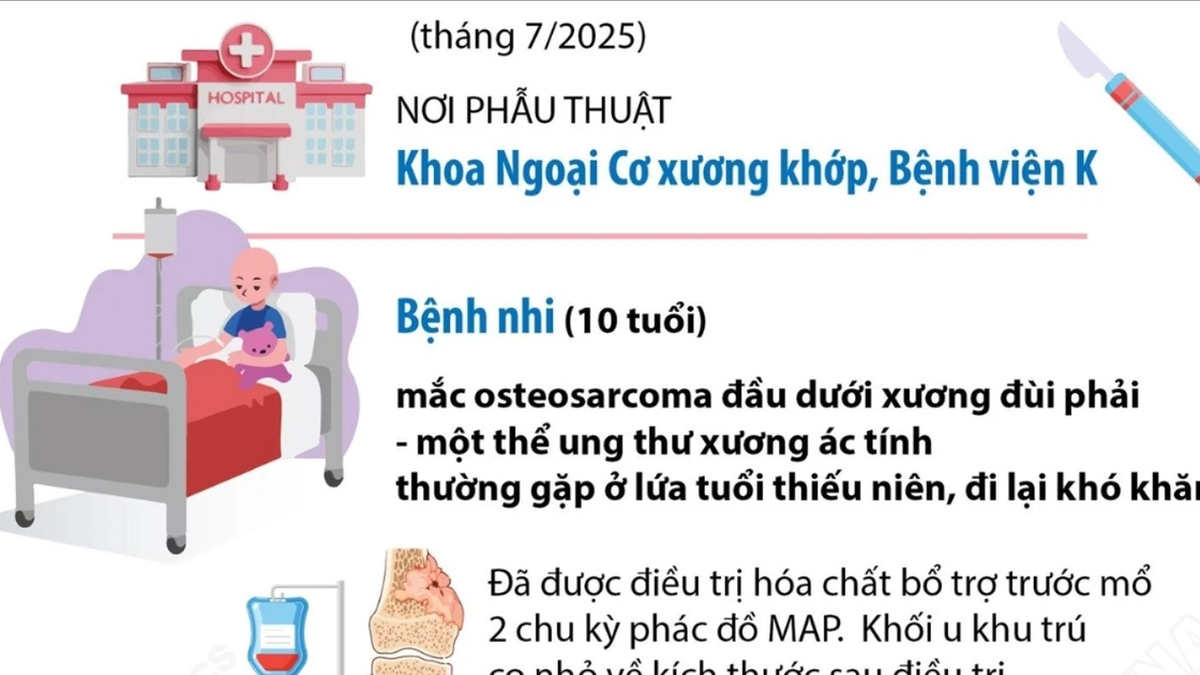



























































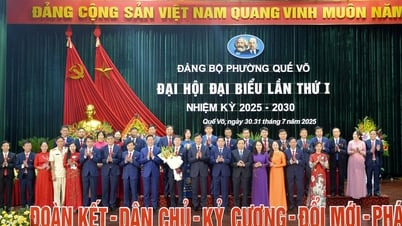
























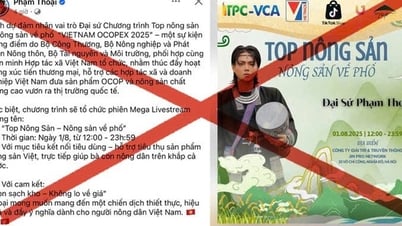






コメント (0)