この傾向は、特定の専門分野の訓練ではなく、学習者の一般教養と学際的知識の向上を目的としています。この変化は、卒業後の学生の就職にどのような影響を与えるでしょうか?

合格者はホーチミン市工業大学への入学手続きを完了します。この大学は、研修プログラムにおいて専門知識を重視する大学の一つです。
2021年から、教育訓練省が2021年に出した「研修プログラムの基準を規定し、大学教育の全レベルにおける研修プログラムの開発、評価、公布に関する通達第17号」に基づき、大学は研修プログラムを改訂します。この通達によると、大学研修プログラムは120単位、レベル7の専門研修プログラムは150単位(体育および国防・安全保障教育は除く)となります。
専門知識は10~20%強
そのため、特定の職業訓練専攻(医師、薬剤師、エンジニア、建築家など)に加えて、残りの大学専攻は現在120単位レベルとなっています。特に注目すべきは、各大学がプログラムにおける知識量を大幅に調整していることです。
例えば、金融マーケティング大学は、122単位(現行比2単位増)の大学研修プログラムを構築しています。このうち、一般知識の単位数は21%(現行28%から21%に減少見込み)です。業界の基礎知識は、現行比18単位(業界によって24単位から39単位)増加する予定です。一方、専門知識は24単位から15単位に減少し、大学研修プログラム全体の約12%(現行20%から減少)を占める予定です。
上記の調整を行う前に、金融マーケティング大学科学管理学科長のファン・ティ・ハン・ガ准教授は、同校が同分野の他の研修機関と比較したと述べた。「今回の調整により、金融マーケティング大学の研修プログラムに占める専門研修知識ブロックの割合は12%になります。一方、国民経済大学の専門研修知識ブロックの割合は現在約14%です。海外の大学でも、研修プログラム全体の約14~16%を占めています。したがって、本校の変更は、現在の国内外の大学の状況と一致しています」とハン・ガ准教授は述べた。
ハン・ンガ准教授は、この変更について説明し、学部の目標は学生が多様な職に就けるよう、学際的な基礎知識を増やすことだと述べた。「この目標を達成するには、学生が学際的な基礎知識を十分に身に付け、環境、規制、法律、技術、そして多くの職業の変化に適応し、研究思考力と適応力を高める必要があります。たとえそれらの職を失ったとしても、学生は自信を持って別の職に就くことができるでしょう」とハン・ンガ准教授は付け加えた。
適応性を高める
ホーチミン市経済大学は現在、学士課程で120単位、工学課程で150単位の大学教育プログラムを構築している。このうち、一般知識はプログラム全体の約30~40%、基礎知識は40~50%、専門知識は約20%を占める。同大学副学長のブイ・クアン・フン准教授は、「将来、変化する労働環境に適応する能力を高めるために、学校は一般知識と基礎知識を更新する必要がある」と述べた。フン准教授が挙げた例の一つは、ホーチミン市経済大学の全専攻の学生が、データサイエンス入門、ソフトスキル、起業、心理学的基礎、デザイン思考、持続可能な開発という、トレンドと時代に密接に関連する6つの必修科目を履修しなければならないという点だ。これらのトレンド科目とは対照的に、同大学は一般課程において依然として高度な数学を維持している。
ホーチミン市工業大学は2016年以降、研修プログラム全体における専門知識の比率を17%から12%に削減し始めました。同校研修部門長のグエン・チュン・ニャン博士は、「本校はこれまで、研修プログラムの構築にあたり、学習者の専門知識の向上を目指してきました。しかし、プログラムが専門的すぎると、学習者が様々な職種に就く機会が限られてしまいます」と述べています。

特定の研修専攻(医師、薬剤師、エンジニア、建築家)向けの研修プログラムには 150 単位が含まれます。
専門知識が乏しく、多様な仕事の機会が限られている
大学の代表者によると、プログラムにおける専門知識の増加または減少は、分野とトレーニングの方向性によって異なります。
ドゥイタン大学副学長のヴォ・タン・ハイ博士は、「専門知識の増減は、各校の研修プログラムによって異なります。研修プログラムの構築において重要なのは、重複する知識を見直し、専門分野の最新の知識をカリキュラムに加えることです。同時に、教育方法を革新し、教育に情報技術を徹底的に活用する必要があります。そうすることで初めて、学習者は卒業後すぐに仕事に適応できるようになります」と述べました。
グエン・チュン・ニャン博士は、大学の専攻別研修プログラムを構築する際には、他の専攻との差を30%確保する必要があると考えています。この差は一般専攻と基礎専攻に共通しますが、専攻においては特に顕著です。ニャン博士は、特定の専門専攻を除き、残りの専攻は研修の方向性に応じて適切な専攻比率を維持する必要があると考えています。「専門知識が多すぎると、『職業訓練』と大差がなくなり、学習者の就職機会は限られてしまいます。さらに、約120単位のプログラム全体の中で、専門知識に重点を置きすぎると、専攻の基礎が不十分になります。逆に、専門知識が少なすぎると、専攻間の差がなくなり、卒業生が特定の職種の要件を満たすことが難しくなります」とニャン博士は指摘しました。
ホーチミン市商工大学入学・広報センター所長のファム・タイ・ソン氏は、教育の方向性に応じて適切なプログラムを設計する必要があると述べた。研究志向の大学であれば、知識ブロックは産業の基礎科目に重点を置く一方、応用研究志向の大学は専門科目に重点を置く。深い知識を伴う応用研究の方向であれば、学生は卒業後すぐに仕事に適応できるだろう。 (続き)
応用重視の学校では専門知識が重要です。
一方で、多くの大学では、依然として大学レベルで専門知識の蓄積が盛んに行われている。例えば、ホーチミン市文化大学の研修課程(国防・安全保障教育を除く)の131単位のうち、専門知識が最も多くを占めている。具体的には、専門知識は50単位(38%以上)を維持しており、一般教養は31%以上、基礎知識は30.5%となっている。
このデータを共有した同校研修部長のグエン・タン・トゥン師は、同校は教育管理の専門家と綿密な協議を行い、応用志向に応じて知識ブロック間のバランスを調整しながら研修プログラムを作成したと述べた。「専門知識が簡略化され、内容が乏しいと、卒業生は何でもできるものの、専門的な業務を行うことは困難になります」とトゥン師は分析した。
同様に、ホーチミン市工科大学では、現在、専門知識の割合を約40%に抑えています。同校の教育プログラムは、120単位の学士課程と150単位の工学課程の2種類で構成されています。例えば、経済学専攻では、一般知識が約26.5%、基礎知識が31.4%、専攻科目と専攻科目が40%以上を占めています。一方、工学専攻では、一般知識と基礎科学が26.8%、基礎知識が24.2%、学士課程第1期が30.4%、専門課程第2期(工学学位)が18.6%を占めています。専門知識重視の視点を共有し、同校入学・広報センター所長のファム・タイ・ソン氏は、「特に応用研修志向の学生にとって、専門知識は就職時に重要です」と述べています。
[広告2]
出典: https://thanhnien.vn/truong-dh-giam-dao-tao-chuyen-sau-de-sinh-vien-de-tim-viec-185240521192600071.htm

































































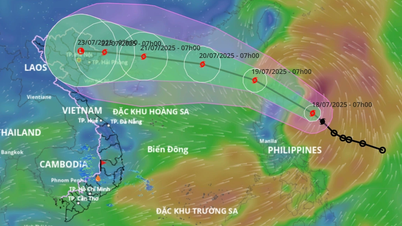



























![[インフォグラフィック] 2025年には47の製品が国家OCOPを達成する](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/402x226/vietnam/resource/IMAGE/2025/7/16/5d672398b0744db3ab920e05db8e5b7d)





コメント (0)