カニのスープで煮たマラバルほうれん草、
半死半生の者が生き返って食べる。
(民謡)
「ラウ・ボー・ラ・カイン・クア」という諺は、多くの文献や辞書に記録されています。ベトナム語の慣用句・諺辞典(グエン・ラン教授著)には、「ラウ・ボー・ラ・カイン・クア」(ラウ・ボーは湿った土壌に生えるシダ植物で、栽培する人はいませんが、食べられます)と説明されています。これは、ラウ・ボーがカニスープを作るのに適しているという意味です。
実は、同じシダ科に属しているにもかかわらず、マルシレア・クアドリフォリア(Marsilea quadrifolia)の形はシダとは全く似ていません。グエン・ラン教授の説明によると、マルシレア・クアドリフォリアは低木の縁や林冠下に生育するシダ植物であると考えられます。
マラバルほうれん草は、シダ目マラバルほうれん草科に属しますが、「シダの種」ではありません。マラバルほうれん草は、葉が4つの小さな部分に分かれていることから、四葉草(よつばのくろば)や四葉菜(よつばのくろば)などの中国語名でも呼ばれています。また、葉が4つに分かれ、田の字のような形をしていることから、田字草(たじょうのくろば)とも呼ばれています。
特に、蘋藻(タンタオ)という言葉では、rau bo は rau tan です。
「タンタオ」または「タオタン」は中国語由来の合成語で、もともとはラウタン(草)とラウタオ(藻類全般)という2種類の水生植物を指していました。古代の人々はラウタンとラウタオを供物としてよく摘んでいました。『詩経』(Chieu Nam - Thai Tan)には、「ヴー・ディ・タイ・タン? ナム・ジャン・チ・タン;ヴー・ディ・タイ・タン? ヴー・ビ・ハン・ラオ」(それからラウタンを摘む/南の渓流の岸辺で/それからラウタオを摘む/あの浮いた場所で)という一文があります。鄭桂冠は次のように述べている。「昔、結婚の3ヶ月前、祠がまだ残っていたら女性は宮殿で、祠がなくなっていたら祠で教えを受けました。そして、徳、言葉、美しさ、仕事という4つの徳目について教えられました。教えが終わった後、供物を捧げました。命の供物は魚、野菜の供物はラウタンとラウタオでした。この頃、女性は徳を積み、孝行する人になったのです。」[原文:蘋藻 1. 蘋與藻.皆水草名.古人常采作祭祀之用. 「詩‧召南‧藻采蘋」: 「以以采蘋? 南澗之濱; 以以采?彼行潦」 漢鄭玄メモ: 「古者婦人先嫁三月、祖廟未違反、教に対して公宮、祖廟共犯、教宗室。教以婦德、婦言、婦容、婦功。教成之祭、消費用魚、芼用蘋藻、所以成婦順也 – 大中国語辞典]。
後に「タンタオ」は、優れた資質を持つ女性を指すようになりました。ベトナム語では、「タンタオ」または「タオタン」は、困難で恵まれない生活の中で、勤勉で勤勉で家事をこなす女性を指します。
「ラウボーはカニスープの妻」という諺に戻ります。
晴れと雨が交互に訪れる夏は、脂の乗ったカニと若くて緑色のムクゲの季節です。ムクゲを使ったカニスープは、風味豊かでとても美味しいだけでなく、民間療法によると、炎症を鎮め、体を冷やし、不眠症や睡眠障害の神経を落ち着かせる効果があると言われています。そのため、ムクゲをカニスープで煮ると、半死半生の人が生き返って食べるという言い伝えがあります。
かつて農家は、休耕地や溝に生えるマラバルほうれん草を豚の飼料として収穫することが多かった。しかし、前述のように、マラバルほうれん草は今でも貧しい人々の野菜である。 農業百科事典には、マラバルほうれん草に関する具体的な情報が次のように記載されている。
ベトナムでは、マラバルほうれん草は湿気の多い場所、浅い水田、稲の苗などに自生しています。茎と葉は豚の飼料として、生のまま、またはぬかと一緒に調理して与えます。マラバルほうれん草は、他の野菜に比べてタンパク質含有量が高く(生野菜中4.6%)、ビタミンCも豊富(760mg%)です。腫れ、痛み、蛇に噛まれた時の治療薬として民間療法で使用され、茹でて飲むと利尿作用もあります。
ド・タット・ロイ教授著『ベトナムの薬草とハーブ』にも、「ラウボーは、マメ科、ヒヨコマメ目に属します。…ベトナムでは、一部の地域では生食されています。また、摘んだ後、黄金色になるまで焼いたり、乾燥させて煮詰め、濃縮飲料にして、尿路を清浄し、帯下、膣分泌物、不眠症に効く清涼飲料水として利用する地域もあります。さらに、生のラウボーをすり潰して絞り、その汁を蛇毒の治療薬として飲んだり、残った液を腫れや痛みのある部分、乳房の腫れ、乳管の詰まりに塗ったりする地域もあります。」と記されています。
このように、人々がラウボーをカニスープの妻に例える理由は、ラウボーがカニスープを作るのに非常に適しており、美味しくて民間療法でもあるためであることがわかります。
ホアン・チン・ソン(寄稿者)
出典: https://baothanhhoa.vn/ve-cau-rau-bo-la-vo-canh-cua-244583.htm








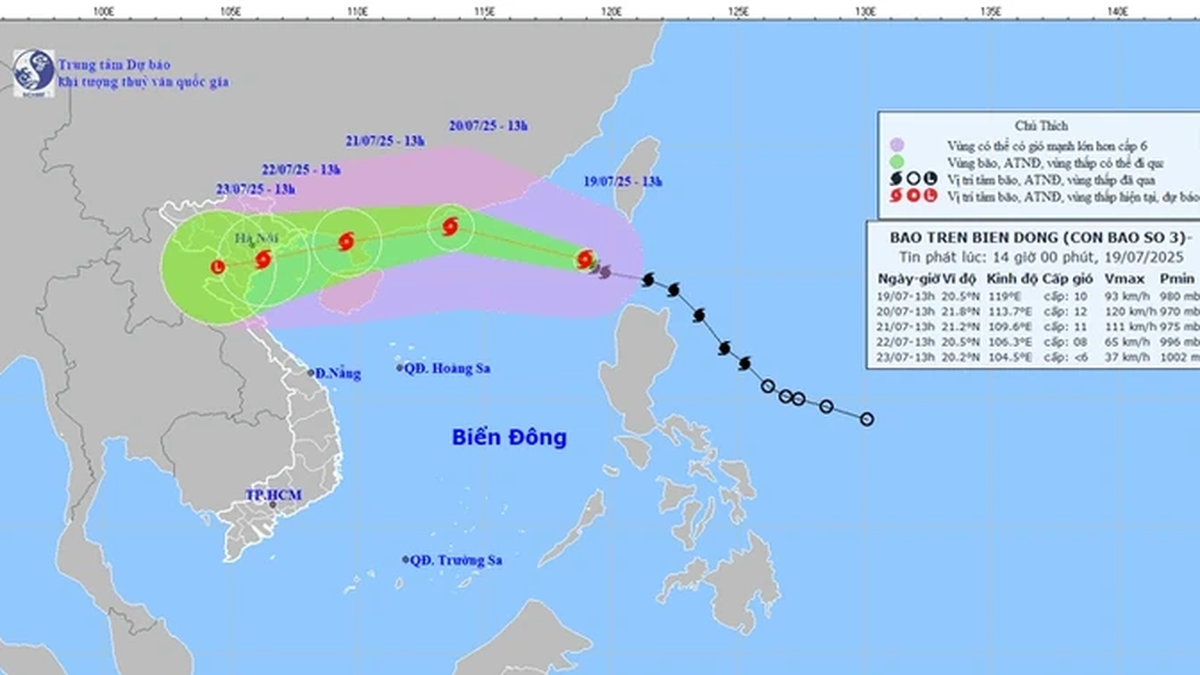






































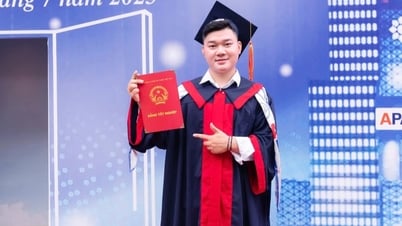




















































コメント (0)