 |
北京のGoogleオフィス。写真: Inc. |
中国は、米国による自国製品への関税賦課への対応策として、Googleに対する独占禁止法調査を実施している。しかし、国家市場監督管理総局の発表では、このインターネット企業の疑わしい活動や監視の範囲は明確にされていない。Googleの検索エンジンとそのすべてのサービスは中国では長らく利用できない状態にあることを考えると、これはなおさら驚くべきことだ。
しかし、同社は依然として、人口10億人の国に関連した広告、クラウドコンピューティング、ハードウェア製造、アプリケーション開発などの活動を数多く行っています。
Googleの中国における事業
Googleは2006年、.cnドメイン名で10億人規模の市場向けに検索エンジンを立ち上げました。2009年までに検閲を突破し、中国本土市場に参入し、最も利用されているウェブサイトの一つに成長しました。しかし、2010年までに、当局の検索結果フィルタリング要請に従わなかったため、すべてのGoogleサービスが停止を余儀なくされました。それ以来、Googleのウェブサイトとすべてのサービスは中国で利用できなくなっています。
目立った活動はないものの、Googleは依然として北京、上海、深圳にオフィスを構えている。CNBCによると、この米国企業のこれらの市場における事業活動には、広告、クラウドコンピューティング、ハードウェア製造、アプリケーション開発、AI研究などが含まれる。Googleの目標は、国内企業が国際展開する際にインフラを提供することだ。
 |
この検索エンジンは2010年に中国での運営を停止したが、同社は撤退しなかった。写真:フォーチュン |
例えば、Googleは、支配権を握りたい市場において、中国企業に検索エンジンやYouTube上のキーワード広告を販売しています。また、東南アジアやその他の地域で事業を展開するTikTok、NetEase、Sheinといった多くのユニコーン企業にクラウドサービスを提供しています。
AI分野では、このインターネット界の巨人は2017年に北京に人工知能研究センターを設立し、 教育と自然言語理解に注力しています。TensorFlowやKubernetesといったオープンソースプロジェクトは、中国の開発者コミュニティに大きな影響を与えています。また、10億人の人口を抱える中国のプログラマー向けに、独自のI/Oイベントを毎年開催しています。
Playストアは中国では利用できません。しかし、Googleは依然として中国製アプリを世界に提供することに協力しています。中国で販売されている中国製スマートフォンは独自のユーザーインターフェースを採用していますが、Googleが主導するAOSP(Android Open Source Project)カーネルをベースに構築されています。
アルファベットは2023年、収益の17%がアジア太平洋地域から得られていると報告した。しかし、10億人規模の市場がどの程度寄与しているかは明らかにされていない。
中国は何を調査しているのか?
フィナンシャル・タイムズによると、情報筋によると、当局の捜査はAndroidオペレーティングシステムを対象としているという。言及されている問題は、このプラットフォームを採用しているXiaomiやOppoなどの中国モバイルメーカーに打撃を与えている独占状態だ。
情報筋はまた、中国がファーウェイの取引を禁止した2019年からグーグルの調査を開始していたことも明らかにした。しかし、調査はトランプ氏が大統領に就任する2024年12月まで棚上げされていた。フィナンシャル・タイムズ紙によると、当局は1月初旬からグーグルの北京事務所を捜索し、関連情報を要求していたという。
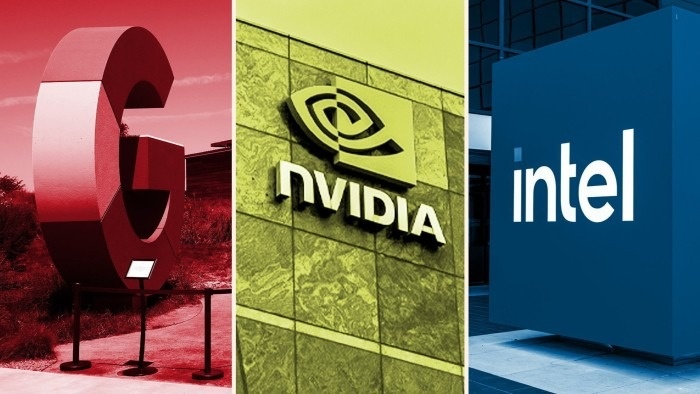 |
中国当局は3つの米国企業を監視対象にしている。写真: FT |
中国清華大学国家戦略研究所の研究員、劉旭氏は、今回の調査はトランプ政権による中国製品への関税への報復措置の一環として、米国企業を標的にしていると述べた。中国政府はグーグルに加え、NVIDIAとインテルも調査対象にしている。
一方、中国商務貿易大学の龔炅氏によると、中国のモバイル企業は長年、GoogleによるAndroidの市場操作に不満を抱いてきた。現在、AppleとHuaweiを除くすべての企業は、国際的に販売されるスマートフォンでこのOSを使用するために料金を支払わなければならない。
近年、Googleは繰り返し独占禁止法違反の疑いに直面しており、EU、韓国、ロシア、インド、トルコで多くの訴訟が起こされています。2024年8月、米国連邦裁判所はGoogleが検索市場を違法に独占していたとの判決を下しました。米国司法省は、AndroidオペレーティングシステムとChromeブラウザの売却を含む、同社の事業分割案を検討しています。


































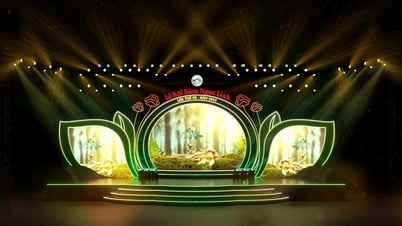

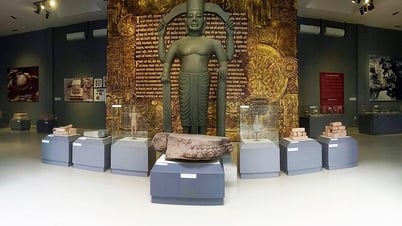

































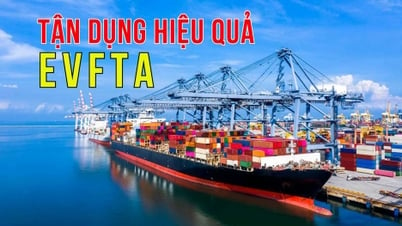




















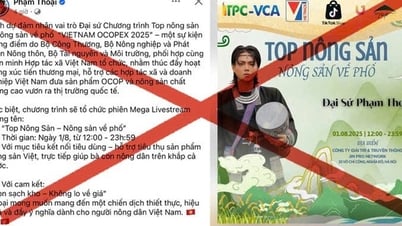






コメント (0)