琴は何年も同じまま、まだ砂の上で休みなく演奏し、誰かが戻ってくるのを待っているのだろうか?
「一人で行けば帰り道は分かるよ。」
父は叫びながら、窒息死した魚を網の目から数匹手で取り除いた。嵐の季節の薄暗がりの中で、魚は鍋の底に干からびて横たわり、女の手も借りずに慌ただしく盛り付けられていた。私と父の食事、二人の男の間、どこを見渡しても静寂と空虚が広がっていた。
「瓶の中の水をきれいにして、塩分を洗い流してください。」
父は顔を上げて叔母に話しかけた。魚の群れはメロン色の網から逃れようともがいていた。父の声は砂浜を吹き抜ける風の音にかき消され始めた。海の塩辛さは漁師たちの生活を悩ませていた。夜になると、人々の心は波のようにざわめく。叔母は父の言葉に軽く頷き、静かに頭を下げて、出て行った時と同じように家の中に入っていった。
父は母への恋しさが徐々に薄れてきた頃、彼女と結婚した。結婚式と称してはいたものの、用意したのは三度の食事とビンロウジュの箱数個だけだった。彼女は荒々しい体つきで、口は突き出した魚のようだったと村人は言った。漁村の人々の伝説は海にまつわるものだった。美は魚のようで、醜もまた魚を呼ぶのだと。
母が亡くなった日、父は半分空になった白ワインのボトルを持って砂丘に登りました。そして、その日の終わりまで、月が昇って白い砂浜を照らすまで、残りの半分を飲み干しました。
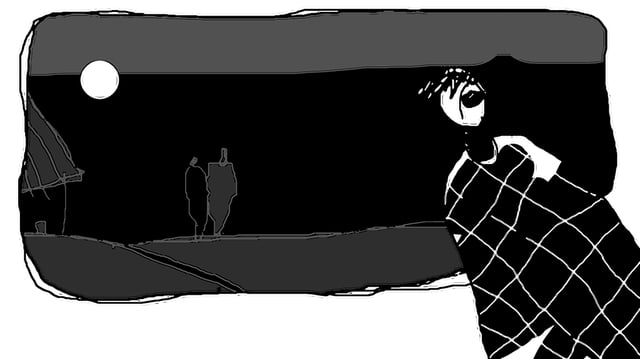
イラスト:ヴァン・グエン
父が酒に酔っている間は、叔母は一人で家族のために料理を作るのに忙しかった。
海が荒れ始めた。ある夜、父が砂丘からよろめきながら戻ってくると、叔母は言った。「死ぬ勇気がないなら、人間らしく生きなさい」。「人間」という言葉が叔母の喉に詰まった。モクマオウのざわめきが間近に響き、少女の命を吹き飛ばすようだった。叔母は一言だけ言い残して去っていった。私は寝たふりをして反対側に横たわった。叔母のつま先立ちの音ははっきりと聞こえ、ベッドのそばで長い間止まっていた。嵐はドアの向こうで止まり、叔母の心は嵐のようだった。目を開けていなかったが、叔母が私を見ているのがわかった。暗い夜の闇の中、叔母の息が静かに響いていた。叔母の手を握る勇気は私にはなかった。叔母は、いつも岸辺へと向かうハイビスカスの花のように、これから先、自分自身の幸せを見つけなければならないのだろう。そう思って、父にひどく腹を立てた。叔母が出て行ったのは、父の酒浸りのせい?この家のためにあれほど苦労したのに、結局は無駄な報酬しか得られなかった。翌朝、海はまだ霧の中で眠っていた。本当に眠っているのかどうか分からなかったが、昨夜、父は夜明けまで明かりをつけたままにしていた。漁師たちの声が、まるで蜂の巣が割れたように響き始めた。子供たちは学校を早退し、夢を海と共に流してしまった。
叔母の不在で父親は目を覚ました。
朝、父は私を海へ連れて行ってくれました。夕方、叔母は私をパッチワークのような記憶の広大な世界へ連れて行ってくれました。海の広大さ、白い砂浜の広大さ、遠い夢の広大さ。
父は私を塩辛い海水に沈めました。海で生まれたなら、生きて行くためには泳げなければならない、と父は言いました。私は網にかかった魚のようにもがき、水にむせ、頭が震え続けました。父は言いました。「深い海を見たいなら頭を下げろ。海は最も低い場所を選ぶからこそ広いのだ」。叔母と過ごした年月の間、なぜ父はプライドを捨てないのか、私は父と口論しました。父は海の王のように傲慢でした。父は手を振り回し、私を強く叩きました。子供に何が分かるというのでしょう?毎晩、父が母の肖像画を見上げるたびに、私はこっそりとちらりと見て、父に腹を立てることができませんでした。あの人も海のように深い人だと分かっていたからです。母が亡くなると、父は玄関の右側に真水の入った壺を置きました。父は家族に、家に入る時は足を洗うように言い聞かせました。ある時、叔母が忘れてしまい、父に叱られました。叔母は黙って、汚れた足元を見つめていました。私は父の言うことをよく理解できないまま、言われた通りにしました。
ある日、父は私に網を投げる方法を教えた。シャツを脱ぎ捨て、逞しい胸板を露わにした。投げた糸は母の髪よりも滑らかだった。まるで心の中の恨みを全て捨て去り、白い泡のように立ち上る夜ごとの目覚めをも投げ捨てるかのように。
十代の頃、私の体は魂を抜かれた魚のように痩せ細っていました。父の教えはすぐに吸収しましたが、網を振り回す力はありませんでした。放浪の幻想が私の肩に重くのしかかっていました。父は何も言わず、ただその目に深い失望を浮かべていました。
私は幼い頃から、自分が海に属していないことを知っていました。子供の頃、海の夢は一度も見たことがなく、ただ白い馬の群れが私を山頂まで引っ張っていき、波の轟音から逃れさせてくれる夢ばかりでした。
村人たちは、母が夏のある日、イバラの草が生い茂る丘の上で私を産んだと話していた。太陽が頭上に昇り、イバラの草が風に揺れていた。その日、父は遠い海で漁をしていた。後になって、記憶を呼び起こす物語の中で、父はそれが人生で最も失敗した航海だったと語っていた。時折、私はその航海と自分の存在との繋がりを疑った。記憶の波は、父が名付けることのできない海を探し求めた。イバラの草の茂みの上で、私は大声で泣いた。私の体はイバラの草の花でいっぱいだった。それが、後に私の心もイバラで覆われるようになった理由だろうか。人生のある時点で立ち止まり、振り返ると、私に触れたすべての人が血を流していた。
***
叔母は昔ながらの仕事で忙しく帰ってきていた。午前中は雇われて魚を捌き、午後には戻ってきて魚醤を作っていた。父は相変わらず海で懸命に働いていた。
叔母が帰宅した時の食事も、いつもより上品で、エビとサバの煮込みが入ったアマランサススープが添えられていました。父はいつもよりたくさん食べました。初めて、父が叔母のために料理を買っているのを見ました。心が安らぎました。叔母に対する父の態度を見て、父が変わろうと懸命に努力してきたことが分かりました。食事を終えると、父は立ち上がり、干物の入った籠をひっくり返しに出かけました。ある日、叔母はそれを袋詰めにして市場に持ち込み、そこで売ったり、新鮮な肉を買ったりしていました。美味しい食事はいつまでも続くのです。叔母が「T、どう思う?」と尋ねた時、私はふと、ぼんやりとした考えから引き戻されました。その時、父の足跡は遠くまで届いていました。
「おばさん、私は相変わらずです。町に行って何か仕事を覚えようかな。」
「お父さんはどうですか?」
「あなたがここにいるともっと安心します」と私は答えました。
「つまり、お父さんは僕が海に留まることを望んでいるってことか。」
"知っている。"
彼女は黙っていた。
午後、空は珍しく晴れ渡っていた。父がかつて、これは嵐が近づいている兆しだと言ったのを思い出す。遠くでは、叔母と父が荒れた日に魚やエビを捕まえようと網を繕っていた。浮かぶ籠舟は人々の運命を担っていた。砂丘では、黄色い牛の群れが草原を遥か彼方へと引きずり、遊牧民たちは新天地を求めて人生を謳歌していた。人生のひととき、足音を愛でながら。夜になると、ベッドのフレームが優しく寝返りを打ち、きしむ音が聞こえた。竹の音、竹の音が眠りを呼び戻した。
「おばさん、これは何という嵐ですか?」
彼女は首を横に振り、覚えていないと言った。
***
「絵を描くことを学ぶために町に行きます。」
ある晴れた朝、私は父に言いました。
父は反対はしなかったが、悲しそうな目をしていた。「安定した人生を選びなさい、移り気な人生を送るな」と父は言った。
数週間後、私は美術の先生に不満があり、家に戻りました。先生が生徒全員に絵を描くときは裸になるように言ったとき、私は怒涛のように叫び、何十人もの目の前でイーゼルをひっくり返したのを覚えています。私は、先生がこの病的な要求の納得のいく理由を述べるのを待たずに、座礁した魚の群れのように私たちを裸にし、自由を求めてもがき苦しませたかったのです。先生は私の襟首をつかみ、「おい、すなぎの生き物たちよ、絵筆を取って私たちの世界に泳ぎなさい。おいT、お前たちの先祖は魚じゃなかったのか?」と怒鳴りました。私はギャラリーから走り出しました。私の後ろには魚の体を持つ人間の顔がありました。ナマズ、ボラ、ニベ…奇妙な名前がたくさんあり、私が区別できないというだけで父に怒られたことがありました。
この敗北はまるでバケツの冷水を浴びせられたようだった。
時には、ある人の失敗が別の人の喜びとなることがある。今回、私は父の願いに従い、海に出ることを学びました。少なくとも今は、美術教師の顔を思い浮かべると、安全な選択だと感じました。父は高らかに笑い、「この子はいい子だ」と言いました。叔母も父の喜びに微笑みました。何十年にも及ぶ海上経験を持つ父は、私に才能を授けてくれると信じていました。私にはまだ才能はありませんでしたが、災難は目の前に迫っていました。私は父の重い手を肩から離しました。「いや、教えてもらう必要はない」。父の表情が変わりました。「どういう意味だ?」先生を探すということは、家に帰れないということか。父は「わかった、いいよ」と言いました。父は私を解放してくれました。まるで、私が影を海に落とした午後のように。
コスモスの黄色い季節は過ぎましたが、私はまだ父の心の中に心配事や不安を抱えています。
「師の道を学ぶ」旅に出る私に、叔母が送別会を用意してくれました。食事は、イチジクの葉を添えた魚のサラダ、茹でたサツマイモの葉、そしてワインでした。季節外れのサツマイモの葉は口の中で苦く感じられました。
「明日出発するから、心配しないで、お父さんとおばさん。」
私が留守の間、家は何も変わっていなかった。枕はそれぞれのベッドに一つずつ置かれたまま、動いていなかった。今回は何も聞かなかったが、叔母は嵐が低気圧に消えて広範囲に雨が降るだろうと言った。早く寝るようにと言われた。私は安堵のため息をついた。
明日、私は家を出る。父は風よけに屋根を縛ってくれる。叔母は庭に駆け出して、残っていたひょうたんやカボチャを摘む。夜、私たち二人に残された唯一の夜は、願い事をする夜だ。願い事は私に多くの希望を与えてくれる。実際には、毎晩魚の群れが泳いでいるわけではない。父は今も壁を向いていて、反対側には叔母がいる。祭壇では、母が妖精のように優しく微笑んでいる。
***
私の先生の名前はクイでした。「クイ爺さんと呼んでくれ。私は誰にも教えたりしない。『先生』という言葉には重みがあるからね」と彼は言いました。そして続けました。「でもね、私の名前はクイだけど、生まれてこのかたずっと直立不動で、誰の前でも跪いたことがないんだ」。クイ爺さんはヤシの葉で葺いた茅葺き屋根の小屋に一人で住んでいて、家は海に面していました。初めて彼に会った時、彼は「家に帰れ」と言いました。私は理解できずに首を横に振りました。「坊や、君は海に向いていないんだ」と彼は言いました。「君の目は定まっていない。生まれてこのかた、魚が泳ぐのを見てきたのに、どうしても人が見えてしまうんだ」。私は長い間彼に懇願し、彼は渋々頷きました。「じゃあ、ここにいてくれ。誰かに付き添ってもらえるのは嬉しいよ」
彼が私に教えてくれた最初の教訓は、海のことではなかった。彼は立ち上がり、コンロの火をつけてハゼの鍋を温めた。胡椒を振りかけ、「かわいそうな恋煩いのハゼ」と呟いた。しばらくして、ワインボトルを手に彼が出てきた。雨はますます激しくなり、空は真っ暗になった。突然、風向きが変わり、雨粒が空高く舞い上がった。彼は手を伸ばして顔を拭き、物思いにふけるような目を浮かべた。今度は、むせそうにくすくす笑った。彼を見ていると、どれほどの夜を孤独に過ごし、悲しい思い出に人生を無駄にしてきたのか、想像もできなかった。
夜は薄暗く、風が強かった。老人は、どんな生き物にも、たとえ魚でさえも、声があると言った。それは彼が長年海で培ってきた経験だった。彼の話は、地球上で最も孤独なクジラの物語を思い出させた。仲間を必死に探していた孤独なクジラだ。
「人の声はたくさんある。だから、心も暗いんだ」彼は手をこすり、体を温めた。嗄れた声で言った。夜、老クイと共に広大な波間に横たわっていると、私の中の荒馬はますます大きくなった。明日もまた老クイと共に海へ行き、肩に網を担ぎ、遠い願いを紡ぐ。彼の影が消えた時、砂浜に残された彼の足跡を辿る。そして海に辿り着いた時、私は彼の名前を呼び始める。海には足跡がないのだから。
彼に出会った時、私はまるで長い飛行のために岩の上で休む嵐の鳥のようでした。家を離れたある夜、天使が叔母に赤ちゃんを授け、父が微笑んでいるのを夢で見ました。
私の中の野生の馬が、広大な草原を独り駆け抜けた。そして背後では、足跡一つないまま、とげとげした草が芽吹き始めた。
出典: https://thanhnien.vn/chiem-bao-bien-truyen-ngan-du-thi-cua-le-van-than-18525110816005123.htm




















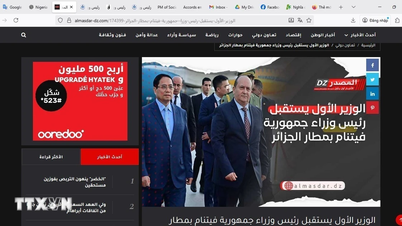






























































































コメント (0)