患者は21歳で、 ハノイの大学に通う学生です。3週間の集中治療の後、意識は回復し、循環停止にもかかわらず神経学的後遺症もなく、通常の生活に戻ることができます。
2月28日の夕方、少女は家庭教師の仕事を終えて帰宅途中、突然事故に遭いました。衝突事故で少女は重体となり、トゥオンティン地区病院(ハノイ)に緊急搬送され、その後中央病院に搬送されました。

バッチマイ病院の院長であるダオ・シュアン・コー准教授は、3週間の治療の後に命が救われた特殊な症例について報告した。
バクマイ病院では、少女は昏睡状態で救急室に搬送され、循環停止状態でした。医師は直ちに心肺蘇生を実施しました。少女は循環を再開し、すぐに手術室に搬送されました。
手術室で心臓専門医は患者の心臓が破裂し、約1.5kgの血栓と血液が除去されたことを発見しました。手術は緊急を要し、医師たちは手術中に10リットルの輸血をしなければなりませんでした。「学際的な連携が患者の命を救うのに役立ちました」と、Co准教授の博士は述べています。
患者の命を救うには、部門間の連携に加え、初期救急医療が重要です。 「患者が院外で治療を受け、一次救急医療が効果的であれば、患者を救うチャンスがあります」とコ准教授は述べています。
コ准教授は、A9救急センターがベトナム蘇生・毒物対策協会や蘇生部門と連携し、地域の多くの人々に院外救急訓練を提供して、残念ながら脳卒中や心停止、事故に遭った患者をより多く救えるようにすることを提案した。
日本、アメリカ、そして世界中の多くの国では、 医療従事者が心肺蘇生や応急処置の方法を知っているだけでなく、大学生も応急処置の訓練を受けています。応急処置の知識を持つ人が増えれば増えるほど、地域社会における事故の救命率が高まるでしょう。
[広告2]
ソース




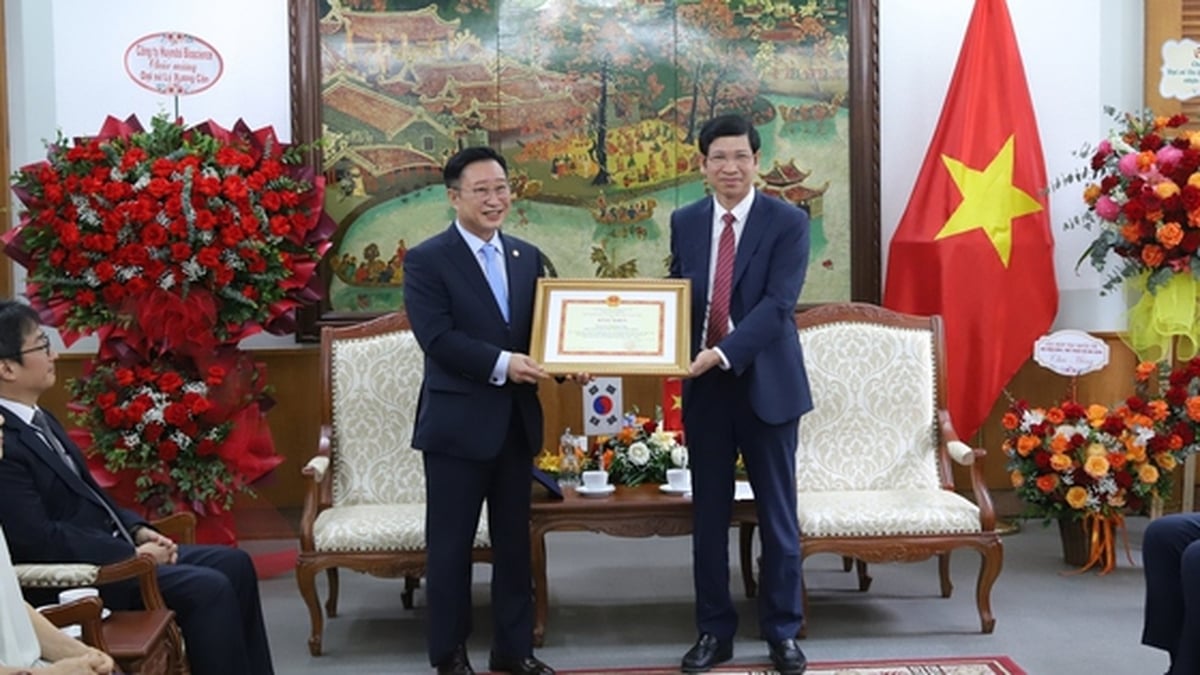



















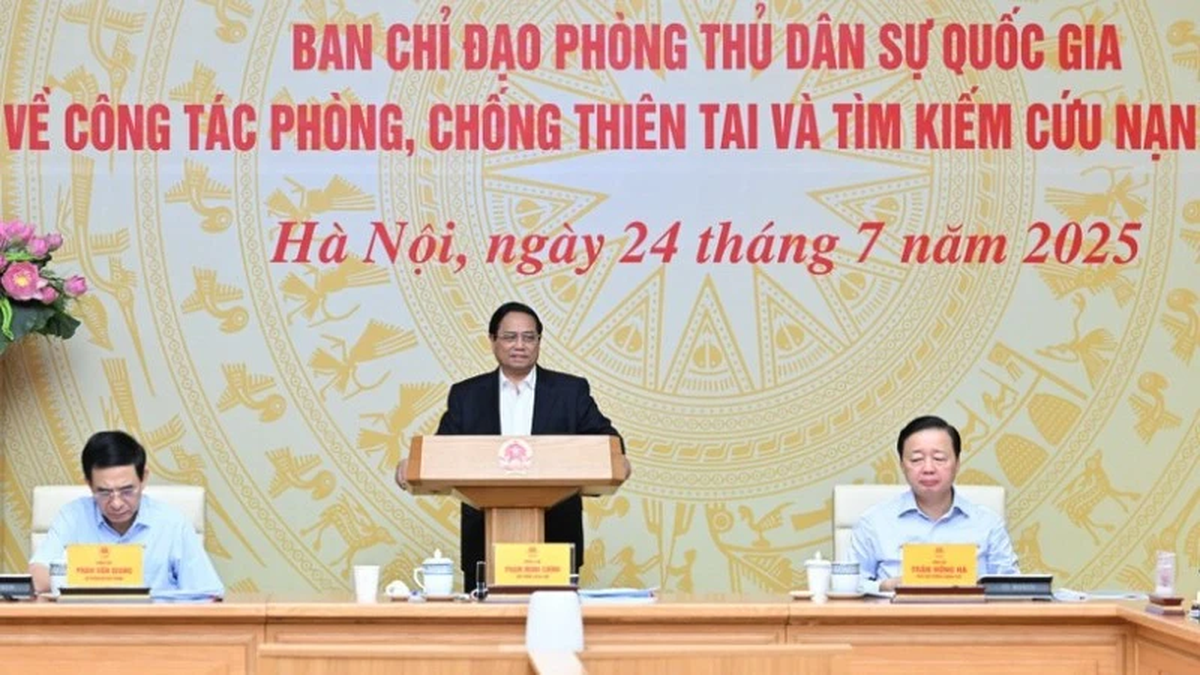






![[写真] ベトナムとセネガルの省庁、支部、地方自治体間の協力協定の調印](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/7/24/6147c654b0ae4f2793188e982e272651)








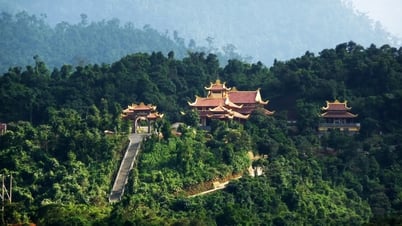

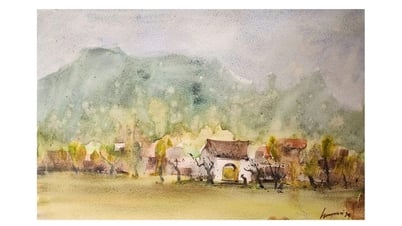












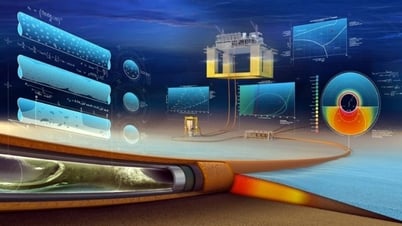





















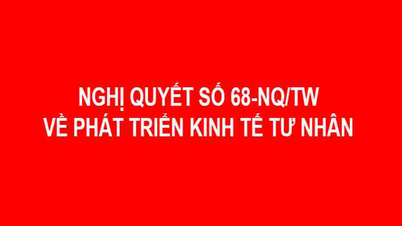










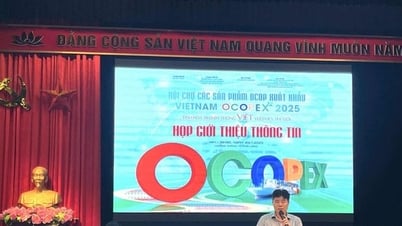












コメント (0)