革命に同調した知識青年層は、共産党の誕生と八月革命の勝利の決定的な要因となった。ベトナム民主共和国の誕生に伴い、抵抗戦争に参加する有能な人材を発掘・選抜するため、 ホー・チ・ミン主席は指令(1946年11月20日)を発布した。この指令には、「国を建設する必要があり、建設には有能な人材が必要である…地方は、有能で高潔な人材がいる場所を直ちに調査し、政府に報告しなければならない」と明記されていた。
ホー・チ・ミンは、才能の大きさに関わらず、才能を尊重した。「大きな仕事には大きな才能を、小さな仕事には小さな才能を活用する。能力のある人材を、その仕事に投入する。そのような人材をどのように活用するかを知っていれば、幹部不足に悩むことはない」。ホー・チ・ミンは、才能とは「徳と才能という二つの要素の融合を必要とする」と考えていた。彼は「徳のない才能は役に立たず、徳があっても才能がなければ何もできない」と信じていた。ホー・チ・ミンの思想における才能の概念は、「才能は知性と洞察力に表れ、同時に心と密接に結びついている必要がある」というものだ。心とは、忠誠心、献身、勤勉、質素、正直、公平であり、公共の利益のために私利を犠牲にすることを知る徳である。才能は理解の資本であり、実践によって鍛えられた科学的知識である。

ホー・チ・ミンの人材観は非常に具体的かつ実践的だった。彼は「人を木材のように使う」「才能に応じて使い、適材適所で巧みに活用する」と述べた。1945年の8月革命後、彼はグエン朝とチャン・チョン・キム政権の官僚、そして国内外のベトナム知識人を革命に引き入れることを提唱した。その中には、大臣ブイ・バン・ドアン、帝国長官ファン・ケ・トアイ、事務総長ファム・カック・ホエ、青年大臣ファン・アイン、ハドン・ホー・ダック・ジエム知事などが含まれる。
1945年8月28日に樹立された臨時政府には15人がおり、そのうちベトミン出身者はわずか6人で、残りは経済大臣のグエン・マイン・ハ、運輸公共事業大臣のドアン・チョン・キム、救済社会問題大臣のグエン・ヴァン・トー、青年大臣のズオン・ドゥック・ヒエンなど、党やベトミン戦線に属さない知識人だった。1946年3月までに抵抗連合政府が樹立され、10の省が置かれ、ベト・クオックとベト・カッチの2つの党が4つの省を占め、内務省と国防省という2つの重要な省は、どちらも党員ではない大臣が務めた。
1946年11月、ベト・カチ党とベト・クオック党の代表が撤退すると、ホー・チ・ミン主席は国会から新政府の樹立を承認された。彼は依然として「国民統一の政府であり、超党派の人材を集めなければならない」と主張した。平和が回復した後(1954年)、政府はグエン・ヴァン・フエン、ファン・アイン、ギエム・スアン・イェム、チャン・ダン・コアといった党外の知識人を大臣として擁していた。ホー・チ・ミンはまた、ホー・ダック・ディ、トン・タット・トゥン、チャン・フー・トゥオック、チャン・ダイ・ギアなど、多くの海外の知識人を医療、教育、司法、科学技術の要職に招聘した。抗日戦争中も、彼は優秀な若者を選抜して海外留学させることを提唱し、同時に国内に大学を開設して人材育成に努めた。
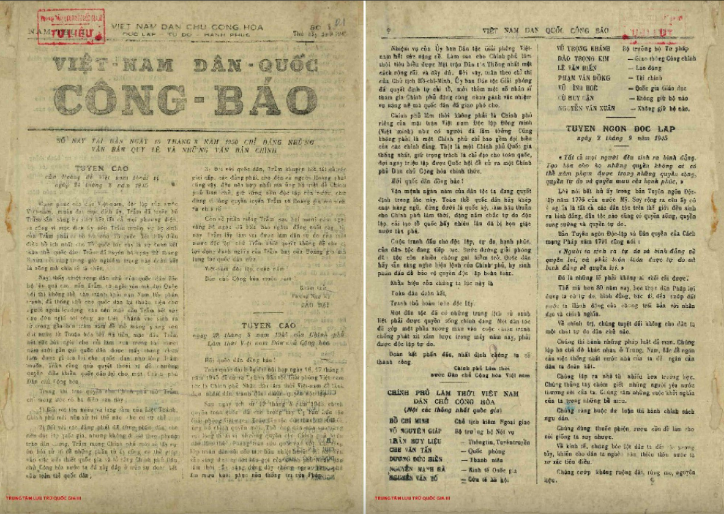
ホー・チ・ミンは革命活動において、その輝かしい徳と深い叡智によって、数え切れないほどの知識人の心を掴み、革命の道を歩み、祖国に奉仕する道へと導きました。ホー・チ・ミン自身も犠牲の模範となり、名利を顧みず、生涯をかけて祖国と人民のために献身しました。ホー・チ・ミンは愛国心を喚起し、知識人や才能を結集させ、彼らを愛国心に引き寄せる旗印となりました。そのおかげで、ベトナムの知識人社会は強力な力となり、全人民を団結させて民族の独立を勝ち取り、強大で繁栄した祖国を築くという大業に重要な貢献を果たしました。
我が党は、ホー・チミンの人材発掘・獲得という理念を継承し、革新事業において、この問題に関する多くの政策、決議、結論を発表してきました。「社会主義移行期における国家建設綱領」(1991年)は、人材は国家と人民の貴重な財産であるだけでなく、国家建設、発展、そして国際統合事業においても中心的な役割を果たすと明確に述べています。1997年6月18日付中央執行委員会第8期決議第03-NQ/TW号「国家の工業化・近代化推進期における幹部戦略について」は、「人材の発掘、育成、育成に特に重点を置く」と規定しました。第10回党大会の文書は、「党内外を問わず、人材を発掘・育成し、重要な分野に人材を引きつける政策を実施する」ことを強調しました。第11回党大会においても、党は「国の人材のための特別な政策がある」と強調しました。 2018年5月19日付決議第26-NQ/TW号は、「任務に見合う十分な資質、能力、威信を備えた、各レベル、特に戦略レベルにおける幹部部隊の育成に重点を置くことについて」と定め、「党員・非党員、国内外のベトナム人を区別することなく、人材の誘致・育成に関する国家戦略を構築する」としている。第13回党大会では、この視点が党大会決議においても引き続き強調された。「人材を誘致し、有効活用するための画期的なメカニズムを確立する…革新と創造性を促進し、国の急速かつ持続可能な発展のための新たな原動力を生み出す」。我が党は、社会主義祖国の建設と防衛という事業における人材の役割、そして人材の誘致と活用を深く認識していると言える。
重要なのは、人材を評価する意識を革新することです。ホー・チ・ミンは「人材を巧みに活用する」と指摘しました。これは、国家と人民の利益を第一に考えるという一貫した視点に基づき、具体的な倫理基準と人材基準を数値化するだけでなく、真に公平で、人事業務や市場メカニズムにおける幹部の評価について革新的な思考を持つ必要があることを意味します。「ロビー活動」「ごまかし」「地位や名声の買収」「集団の利益」など、現実離れした手段による人材の不当な評価には注意が必要です。
才能は自然に生まれるものではありません。なぜなら「完璧な人間などいない」からです。すべての人に必ず良いところと悪いところ、善と悪があります。人は皆、個性があり、それぞれに価値があります。ですから、才能を真に求め、育成するためには、「賢明な視点、寛容な心」を持ち、才能を評価し、公益のために献身的に育成する方法を知らなければなりません。優秀な人材を発掘し、訓練し、育成し、実践で鍛え、合理的で適時かつ科学的な仕事を割り当て、真に民主的で敬意を払い、彼らが働き、貢献できる環境を作らなければなりません。才能を評価し、条件を整え、教育することで、彼らの能力を伸ばし、新しいものを創造する方法を知りましょう。公平さと民主主義があって初めて、革新と創造性が生まれ、才能を育成することができます。考え、創造し、貢献するための環境と条件があって初めて、才能は開花します。
豊かな国づくりの実現には、優秀な人材を発掘し、育成し、結集することが不可欠です。人材を引きつけ、活用する仕組みがなく、嫉妬や競争心から人材が流出し、「人材が枯渇」してしまうのは、国にとって損失であり、無駄です。刷新政策の実施においては、真に効果的な政策メカニズムの構築に細心の注意を払い、あらゆるレベル、あらゆる分野、あらゆる分野の人材を育成、育成、引きつけ、活用することを十分に意識する必要があります。幹部選抜プロセスの実施には特別な規定を設けるべきです。これは、ホーチミン主席が願った「世界の列強と肩を並べる」という民族独立と社会主義の目標の実現に向けて、国を繁栄へと発展させるための幹部チームを構築する上で、最も実現可能かつ必要な道です。
[広告2]
ソース
























![[写真] ベトナムとセネガルの省庁、支部、地方自治体間の協力協定の調印](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/7/24/6147c654b0ae4f2793188e982e272651)




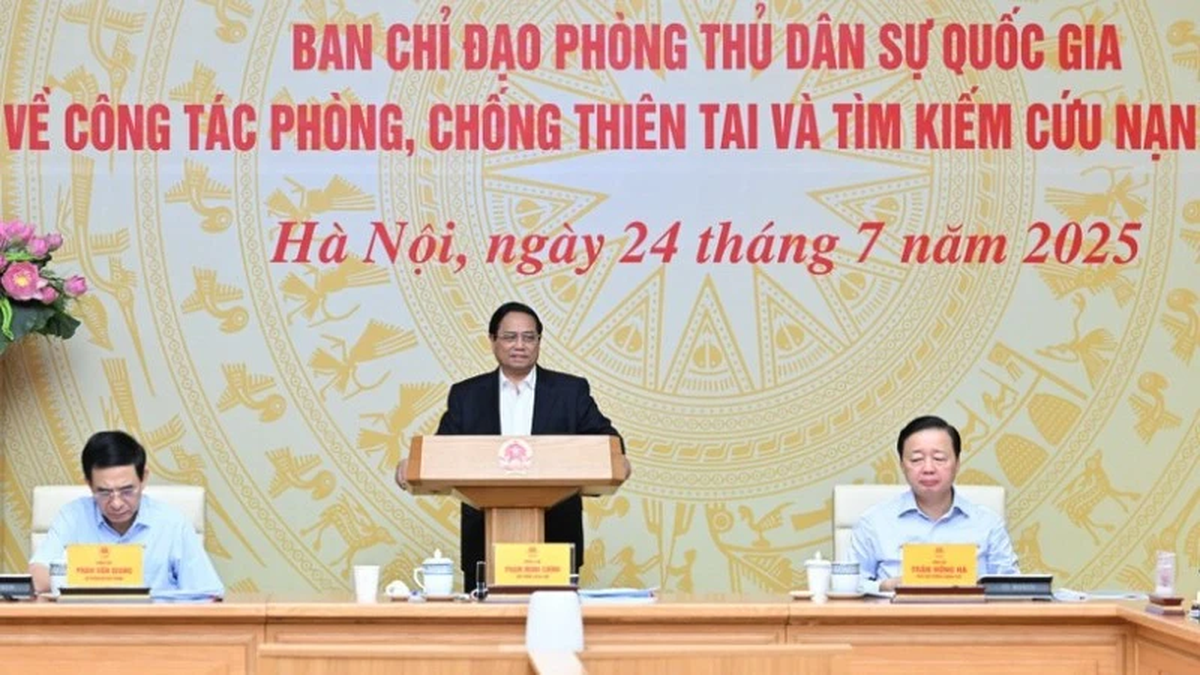















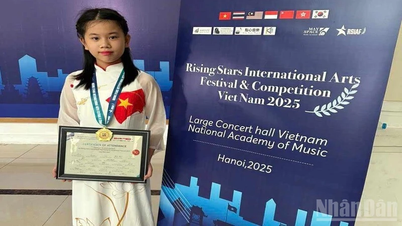












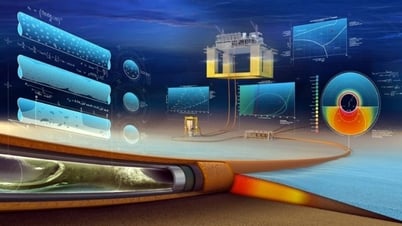











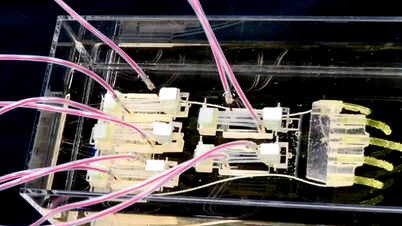



























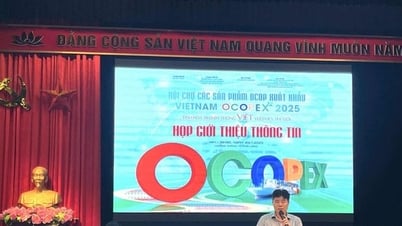





コメント (0)