TPO - ドイツの考古学者らが、第二次世界大戦中に破壊されたドイツ国内の掩蔽壕の跡から、珍しい17世紀の日本の侍の刀を発掘した。
アイデア
 |
修復後の脇差。(写真:©ベルリン国立博物館、世界遺産博物館) |
ベルリン最古の広場、モルケンマルクトの発掘調査中に、研究チームはひどく腐食した脇差(わきざし)を発見した。当初、考古学者たちはこの武器を軍刀と考えていたが、その後の分析で、この刀は日本の江戸時代(1603~1868年)のものであることが明らかになった。ベルリン国立博物館の先史・古代史博物館の翻訳された声明によると、刀身はさらに古く、おそらく16世紀にまで遡る可能性がある。考古学者たちは、この刀は1800年代に外交使節としてドイツに持ち込まれた可能性があると述べている。
 |
日本の七福神の1人である大黒様の拡大図。槌(右)と米俵(左)を持っています。 (写真: © Staachliche Museen zu Berlin, Museum für Vor- und Frühgeschichte / Anica Kelp) |
「日本が鎖国し、ヨーロッパからの訪問者がほとんどいなかった時代に、これほど長く使用され、豪華に装飾された武器がベルリンで発見されるとは誰が想像したでしょうか?」とベルリンの考古学者で先史・初期歴史博物館館長のマティアス・ヴェムホフ氏は語った。
ベルリン州立記念物局の考古学者たちは、2022年冬、第二次世界大戦中に破壊され、1960年代に道路や交差点に置き換えられたモルケンマルクト地区の住宅や商業ビルの地下室を発掘中に、この日本刀を発見した。声明によると、地下室には以前、戦争終結時に廃棄された手綱、あぶみ、縁石、手綱など、戦争関連の遺物で満たされていたという。しかし、地下室の一つで日本刀が発見されたことは予想外だった。
修復作業の結果、この武器は脇差の一部であることが判明した。脇差はかつて社会的地位を示す武器として高官のみが所持していた刀である、とウェムホフ氏は述べた。歴史的に、脇差は侍が予備の武器として携帯していた。狭い部屋や標的に近い場所で戦う場合など、刀と呼ばれる長い刀を抜くのが難しい場合に備えてだ。大英博物館によると、脇差は「相棒刀」とも呼ばれ、侍階級の人々が常に身に着けていたという。
新たに発見された木製の柄は熱による損傷を受けていたが、木片と刀身を覆う布は保存されていたと声明は述べている。さらに修復を進めたところ、刀身近くの柄の根元に、幅1センチほどの金属製の輪またはリングが発見された。この輪には、槌と米俵で識別される七福神の一人、大黒様が描かれていた。
調査チームはまた、柄に菊花文様の装飾と透かし模様が損傷していることを発見した。刀の意匠から、江戸時代のものと推定される。
博物館関係者は、柄がオリジナルではないため、刀身は江戸時代よりも古く、おそらく1500年代のものである可能性があると記している。
剣がどのようにしてベルリンに渡ったのかは不明だが、ヴェムホフはいくつかの考えを持っていた。
「おそらくこの刀は、1862年の竹内使節団、あるいはその11年後に行われた岩倉使節団から贈られたものでしょう。彼らはヨーロッパやその他の西洋諸国を訪れ、関係を築き、印象を残した日本の大使たちでした」と彼は述べた。「モルケンマルクト広場とベルリン宮殿周辺の貴族の宮殿との空間的な近接性が、このことを示唆しています。」
ドイツ皇帝ヴィルヘルム1世は、皇帝在位中、竹内使節団の日本代表団を宮殿で迎えました。1873年に即位したヴィルヘルム1世は、岩倉使節団の代表団を接見しました。しかし、第二次世界大戦中にモルケンマルクトに捨てられた剣がどのようにして入手されたのかは不明です。
ライブサイエンスによると
[広告2]
出典: https://tienphong.vn/khai-quat-duoc-thanh-kiem-long-lay-tu-thoi-edo-nhat-ban-post1668542.tpo









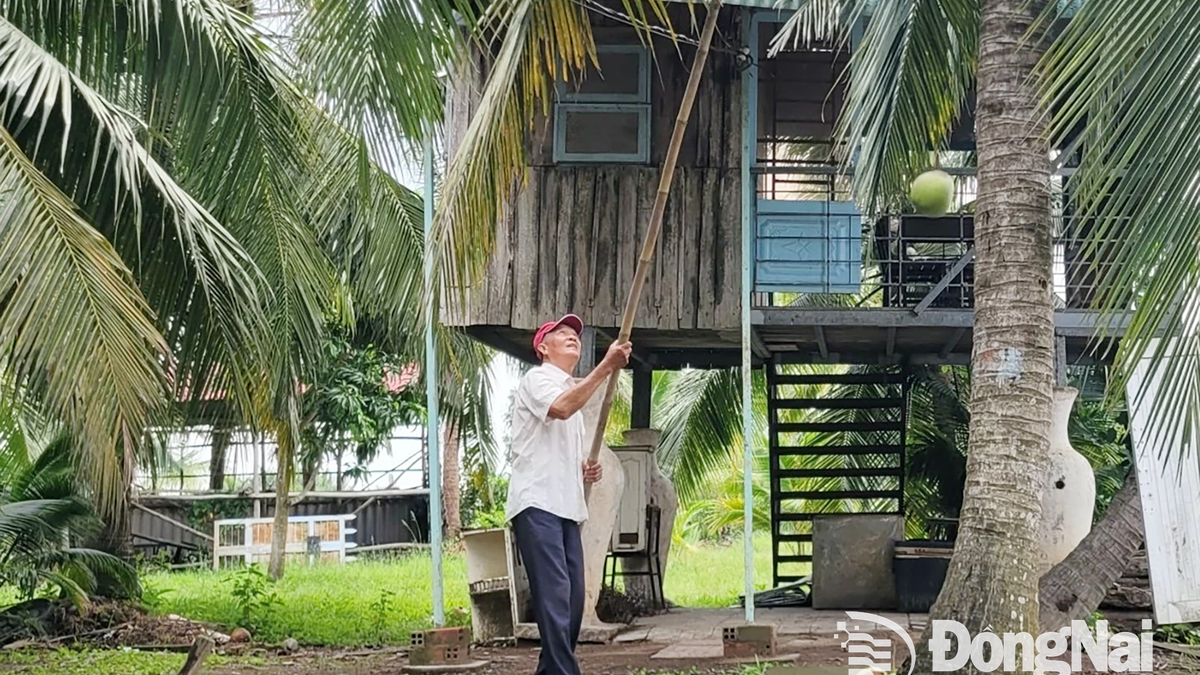



































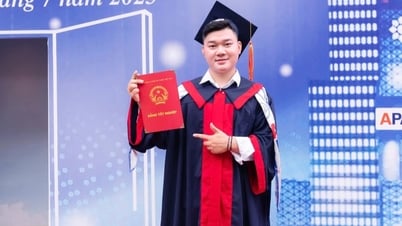




















































コメント (0)