 |
| イラスト:ファン・ニャン |
ラムはドアを押し開け、新しいアパートに入った。いや、正確には、新しいアパートだ。10年以上も愛着を持っていた場所を出て…
新しい住まいは古い家で、家主は彼女の希望通り、古いピンクのペンキの上に翡翠色のペンキを塗り重ねていた。家は空っぽだった。しかし、目に見えるものも見えないものも、見張っているものも一人もいなかった。そしてもちろん、家具や家財道具で溢れかえっている家が空っぽだという意味ではない。ラムのような繊細な女性にとって最も恐ろしいのは、物、家財道具、そしてたくさんの人で溢れかえる家の中で、常に空虚感と孤独感を味わうことだった。触れるものすべてが自分のものではなく、誰とも分かち合えないように感じられたのだ。
「あらまあ、ドアを優しく閉めて。耐久性は使い方次第よ。あなたのような使い方は壊すのと同じよ」――夕食を急いで作ろうと冷蔵庫を急いで閉めたとき、フンはサッカーを見ながらそう言った。声は柔らかかったが、まるでシューという音のように聞こえた。ラムはご飯をカスカスのように平らげた。
「私が使っているものって全部丈夫だと思う?私のスマホは5年間、傷一つつかず、一度も落としたこともない。もしあなたが子供に持たせて落とさせているなら、無駄にしないために石でできたスマホを買った方がいいわ。」
まあ、人それぞれ個性があるんだから、目を閉じて一緒に暮らしてもいい。邪魔をする第三者なんていない。愛する者も、夫か妻以外に考える者もいない。喧嘩なんて一度もない…。そんなある日、彼女は毎日、毎日、隠れた波動と共に暮らしているうちに、自分がこんなにも変わってしまったことに気づいた。一番大きな隠れた波動は、クリスマスイブに親友をワインセラーに誘った日だった。結婚して10年以上経った今、彼女は夫にクリスマスを祝ってどこかへ行こうと誘っていた。ただ外に出て、人々が行き交う様子を眺め、温かい雰囲気を少しでも味わい、きらめくイルミネーションの灯りを眺め、短くざわめく着信音に耳を傾けるだけだった。「正気じゃないの?こんなに寒いのに、こんな渋滞なのに、家で楽しく過ごして。埃や煙の匂いを嗅ぎながら押し合いへし合いしたり、お互いにオナラをしたり、詐欺師に頭を突き出してぼったくられたり、駐車違反切符の料金が5倍になったりするより。」
洪から十回近く電話を受けた後、彼女は酔って帰宅した。子供はすでに寝ていた。ラムは必死に起き上がろうとしたが、寝室に上がることができず、リビングに倒れ込んだ。リビングの娘のピアノの横で、彼女は丸くなって横たわった。寒くて、マットも毛布もない。突然、橋や深夜のポーチを通り過ぎた時のことを思い出して悲しくなった。そこでホームレスの人々が暖を取ろうと身を寄せ合っていた。毛布があればあげられたのに、と彼女は思った。そして、家に帰って暖かい毛布にくるまると、罪悪感に苛まれた。それでも、ラムのルームメイトたちは寒さに丸まっている彼女を見て、無関心に通り過ぎていった。壁一枚で隔てられているだけなのに、まるで二つのオアシスのように遠く離れていた。
あの冬の夜を境に、ラムは人の違いは思いやりにあると痛感した。フンは家族への思いやりさえなく、彼が変わるのを待つのは空から星を拾うほど難しかった。彼女はいわゆる「家」から抜け出すことを決意した。互いに声を荒げることもなく、多くの人々の目には幸せと映る場所。
「なぜ昔はお父さんを選んだの?」母と娘が新居のカーテンを取り付けているときに、ニさんは尋ねました。
- 母は父が几帳面で、現実的で、人生経験豊富だと思っている。父には、母のようなロマンチックな23歳にはない多くの長所がある。
「お母さん、それは利点じゃないと思うわ!少しなら利点になることもあるし、やりすぎは刑務所の看守と変わらないわ。でも、ロマンチックな人は花や草と共に生きるべきよ、刑務所を選ぶべきじゃないってことを覚えておいて!」14歳の少女は微笑んだ。ラムはくすくす笑いながら我が子を見ていた。ニは知らないうちに成長していたのだ。
* * *
ヴァンは新しいアパートのバルコニーにジャスミンの苗を植えた。何年も経った今でも、ヴァンはラムのジャスミンへの情熱的な愛情を今でも覚えている。ラムの実家の小さなバルコニーには小さな花があり、そこで育てていたのはジャスミンだけだった。花が咲くたびに、朝、友達が学校に行くのを待つヴァンの周りはジャスミンの香りで満たされていた。ヴァンはそれでも不思議に思った。たとえそれがFacebookにさりげなく書き込まれた数行の文章であっても、ラムに予期せぬ出来事が起こるのをいつも感じていたからだ。この強い女性はFacebookで私生活について決して触れなかった。触れる時は、夕方に孤独な小鳥を描いた絵を添えた。ヴァンはそれだけでラムを理解し、胸が痛むほど愛することができた。何年も離れて暮らしていたにもかかわらず、友人たちの目には、ヴァンは常に女性に無関心な人物に映っていた。
ヴァンがラムと結婚したいと思っていた時期がありました。大学受験を終えたばかりの頃で、二人は暇を持て余すことが多く、ヴァンの小さな庭で何時間も座って語り合ったものです。ヴァンの家には小さな池があり、熟した真っ赤なイチゴが水面に揺れていました。幼いラムは目を細めながら、子供の頃にイチゴを盗んだこと、池に落ちたこと、犬に追いかけられたことなどをヴァンに話しました。ヴァンは座って塩と唐辛子をすりつぶし、ラムにつけるイチゴを漬けました。イチゴは熟して、カリカリとしていて、歯ごたえのあるものでなければなりませんでした。唐辛子はほんの少し辛く、ラムは塩の入ったボウルの中の鮮やかな色の唐辛子を見るのが好きでしたが、辛いものは苦手でした。ラムは目を細めましたが、それでも歯並びの悪い歯を見せながら微笑みました。そして二人は、木や花のある小さな家の夢を語り合いました。
- 私の家族には庭がありませんが、私は庭が大好きです。今のように近所に住んでいるなら、庭の手入れを忘れずに。あなたの庭を見に行きますよ。ジャスミンと蓮を植えて、見せてあげてくださいね。グレープフルーツの木があれば、さらに素敵になります。祖父の庭の隅のように、毎年春にとてもいい香りがするんです。あの香りが大好きです!
当時、ヴァンもラムもどちらを愛しているのかわからなかったが、なぜかヴァンの心の中にラムとの結婚の考えが浮かんだ。ヴァンは池のほとりにジャスミンの花を植え、水面に蓮の花を落とし、ラムが指差す庭の片隅にグレープフルーツの木を植えることさえ想像した。ラムは時々立ち寄るのではなく、むしろその庭の主人になりたいと思った。
ラムはサイゴンで、 ハノイで文学を学ぶことを選んだが、愛を告白する機会もなく、ロマンチックな少女は恋人がいると自慢していた。恋人がいたのに、彼を去った。いや、正確に言うと、恋人が去ったのだ。「彼のことは忘れて、私を愛して。絶対にあなたを離れないと約束する!」ヴァンはラムの手をしっかりと握り、彼女の目をまっすぐに見つめた。「おかしい!」ラムはそう言って大声で笑った。彼女は友人の肩に頭を預けた。「恋人は私を去るわ。永遠に続く愛なんてないわ。でも親友はそうじゃないのよ、友よ。そういう風に、時々私が疲れたときは、あなたに寄りかからせて。」ラムはそんな瞬間に支えが必要だった。庭のその片隅は平和だったが、手を握って頭をもたせただけでは愛にはならなかった。
ヴァンはオーストラリアへの奨学金を獲得しました。出発当日、彼はこう言いました。
学校を卒業したら、あなたと結婚するために戻ってきます。待っていてくれますか?
- いいえ、私は愛する人としか結婚しません。あなたは私の親友であって、恋人ではありません。
ラムはその後、ヴァンに喜びを分かち合うために結婚写真を送るまで、さらに何度か恋愛を経験しました。ヴァンは初めて、時折耳にする歌のように、自分の心が砕け散っていくのを感じました。ヴァンは彼女を奇妙に感じました。どうしてこんなに多くの人を愛しているのに、自分を愛してくれないのでしょうか?愛には必ず理由があり、この世のいかなる理由にも基づいていないのでしょうか?
ヴァンの生活は勉強と仕事ばかりで、ラムが結婚して以来、恋愛のことなど考えることもなくなり、二人の会話にも見えない壁ができていた。時折、昔の庭について話している時、ヴァンは40代に差し掛かる彼女の声に、18歳や20歳の頃と同じような純粋な興奮を読み取ることさえできなかった。
だが、ヴァン自身はとっくの昔にあの時代を去り、二度と戻ることはできない。
- 大丈夫ですか、ラム?
ヴァンは今回、いつもの「大丈夫ですか?」ではなく、直接尋ねることを選んだ。
- いいえ、大丈夫です!
― 長年仲良しだったんだから、君が言いたいことを何でも言うようにさせるほど私はバカじゃない。もう私と分かち合いたくないの?
- ない…
- 私の肩が必要ですか?
― あなたはとても遠くにいるから、私には届かない。私もとても遠くにいるのに、まだ昔のことなの?
ヴァンは長年の安定した海外勤務を経て、キャリアをスタートさせる地としてサイゴンを選んだ。何度も故郷を懐かしみ、すべてを捨てて故郷に戻りたいと思ったが、異国の地で長年学び、キャリアを築いてきたことを後悔した。これまでの功績を捨てて帰国するほどの大きな理由はなかった。漠然とした数行の約束、そして孤独な小鳥の絵を描いただけで、多くの友人を困惑させながらも、彼は全てをうまくまとめることができた。ラムが頼れる肩が必要な時は必ず戻ってくると分かっていたのはヴァンだけだった。そして、それこそが彼が長年望んでいたことだったのだ。
* * *
ヴァンは、別れた後、彼女が以前より控えめになったことに気づいた。何かに満足した時、無邪気に彼の肩を叩くような癖はもうなかった。笑っても瞳が輝かなくなり、夕暮れ時に残された午後の陽光のように、時折キラキラと輝くだけになった。
ラムは時折、ヴァンの後ろ姿を見て、密かにため息をつき、感情を抑えようとしていた。ヴァンは何年も経った今でも、彼女が好んでいた植物や花のことを覚えていた。その間、彼女は忙しさに追われ、憂鬱な日々が続き、自分の趣味さえ忘れかけていた時期もあった。
「もし田舎にいたら、自由に庭を作れるのに。あなたは長い間田舎に戻っていないし、昔の庭にも行ったことがないから、わからないでしょう。ジャスミンの花を一列、蓮池の片隅、そしてグレープフルーツの木を2本植えました。ここでは、ちょっとした彩りのために観賞用の蓮とジャスミンしか植えられませんが、ラム、アパートでグレープフルーツを育てようとしても無理ですよ!」
ヴァンの後悔の表情を見て、ラムは思わず笑い出した。彼はバルコニーの隅にある小さな陶器の鉢に蓮を植えるのを手伝っていた。彼女は突然こぼれた涙を隠すように、顔を背けるふりをした。何十年もの間、ラムは自分の欲望や好みを満たすことさえできず、ましてや誰かに甘やかされることなど考えられないことに慣れてしまっていた。
― 戻れる庭があるなんて、本当に幸運ですね。でも、自分が好きな植物、あるいは多くの人が好きな植物をたくさん植えるべきです。いつか誰かが庭に来て、なぜこの花やあの花を植えたのかを知り、悲しむでしょう。
- そんなことはどうでもいいわ。ただ、いつかラムがあの庭に居てくれることを願っているだけ。それに、あの植物は気にしないでしょ?
ラムは、自分を物欲しそうに見つめるヴァンの視線を避けた。昨夜、ニが言った。「お母さん、あなたは小さい頃からずっと植物を育てる庭を夢見ていたのに、一度も実現できなかった。でも、ヴァンおじさんはもう庭になっているのよ」
春の庭には季節外れの蓮が咲いています。
ソース



























































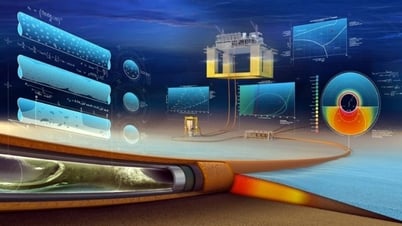






































コメント (0)