肺魚は地球上で3億9000万年もの間存在し、長期間の暑さと干ばつの期間を生き延びるために特別な冬眠機構を進化させてきた。

肺魚は4年間も飲食せずに生き続けることができる。写真: Futurism
コートジボワールのバンダマ川の水面に広がる波紋は、昆虫を捕らえる代わりに呼吸するために水面に浮かび上がる斑点のある生物から放射状に広がっている。これは西アフリカ産の肺魚だが、オックスフォード・サイエンティスト誌によると、アフリカには他に3種の肺魚が分布しているという。
体長1メートル、ウナギのような姿をした肺魚は、まだら模様の皮膚とオリーブブラウンの鱗のコントラストが美しく、水中と陸上の境界で生活しています。一対の肺を持つ肺魚は、鰓から十分な酸素を供給できないため、頻繁に水面に浮上して酸素を摂取する必要があります。他の魚とは異なり、肺魚は乾季に川が干上がっても生き延びることができます。
他の魚が狭い池に逃げ込んだり回遊したりするのに対し、アフリカハイギョは乾いた川底に潜り込みます。そこで彼らは体をぬるぬるした繭で包み、口だけが入る隙間を空け、空気呼吸をしながら、何ヶ月も、時には4年間も、水も食料もなしで生き延びることができます。これは冬眠と呼ばれ、高温で乾燥した環境に耐えるために、身体活動と代謝を停止する状態です。
冬眠は熱帯動物によく見られる習性です。ビクトリア朝時代の博物学者たちは、アフリカハイギョの生理学的特徴を観察するため、地球の反対側にあるイギリスとアメリカへ輸送することに成功しました。それ以来、技術の進歩により、ハイギョの冬眠の細胞・遺伝学的プロセスが解明されてきました。陸上を移動するための脚を持たず、水が枯渇すると他の環境から切り離されるアフリカハイギョは、水が戻るまで泥の中で休眠するように進化してきました。
冬眠の第一段階である誘導は、その後数ヶ月間を地下で過ごすための準備となります。1986年、研究者たちは冬眠を誘発する一連のシグナルとして、脱水、空腹、空気呼吸の増加、ストレスなどを挙げました。さらに、周囲の水における塩分濃度や溶解性化合物(カルシウムやマグネシウムなど)の組成の変化は、川の水が干上がっていることを示すシグナルとなります。鰓は魚の体内の水分量を感知する役割を果たしている可能性があります。
周囲の環境が温暖化し乾燥している兆候が見られると、肺魚は口と筋肉質の体を使って泥の中に潜ります。そして巣穴に引きこもり、長い体を丸めて、分泌された厚い粘液の層で体を覆います。粘液は固まると防水性の繭を形成し、水面との隙間はわずかしかなく、肺を通して空気を呼吸することができます。
遺伝子解析により、遺伝子活性の上昇により脳内のホルモンシグナル伝達レベルが上昇していることが明らかになりました。代謝停止は維持期に起こり、粘液繭が乾燥するとすぐに始まります。酸素の摂取は肺のみから行われ、水中で活動する肺魚と比較して酸素消費量は半分に減少します。これらの変化は、代謝活動の急激な低下、心拍数(通常は毎分25回)から毎分2回への低下、そしてアンモニア産生の停止を伴います。腸、腎臓、心臓など、多くの身体系に変化が見られ、冬眠中の機能低下を反映しています。肺魚にとって、体内貯蔵は唯一のエネルギー源です。
雨季に肺魚の腸、腎臓、生殖腺に蓄積する大量の顆粒球(免疫系に重要な白血球)も、夏の退避行動に関与している。2021年にScience誌に掲載された研究では、粘液嚢が顆粒球で満たされていることが明らかになった。顆粒球は冬眠中の肺魚への病原体の到達を阻止する。顆粒球は内臓の貯蔵部位から血流を介して皮膚へと移動し、粘液嚢内での移動を完了する前に炎症状態に入る。そこで顆粒球は細胞外トラップを形成し、冬眠中の肺魚への細菌の到達を阻止することで、粘液嚢を免疫状態にする。
やがて水が戻り、肺魚は粘液の繭に覆われていない唯一の体の部分である口に水が満たされ、冬眠から目覚めます。こうして冬眠の覚醒期が始まります。これは3つの時期の中で最も神秘的な時期でもあります。繭から這い出し、ゆっくりと水面に浮上してきた肺魚は、冬眠中に蓄積した老廃物を排泄します。約10日後、内臓が再起動すると、肺魚は再び摂食を始めます。
アフリカ肺魚は3億9000万年の間、ほとんど姿を変えずに生息しており、デボン紀にまで遡る穿孔肺魚の化石も発見されています。しかし、人間の活動による壊滅的な被害に直面しています。例えば、ビクトリア湖流域では、乱獲と農業による湿地の劣化と消失により、マダラ肺魚の個体数がわずか5年で11%減少しました。
アン・カン(オックスフォード・サイエンティスト誌による)
[広告2]
ソースリンク






















































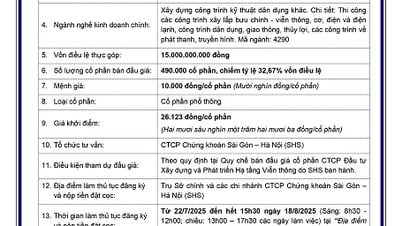












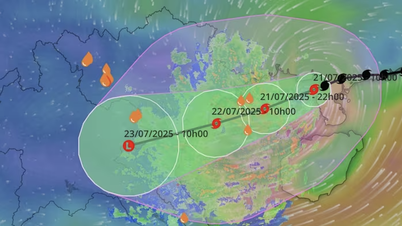





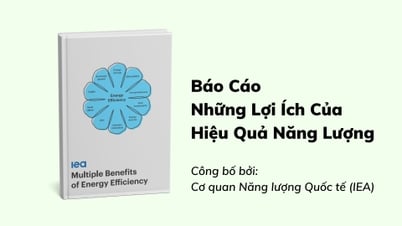





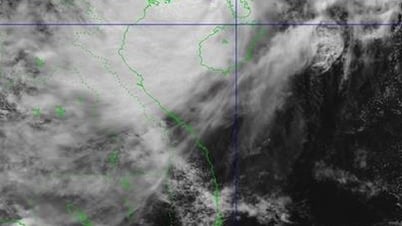





















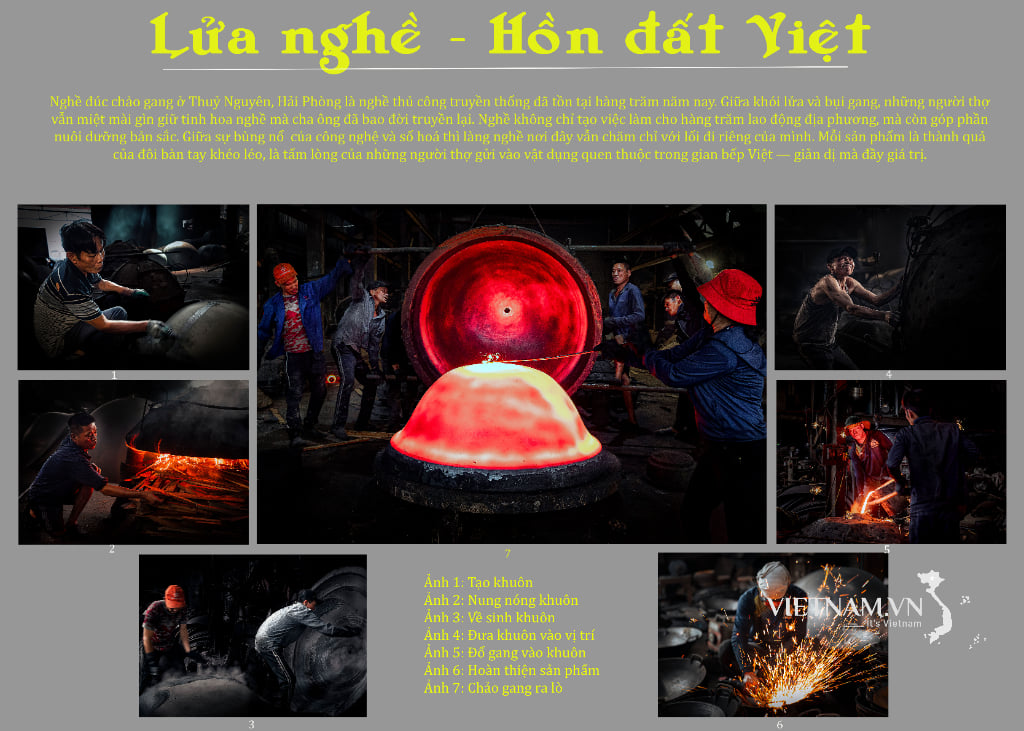

コメント (0)