これは、最近ダナン市でベトナム社会科学アカデミー、中部地域社会科学研究所、ダナン市科学技術局が共催したワークショップ「ベトナムの海洋経済発展 - 現状と提起された課題」で多くの科学者が発表した情報である。
ワークショップで発表された情報の中で、気候変動の状況におけるベトナムの沿岸住民の生活に関する研究結果を発表したハ・ティ・ホン・ヴァン博士(ベトナム社会科学アカデミー分析予測センター)の意見は注目に値する。
ハ・ティ・ホン・ヴァン博士は、2016年から2020年までの期間の気候変動の影響下にあるベトナムの沿岸住民の生活活動を体系的かつ全体的に評価および分析し、クアンニン省、 クアンナム省、カマウ省の3つの省の事例を研究したと意見を述べています。
ハ・ティ・ホン・ヴァン博士は、600世帯を対象とした調査と、上記3省における観察プロセスの結果から、クアンニン省、クアンナム省、カマウ省の沿岸住民の生活様式には類似点と相違点が見られたと述べました。特に、調査地域では漁業活動が依然として盛んで、全世帯の19.16%を占めています。カマウ省は33%と最も高い割合となっています。しかし、漁業のほとんどは沿岸部での小規模な漁業です。さらに、漁業に従事する世帯の割合が大幅に減少し、調査対象3省全体でわずか4.5%にまで減少しました。
また、漁業活動に関連して、ハ・ティ・ホン・ヴァン博士によると、海を離れ、陸上の仕事や遠方で働く仕事に転職する住民の数が徐々に増加しているという。その結果、カマウ省では遠方で働く世帯の割合が最も高く(14.5%)、クアンニン省では低くなっている(5.5%)。「主な理由としては、クアンニン省とクアンナム省では近年の力強い経済発展により、人々に多くのより良い選択肢がもたらされたのに対し、カマウ省では依然として経済が主に森林と漁業に基づいており、工業団地は少ないことが挙げられます。しかし、調査地には、家族の生活の糧として船を所有したり、漁業を続けている世帯もまだかなりあります」とハ・ティ・ホン・ヴァン博士は語った。
本研究の第二の特徴は、カマウ住民の生活活動が他の2つの地域とは異なることを示している。カマウの調査地では、森林・エビ・カニ漁業による生計が顕著な特徴となっている。そのため、この地域の人々は森林保護意識が非常に高く、森林は彼らにとって家族の生計の源泉となっている。
ハ・ティ・ホン・ヴァン博士が本研究を通じて指摘した3つ目の特徴は、約71.5%の世帯が漁業や養殖業を含む水産養殖に関連した生計活動を行っていることです。クアンニン省では、住民は主にカキ、アサリ、ハタを養殖しており、クアンナム省では、シロエビ、クルマエビ、淡水エビを半工業的に養殖しています。カマウ省では、クルマエビが主な養殖で、世帯による水産養殖の多様性が最も高く、95%の世帯がエビ、カニ、魚を同じ地域で養殖しており、カマウ省は調査対象の他の2省と比較して、最も多様な水産養殖を行っている場所となっています。
しかし、「水産種子はまだ未発達で、10.7%の世帯が他省から種子を購入しなければならないと回答しています。クアンニン省では、カキの種子は依然としてニンビン省から調達しています。カマウ省では、アサリの種子はタンホア省やナムディン省から購入しています…」とハ・ティ・ホン・ヴァン博士は述べた。
ハ・ティ・ホン・ヴァン博士が発表した上記研究の4つ目の特徴は、沿岸地域では耕作と畜産業が依然としてかなり発達しており、42%を占めているものの、規模は全般的に非常に小さいという点です。「クアンニン省ヴァンドンでは、人々が土地を売却したり、用途を変更したり、観光目的で土地を埋め立てたりしているため、耕作地が減少しています。クアンナム省タムキー市とヌイタン郡では、海上観光の発展により、土地の売却に頼る傾向が生まれ、沿岸地域の世帯における耕作や畜産業用の土地面積も大幅に減少しています。カマウでは、多くの世帯がヤギ数頭や鶏の群れを飼育しているか、5~6平方メートルの野菜を栽培しているだけですが、それでも世帯の生計手段と考えられています」とハ・ティ・ホン・ヴァン博士は説明しました。
上記の4つの特徴に加え、政府による海洋経済開発の恩恵を受け、工業団地で働く世帯が増加しています。調査によると、世帯主の24.3%が、家族に地域の工場や小規模な民間製造企業で働く人がいると回答しました。この傾向はクアンニン省とクアンナム省で最も顕著で、ヴァン・ドン地区では近年、多くの企業や工場が建設され、海洋経済が発展しています。また、クアンナム省にはチューライ工業団地と周辺産業集積地があります。「そのため、これらの産業集積地は、住民にとって、仕事、安定した収入、個人の安全、そして家族との暮らしやすさという点で、海上労働から工業団地への転身の選択肢となっています」とハ・ティ・ホン・ヴァン博士は付け加えました。
ハ・ティ・ホン・ヴァン博士の調査結果が示したもう一つの特徴は、3つの調査対象地域の世帯が共通の生計手段の多様化という点です。ハ・ティ・ホン・ヴァン博士によると、世帯員は生活を支え、互いに支え合うために、様々な仕事に就いています。調査対象となった600世帯の収入源であり生計の源となっている仕事の数に関する統計によると、カマウ省では64%の世帯が2つ以上の生計手段を有しており、次いでクアンニン省が45%、クアンナム省が37%となっています。
上述の研究の特徴から、研究会では、沿岸住民の生活様式が現在変化しつつあり、人々が家族や個人の生活を保障するために選択する生計の多様性が生じているとの意見が多く聞かれました。これは、党と政府が長年にわたり実施してきた海洋経済政策の文脈とも一致しています。これらの政策は継続的に発布、革新、補完され、沿岸世帯が職業へのアクセスや転職、より適切で安全な仕事の獲得に有利な状況を生み出してきました。同時に、世帯内では工業団地、工場、企業、企業で働くメンバーもますます増えており、経済生活を向上させ、文化的・精神的な生活価値や現代社会の生活サービスの享受レベルを高める条件が整っています。
調査対象地域における世帯資本(人的資本、世帯の社会資本、自然資本、物的資本、金融資本を含む)が増加し、徐々に開発ニーズを満たしているというハ・ティ・ホン・ヴァン博士の研究評価にも、多くの意見が賛同している。この変化により、沿岸地域の人々は徐々に生計を立てるための条件を整え、あらゆる面で生活の向上に貢献している。同時に、党と国家の方針に沿って、天然資源の保護、国防の確保、海域および島嶼地域の安全保障にも貢献している。
[広告2]
ソースリンク



![[写真] ホーチミン市は2025~2030年任期の第1回党大会前夜、国旗や花で華やかに彩られている](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/10/10/1760102923219_ndo_br_thiet-ke-chua-co-ten-43-png.webp)



![[写真] プー・ジャーのユニークな馬帽子編み工芸](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/10/10/1760084018320_ndo_br_01-jpg.webp)













































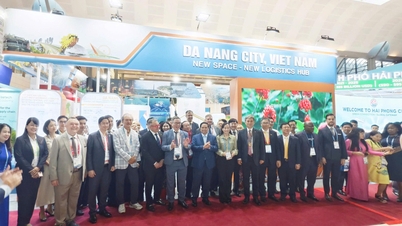











































コメント (0)