日本は3月26日、英国、イタリアと共同開発する次世代戦闘機の全世界への輸出を可能にするため、厳格な防衛装備移転規制を緩和し、三国間プロジェクトの障害を取り除いた。
岸田文雄首相の内閣は、与党の自民党と連立政権を担う公明党が3月15日に輸出規制の見直しで合意したことを受け、「防衛装備移転三原則」の改訂ガイドラインを閣議決定した。
改正規則では、東京・ロンドン・ローマ3国が2035年までに配備を計画している戦闘機を日本が第三国に輸出できると規定されているが、戦争状態にある国への移転は除外されている。
日本は、国の安全保障上のニーズを満たす戦闘機の開発を確実に行えるよう輸出計画を必要としており、「日の出ずる国」日本は英国とイタリアとの「対等なパートナー」として三国間プロジェクトに参加できる可能性があると内閣は述べた。
また、新規則では、輸出される戦闘機の仕向地は、防衛技術や装備の移転について日本と条約を締結している国に限定されるとしており、現在、そのような国は、日本の緊密な安全保障同盟国である米国を含めて15カ国にのぼる。
さらに、取引を実行するには、それぞれのケースごとに内閣の承認が必要となる。

日本、英国、イタリアの防衛大臣は、2023年12月に東京の防衛省で、三国間の新型戦闘機プロジェクト「GCAP」について会合を開いた。写真:ジャパンタイムズ
戦闘機輸出制限は、岸田氏率いる保守系自民党が、安全保障問題では穏健な立場をとる伝統的平和主義政党である公明党を安心させようとしたために実施された。公明党は、日本が適切な手続きなしに兵器を販売し、紛争を引き起こす可能性を懸念している。
岸田首相は、戦闘機開発への効果的な支出を確保し、将来的に他の国際防衛プロジェクトにおけるパートナーとしての東京の信頼性を維持するために、日本が第三国に戦闘機を移転することを認めることが必要だと述べた。
日本は憲法に基づき、国際的に開発された兵器の第三国への輸出を禁止してきた。
インド太平洋地域で中国の軍事力が拡大する中、NATO加盟国2カ国との戦闘機プログラムは、日本にとって米国以外の国との初の防衛装備品共同開発協定となる。
日本は、地域の緊張が高まる中で、新世代の戦闘機が必要な高度な能力を提供してくれることを期待している。
日本は2014年に武器禁輸措置を解除して以降、一定の条件の下で武器輸出を「解禁」し、武器や弾薬の輸出を通じて志を同じくする国々との安全保障関係を強化し、国内の関連産業を振興することを目指している。
日本は昨年12月、武器輸出規制を改正し、外国のライセンスに基づいて国産された武器をライセンス取得者の拠点国に輸出することを認めた。
ミン・ドゥック(日経アジア、AP通信による)
[広告2]
ソース



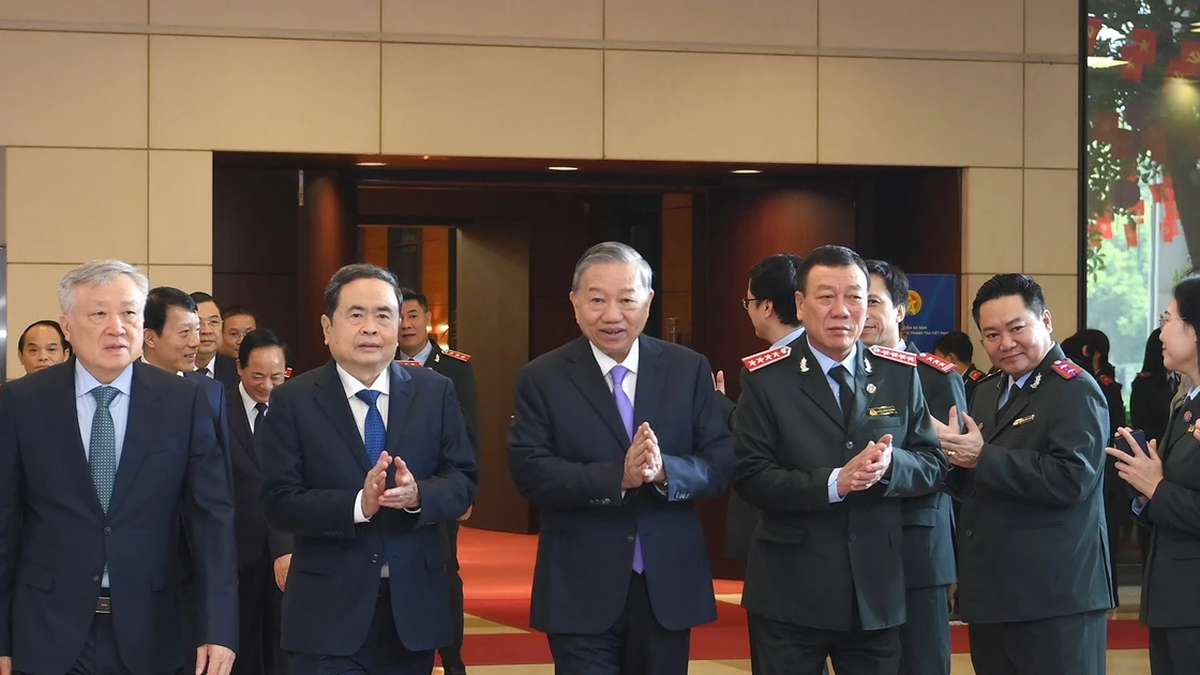








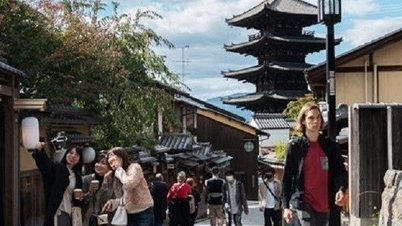



















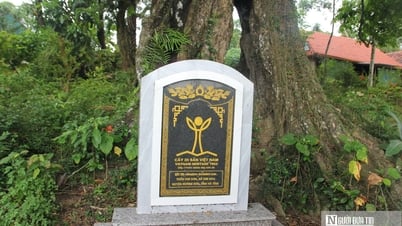
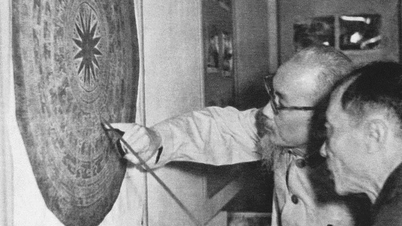







































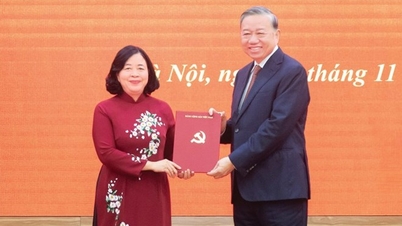





































コメント (0)