愛宕念仏寺:京都千二百面相の寺院
京都北西部の嵯峨野にひっそりと佇む愛宕念仏寺は、驚くほど生き生きとした表情を持つ1,200体の石仏(羅漢)で参拝者を迎え入れます。本堂は平安時代(794~1192年)に遡りますが、これらの羅漢像は1981年から1991年にかけて、住職西村光朝の指導の下、多くの参拝者や信者によって彫られました。
苔むした仏像はそれぞれが、陽気なもの、物思いにふけるもの、滑稽なものなど、それぞれに異なる表情をしており、独特の景観を創り出しています。これは、寺院の主要な建造物が幾多の自然災害や時の荒波を揺るぎなく乗り越えてきたことの証であり、寺院の揺るぎない生命力の証です。

蔵王キツネ村:狡猾な生き物たちと出会う
宮城県蔵王キツネ村では、6種類100頭以上のキツネが自由に暮らしています。来園者は指定エリアで餌を購入し、キツネに餌を与え、キツネたちが自然の中で遊び、触れ合う様子を観察することができます。日本文化において、キツネは知性があり、神秘的な力を持つと考えられています。
蔵王キツネ村での体験は、猫島やウサギ島などの馴染みのある場所と比べて興味深く違った視点を提供し、特に動物好きの人にとって魅力的です。

礼文島:北海道の野花の楽園
利尻礼文サロベツ国立公園内に位置する礼文島は、緑豊かな丘陵地帯を縦横に走るハイキングコースが整備された、エメラルドグリーンの宝石のような島です。フェリーでアクセス可能なこの島は、手つかずの自然と静かな景観を保っています。訪れるのに最適な時期は6月から8月で、80平方キロメートルの島全体が数百種の高山植物で覆われます。
ここの花の多くは島のシンボルであるエーデルワイス・レブン(ウスユキソウ)をはじめ、 世界でもここ以外の場所では見られない固有のものです。

龍泉洞:龍の洞窟と地底湖を探検
日本三大鍾乳洞の一つ、龍泉洞は、宇礼岳の麓に位置しています。入り口からは、地底を流れるせせらぎの音が聞こえてきます。洞内は、無数の鍾乳石や石筍、そして透き通る3つの地底湖が織りなす幻想的な世界です。中でも最も深い地底湖は、深さ98メートルと日本一深い地底湖です。巧みに配置された照明が青い水を照らし出し、底まで見渡すことができます。

吹割の滝:片品川の雄大な美しさ
沼田市近郊にある吹割の滝は、息を呑むほど美しい自然の景観を誇ります。幅30メートルの片品川が、花崗岩の断崖を流れる狭い峡谷を急激に流れ落ち、白い水の帯を作り出します。崖沿いに整備された展望台や遊歩道からは、様々な角度から滝の美しさを堪能できます。

青ヶ島: 太平洋の火山島
青ヶ島は東京沖に浮かぶ孤立した火山島で、独特の二重火口構造で知られています。ヘリコプターで約20分の飛行で島へアクセスできます。面積は3平方キロメートル強で、約160人の住民が暮らしています。最後の噴火は1785年ですが、現在も地熱が残っており、地元の人々は天然の蒸し器で食材を調理しています。青ヶ島はハイキング、星空観察、そして外界から離れた生活を体験するのに最適な場所です。

下栗の里村:「日本のチロル」
東京の喧騒とは対照的に、長野県下栗の里は静寂に包まれた空間です。日本三秘境の一つに位置するこの村は、オーストリアアルプスを思わせる山岳風景から「日本のチロル」と呼ばれています。驚くべきことに、地元の人々は今も斜面で暮らし、農業を営んでいます。斜面は最大38度の傾斜があり、ジグザグの道や壮大な段々畑が広がっています。

通潤橋:ユニークな水路橋
通潤橋石造アーチ橋は、美しい建造物であるだけでなく、1854年に水田の灌漑用に建設された古代の水路橋でもあります。現在も現役で使用されており、毎日正午になると橋の両側から水が放水され、迫力ある人工滝が作られます。近くには竹林を抜け、高さ50メートルの五郎ヶ滝まで歩くことができます。五郎ヶ滝では、水蒸気が幻想的な虹を創り出すこともしばしばあります。

竹田城跡:「日本のマチュピチュ」
朝来市の山頂にそびえる竹田城跡は、早朝には雲に覆われることが多く、「日本のマチュピチュ」の異名をとっています。1443年に築城されましたが、16世紀後半に大部分が破壊されました。ここへは、立雲峡公園を歩いて行くことになります。道のりは険しいですが、その道のりを歩くことで、幻想的な景色と息を呑むような周囲の絶景に出会うことができます。

出典: https://baolamdong.vn/nhat-ban-khac-la-9-diem-den-doc-dao-it-nguoi-biet-den-399756.html



![[写真] 2025年から2030年までのニャンダン新聞愛国模範大会のパノラマ](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/11/04/1762252775462_ndo_br_dhthiduayeuncbaond-6125-jpg.webp)


![[写真] ホーチミン市の若者がよりきれいな環境を求めて行動を起こす](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/11/04/1762233574890_550816358-1108586934787014-6430522970717297480-n-1-jpg.webp)



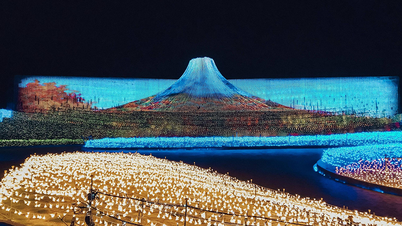
































































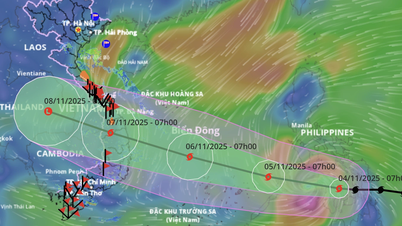



























コメント (0)