ボラティリティとは何ですか?
経営の文脈において、「ボラティリティ」は、 地政学、市場(価格、インフレ、為替レート、サプライチェーン)、政策、ESG危機、顧客行動、技術革新など、突発的で予測不可能な変化と関連付けられることが多い。しかし、より広い視点と長い時間軸で捉えてみると、ボラティリティは例外ではなく、普遍的なルールであることがわかる。ボラティリティは単なる「偶然」によるものではなく、常に変化し、動き続ける現実の性質から生じるのだ。

変動をコントロールし、困難を乗り越えようと努力する中で、 ペトロベトナムは多くの生産目標と事業目標を上回り、多くの新記録を樹立しました。写真:ペトロベトナム
哲学、 科学、宗教の交差点
古代において、有名な哲学者ヘラクレイトスは「パンタ・レイ(万物は流れる)」という言葉で無常性について初めて言及しました。彼によれば、不変のものなど存在せず、万物は絶えず変化しており、「誰も同じ流れに二度足を踏み入れることはできない」のです。
マルクス・レーニン主義の古典は、運動は物質の固有の性質であり、存在様式であると指摘しました。物質世界のすべてのものは、単純な位置の変化から思考過程に至るまで、常に運動しています。この運動は永遠であり、「否定の否定」へと向かう傾向を伴います。これは自然、歴史、そして思想の発展における普遍的な法則です。カール・マルクスとフリードリヒ・エンゲルスは、この法則が事物と現象の発展の客観的な道筋を反映していると強調しました。
哲学だけでなく、科学もあらゆる現象の変化を肯定し、さらに、宗教における名色の性質の変化という認識の類似性を証明しています。言い換えれば、哲学、科学、宗教は、変化こそが現実の本質であるという認識において、すべて出会うのです。私たちが「現実」と考えるものはすべて、一時的なものであり、因果関係、あるいは仏教における「縁起」の原理によって固定されているわけではありません。マルクス・レーニン主義哲学が「それはそれであるが、それはそれではない」と表現するように、事物の絶え間ない変化を示すのです。
宗教的観点から、特に仏教においては、変化は普遍的な真理として無常(anicca)と結び付けられています。仏教では、無常はあらゆる因果律の三つの基本特性の一つとされています。悟りを開いた衆生の洞察と悟りに基づき、仏教は、生まれたものはすべて変化し滅び、永遠に存在するものはなく、すべての意識(名)と物質(色)は無常の摂理に従うと断言します。つまり、変化は「異常」ではなく「当然」であり、本質なのです。
変化の管理:逆説か、それとも必然か?
変化は無常の一種であると認めると、パラドックスが生じます。本質的に制御不能、予測不能、そして不変であるものを、私たちはどのように管理できるのでしょうか?この問いは、哲学的なだけでなく、経営における認識論的かつ実践的な問題でもあります。
組織においては、状況の変化、市場要因、急速な技術革新など、内外の変動を完全に「制御」できる者は誰もいません。新型コロナウイルス感染症のパンデミック、地政学的危機、伝統的・非伝統的な武力紛争、自然災害など、かつてないほど頻繁に発生するブラックスワンリスクやグレイスワンリスクを予測できる者は誰もいません。問題は、では何を管理できるのかということです。
人生のあらゆる分野において「変化、変化、そして変化」を特徴とする不安定な現実は、現代の経営理論をより実践的かつ科学的な目標へと調整し、転換することを迫っています。それは、不安定な状況における目標管理であり、「ボラティリティ・マネジメント」の中核を成すものです。実際、ボラティリティそのものを管理することは不可能であり、また目指すべきでもありません。なぜなら、それは自然と社会の避けられない要素であり、状況は常に制御不能であり、人間の心理や感情さえも不変ではないからです。私たちができることは、意識、態度、対応、そして戦略を管理し、適応し、対処し、目標に向かって進むことです。
ペトロベトナム取締役会長のレ・マン・フン博士によると、変動管理とは、急速かつ予測不可能な変化という状況下で計画目標を管理するための境界条件を管理することです。このアプローチには、(i) 計画の立案と実施における柔軟性、(ii) 適切な対応策を講じるために、常に主要な要因と各目標への影響レベルを特定すること、(iii) 予測だけに頼るのではなく、迅速かつ十分に適切な対応能力に焦点を当てること、(iv) 要件を満たすチームを構築すること、(v) 対応時間と意思決定時間を短縮するための適切な組織ガバナンスモデルと分権化が必要です。
変化がますます急速かつ予測不可能になる状況において、企業は「柔軟な対応」戦略を追求する必要があります。その実行には、(i) 目標を管理可能なセグメントに分割すること、(ii) 継続的な監視、追跡、フィードバックを行うこと、(iii) 変化を避けられない客観的な一部として受け入れること、(iv) 不変の計画に「賭ける」ことを避けること、(v) 管理されたリスクを受け入れることが必要です。
仏教で「ダルマ」と呼ばれるカテゴリーにおける科学、哲学、宗教の交差は、新たな視点を示唆していると言えるでしょう。変化は無常の現れであり、表面的な変化だけでなく、現実の深層的な本質をも表すものです。これは、経営、言い換えれば、避けられない変化への対応において、客観的な要件を提起します。

ペトロベトナムの工場は、常に高い可用性を維持しながら、生産能力とパフォーマンスを最適化しています。写真:ペトロベトナム
経営への影響
上記の分析から、「チェンジマネジメント」の意味をさらに明確にすることができます。それは、常に変化し、速く、予測不可能な状況において、古い考え方やモデルに「固執」することなく、柔軟に目標を設定し、追求し、実行する能力です。
「変化の管理」とは、生産やビジネス、そして一般的には事物の世界において起こるあらゆる変化や変動をコントロールするという幻想ではなく、変化する環境を受け入れ、全体目標を確実に達成するために、境界条件を制御する能力を通じて、変化を特定し、対応し、適応するプロセスです。変化は波であり、マネジメントとは波を防いだり消したりすることではなく、サーフィンをする技術であると言えるでしょう。
存在論的な観点から見ると、変化は現象の固有の特性であり、避けることはできません。このことを認識することで、私たちは変化に対してよりオープンになり、変化への対応が形式やスローガンではなく、客観的な必然性、個人、組織、国家、そして人類に至るまで、あらゆる主体にとって真に必要なものであることを理解するようになります。
「変動を管理するということは、急速で予測不可能な変化の中で計画目標を管理するための境界条件を管理することです。」ペトロベトナム取締役会長、レ・マン・フン博士 |
|---|
出典: https://daibieunhandan.vn/quan-tri-bien-dong-tu-goc-nhin-ban-the-luan-10378586.html



![[写真] カタツムリ麺料理が中国柳州市を有名に](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/8/30/56e738ed891c40cda33e4b85524e30d3)
![[写真] 国際軍事代表団がバーディン広場でのリハーサルに参加](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/8/30/1fe13d6df1534ce8a798fa91962ed487)

![[写真] ハノイ市民は大祭典のパレードのリハーサルを待って徹夜している](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/8/30/d14625501aee42e28bbd5227a1ff2b11)








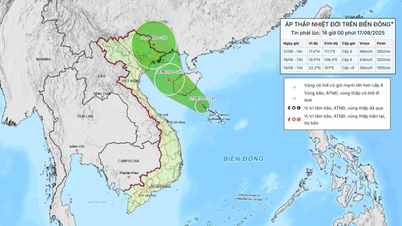













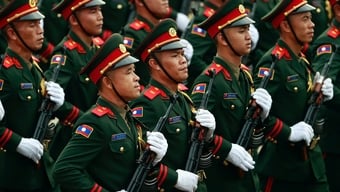


























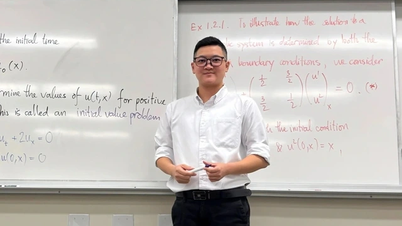










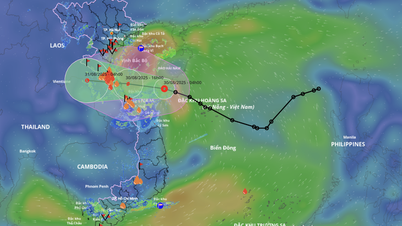














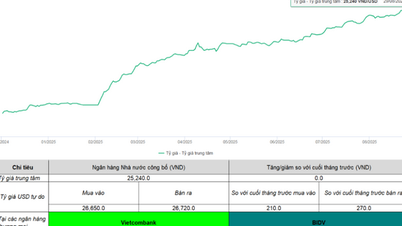














コメント (0)