 |
| 不動産市場は徐々に回復し、「底値」を脱した。(Nguonf: Dan Tri) |
市場は「底値」を越えた
ホーチミン市不動産協会(HoREA)による2023年最初の10か月間の不動産市場レポートでは、市場は「底」を越えたものの、全体として不動産市場は依然として非常に厳しい状況にあると述べられています。ただし、難易度は時間の経過とともに低下する傾向があり、翌月は前月よりも良くなり、次の四半期は前の四半期よりも良くなります。
HoREA会長のレ・ホアン・チャウ氏によると、ホーチミン市の不動産市場において、上記の評価は非常に明確です。今年第1四半期の不動産価格は前年同期比16.2%減でしたが、第3四半期末時点では前年同期比8.71%減と依然として低いものの、年初来6ヶ月間と比較すると2.87%減少しました。9ヶ月経過時点で、不動産市場の難易度は第1四半期と比較して42.3%低下しました。
チャウ氏によると、今年最初の9か月間でホーチミン市の住宅供給は、資金動員対象となる商業住宅プロジェクトが13件、1万5020戸あり、2022年の同時期に比べて1.37倍増加したが、動員収入は4.7%減少した。
具体的には、計13プロジェクトのうち、マンションは13,767戸(91.6%)、低層住宅は1,253戸(8.4%)で、そのうち高級住宅は9,969戸で66.37%(全国平均の58%を上回る)、残りは中級住宅が5,051戸で33.63%(全国平均の26%を上回る)を占めています。市場は依然として手頃な価格の住宅がなく、社会住宅も不足している状態です。
チャウ氏によると、ベトナム国内およびホーチミン市の不動産市場は引き続き「需要と供給のバランスが崩れている」状態にあり、プロジェクトの供給不足が住宅供給不足、特に手頃な価格の住宅や社会住宅の不足につながっているという。
特に、HoREAの会長によると、住宅価格は2017年以来継続的に上昇しており、中間所得者、低所得の都市部住民、役人、公務員、国家職員、軍人、労働者、移民の経済的能力を超えて依然として「高騰」しているという。
「20億~30億ドンの手頃なアパートの場合、年間約1億ドンの貯蓄しかない低所得者でも、住宅を購入するには約25年かかるだろう」とチャウ氏は分析した。
不動産市場を概観すると、 建設省住宅不動産市場管理局長のホアン・ハイ氏によると、政府、省庁、銀行システム、企業、そして仲介業者自身の努力が、不動産市場の「維持」にプラスの影響を与えているという。市場は「傾斜を乗り越える」ほどの力強さはないものの、「ブレーキを失う」リスクからは基本的に脱し、勢いを取り戻しつつある。
債券の満期圧力は依然として企業を取り巻いている
ベトナム債券市場協会(VBMA)のデータによると、今年最初の10ヶ月間の社債発行総額は209兆1500億ベトナムドン(約2兆1500億ベトナムドン)に達しました。これは、債券チャネルを通じた資金調達活動が2022年と比較して改善していることを示しています。
そのうち、銀行セクターが99兆230億ドン(総額の47.3%)で最大規模を占めています。次いで不動産セクターが68兆2560億ドン(32.6%)となっています。
しかし、ベトナム不動産協会(VARS)の調査によると、債券の満期圧力は依然として不動産業界を「取り囲んでいる」ことが示されています。新規発行および買戻しされた不動産債券の総額は、満期を迎える社債の総額と比較して依然として非常に低い水準にあります。
その結果、2022年には不動産企業が約219兆VNDの自社株買いを行いました。最初の10ヶ月間では、約153兆8,000億VNDの自社株買いを行いました。一方、2023年と2024年の最後の2ヶ月間に不動産グループが満期を迎える債券の総額は、それぞれ15兆6,000億VNDと121兆1,000億VNDに達しました。
社債債務の返済が遅れている企業のリストは、特に不動産業界において日に日に増加している。ハノイ証券取引所によると、10月3日現在、社債の元利金の返済が遅れている企業は約69社あり、その債務総額は約176兆1000億ドンに上る。これは市場全体の社債債務残高の約17.8%に相当する。
債券の償還期限のプレッシャーに直面し、キャッシュフローを再構築し、債務返済能力を向上させるための時間を確保するため、VARSは、信用資金へのアクセスが困難で市場が完全に回復していない状況において、期限延長交渉が不動産事業者にとって第一の選択肢であると考えています。4月以降、期限延長交渉は活発に行われ、かなりの成果を上げています。
ハノイ証券取引所によると、10月3日時点で50以上の発行体が債券の償還期限を延長することで合意し、その総額は95兆2000億ドンを超えている。償還期限は主に2年間延長され、債務返済圧力は2025年から2026年にかけて先送りされた。
VARSは、債券の返済期間延長交渉は今後も引き続きトレンドになると予測しています。しかしながら、依然として困難な状況が待ち受けており、債務返済期間の延長は、企業が生産と事業を安定させ、債務再編による回復を図るための時間を確保することにしか役立ちません。基本的に、債務をある時点から別の時点に移管しているに過ぎません。
倒産リスクを回避するために、企業はこの機会を捉えて債務再編を行う必要があります。資産売却を真剣に検討し、損益分岐点や損失を許容することでキャッシュフローを確保し、債務返済や、市場に投入後すぐに清算可能なプロジェクト完了に必要な資金を確保する必要があります。
さらに、一般的な資金調達源(銀行融資や社債)に加えて、他の金融商品(不動産投資ファンド(REIT)、住宅貯蓄ファンド、不動産証券化など)や他のチャネル(直接的および間接的な外国投資)からの資本源を開発、誘致し、効果的な運用を確保するためのメカニズムとポリシーが必要です。
ハノイのレヴァンルオン通りN14、N15プロジェクトへの投資政策の停止
ハノイ市人民委員会は、長年の遅延を経て、N14・N15レ・ヴァン・ルオン通りプロジェクトに関する投資政策決定の実施を停止するよう指示しました。このプロジェクトは、公共サービスと住宅建設の複合型投資プロジェクトであり、投資家はルイ・インベストメント・アンド・トレーディング株式会社です。
 |
| 土地区画 N14、N15 Le Van Luong 通り、ハノイ。 (出典: BXD) |
レ・ヴァン・ルオン通りのN14、N15プロジェクトに関して、ハノイ市人民委員会は有権者への最新の回答報告書の中で、N14、N15の土地区画の総面積は12,561平方メートルで、市は2016年8月に投資方針を承認したと述べた。これは公共サービスと住宅の複合投資プロジェクトであり、投資家はルイ・インベストメント・アンド・トレード・ジョイント・ストック・カンパニーである。
用地取得手続きの過程で、プロジェクトへの苦情が寄せられました。ハノイ市監察官の報告書に基づき、苦情を検討した結果、ハノイ市人民委員会は2020年2月、本プロジェクトに関する投資政策決定の実施停止を指示しました。プロジェクトの既存の内容の取り扱いについては、市は各部署、支部、セクターに現行の規制の見直しを指示し、助言と提案を行いました。
N14およびN15プロジェクトの土地は、カウザイ県チュンホア区のQH 46番地(区画記号)に位置することが分かっています。プロジェクトの南西はホアン・ンガン通りに、北西はレ・ヴァン・ルオン通りに接しています。N14およびN15の土地区画は、以前は5.1-NOおよび5.5-NOと呼ばれていました。2018年以降、プロジェクトエリア内の世帯は土地回収の決定を受けています。記録によると、プロジェクトに属する土地の一部は整地され、波形鉄板で囲まれています。
レッドブックとピンクブックの法的価値
規定によると、2009年12月10日以前に発行された土地使用権証書は依然として法的有効であり、土地使用権証書、家屋所有権証書、その他の土地に付随する財産証書への転換は不要です。法的価値の観点からは、レッドブックとピンクブックは同等の法的価値を有します。
レッドブック、ピンクブックとは、土地使用権証書の外側の色によって、土地使用権に関する文書を指す用語です。
ベトナムでは、土地使用権証明書は、それぞれの時代によって名称が異なります。具体的には、土地使用権証明書、家屋所有権および土地使用権証明書、家屋所有権証明書などがあります。
2009年より、 天然資源環境省は、土地使用権、住宅所有権及び土地に付随するその他の資産の証明書(証明書の表紙はピンク色で、ピンクブックとも呼ばれる)と呼ばれる全国的に適用される新しい証明書フォームを発行しています。
2013年土地法第97条は、土地使用権、家屋所有権、土地に付随するその他の財産の所有権を持つ人に対し、全国で統一された様式に従って土地使用権、家屋所有権、土地に付随するその他の財産の証明書を発行することを規定している。
2009年12月10日以前に発行された土地使用権証書は、現在も法的に有効であり、土地使用権証書、家屋所有権、その他の土地に付随する資産に変換する必要はありません。
2009年12月10日以前に発行された証明書のうち、変更が必要なものは、土地使用権、家屋所有権、その他土地に付随する財産に関する証明書に変更することができます。したがって、法的価値の観点からは、レッドブックとピンクブックは同等の法的価値を持ちます。
政令01/2017/ND-CP第2条第40項の規定によれば、レッドブックおよびピンクブックの申請処理期間は、有効な申請書を受領した日から30日を超えてはなりません。山岳地帯、島嶼、遠隔地、社会経済状況が困難な地域、および特に社会経済状況が困難な地域の場合は、40日を超えてはなりません。
[広告2]
ソース
































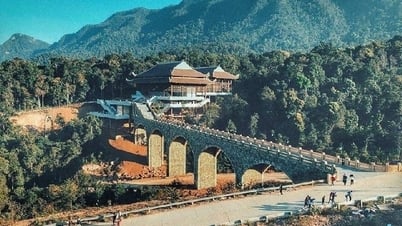

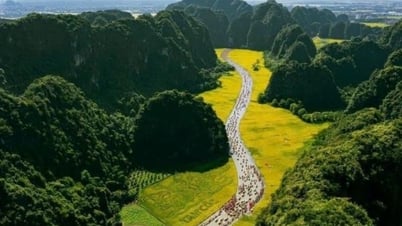






























































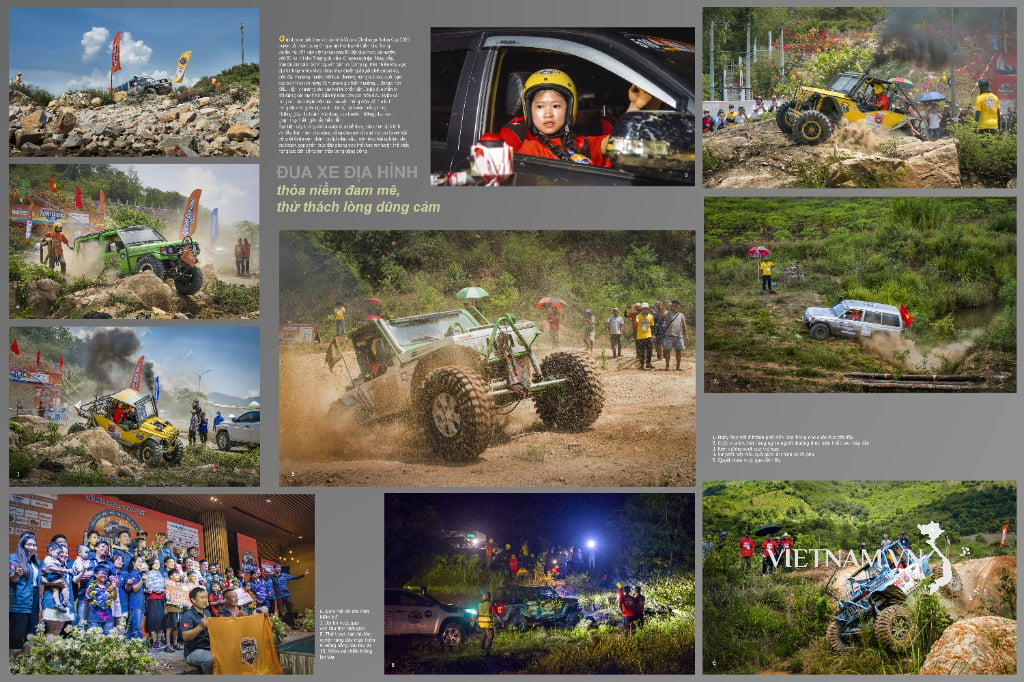


コメント (0)