国会法務委員会常任委員のド・ドゥック・ヒエン代表(ホーチミン市国会代表団)によると、「空中工事、地下工事、海上侵入活動により形成された土地の建設のための土地利用体制」に関する規制は、中央委員会決議第18-NQ/TW号に定義されている社会主義志向の市場経済の制度的発展に合わせて、土地管理と利用に関する制度的政策を完成させるという課題の内容の1つである。
この内容を制度化するために、土地法案(改正案)では、地上の土地の管理および使用の仕組みに関する規制に重点を置くほか、空中工事や地下工事の建設のための土地利用体制に関する規制も盛り込まれている。特に、法案第214条は地下建設のための土地を規制するために充てられている。
「上記の規制は、土地利用の効率を最大化し、空間における土地利用の拡大という方向へ向かう法的メカニズムを初めて形成したと言える。これは、特に都市部の土地といった土地利用がますます逼迫する状況において、社会経済発展の目標達成に貢献するものである。これは、多くの国々で既に実施され、現在も実施されている、土地管理・利用政策における重要かつ極めて必要なイノベーションの一つであると考えられる」と代表は断言した。
地下空間計画に関する規制は依然として散在し、個別的であり、統一性に欠けている。
しかし、ド・ドゥック・ヒエン代表は、現行土地法第179条第1項の規定によれば、「土地使用者は、地下の深さや天井の高さに関する規制に従い、正しい区画の境界内で、正しい目的で土地を使用し、地下の公共工事を保護し、その他の関連する法的規定を遵守する義務がある」と指摘した。この内容は、土地法案(改正案)第30条第1項に引き続き記載されています。一方、民法第175条の規定によれば、「土地使用者は、法律の定めるところにより、土地の境界から垂直方向の空間及び地下空間を使用することができる」とされています。そのため、現行の土地法、民法、土地法草案(改正案)には、土地使用権を有する組織や個人が開発・使用できる高さや深さに関する具体的な規制がありません。この高さと深さの制限は専門法の規定に従って実施されます。
検討の結果、代表団は、建設法、都市計画法、および現在の実施文書には、地上空間と地上空間を管理するための個別の規制がいくつかあるとコメントしました。地下空間に関しては、政府の2010年政令第39号があり、現在ハノイなど一部の地域では地下空間の計画があります。しかし、これらの規制は依然として非常に散在しており、アプローチも依然として個別であり、統一性が欠けていることがわかります。計画の範囲がまだ完了しておらず、経営に混乱が生じています。多くの場合、土地利用者による土地利用の範囲は非常に広範であったり、範囲が定まっていなかったりするため、1つの土地区画において同時に開発および使用している主体が1つしか存在せず、土地資源の有効活用が困難になっています。
地下の土地使用権を垂直的に区分する原則に関する規定を補足する必要がある。
上記の分析から、これらの問題を克服するために、土地法の改正案を検討し、地下の土地使用権を垂直な区画に分割する原則に関する規制を補足する必要があると、代表のド・ドゥック・ヒエン氏は述べた。したがって、それぞれの土地の種類に応じて、土地使用者の表面積に加えて、表面土地使用者が開発および使用できる最大の深さも指定されます。同時に、地上空間の利用に関する規制を補足し、一貫性を確保します。
また、同代表によれば、第214条第1項は、地下工事用地には(1)地下工事の運営、開発および使用に役立つ地上工事の建設用地と(2)地上工事の地下部分ではない地下工事の建設用の地下空間が含まれると規定している。しかし、新法案の規定のほとんどは、地下工事の運営と利用に役立つ地上工事の建設用地についてのみ言及しており、建設工事のための地下空間を規制する規定はない。例えば、公共エリア、花壇、公園、広場などにおいて、団体や個人に地下空間の使用権を与えることはできるでしょうか。さらに、代表者は、地上工事の地下部分ではない工事を建設するために地下空間の使用を許可する場合には、土地利用の仕組みと、土地表面を使用する権利を持つ主体と地下工事の所有者との関係がどのように解決され、開発と使用のプロセスが促進されるかについても明確にする必要があると述べた。
一方、土地法案第214条第2項は、本法の規定による土地使用者は、建設法、都市計画法、建築法等の規定により国が定める地下空間を法律の規定に従って譲渡、賃借、転貸することができると規定している。これにより、建設法、都市計画法、建築法等が土地使用者に使用を許諾する地下の深さの制限の範囲内において、土地使用者は地下空間を譲渡、賃借、転貸する権利を有すると解される。代表者によれば、このアプローチは、民法に規定されている地上権に関する制度とも基本的に一致しており、「地上権とは、その土地使用権が他の主体に属する、土地、水面、地上空間、水面および地下に対する主体の権利である」とされている。しかし、法案では譲渡、賃貸、転貸の目的や具体的な手続き、実施手順などについてはまだ規定されていない。規制の実現可能性を確保するため、代表のド・ドゥック・ヒエン氏は、法案草案も検討し、補足してこれらの内容を明確にする必要があると提案した。
代表は、土地法草案(改正案)には、地下工作物の運営、開発及び使用に役立てる地上の工作物の建設に関する土地使用権及び地下工作物の所有権に関する初回登記及び変更登記の規定があるが、地上権を持つ主体が地上権を登記しなければならないという規定はない、と分析した。登録は、地上権と土地使用権の関係、および地上権を持つ人の主体としての地位を決定できる唯一の手段であるため、非常に重要であることを考慮し、代表者は、起草機関がプロセスと手順に関する規制を追加すること、およびサンプル文書、料金、地上権の登録メカニズムを公布することを検討するよう要請しました...
また、土地法改正案には、土地使用者と地上権者の間、初めて地上権を与えられた者とその後の者の間など、地上権の移転費用の算定、当事者の利益を調和させるための地上権の移転の合理的な水準など、地上権に関する事項の実施を導く規定も補足する必要がある。地上権を与えられた者の共有財産の保護および管理の責任、または土地の表面または土地に付属する財産に生じた損害を賠償する責任を定める方法...。


![[写真] フランスのエマニュエル・マクロン大統領夫妻、ベトナムへの公式訪問を開始](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/5/25/03b59c7613144a35ba0f241ded642a59)
![[写真] ハノイ、「シャークジョーズ」ビルの解体をフェンスで阻止](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/5/25/1b42fe53b9574eb88f9eafd9642b5b45)

![[写真] エア・イエン村の入植計画が中止](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/5/25/57a8177361c24ee9885b5de1b9990b0e)
![[写真] クアンガイ省でのチャン・ドゥック・ルオン元大統領の葬儀](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/5/25/ccf19a3d8ea7450bb9afe81731b80995)









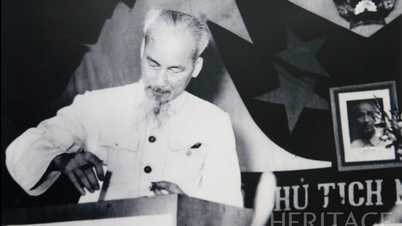


































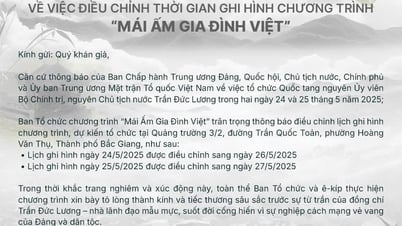

















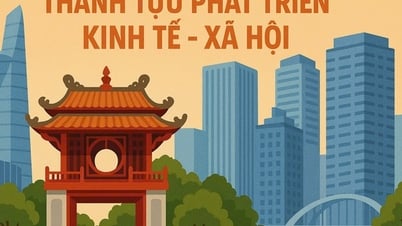


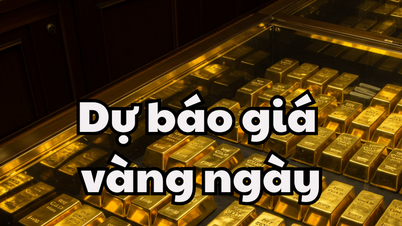


















コメント (0)