時折、突風が吹き抜け、水に濡れた枝を揺らした。フェンスの向こう側、貨物列車が今も日に数回通る場所では、老人が擦り切れたコートを羽織ってうずくまっていた。ウールのマフラーも色褪せ、足元のピカピカの黒い靴だけが新品のようだった。露天商が置いていったと思われる椅子に座り、まるで眠っているかのように顔を伏せ、時折汽笛の音が聞こえて驚かされる。晩冬の日に戸惑った表情は、空しく待つ人の孤独を思わせる。彼女は遠くからその姿を垣間見た。一目見ただけで、静かに座り、誰もいないプラットフォームをじっと見つめる彼の姿に目を奪われた。
イラスト:トゥアン・アン
駅は道路からそれほど遠くなく、甲高い汽笛が鳴るたびに、乾いたレールの上を鉄の車輪がゴロゴロと転がる音が響き、緩んだ窓が揺れた。いつものように、旅客列車はこの駅には停車せず、この辺鄙なプラットホームには市場列車だけが停車していた。列車が姿を消すと、空は空っぽになり、辺りは静まり返った。市場列車が駅に入ってくると、数人の乗客が降りただけで、彼らの存在はこの荒涼としたプラットホームに何の活気も加えなかった。
彼女はイヤホンをつけて、ぼんやりと辺りを見回していたが、実は老人に目が釘付けになっていた。老人は立ち上がり、ゆっくりと歩き始めた。杖が地面を軽く叩く音は、しかしカチャカチャという音ははっきりと聞こえた。砂丘の向こう側から、ゆっくりと走る列車が、疲れた息を吐きながら近づいてきていた。きらめくガラス窓の向こうには、豪華なスーツケースが赤や緑の旅行バッグの横に積み重なり、クッション付きの座席に座る人々は、すべてが遠ざかっていくのを無関心な顔で見ていた。列車は遠く離れ、老人は椅子に近づき、手探りで座った。まるで地面に落としたものを探しているかのような思慮深い表情で、時折杖を持ち上げ、軽く叩いては足の間に挟んでいた。彼の隣には、肘掛けに丁寧に彫られた光沢のある黒い杖以外、荷物は何もなかった。彼女はイヤホンを外し、話しかけようと彼に歩み寄った。「どの列車を待っているんですか?」
老人は顔を上げて、尋ねてきた人が見覚えのある人なのか、それとも見知らぬ人なのかを注意深く見ていた。その目にはかすみがかかっているようだった。「えっと…終バスを待っているんです」老人はポケットからハンカチを取り出して口を覆い、咳をしながら答えた。
彼女は砂利道からまばらに生えてくる草をぼんやりと眺め、それ以上の質問を諦めた。冬の午後の風が、焼け焦げた草の茎が生い茂る不毛の地を時折吹き抜ける。隣で老人は眠っているかのように目を閉じていたが、それでも彼女は彼の孤独でうずくまる様子に、かすかな悲しみを感じ取ることができた。それは、物憂げで壮大でありながらも胸を締め付けるクラシック音楽を思い出させた。突然、老人は振り返って尋ねた。「あなたも電車を待っているのですか?」「ええ!」
彼女が話し終えると、改札の向こうから汽笛が長く鳴り響き、駅への入り口が近づいてきたことを知らせた。彼女は老人に挨拶をし、急いで最後尾の車両に飛び乗った。老人はしばらくぼんやりしていたが、杖を振りながら立ち上がり、急いで列車に乗り込み、空いているベンチを選んで静かに座った。重たい列車が動き始めた。この時、彼はマフラーを外し、頭を覆って体を温めていたが、杖はしっかりと脚の間に挟んでいた。彼女は立ち上がり、老人に歩み寄り、ミカンの皮をむいて半分に割り、差し出した。「喉の渇きを癒すために、ミカンを一切れ召し上がってください!」
老人はミカンの房を取り、ゆっくりと食べた。窓から吹き込む風に、額の銀髪がフードの下に垂れ下がった。冬の冷気が車内に入り込み、彼女は肩をすくめてシャツを閉じた。すると突然、老人が静かに尋ねた。「どこで降りるんだい?」「僕はニハー駅で降りるんだけど、君はどうするの?」「僕も…ニハー駅で降りる」「子供たちに会いに行くのかい?」
老人は広大な砂丘を静かに見つめ、まるで錨を下ろす場所もないかのように、視線をさまよわせていた。列車はわずかに揺れ、冷たい墓が点在する墓地を通過した。向かい側のベンチでは、数人の乗客がうとうとと眠り、列車の急激な揺れに時折咳き込んでいた。彼女は老人を黙って見守り続け、奇妙な感覚に胸が締め付けられる思いがした。列車は駅に到着し、長い汽笛を鳴らして、人気のないプラットフォームの前に停車した。乗客は次々と降りていった。彼女は老人のところに歩み寄り、「お手伝いしましょう!」とささやいた。
老人は理解し、手を上げて彼女を止め、軽く頷いて礼を言った後、慎重に降りて駅のドアへと向かった。彼女は立ち止まり、痩せた人影が消えるまで見守った。
* * *
静かに冬が過ぎていく…
慌ただしい帰り道、市場行きの列車が到着したり出発したりするたびに、彼女は時折、老人の姿が目に留まった。彼はゆっくりと車両のドアに向かって歩き、背が高く痩せたその姿はプラットフォームの真ん中に消えていくようだった。見慣れたコートとスカーフのおかげで、彼女はすぐに彼だと分かった。しかし、一瞬にして彼の姿はぼやけ、賑やかな人混みの中に消えていった。杖を股に挟んだまま、静かに座っていたが、彼女が彼の隣に座る機会を得たのは、それから1年以上経ってからだった。彼は長いベンチに座り、薄暗い黄色い光の下で、まるで眠りに落ちるかのように頭を下げていた。霧の中を走り抜ける、蒸気を帯びた揺れる鉄の列車の真ん中で、彼女は彼の孤独な姿を静かに見つめていた。
列車が駅に到着し、乗客が次々と降りていった。老人はまだベンチでうとうとしていた。駅員が近づいて優しく呼ぶと、老人は目を覚まし、ふらふらと立ち上がった。荷物は、すり減った杖だけだった。老人は駅の入り口に向かってゆっくりと歩いた。駅の外では、バイクタクシーの運転手が数人駆け寄ってきて、乗せてあげようとした。老人は手を振って断り、ゆっくりと道の反対側、川にかかる鉄橋へと歩いていった。上からは雨粒がちらついていた。晩冬の雨らしい雨で、激しい雨ではないが、肌を冷やすには十分だった。好奇心を抑えきれず、彼女は適度な距離を保ちながら、静かに彼の後を追った。
道端から五色の花の香りが漂い、風の強い野原に強い香りが広がった。老人は橋に着くと立ち止まり、失くしたものを探すかのように川面を見下ろした。夕暮れ時の彼の老いた姿は、まるでそれが彼の既成概念であったかのように、彼の孤独を一層際立たせていた。唸り声を上げる冬の風が、寒気を切り裂いて吹き抜けた。彼女は長い間迷った後、彼に向かって歩いていくことにした。鉄板が激しく揺れ、彼は振り返った。「まだ私のことを覚えているの?」彼女は頭を下げ、親しみを込めた笑顔で挨拶した。
老人はじっと立っていた。銀色の眉毛の下の煙のような目にしわを寄せ、以前彼女をどこで見たか思い出そうとしているようだったが、思い出せないようだった。
「去年、あなたと一緒に電車を待っていたの…」と彼女は優しく思い出させた。彼は手を上げて額を軽く叩きながら、「ああ…思い出した。ミカンの皮をむいてくれたの…」と叫んだ。「私もついさっきまであなたと一緒に電車に乗っていたのよ」「この辺りの出身ですか?」「ええ!川の向こう側に住んでいます。この橋を渡ると長い未舗装道路があります。家はニハ村です」「ああ!」老人は興味深そうに叫んだ。彼女の言葉が彼の注意を引いたようだった。
午後は晴れ渡っていたが、雲が集まり始め、空は陰鬱な雰囲気を漂わせていた。老人は川から目を離すことができず、震える手で杖を握りしめ、感情的な表情を浮かべていた。「どこへ行くんだ?家まで送ってやるからな!橋の上は風が強いぞ!」 「わ…どこにも行かない。ここには行くところがないんだ」「どういう意味だ?子供や孫に会いに来たんじゃないのか?」老人は首を振り、遠くを見つめながら川を見下ろした。
時計を見ると、すでに夕方の六時だった。冬の夜は長く感じられた。この時間、母親はきっと外で心配そうに待っているのだろう。夕暮れに刻まれた老人の孤独な姿と、その寂しそうな瞳を見つめていると、彼女は目をそらすことができなかった。何かが彼女を分け与えるように引き寄せているようだった…。遠くの川面に、カッコウがホバリングしていたが、突然川底に舞い降りて姿を消した。くちばしに小魚をくわえて現れ、乾いた枝に舞い上がり、そこに立って獲物をついばんでいた。彼女はそっとこちらを覗き込んだ。老人の目はカッコウに向けられていたが、心はどこか別の場所にあるようだった…。
「若い頃、ここに住んでいた時期があったんだ…」老人は突然、まるで独り言のように低い声で言った。彼女は彼の言葉の一つ一つを静かに聞き取った。「あの日、君はここで恋人に会ったんだね?」老人は滑稽そうに目尻を細めて笑った。彼女は一瞬、その寂しげな姿の中に、かつては明るく勇敢な青年がいたことに気づいた。彼はポケットからハンカチを取り出し、冷たい午後の空気にもかかわらず汗でびっしょりと滴る額を拭った。
「あの日、私はここに配属されました。橋がなかったので、毎日この川を船で渡らなければなりませんでした…」老人はそこで言葉を止め、また呟いた。「この川には船が一艘しかなく、その日の船頭は若い娘でした…私たちは知り合い、そして恋に落ちました。愛はこんなにも自然に、そして美しく訪れたのです!その年、娘は19歳、私は23歳、結婚できる年齢でした。両親にこの話を聞いた時、彼らは強く反対しました。彼女と私は身分的に合わないし、うまくやっていけるはずがないと思ったからです。彼女はそれを知って私を避けていましたが、私はどうしても両親を説得しようと決意していました…ある時までは…」老人はそこで言葉を止め、タオルを取り出してこめかみを拭き、感慨深げに言った。その日、洪水が川を流れ下り、近隣の家々からたくさんの木材、水牛、牛などが流されました。当時、私は若く活動的だったので、人々の財産が洪水に流されていくのをただ見ているわけにはいきませんでした。泳ぎの得意な友人数人と、人々を助けるために駆けつけました。3時間以上も洪水に浸かり、疲れ果てていた私は、泳いで入ろうとしましたが、その時、上流から大洪水が押し寄せ、私と友人2人をさらってしまいました。渦に揉まれながらも、私は冷静に泳ごうとしましたが、試みるほどに深く沈んでいきました。あと一歩のところで死に瀕していると思ったその時、誰かが私の手を掴み、引き上げてくれました。命の危険にさらされる中で、彼女が私を支えてくれていることに気づきました。岸に運ばれましたが、そのまま意識を失いました。目が覚めると、私は診療所で横たわっていました。周りに誰もいないのに…」
老人は言葉を失い、極度の感情を露わにした。「家に帰ると、皆が同情の眼差しで私を見ていました。直感がそう告げていました。新しい家に駆け込み、岸辺に引き上げた妻が洪水に流されたことを知ったのです…」「あの時、誰も彼女を助けられなかったのですか?」彼女はショックで叫びました。老人は首を横に振りました。「誰もいませんでした。二人の友人も洪水に流されてしまいました」老人は胸を抱きしめ、黙り込みました。しばらくして、彼は囁きました。「二年後、私は仕事のために街に戻りました。妻と出会い、結婚するまで、誰も愛することができませんでした」「彼女に過去のことを話したことはありますか?」
老人は頷いた。「毎年その日になると、妻と私は白いユリの枝をここに持ち帰り、この川に流します。妻は私に平穏な人生をくれましたが、もう10年以上も亡くなっています…。私は…月に一度、ここに戻ってこの川辺に立ち…あの頃を思い出すのです…」。「まだ悲しいのですか?」と彼女は優しく尋ねた。「人には簡単には手放せない美しい悲しみがあります。それを心に抱えることもまた、癒しとなるのです」と老人は囁いた。
彼女は夕日に染まる川面を静かに見つめていた。冬の午後の冷たい風が吹き、ゆっくりと刻まれる時間の音のように響いていた。隣では、老人の声が今も囁いていた。「ある日、昼寝をしていると、彼女が戻ってきて私のそばに座り、優しく揺すった。『午後よ、起きて!』と。目が覚めると、もう午後は終わっていた。私は涙を流した。夢の中でも彼女は私を愛してくれていたのに…」
夜が更け、空の星々が川面に輝き、銀色の光が川面を照らし、餌を探しに遅く帰ってきた一羽の鳥がカサカサと音を立てた。冬最後の日の夕暮れの中、彼女は川から過ぎ去った時の思い出がこだまする音を聞いた。耳元で、老人の声がまだ囁いていた。「あの夜、僕と彼女は手を繋いで川岸を走ったんだ…」そう言って、ハンカチをポケットにしまい、彼女の方を向いた。「そろそろ市場の最終列車に間に合うように出発しないと。」
「さようなら、旦那様!」彼女はかがんで、彼のコートのボタンを留めるのを手伝った。「少し一緒に歩かせてください」 「一人でも歩けますよ、大丈夫ですよ!」老人は優しく微笑んだ。「私がよくここに来るのを忘れたのですか?道も、市場行きの電車も知っていますよ。夜8時15分には、ニハー駅行きの最終の市場行きの電車が出発しますよ」
老人は背を向け、その背中は夕暮れに溶け込んでいった。その下では、紫色のホテイアオイが数本、闇を吸い込んでいた。ホテイアオイは下流に流れているのだろうか、それともまだ古い川の真ん中に留まっているのだろうか、と彼女は思った。
出典: https://thanhnien.vn/chuyen-tau-cuoi-tren-ga-nhi-ha-truyen-ngan-cua-vu-ngoc-giao-185250308191550843.htm











![[インフォグラフィック] Galaxy Z Fold7:サムスンの最先端技術の飛躍](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/7/30/2fced87d84e54fb6afaee83be89735c1)


















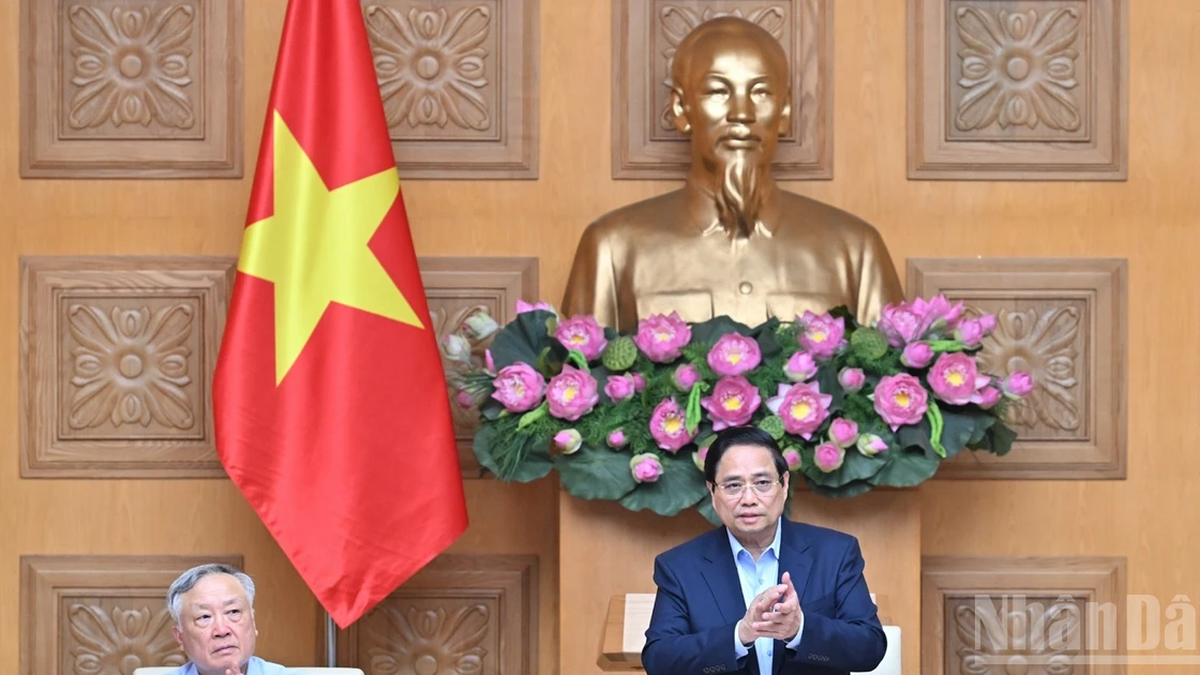








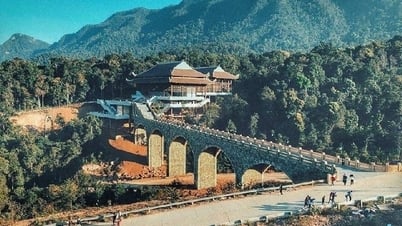





























































コメント (0)