
ホーチミン市工業大学の学生が会議に出席
写真: TH
大学環境で人工知能(AI)を活用する方法に関する示唆的な情報は、本日(6月5日)、ホーチミン市工業大学で開催された全国ワークショップ「デジタル技術、デジタル経済に関する法的課題(デジタル技術産業に関する法的枠組み)」で共有された多くの内容の1つです。
ワークショップでは、ホーチミン市工業大学の講師であるダン・ホアン・ヴー博士とチュオン・ティ・マイ博士が、「教育と学習におけるAI:デジタル大学における法的・倫理的境界」に関する研究成果を発表しました。講演の中で専門家らは、2023年のユネスコ報告書のデータを引用し、調査対象となった世界の大学の60%以上が、研修管理または教育に少なくとも1つのAIアプリケーションを導入していることを示しています。ベトナムでは、多くの調査で、大多数の講師や教員が、主に文書検索、多肢選択式テストの採点、教材作成など、少なくとも1つの教育段階でAIを活用していることが示されています。しかし、大学教育におけるAIの急速な発展と多様化は、現行の法制度では対応できない一連の法的・倫理的問題を引き起こしています。
2人の専門家は、ベトナムにおけるAIに関する法的ギャップを指摘し、具体的な規制の欠如だけでなく、専門法間の関連性の欠如、政策調整の遅れ、そして大学教育におけるAIエコシステムで中核的な役割を果たす政府、教育機関、テクノロジー企業の3つの主体間の制度的調整メカニズムの欠如も問題であると述べた。
具体的には、現行の高等教育法制度には、学術活動、教育、試験・評価、学習管理におけるAIの活用に関する直接的な規定が存在しないことが議論で指摘されました。現行の高等教育法は、教育イノベーションの内容について、主に機関ガバナンス、大学の自治、国際統合といった観点からアプローチしており、「 デジタル技術」「人工知能」「学術デジタルトランスフォーメーション」といった概念には言及されていません。現在協議段階にある高等教育法改正案では、デジタルトランスフォーメーション、技術の自治、デジタルインフラに関する全体的な方向性が概ね更新されたのみで、AIに特化した章や規定は未だ存在せず、教育におけるAIのリスク分析や品質評価といった方向性にも踏み込んでいません。
さらに、デジタルテクノロジー産業法案は、AIを含むデジタルテクノロジー製品・サービスに関する法的制度の構築において重要な方向性を示唆しているものの、教育分野、特に大学教育に関する具体的な内容は未だ明確にされていません。「AIコンテンツ作成」「AIトレーニング」「AI採点」といった概念は、この法案には全く登場していません。技術開発者(AI企業)と教育機関(技術利用者)の関係が明確化されておらず、不正確な採点やデータ漏洩といった事象が発生した場合の法的責任が未解決のままとなっています。
実践面では、2人の博士は次のように述べた。「ベトナムの大学は、教育、運営、学習においてAIをかなり積極的に活用していますが、その方法は断片的で、共通の方向性や統一された倫理的・法的基準が欠如しています。教育現場で使用されているAIシステムのテストツールと監視におけるギャップは、深刻な弱点です。現在、教育・学習で使用されるAIツールに対し、教育的、倫理的、または技術的な品質テストを受けることを義務付ける規制はありません。」
これを踏まえ、ホーチミン市工業大学の専門家は次のように述べている。「AIがより賢くなればなるほど、人間は選択の仕方、限界を知り、必要に応じて代替を拒否する方法を知る主体として、人間的な倫理的立場を主張する必要性が増す。AIが制御されなければ、学術的腐敗につながる可能性がある。知識が商品として生産され、学習者は行動データと化し、講師は精神的な啓蒙指導者ではなく『機械学習コーディネーター』になってしまうのだ。」
出典: https://thanhnien.vn/du-thao-luat-giao-duc-dh-sua-doi-chua-co-chuong-hoac-dieu-khoan-rieng-cho-ai-185250605162951268.htm







































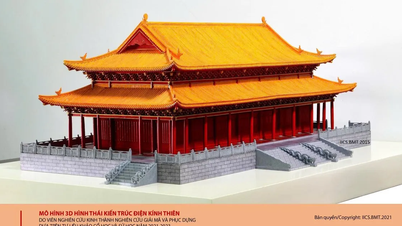





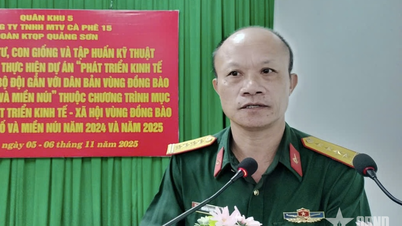


























































コメント (0)