
これまで統一された明確な見解がなかった、フランスに対する抵抗運動の初期を理解するために、聖遺物の名称や建造・修復などの関連情報を明らかにしたい。
名前について
1898年、第10海兵連隊のトレイユ大尉( ダナンのフランス・スペイン合同墓地の修復作業を指揮)の報告書によれば、「フランス・スペイン遠征軍の墓地は、ダナン市の中心部から7マイル離れたソントラ半島の端に位置している」。
1921年の修復記録では、維持管理状況について言及する際に「ティエンチャ墓地(ティエンサ)」という名称が使用されていました。極東考古学学校長が安南駐在官に送った公式文書には、「トゥーラン北部のソンチャ半島にある墓地の荒廃状態についてご報告ください」という要請がありました。安南駐在官事務所第一部がトゥーラン県知事に送った公式文書には、「フランス・スペイン墓地の保存状態の悪さについて」と記載されていました。このことから、この場所の名称の使用には一貫性がなく、主にフランス・スペイン墓地という名称が使用されていることがわかります。
しかし、民間文書によると、ダナンの人々は「イ・パンニョ墓地」という名称をよく使用しています。ベトナムの阮朝時代(1954年以前)には、「イ・パンニョ」はスペインを指して使われていました。そこで疑問が生じます。なぜ人々はそのような名称を使うのでしょうか?フランス・スペインという言葉を使うのは長すぎると考え、もっと短い名称を使うのであれば、なぜフランス墓地ではなくイ・パンニョ墓地を使うのでしょうか?
フランス植民地時代のダナンの歴史全体、特に第一次世界大戦後の20世紀初頭からの流れを見ると、インドシナのフランス政府が人々に日常の呼びかけでイ・パン・ニョという名称を使うように指示し、この遺跡からフランスという名称を排除、あるいは最小限に抑えたいという発想があったのではないかと考えられます。これも仮説ですが、これを通して研究者は、この特別な遺跡にフランス・スペイン墓地という名称を使うという視点を統一する必要があります。
墓地の改修
この墓地の現状を検証すると、この遺跡は実際にどのように建造され、修復されたのかという疑問が生じます。関連文書を調べたところ、1897年までにこの墓地は2段階の修復工事を経たことがわかりました。第1段階は1858年から1885年までで、墓地は基本的に元の状態のまま残っていたようです。
第 2 段階 (1885 年から 1889 年) では、トゥーラン領事館は周囲の柵の建設、入口の鉄門の設置、敷地内のいくつかの墓石に刻まれた文字のペイント、墓地周辺の整地などの改修を開始しました。
1894年、フランス植民地政府は地下納骨所を備えた石碑の設計図を描きましたが、1897年の嵐の後、石碑は完全に崩壊し、地下納骨所が露出しました。
そのため、1998年にインドシナ総督ポール・ドゥメールの指示の下、植民地政府はこの墓地の建設、改修、そして1898年7月13日の開所を計画し始めました。1921年にこの墓地は改修されましたが、礼拝堂のみが拡張されました。
フランス・スペイン墓地は、ダナンにおける外国の侵略者に対する抵抗戦争の初期段階を特定する上で、今でも特別な価値を持っています。
上記の議論は、学術研究の問題であるだけでなく、ここに刻み込まれた歴史的記憶をも呼び起こすものである。
この遺跡は、歴史的事実を尊重し、侵略の波が押し寄せる前のこの国の困難な初期時代を映す鏡として未来の世代のために保存するために、より科学的で統一されたアプローチを必要としている。
出典: https://baodanang.vn/hieu-them-ve-nghia-dia-phap-tay-ban-nha-o-da-nang-3303295.html


















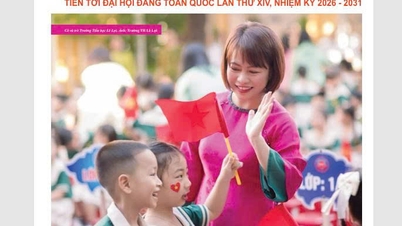














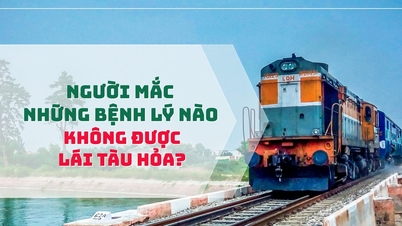
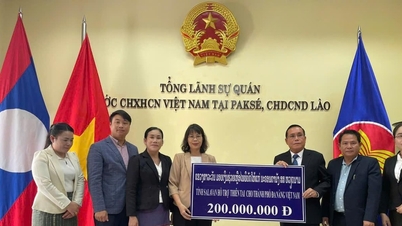














































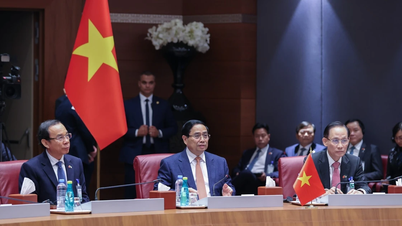
































コメント (0)