具体的には、1月に発行された債券の期間は10年と15年で、それぞれ49.74%と50.26%でした。国庫が発行した期間10年と15年の国債の利回りは、会期を通じて継続的に低下しました。月末の10年と15年の動員金利は、それぞれ4.36%と4.56%で、前月の最終会期と比較してそれぞれ29ポイントと24ベーシスポイント低下しました。このように、2022年2月から現在まで動員金利が継続的に上昇し、2022年12月に年間4.9%の最高値に達した後、2023年1月には低下傾向にあります。
特に、2023年1月の国債(G債)セカンダリー市場の取引総額は65,790億ドン、1セッションあたり平均3,549億ドンで、2022年12月と比較して9.48%減少しました。そのうち、アウトライト取引は市場全体の取引総額の53.74%を占め、残りはレポ取引でした。
国庫発行の国債の平均取引利回りは、15~20年および1年の期間で最も上昇し、現在それぞれ約4.91%および4.50%の平均利回りに達しています。一方、平均利回りは2年および20~25年の期間で最も低下し、現在それぞれ約4.17%および5.01%の平均利回りに達しており、債務証券の取引利回りの上昇と下降の傾向が逆になっていることを示しています。
満期別に見ると、市場全体では中長期債が最も取引量が多く、10年債、7~10年債、10~15年債がそれぞれ20.18%、19.11%、12.85%と集中しています。アウトライト取引では、7~10年債、10年債、20~25年債の取引量が最も多くなっています。レポ取引では、10~15年債と10年債の取引量が最も多くなっています。上記の統計から、市場では主に7年以上の中長期債が取引されていることがわかります。
[広告2]
ソースリンク





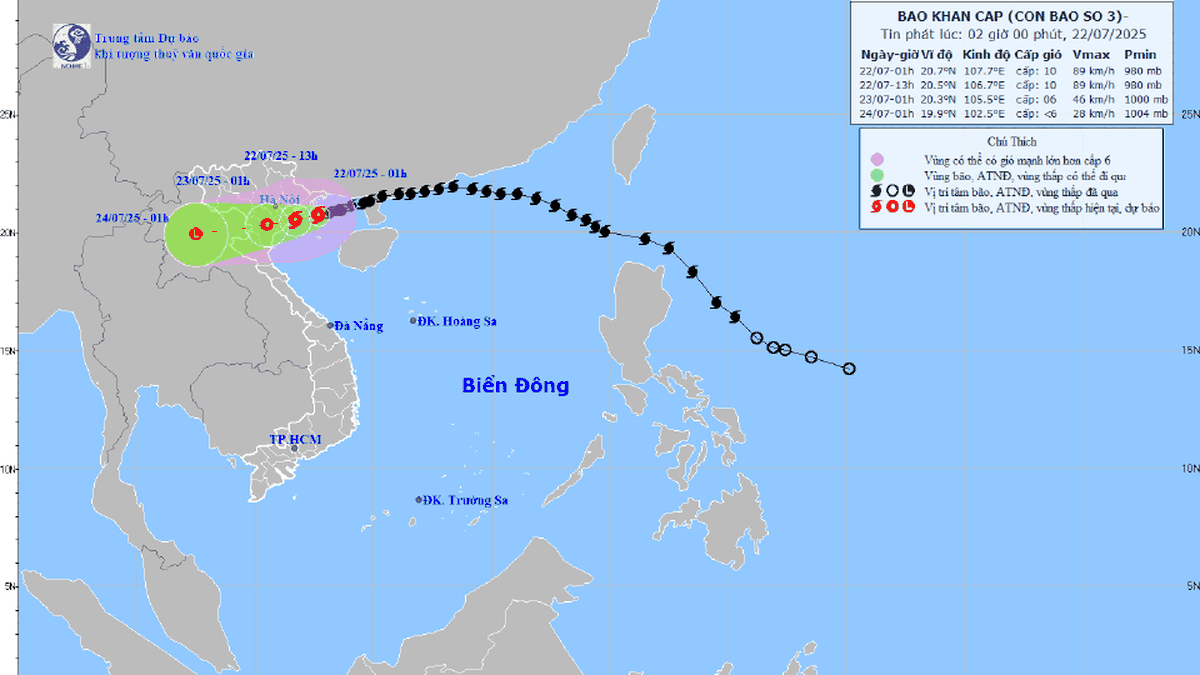

















































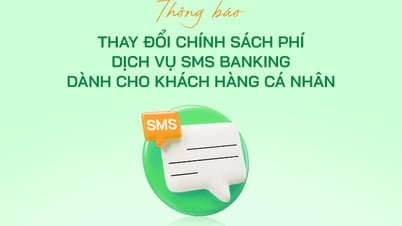

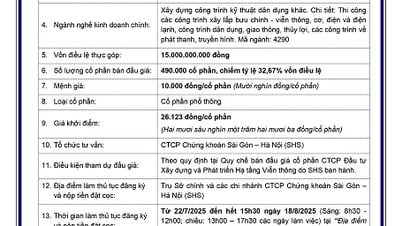








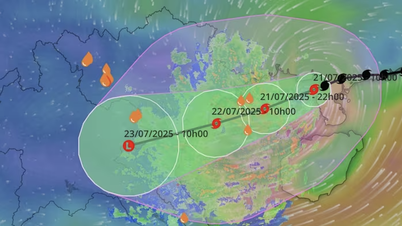





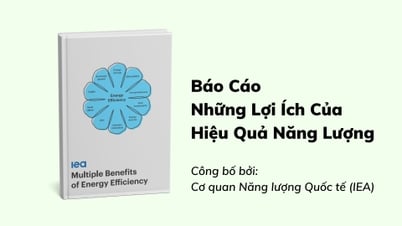





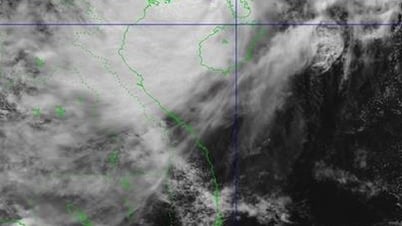





















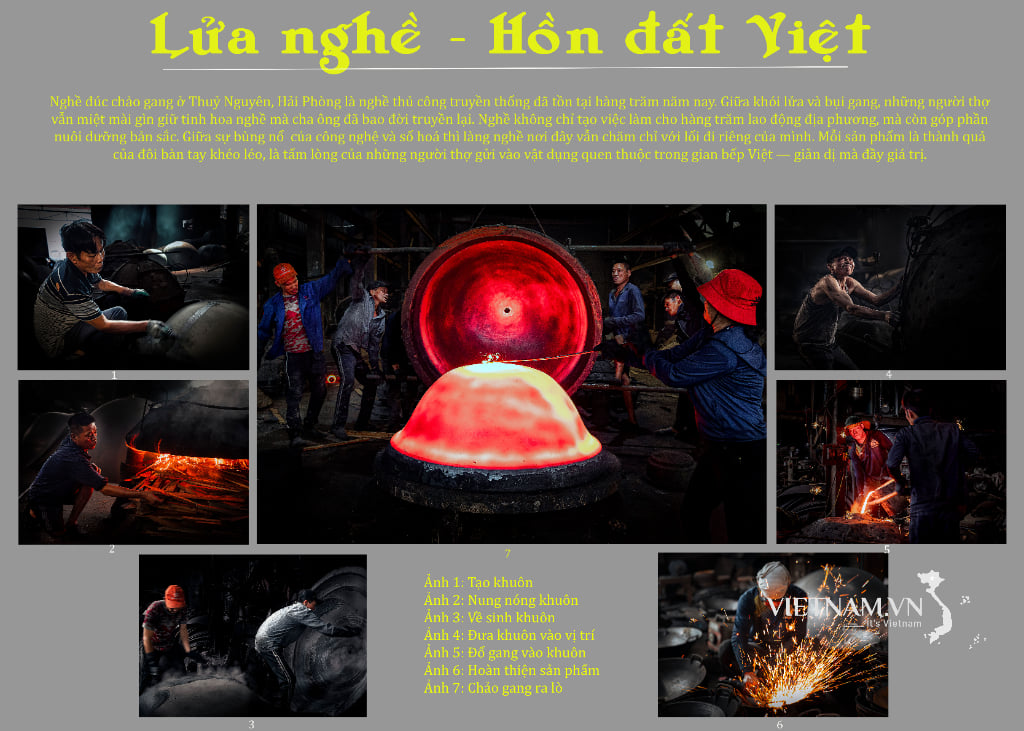

コメント (0)