日本の北部、岩手県にある黒石神社は、毎年行われる蘇民祭で有名です。これは日の出ずる国で最も奇妙な祭りの一つと考えられており、千年も昔の伝統に従って、何百人もの裸の男たちが木製のお守りの入った袋を奪い合います。
しかし、今年はこの祭りが開催される最後の年であり、人口危機が日本の伝統文化に与えた最新の影響を示すものとなる。毎年何百人もの参加者と何千人もの観光客を集めるこの行事の運営は、祭りに伴う重厚な儀式に対処することがますます困難になってきており、地元の高齢住民にとって負担となっている。
「これほどの規模の祭りを催すのは非常に困難です。今日の様子を見れば、多くの人が集まり、すべてが非常に盛り上がっていることがわかります。しかし、舞台裏では多くの儀式があり、やるべきこともたくさんあります…この厳しい現実を無視することはできません」と、729年創建の黒石神社の宮司、藤波醍醐氏はAFP通信に語った。

2月17日、黒石神社で蘇民祭が行われる。
日本社会は他のほとんどの国よりも急速に高齢化が進んでいます。この傾向により、特に小規模または田舎のコミュニティでは、数え切れないほどの学校、店舗、サービスが閉鎖に追い込まれています。
黒石神社の蘇民祭は、例年、旧暦1月7日から翌朝まで行われます。しかし、新型コロナウイルス感染症のパンデミックの間、祭りは簡素化され、祈りの活動と小規模な儀式のみが残された。
地元住民によると、2月17日の前回の祭りは短縮版で午後11時頃に終了したが、近年で最大の観客を集めたという。
日が沈むと、白いふんどしを締めた男たちが山の寺に行き、小川で沐浴をし、境内を練り歩きます。杉林の中、北日本の冷たい冬の風が吹く中、彼らは「ジャッソジョヤサ」(「悪よ、去れ」という意味)と唱えた。
何人かはカメラを手にして彼らの体験を記録し、数十のテレビクルーが寺院の石段や土の道を歩く男性たちを追った。
祭りのクライマックスは、お守りの入った袋をめぐって何百人もの男たちが寺院の中に群がり、叫びながら激しく押し合いを繰り広げる場面だ。
来年から、黒石神社は祭りの代わりに祈祷儀式やその他の方法で精神修養を継続する予定です。
フェスティバル参加者の西村康夫さんは「日本は少子高齢化と様々な仕事を担う若者の不足に直面している。これまでと同じことを続けるのは難しいかもしれない」と語った。
お守りを受け取り、長年祭りの運営に協力してきた地元住民の菊地敏明さんは、将来この祭りが再び開催されることを期待していると語った。
「形は変わっても、この伝統を守っていきたいです。参加して初めてわかることもたくさんあります」と祭りのあと、彼は語った。
日本各地の神社でも、男性がふんどしを締めて冷たい水に浸かったり、お守りを競い合ったりする同様の祭りが続いています。
いくつかの祭りは、存続するために現代の民主主義と社会規範に合わせてルールを適応させている。例えば、以前は男性に限られていた儀式に女性が参加できるようにしている。
[広告2]
ソースリンク


![[写真] ファム・ミン・チン首相が米国下院の超党派代表団を歓迎](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/5/28/468e61546b664d3f98dc75f6a3c2c880)

![[写真] ベトナムとハンガリーの首脳が写真家ボゾキー・デゾ氏の展覧会のオープニングに出席](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/5/29/94d8ceca5db14af3bf31285551ae4bb3)




















![[写真] 閉校式で別れを告げ、新たな旅立ちの準備をする12年生たち](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/5/28/42ac3d300d214e7b8db4a03feeed3f6a)



























































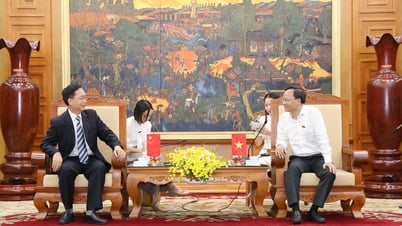



コメント (0)