 |
| 日本の経済成長に関する最新の統計では、日本が世界第3位の地位を失ったことが確認されている。(出典:共同通信) |
経済は夏の急激な減速の後、2024年第4四半期には平均年間成長率1.2%に回復すると見込まれているが、その年の数値を見ると、ドル建てで日本のGDPはドイツに遅れをとることがほぼ確実である。
日本のランキング下落は、国内で国の方向性について新たな疑問を投げかけるだろう。日本の政策担当者に対する国民の反応は、2010年に中国経済が日本を追い越し、現在では4倍の規模にまで拡大する見込みとなった当時ほど厳しくはない。
理由の一つは、経済が大きな為替変動に苦しんでいるという国民の認識です。他の要因としては、ドイツ経済の低迷、そして日本における株価上昇と日銀による2007年以来初の利上げの見通しなど、新たな夜明けの兆しが挙げられます。2月15日に発表される経済指標は、日銀に行動を促すきっかけとなる可能性があります。
第一生命経済研究所のエグゼクティブエコノミスト、熊野英夫氏は、日本のGDP減少の主因は為替変動だと述べた。また、低金利が日本経済の規模を縮小させていると指摘した。
国際通貨基金(IMF)によると、ドル建てで見ると、日本の経済規模は2012年の6.3兆ドルから2023年には約4.2兆ドルに縮小する見込みです。これは主に、円が昨年1ドル=80円未満から約141円に急落したことによるものです。名目円建てで考えると、この期間に日本経済は12%以上成長していた可能性があります。
一方、インフレが続き、エネルギー価格が高騰し、経済成長が鈍化する中で、経済政策に対する国民の不満から、ドイツ経済が日本経済を追い抜く可能性についてはほとんど注目されていない。
両国の経済は、人口の高齢化、天然資源の不足、輸出と自動車生産への依存という共通の問題を抱えている。
ドイツは労働力の減少に直面していますが、この傾向は日本ではより顕著で、2010年頃から人口が着実に減少しています。その結果、慢性的な労働力不足が生じており、出生率が低い状況が続く中で、この状況はさらに悪化すると予想されています。2023年第4四半期の日本GDPデータは、民間消費が横ばいとなると予想されており、経済の外需への依存度が高まっています。
一方、インド経済は今後数年間でこれら2つの国の経済規模を上回ると予想されています。IMFのデータによると、インド経済は2026年までに日本、2027年までにドイツを上回ると予想されています。
インドの人口は昨年、中国を上回り、今後数十年にわたり成長を維持すると予想されています。人口の3分の2以上が労働年齢(15歳から64歳)であるインドは、人口減少と高齢化に直面する他の多くのアジア諸国とは対照的に、より多くの財を生産し、技術革新を推進すると期待されています。
ゴールドマン・サックス・リサーチのインド担当エコノミスト、サンタヌ・セングプタ氏は、インドの人口規模は明らかに有利だが、労働参加率の上昇に伴い労働力を効率的に活用することが課題だと指摘する。企業が中国に関連する 地政学的リスクの軽減を目指す中、インドが規制緩和や関税引き下げによって投資誘致を拡大すれば、中国に対する優位性をさらに高めることができるだろう。
ナレンドラ・モディ首相率いる政府は、国内製造業の振興とインドを世界的な輸出拠点へと転換するため、数十億ドル規模の財政支援策を打ち出している。240億ドル規模のこのプログラムは、アップルやサムスン電子といった企業がインド国内に新たな施設を建設するなど、一定の成果を上げている。目標は、2025年までに製造業のGDPへの寄与度を25%に引き上げることだ。
日本は、その成長の可能性の一部を活用しようとしており、2030年までに国産半導体の売上高を3倍の15兆円(1000億ドル)以上に増やすことを目指す長期計画の一環として、生産能力の増強と国内半導体供給の確保に公的資金を投入している。
熊野氏は、日本は研究開発センターの建設など、国内にもっと技術集約型産業を確立する必要があると述べた。
日本が世界経済ランキングでの地位を失うことをそれほど心配していない理由の一つは、国民の生活水準が安定していることです。人口減少は、現地通貨建ての一人当たりGDPの維持に多少貢献しています。
しかし、日本は製品を生産し、消費するためにより多くの労働者を必要とします。より多くの外国人労働者を誘致することは、その方向への小さな一歩です。
(VNAによると)
[広告2]
ソース





















































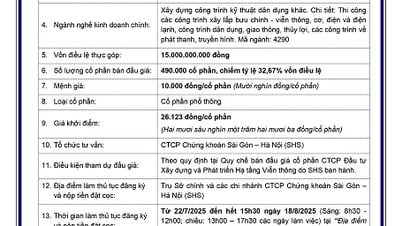












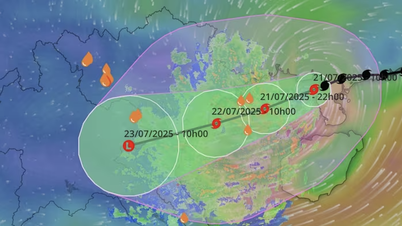





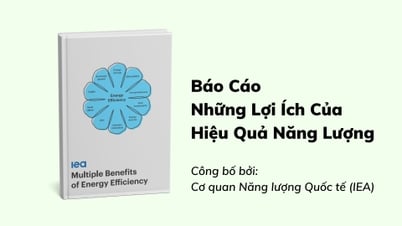





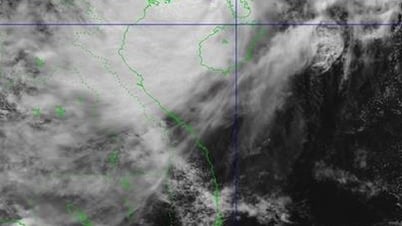























コメント (0)