T. TRUC(ジャパンタイムズ、共同通信による)
日本政府は、今後3年間の少子化対策の優先政策の一つとして、より多くの男性の育児休暇取得を奨励する計画を発表した。
育児休暇中に子供を公園に連れて行く父親。写真:共同通信
小倉昌伸保育担当大臣は、主に女性が担っている育児負担の不平等是正に取り組む決意を表明した。「仕事と育児の両立支援から、共働きや共同保育の推進へと転換し、あらゆる役割におけるジェンダーバイアスをなくすことを目指します」と小倉大臣は述べた。
政府のデータによると、日本の夫の家事・育児時間は1日約2時間であるのに対し、スウェーデン、ノルウェー、米国では3時間以上となっている。夫の家事・育児時間が増えれば、出生児数の増加が見込まれる。2021年度の男性の育児休業取得率はわずか13.97%だった。政府は、2025年までに取得率を30%から50%に引き上げ、2030年には85%に引き上げる目標を掲げている。「官民一体となって、育児休業が当たり前の社会の実現に向けて取り組んでまいります」と政府の報告書は述べている。
目標達成のため、政府は男性の育児休業取得基準を引き下げます。まず、産休中の収入減少への不安を軽減するため、給付を拡充します。具体的には、産後休業を含む育児休業を取得した夫婦への補助金を、現在の収入の80%から100%に引き上げます。また、子どもが2歳になるまでの就業時間が短縮された配偶者の収入減少についても、政府が補償します。「若者の収入増加は、少子化対策の前提条件です」と小倉氏は付け加えました。
しかし、収入減への懸念だけが、男性が育児休暇を取得できない唯一の要因ではありません。政府の調査によると、現在の職場環境は、育児休暇を取得している、または取得を計画している男性にとって好ましいとは言えません。具体的には、男性の41.4%が「収入を失いたくない」という理由で育児休暇を取得していないと回答し、27.3%は「職場の雰囲気が育児休暇の取得を難しくしている」または「職場が育児休暇を重視していない」と回答しました。また、21.7%は「自分にしか対応できない業務がある」と回答しました。
この問題に対処するため、政府は中小企業への補助金を増額し、育児休業中の従業員の代わりに仕事をする同僚に「補助金」を支払えるようにする計画だ。
三井住友海上は、この取り組みの先駆けとして、4月から育児休業を取得する社員の同僚に最大10万円を支給する制度を導入しました。当初は育児休業を取得する社員への給付金補助を予定していましたが、社員の声をヒアリングした結果、周りの同僚も給付金を受け取れば、より取得しやすくなるという声が上がりました。
[広告2]
ソースリンク







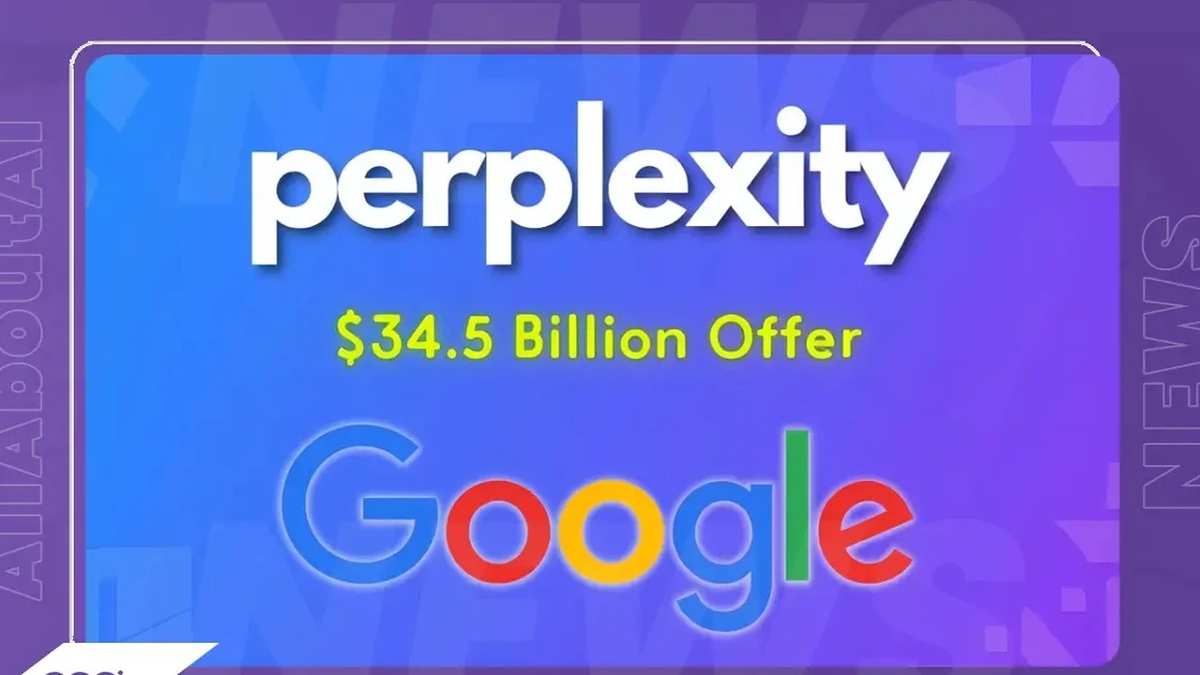






















![[写真]「ベトナムと共に前進」プログラム開始式典での赤と黄色の星](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/8/16/076df6ed0eb345cfa3d1cd1d7591a66f)

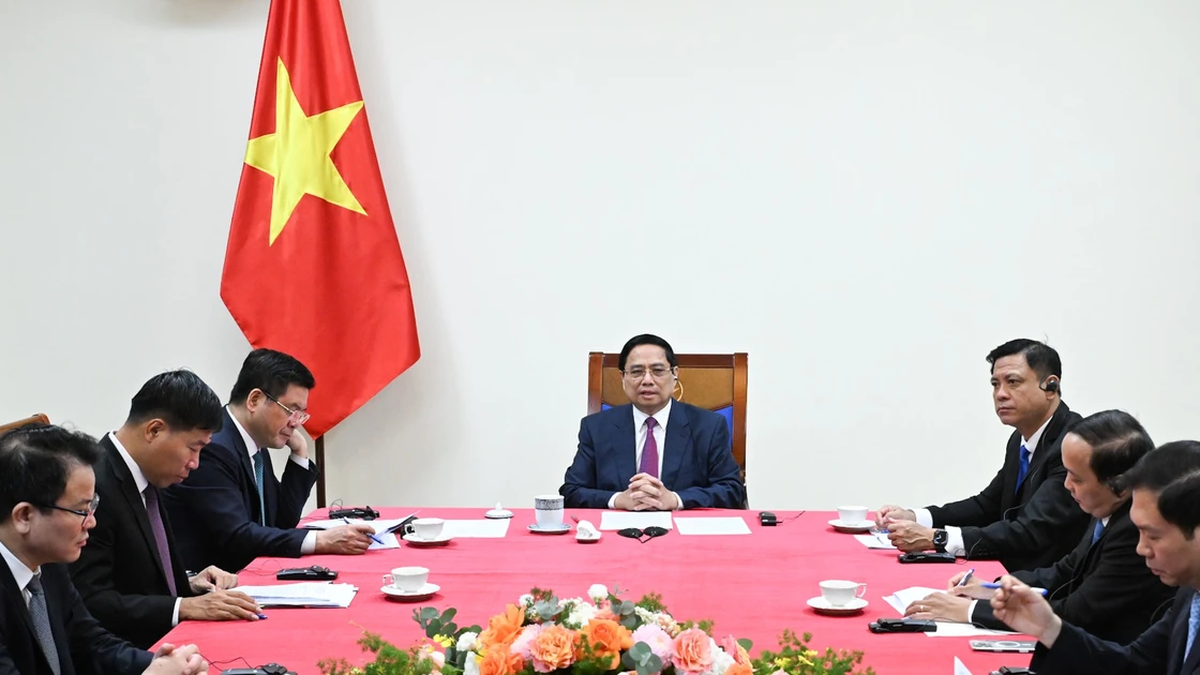












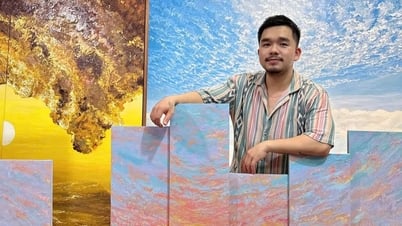























































コメント (0)