5月、夏がやってきます。農民時代の思い出といえば、畑や田んぼです。鋤、鍬、牛車に加え、棍棒や肩棍も農民の生活に欠かせない道具です。
今の若い世代は、三世代同居、四世代同居といった三、四世代が一緒に暮らす家庭を除けば、祖父母や両親が籐や竹でできた竹竿や担ぎ棒の記憶を持っているかもしれない。そして、若い世代がそれらを見る機会はおろか、使う機会もほとんどないだろう。なぜなら、現在市場では竹竿や担ぎ棒はあまり使われておらず、手押し車、自転車、バイクなどが代わりに使われているからだ。今も残っている竹竿は、観光や劇団、映画の撮影クルーが使う程度だ。消費の需要がなくなったため、以前ほど素朴で広く生産されなくなったのだ。私たちの祖父母や両親の時代、村の田んぼや畑で生計を立てたり、市場で取引をしたりするためには、竹竿1本と、運ぶための棒1本、そして、荷物を必要な場所まで運ぶための籠2つが必要でした。そのため、棒1本と運ぶための棒の話は、常に魅力的で興味深い話題です。

子どもの頃、特に夏休みになると、父はよく私を牛車に乗せて森へ薪や材木を集めに行きました。私の主な仕事は牛の世話でした。薪を集めた後、父が5〜7メートルの籐の棒を数本持ち帰るのを見ました。月明かりの夜や暇な時間には、父は家の池の水に浸した籐の棒を取り、それを様々な長さの細い棒に割り、家族の日常の道具として2本1組に結びました。父はよく大人から子供まで家族全員分、長いものも短いものも一度に何組も作っていました。私も自分用のものを持っていました。籐でできた2本の棒は、2つの竹かごと一緒に物を入れて運ぶのによく使われました。父が亜鉛線のコイルのトゲをペンチで取り除き、薪や米などの重くて硬い物を運ぶための鉄棒を2本作るのを見たこともあります。鉄棒は籠としてはあまり使われませんでした。肩にかける棒は、様々な種類の木から作られました。大工が磨いた木製の担ぎ棒には、両端に棒を固定するための目印が付けられています。これは、母親や姉妹が日用品を運ぶ際によく使われます。若者や大人が米、肥料、薪の束、農産物などを運ぶ際に使う棒は、硬くて短いものです。この担ぎ棒は、多くの場合竹で作られています。硬くてしなやかな小さな節のある竹の根を削り、肩にかけた時に両手でちょうど良い長さになるように、長さや短さを調整して担ぎ棒を作ります。担ぎ棒の両端には、棒の両端に引っ掛けるための節が2つ彫られています…
1980年代、私が中学生だった頃、村の川や小川から汲んだ水を、ミョウバンを塗った壺にバケツで汲み、炊事や入浴に使っていました。母が持っていた両端が尖った木製の担ぎ棒をよく使っていました。担ぎ手は慣れていなかったため、バケツが揺れて足に当たったり、水が飛び散ったりすることもありましたが、次第に慣れてきて揺れなくなりました。私の故郷はハム・トゥアン・ナム郡の純農業地帯で、担ぎ棒と一対の籠は常に母親や姉妹たちの肩に担がれ、日々の生活に役立っていました。
今、私の故郷には田んぼはなくなり、土手や畑は日に日に消えていっています。母や娘、あるいは農夫が肩に担いだ竿を担ぐ姿は、もはや完全に消え去ってしまいました。社会の進歩と科学技術の発展に伴い、機械が原始的な道具に徐々に取って代わり、人々は日々の労働に多くの労力と汗を費やすことなく済むようになりました。しかし、正直なところ、田舎で暮らし、その後都会で働くようになった私や人々の心の中には、故郷に帰るたびに、肩に担ぐ竿という素朴でありながら詩的なイメージが懐かしく思い出されます。月明かりの中、水を運び、二つのバケツに竿をかけて休ませた日々、そして子供たちが市場から帰ってきて竿に何か入っていないかと母親を待つ姿…そして、昔の田舎、貧しく苦しい時代の二本の肩に担いだ竿への郷愁に、私の心はときめきます。
[広告2]
ソース






![[動画] 100以上の大学が2025~2026年度の授業料を発表](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/7/18/7eacdc721552429494cf919b3a65b42e)

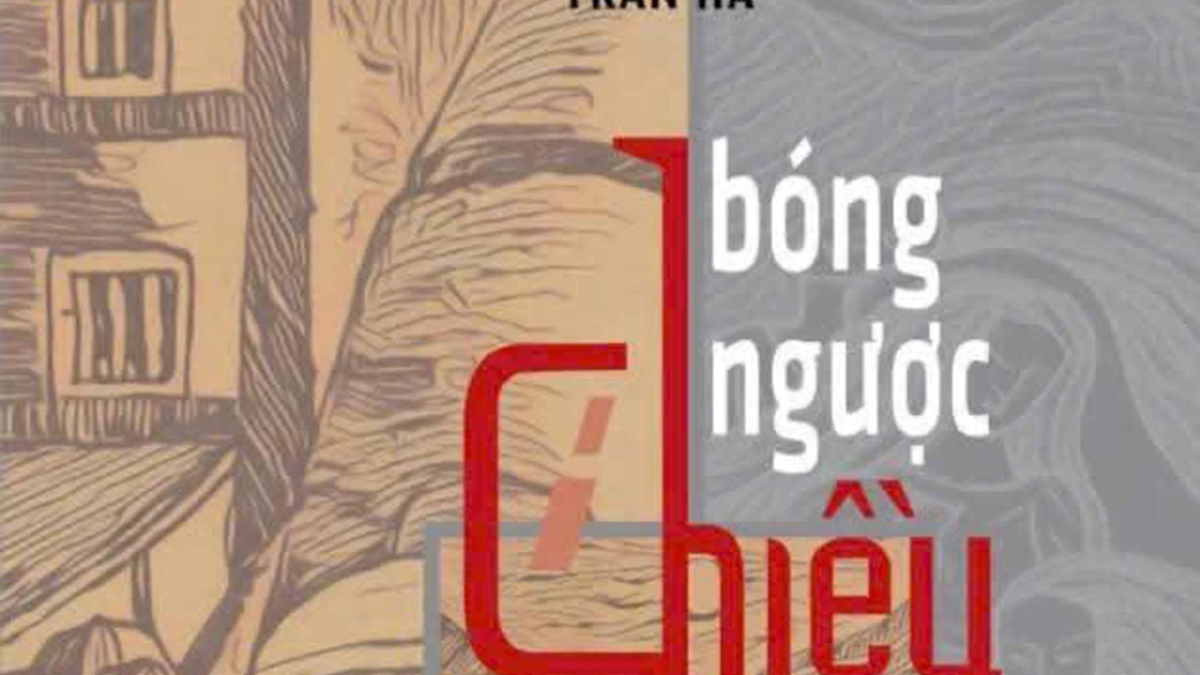

























































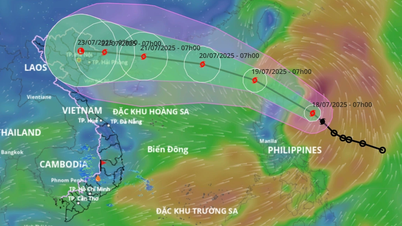



























![[インフォグラフィック] 2025年には47の製品が国家OCOPを達成する](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/402x226/vietnam/resource/IMAGE/2025/7/16/5d672398b0744db3ab920e05db8e5b7d)





コメント (0)