戦争というテーマは、映画製作者が常に活用し、視聴者にメッセージを伝えたい貴重なリソースでした。
鶴は飛ぶ(1957年)
ミハイル・カラトーゾフ監督による映画『鶴が舞いゆく時』は1957年に制作されました。ヴェロニカという女性を通して、戦争における女性の運命を鮮やかに描き、何百万人もの観客を涙で満たしました。また、ヴェロニカが戦争という過酷な日々を待ち望みながら生き抜いた時の、深く悲しげな瞳も、何百万人もの観客の記憶に焼き付きました。この作品は後に、1958年のカンヌ国際映画祭でパルムドールを受賞しました。
三島由紀夫 四つの章からなる生涯(1985年)
日米合作の本作は、アメリカ人脚本家・映画監督のポール・シュレイダーが監督を務め、オール日本人キャストで構成されている。三島の生前のエピソードを振り返る回想シーンを通して、観客は三島が病弱な少年から戦後日本を代表する作家の一人へと成長していく過程を目の当たりにする(三島は成人後、病気と軍国主義的な男らしさと肉体文化への執着から、自ら筋力鍛錬を積んだ)。近代日本の物質主義への「嫌悪」が、彼を極端な伝統主義へと駆り立てた。
人間の条件 I、II、III(1959)
『人間の条件』は、日本映画史上最高の監督の一人である小林正樹監督による、壮大な日本の戦争ドラマ三部作です。五味川純平の同名小説を原作としています。『人間の条件』は、極めて残酷な戦争という文脈における人間の精神を包括的に描き出しています。
火垂るの墓(1988年)
『火垂るの墓』は、スタジオジブリが制作し、1988年に東宝で公開された日本のアニメーション映画です。脚本・監督は高畑勲。原作は野坂昭如の同名小説で、作者の妹への謝罪として半自伝的な形で執筆されました。
ロジャー・イーバートをはじめとする批評家は、『火垂るの墓』を史上最も力強い反戦映画の一つと評しています。アニメーション史家のアーネスト・リスターは、本作はこれまで観た中で最も人道的なアニメーション映画だと述べています。日本では、この映画は反戦感情というよりも、自尊心についての寓話として解釈されることが多いです。
夜と霧(1956年)
「夜と霧」は、アラン・レネ監督によるフランスのドキュメンタリー映画で、ヨーロッパにおけるナチス強制収容所の惨状を描いています。ガス室や死体の山といった映像だけでなく、非倫理的な科学・医学実験、レイプ、そして捕虜の処刑シーンなど、収容所における囚人への非人道的な扱いが克明に描かれています。その厳しい真実味が評価され、戦争の惨状を記録したドキュメンタリーとして高い評価を得ています。
シンドラーのリスト(1993)
この映画は、ナチスのホロコーストの間、自分の工場で働かせることで1000人以上の人々(主にポーランド系ユダヤ人)の命を救ったドイツ人実業家、オスカー・シンドラーの生涯を基にしている。
『シンドラーのリスト』は、アカデミー賞7部門(ノミネート12部門)を受賞。作品賞、監督賞、脚色賞、作曲賞など、数々の主要賞も受賞しました。アメリカ映画協会は、この映画を「アメリカ映画史上最高の100本」の第8位に選出しました。また、2004年には米国議会図書館が米国国立フィルム登録簿への保存対象に選定しました。
ショア(1985)
『ショア』は、クロード・ランツマン監督による壮大な歴史ドラマで、ホロコースト(第二次世界大戦中、ナチス・ドイツとその同盟国によって、男性300万人、女性200万人、子供100万人を含む、ヨーロッパのユダヤ人600万人が虐殺された)を描いています。この映画は公開当時、傑作として批評家から絶賛され、現在では史上最高のドキュメンタリーの一つとされています。
来て見てください(1985)
「おいで、見よ」は、エレム・クリモフ監督によるソビエト戦争映画で、ナチス占領下のベラルーシ・ソビエト社会主義共和国を舞台としています。「おいで、見よ」の恐ろしい物語は、14歳のフリオラの目を通して語られます。母親の反対を押し切ってベラルーシのパルチザンに参加したフリオラは、後にナチスの残虐行為と、この時代に東欧の人々が耐え忍ばなければならなかった苦しみを目の当たりにします。
キム・ニュン/VOV.VN
[広告2]
ソースリンク












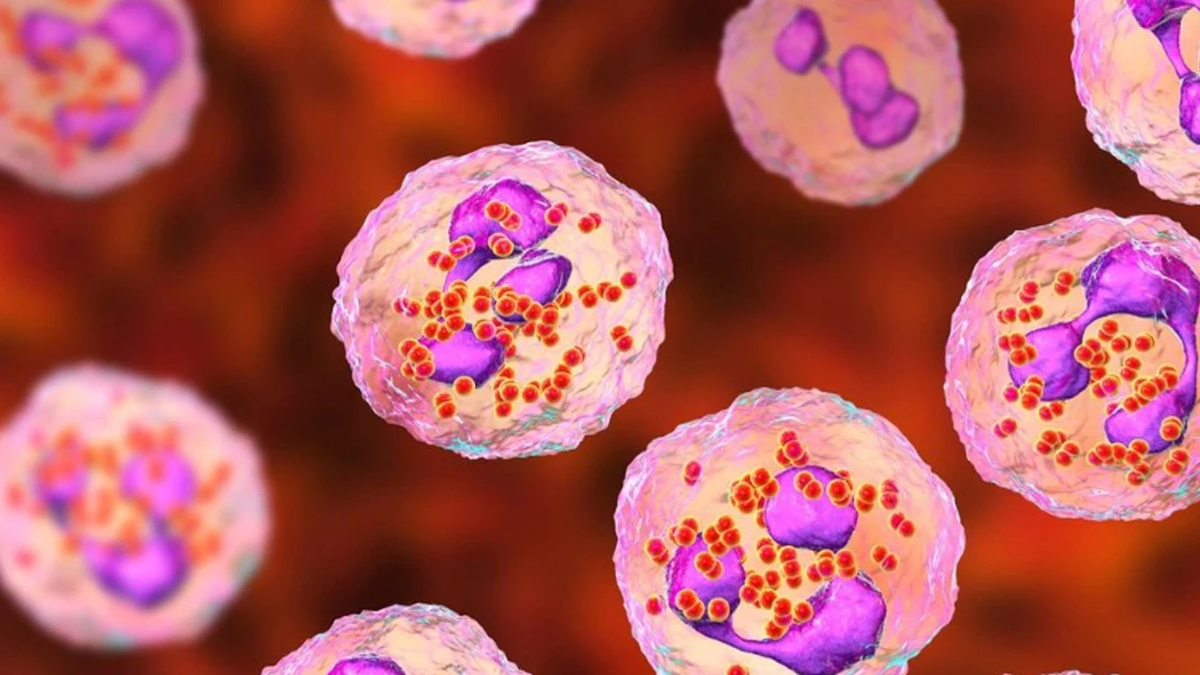





























































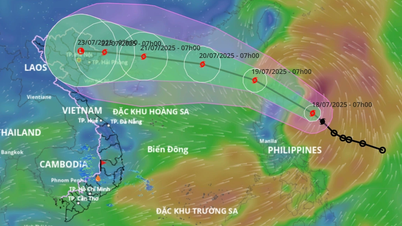



























![[インフォグラフィック] 2025年には47の製品が国家OCOPを達成する](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/402x226/vietnam/resource/IMAGE/2025/7/16/5d672398b0744db3ab920e05db8e5b7d)





コメント (0)