ホーチミン市ゴーヴァップ地区に住むグエン・ゴック・フエンさんは、自身の体験を語り直し、会社員による「無邪気な窃盗」に対するより多くの視点を共有したいと考えている。
数日前、6歳の息子が友達や先生に送るクリスマスカードを飾るのに、A4の両面印刷用紙が必要でした。彼女の家族は紙をほとんど使わず、主に片面印刷の用紙を使っていました。彼女は思わず嬉しそうに言いました。「明日、お母さんの会社に行って、息子にA4の用紙を買ってこようかしら。」
息子は抗議しました。「お母さん、新聞を買いに行かなきゃ。どうして会社の新聞を取ったんだ?それはあなたのものじゃない。会社の新聞を取るのは盗みだ!」
フイエンさんは愕然とした。母親は、娘が貪欲さ、怒り、無知、醜い行動、他人のものを自分のものにしてしまうこと、そして間違えることが当たり前になっていることに気づいた。彼女はよく「都合よく」会社から紙とペンを持ち出し、それを使っている。
それでも、彼女は毎日子供たちに「お腹が空いても空いていなくても、清潔にしておきなさい。ぼろぼろでも香りを漂わせておきなさい」「落とし物を見つけたら持ち主を探して返しなさい」と教えているのです...
他人の物を自分の物のように取る、つまり率直に言えば「軽窃盗」――倫理に反する行為――は、至る所で見受けられます。こうした「泥棒」行為の加害者は、「プロの」スリや万引き犯、あるいはまだ十分な知識を持っていない子供たちではなく、教育を受けた大人、経営者、従業員、労働者などです。

ホアン・トゥー・フォー1小学校の寄宿学校での食事中に、生徒たちがご飯に麺をすくっている(写真はVTV24のクリップから)。
学校給食の削減が相次ぎ、近年、蔓延する「窃盗」行為が社会の激しい怒りを招いている。 ラオカイで発生した、11人の生徒がインスタントラーメン2袋を米と一緒に薄切りにして食べた事件は、社会全体を揺るがした。
建設請負業者が資材を節約したり、修理工が実際とは異なる機械の状態を報告したり、テクノロジーベースのバイクタクシーの運転手が会社に%の手数料が失われるのを避けるために顧客にアプリで乗車をキャンセルするように求め、顧客が同意したりすることで、盗難を特定することもできます...
しかし、窃盗とは、他人の食べ物、持ち物、お金を自分のものにするだけではありません。他人の知識や時間を奪うことも含まれます。
盗作は、教師が追加授業の分を確保するために通常の授業からレポートを「カット」した場合に発生することがあります。
近年、ベトナムにおける科学研究論文の総数が着実に増加していることも、この現象と言えるでしょう。多くの専門家は、この数字の背後にある真実は、研究プロセスに参加していない人物を著者や共著者として挙げることや、盗作といった科学的誠実性の侵害のリスクにあると警告しています。これは、知識という装いの下に巧妙に隠蔽された「盲目」行為でもあります。
「窃盗」といえば、バクニン省農業局長が勤務時間中に職員とゴルフをしていたという最近の事件を思い出さずにはいられません。このような勤務時間の「窃盗」は、実際には珍しいことではありません。

VTCニュースは、バクニン省農業局長が勤務時間中にゴルフをしていた事件について報じた。
子供の頃から盗むことを「教えられた」?
ダクラク省バンメトートにあるフライドバナナチェーン「ゼロ7」のオーナー、トラン・チュウ氏は、店のガスコンロの火仕切りが盗まれたと話した。手のひらほどの丸い鋳鉄片をスクラップとして売った人は、おそらく数ペンスしか手に入らなかっただろうが、被害に遭った人にとっては大きな損失だった。
窃盗事件の後、男性はベトナム人の軽窃盗癖について嘆いた。トリウ氏は、マンホールの蓋を盗んだり、線路のボルトを外したり、車のロゴやワイパーを壊したり、バイクのバックミラーを盗んだり、さらには庭の鉢植えを盗んだりするベトナム人の例を挙げた。
トリウ氏は、この些細な窃盗について説明しながら、胸が張り裂ける思いでした。幼い頃から、学校に通う子供は、模擬試験の「盗み」や他人の試験問題の模写に慣れています。観察授業の「配置」を目の当たりにし、先生は自然に生徒を静かに座らせ、どの生徒が話すか、どの生徒が答えるかを決めます…。先生と生徒が一緒にカンニングをしていたなら、子供が成長して、ずる賢く盗むことが普通のことだと気づかないのはなぜでしょうか?
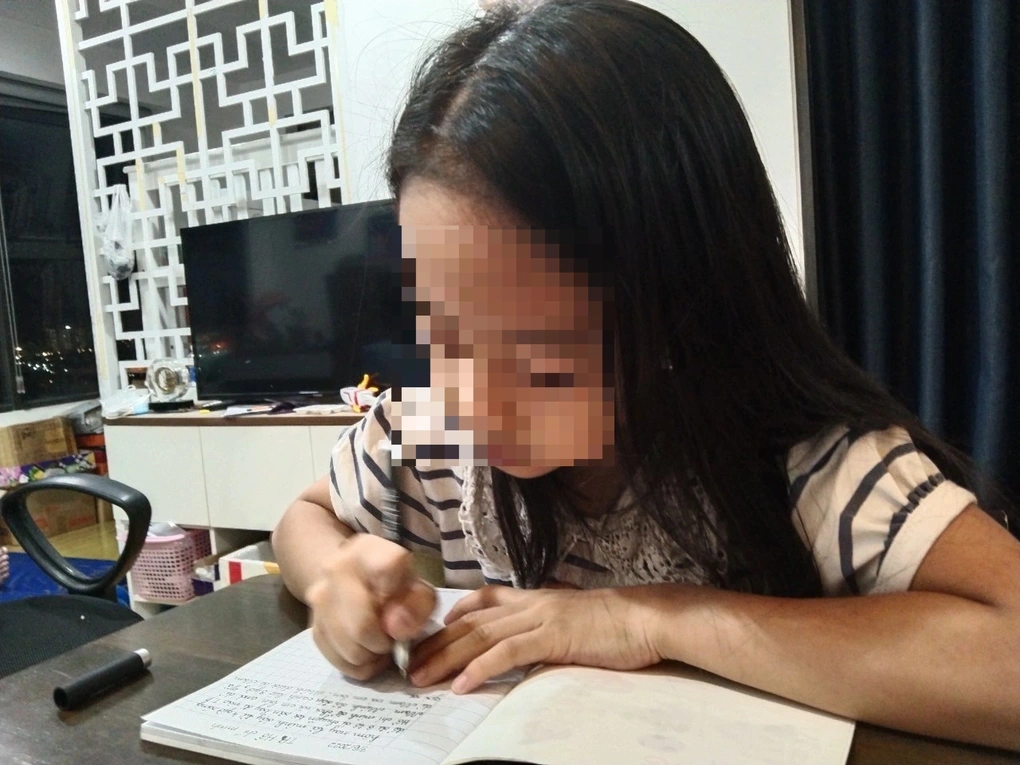
子どものころに習う模範作文は、子どもに「盗む」という考え方しか植え付けないと言われています(イラスト:ホアイ・ナム)。
ホアセン大学の元学長ブイ・トラン・フォン博士が語ってくれた、教育協力プログラムで海外留学したベトナムの優秀な女子学生の事例をもう一度お話ししたいと思います。
最近、ある外国で、彼女の最初のエッセイは「とても良い」「とても良い」と評価されましたが、点数1点と厳重警告を受けました。理由は、彼女のエッセイが多くの情報源を勝手に引用していたことが発覚したためです。
しかし、ゴック・フエンさんと同じように、この女子生徒もそれが盗作、つまり盗作であることに気づいていませんでした。彼女は幼い頃、教師が事前に用意したサンプルエッセイを生徒に渡し、それを暗記するように求め、試験当日にはそれを書き写すだけという生活に慣れていました。それ以来、生徒たちは他人の考えや言葉を盗用することに慣れてしまっていたのです。
ベトナムに帰国したある日本の教育研究者は、まず第一に、他人のものを自分のものとして取らないという教訓をすべての人に教えたいと話してくれました。なぜなら、それは尊厳、道徳、自尊心、そして自尊心だからです。
[広告2]
ソースリンク










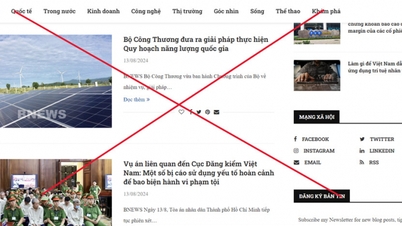








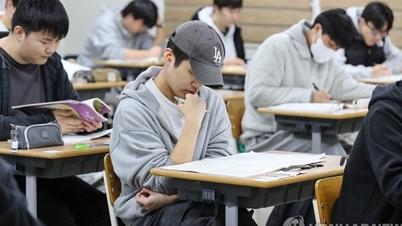







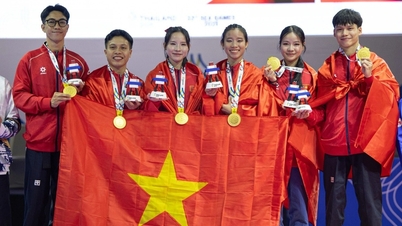










![[動画] ドンホーの民画制作の工芸が、ユネスコの緊急保護が必要な工芸品リストに登録されました。](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/402x226/vietnam/resource/IMAGE/2025/12/10/1765350246533_tranh-dong-ho-734-jpg.webp)




































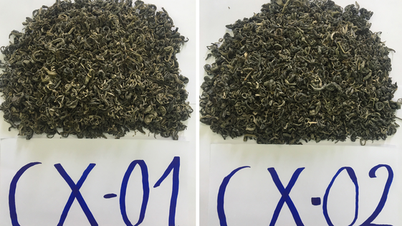






























コメント (0)