モデルとプロジェクトから生まれた「甘い果実」
ハイフォン市は、推定総面積1万1千ヘクタール以上を有し、汽水、海水、淡水養殖の発展に多くの潜在性と優位性を有しています。特に淡水養殖は、ティエンラン、ヴィンバオ、アンラオ、キエントゥイ、キエンアンなどの地区に集中しており、ソウギョ、コイ、ティラピア、ナマズ、オオテナガエビ、観賞魚など、多様な魚種が養殖されています。

ティエンラン県における雄だけのオオテナガエビ養殖モデル。写真:ディン・ムオイ
オオテナガエビは、経済的価値の高い養殖種であり、1998年以来ハイフォンで積極的に開発されてきました。しかし、養殖業者の技術と管理レベルの低さ、伝統的なエビの品種、池の中のメスのエビの比率がオスのエビより高いなどの理由で、開発と拡大は遅れています。
このような状況に直面し、ハイフォン農業普及センターは近年、多くのパイロットモデルを実施し、驚くべき成果を上げてきました。収入増加だけでなく、環境的・社会的価値も実現しています。例えば、2022年には、アンラオ県タンダン村に住むグエン・ヴァン・ダム氏の家庭で、1ヘクタール規模の養殖を実施しました。この家庭は長年にわたりオオテナガエビの養殖に携わってきましたが、多くの制約により、その効率は高くありませんでした。
モデルに参加した後、グエン・ヴァン・ダム氏は種苗、餌、技術の提供を受け、綿密かつ体系的なモニタリングを実施した結果、生産性が向上し、生存率も高まり、コストも削減されました。この成功を受け、グエン・ヴァン・ダム氏はモデルを7ヘクタールに拡大し、毎年約15トンのエビを平均30万ルピー/kg以上の価格で生産しています。
「オオテナガエビの養殖はシロエビの養殖よりも簡単ですが、生産性は低く、1回の収穫で1ヘクタールあたり約2トン、2回の収穫で30トンです。しかし、オオテナガエビは価格が高く、病気にもかかりにくいため、全体的な効率は依然として優れています」とダム氏は述べた。
ハイフォン農業普及センターは2024年、ティエンラン県ティエンミン村に住むファム・ヴァン・ニエウ氏の家庭において、0.7ヘクタールの試験規模でオオテナガエビ養殖モデルを導入します。これは、必要な基準を満たし、自発的にプロジェクトに参加し、プロジェクトの技術プロセス、指示、および規則を遵守することを約束する選定された家庭を対象としています。
モデル実施過程では、品種、食料、化学薬品、生物製剤などの50%の支援を受けたほか、農業普及センターから水産養殖の発展を指導できる修士号と水産養殖を専門とするエンジニアも同世帯に割り当てられた。

人々はモデルに参加することで得られた成果に興奮しています。写真:ディン・ムオイ。
これらの職員は、水生病害および疫学の研修を受けており、VietGAP水産養殖基準の研修も受けており、全雄の巨大淡水エビ養殖に関する技術指導を提供して、専門的かつ技術的なサポートを提供することができます。
ハイフォン農業普及センターは、生産量を確保するため、収穫後の生産物購入において企業と協力する農家を支援してきました。人々は約束を守り、プロセスを遵守し、企業は生産物消費契約を厳格に履行することで、農家にとって有利な条件を整えています。
その結果、専門家は、このオオテナガエビ養殖モデルが従来のモデルと比較して生存率が4~10%向上し、コストが削減され、生産性が25~80%向上し、要件を満たしていると評価しました。収穫時には、平均利益が従来のモデルより30~55%高い約9億ドンに達し、予想を上回る成功を収めました。
「伝統的な農業モデルは環境変動による困難に直面し、病気の発生にもつながりやすい。しかし、農業普及センターが指導するモデルに従って農業を行うことで、多くの限界を克服できる。さらに、バイオ製品の使用は環境と病気の制御に役立ち、VietGAP基準、食品安全衛生基準を満たす製品を生産し、消費者のニーズに応えるとともに輸出も目指す」とファム・ヴァン・ニュー氏は述べた。
複製対象
ハイフォン農業普及センター養殖技術移転部門長のグエン・ティ・タン博士によると、近年の全雄性淡水エビ養殖モデルの実際の実施から、2段階の全雄性淡水エビ養殖は多くの好ましい結果を達成していることがわかったという。
社会的には、このプロジェクトはハイフォンの人々にとって、養殖業の拡大、環境汚染の削減、疾病の抑制、そしてエビの安定生産の確保に貢献しています。生産物は食品衛生・安全基準を満たしており、輸出額の増加と農業・農村経済の発展に貢献しています。また、このプロジェクトは、農家に対し、VietGAP基準の適用、意識改革、そして科学技術の生産への応用を指導しています。

グエン・ティ・タン博士 - ハイフォン農業普及センター養殖技術移転部門長 - モデルの直接的な実施者。写真:ディン・ムオイ
環境面では、このエビ養殖プロセスは、国の持続可能な開発戦略に沿って、環境を保護しながら、汚染と廃棄物の削減に貢献しています。養殖業者は、新しい技術の移転や品種、資材に関する支援の恩恵を受け、供給から消費までの連鎖的なつながりを構築しています。
「このプロジェクトは、農家や普及員の意識向上にもつながり、彼らの学習と技術向上を支援します。このプロジェクトは、ハイフォン市および近隣省の多くの養殖施設への技術移転を継続する計画があり、大きな可能性を秘めています」とグエン・ティ・タン博士は述べています。
タン氏によると、オオテナガエビは20世紀90年代から養殖されてきましたが、主に雄雌両方を飼育する、粗放的かつ伝統的な方法で行われています。ハイフォン市では、商業的な養殖モデルはアンラオ、キエントゥイ、キエンアンの各県でのみ見られ、総面積は約30ヘクタールです。
二段階式エビ養殖には、養殖池が小さく、管理が簡単で、放流前のエビのサイズが大きく、養殖時間が短縮され、環境負荷が軽減され、池の底がきれいになり、密度や生産性、生産量が増加し、病気が減り、コストやリスクが軽減されるなど、多くの利点があります。
さらに、このモデルは農作業時間を短縮し、単位面積あたりの経済効率を向上させることにも役立ちます。同時に、環境に配慮した新たな方向性と手法を生み出し、農家や漁師の生産活動における選択肢を広げます。大量生産にも完全に応用可能です。
しかし、現在の全雄の淡水エビ養殖も気候変動により多くの困難に直面しており、資本とインフラの不足により養殖業者が二段階技術に投資することが困難になっています。
さらに、北部市場、特にハイフォンでは、オオテナガエビ専用の飼料が不足しており、生産コストが高くなっています。エビの生産量は、主に国内消費向けの集中生産地域を形成するほど大きくなく、生産量は不安定です。
その理由としては、耕作期間の長さ、耕作面積の狭さ、水利の未整備、そして農家の資金と技術不足などが挙げられます。効率を向上させるには、技術的なプロセスを習得し、池の管理を行い、安定した水環境を確保する必要があります。
モデルの結果に基づき、ハイフォン農業普及センターは、そのモデルを、ティエンラン県のフークオン食品加工会社、サンガン株式会社、クエットティエン、バックダン地区の一部農家、アンラオ県のタンダン、チュオントー村、キエンアン県のヴァンダウ、フーリエン区、ヴィンバオ県のヴィエットティエン、チュンラップ、カオミン村などの農業施設に移転し、複製し続ける予定です。
出典: https://nongnghiep.vn/nuoi-tom-cang-xanh-toan-duc-de-nuoi-lai-lon-d745177.html









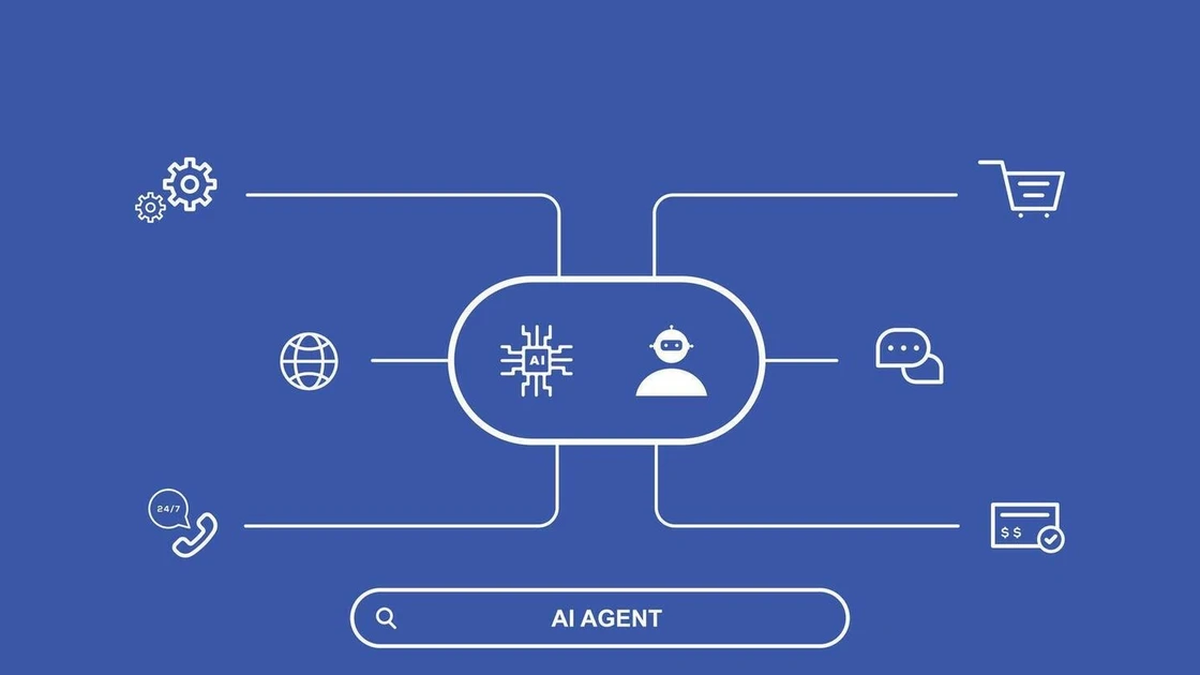

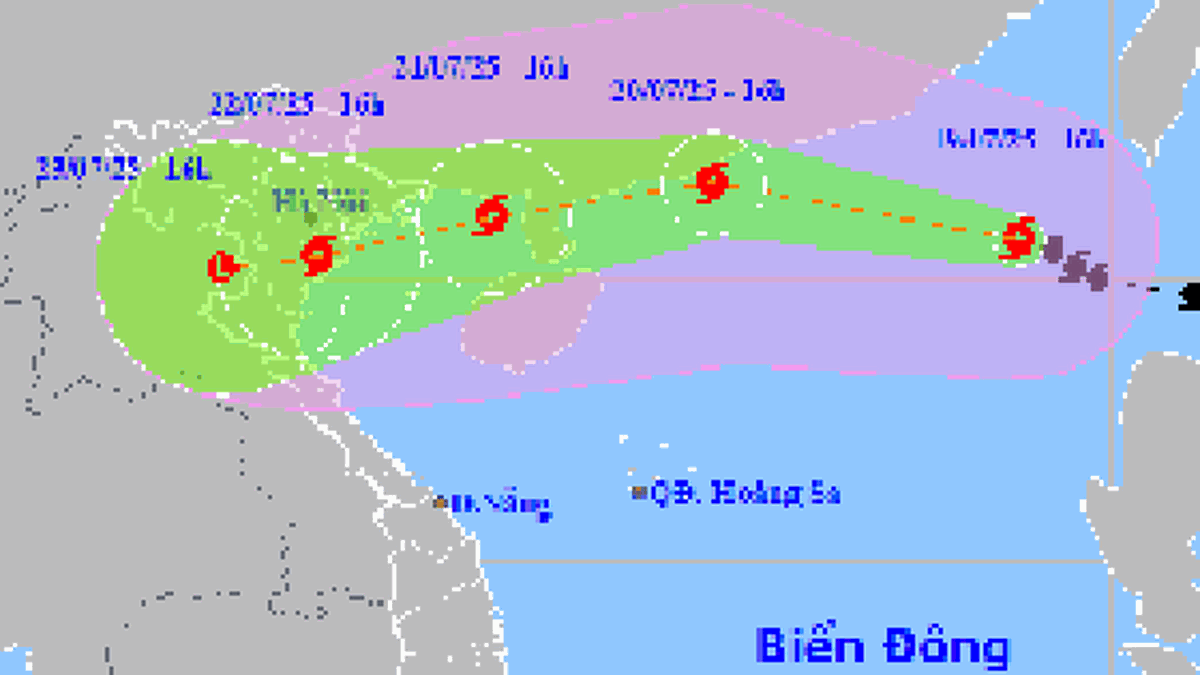






































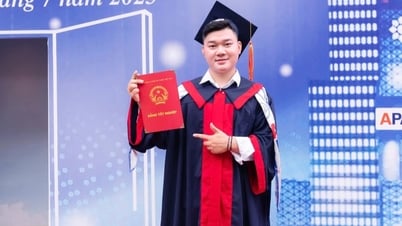



















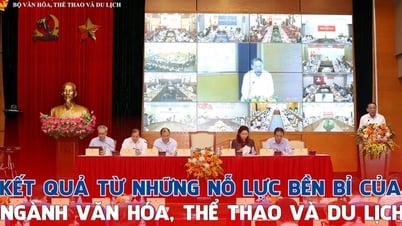

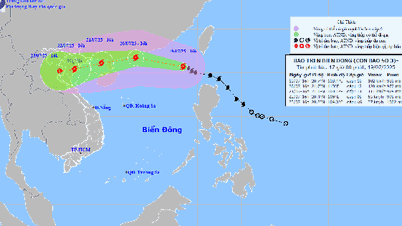

























コメント (0)