 |
ルイス・エンリケはPSGの完全なる変革に貢献した。 |
先制点が勝敗を分けない試合もある。最初の1秒で全てが決まる試合もある。偶然でもスコアでもなく、象徴的な行為、冷たく言葉のない宣言によって。「俺たちはお前たちを絞め殺すためにここにいる」
PSGとインテルの決勝戦はまさにそんな試合で、アクションはラグビーのキックオフのようでした。
新しい戦術コンセプト
ハーフウェイラインから左サイドへロングパス。一見すると素人っぽいミスのように見えたが、実際には冷酷な戦術的設計だった。
PSGは積極的にボールを前に出し、フィールドの最終3分の1付近で攻撃的なスローインの場面を作り出した。ラグビーで言うところの「ラインアウト」だ。そして息詰まるようなプレスをかけ、開始10秒でインテルを圧倒した。シュートでも突破でもなく、ただひたすらに宣言したかのような、戦術的な強烈な一撃だった。
ルイス・エンリケは、戦略家らしい傲慢さで、自らの意図を隠そうとはしなかった。彼は「探りを入れたい」とも、「交渉期間」を必要としていたとも思っていなかった。
エンリケ率いるPSGは、最初の1秒から一つのことを明確に示していた。これは、いつものサッカーではなく、息苦しさとパニック、反応、そして生き残りをかけた90分間になるということだ。そして、決勝進出の途上でバルセロナを破ったインテル・ミラノの、避けられない崩壊の始まりだった。
 |
ルイス・エンリケ率いるPSGはチャンピオンズリーグ優勝に値した。 |
サッカーにおいて、スローインは長らく比較的無害な状況と考えられてきました。守備側が常に有利だからです。しかし、ルイス・エンリケは他の選手が見落としていた点を見抜きました。それは、スローインが極度のプレッシャーの起点となり、プレッシャーをかけるための起点となる点です。
ユルゲン・クロップ監督はリバプールでこの戦術を採用し、デンマークから専任のスローインコーチを招聘して変化をもたらした。しかしPSGはこの考え方をさらに進化させ、スローインはまるで軍隊式攻撃の先制点のように、チーム全員が前線に突進して相手の逃げ道を塞ぐ。
問題は、インテルがこれに備えていなかったことだ。彼らには「プランB」がなく、包囲された際に中継地点となる人物もいなかった。
中盤からの「プレッシャーの解消点」となるはずだったハカン・チャルハノールは、ほとんど姿を消していた。その結果、バルセロナ戦でヒーローだったゴールキーパーのヤン・ゾマーは、プレッシャーを受けながら何度もクリアを強いられ、チームは常に混乱状態に陥った。プレッシャーから逃れる術もなく、阻止点もなく、連携も取れていなかった。インテルは完全に圧倒されるフィジカルの激戦に巻き込まれた。
ルイス・エンリケ監督は2022年ワールドカップで大きなミスを犯し、スペインを無目的なパス回しの機械に変えてしまった。モロッコ戦では1000本以上のパスを繋いだにもかかわらず、決定機を作れなかった。保守主義と戦術の停滞を象徴する存在だった。
しかし、PSGのルイス・エンリケは全く異なる人物だ。ダイナミックで大胆、そして古典的な原則を打ち破ることを恐れない。PSGは今や、適切なストライカーを擁さずにプレーする勇気を持つ数少ないチームの一つであり、その際にも素晴らしいプレーを見せている。
 |
デンベレはゴールデンボール賞を獲得する可能性が高い。 |
ウスマン・デンベレは「偽9番」ではなく、「予測不能なマルチタスクモンスター」だ。プレッシャーをかける際には、シャトルミッドフィルダーのようにプレーする。
デンベレは、組織力においては10番のような存在だ。ペナルティエリアに侵入すると、真のストライカーのように機能する。同時に、デシレ・ドゥエとフヴィチャ・クヴァラツヘリアは常に内側に動き回り、ダイナミックな攻撃トライアングルを形成する。カリム・ベンゼマがクリスティアーノ・ロナウドに見せたような、いわば「お膳立て役」のような存在は必要ない。スペースを生み出すのはシステムであり、「犠牲になる9番」を必要としないのだ。
ハキミは4番目のストライカーだ。もはや単なるサイドバックではなく、中盤にも深く関わり、フィニッシュを助け、トライアングルを連携させる。PSGのシステムはまるで蜂の群れのように機能する。あらゆるポジションが入れ替わり、あらゆるエリアが活用され、インテルのディフェンダーは全員、相手ではなくボールにこだわらなければならない。まさに崩壊の秘訣だ。
勝利は戦略的思考から生まれ、敗北は保守主義から生まれる
インテルの失敗の理由を語るなら、何ページにもわたるだろう。しかし結局のところ、それは精神的な準備不足だった。
シモーネ・インザーギは消極的で、変化に鈍感で、もはや適切ではないと分かっていても、伝統的な3-5-2のフォーメーションを崩そうとはしなかった。フラッテッシを起用せず、4バックフォーメーションに変更しなかったため、インテルは常に5人での守備を強いられたが、それでもプレッシャーに耐えるには十分ではなかった。
後半開始直後の一見無害に思えるキックオフでさえ、保守主義の象徴だった。PSGが試合開始直後に試みたリスクの高いセットプレーではなく、センターバックへのパスを回しただけだったのだ。その時、人々は悟った。この試合は個人のスキルや運ではなく、意志と戦術的ビジョンによって決まったのだ。
この決勝戦は、両チームの激突というだけでなく、戦術思考の転換期でもあった。ルイス・エンリケ監督は、あのラグビーキックで、ヨーロッパの他のサッカーチームに警鐘を鳴らした。柔軟性、変化への勇気、そしてスローインのような小さな要素を活かす能力こそが、現代サッカーにおいて不可欠なアドバンテージとなるのだ。
動きの鈍いストライカーに居場所はない。前半に「探りを入れる」時間はない。試合に「ブレイク」はない。開始1分から最後の1分まで、あらゆる動きが戦術的な攻撃になり得る。そして、この世界において、ルイス・エンリケ率いるPSGは先駆者と言えるだろう。最も伝統的なチームではないかもしれないが、おそらく最も…大胆なチームだ。
出典: https://znews.vn/psg-ve-lai-ban-do-chien-thuat-bong-da-hien-dai-post1557509.html







![[写真] ニャンダン新聞が「心の中の祖国:コンサート映画」を発表](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/10/16/1760622132545_thiet-ke-chua-co-ten-36-png.webp)









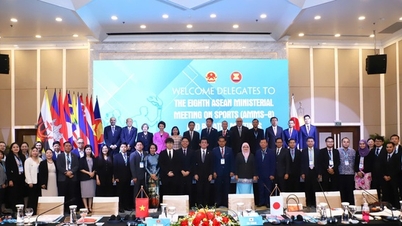





































































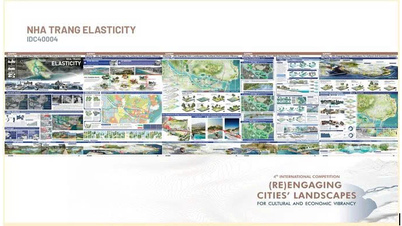



















コメント (0)