重陽の節句(9が2回繰り返されることから)には多くの伝説がありますが、重陽の節句の起源は中国にあると多くの人が信じています。しかし、正確な日付については、漢王朝(紀元前206年 - 紀元後220年)に始まったという説もあれば、唐王朝(618年 - 907年)に始まったという説もあり、依然として意見が分かれています。
しかし、中国の信仰によれば、9という数字には長寿を象徴する吉兆があり、高齢者のための祭りとも考えられているというのが最も正しい解釈でしょう。日本では、重陽の節句は菊の祭りでもありますが、いつから始まったのかは未だにはっきりと分かっていません。

大きな菊
出典: hatgiongphuongnam
研究者として、今日の重陽の節句、旧暦9月9日(10月23日)を機に、歴史文書からこの祭りについてのいくつかの情報を次のように明らかにしたいと思います。
陳朝(1225年 - 1400年)、元・モンゴルの侵略者に対する抵抗戦争の際、有名な将軍である陳克鍾は、重陽の節句と菊を用いて、余暇を楽しむ代わりに、国王を支持し、侵略者を撃退するために国を助けるよう皆に呼びかける詩を書きました。例えば、 「重陽の節句に菊を摘み、桃を発酵させる/秋が来て花を食べる、私の叔父が亡くなった/ロマンチックなカップルは千年の間一緒にいる/隠れた菊は高い空を運ばなければならない」などです。 「クック・アン」という名を持つトラン・カック・チュンは、ベトナムの菊の詩の先駆者とみなされている(トラン・カック・チュンの詩は『Ly Tran Poetry and Literature』第2巻、Social Sciences Publishing House、1988年に所蔵されており、著者のルー・ホン・ソンの詩「ベトナムの古代詩と韓国の古代詩における陶淵明の菊の象徴」は『Northeast Asian Studies』第11号(141)、26-36ページに掲載されている)。
次は、陳朝に住んでいた禅僧フエン・クアンの詩です。年末の森の真ん中に暦はない/菊の咲くのを見て、私はチュン・ドゥオンを知る(フエン・クアン禅僧の菊の詩)
さらに、 『An Nam chi luoc』という本では、陳朝時代の重陽の節句についても次のように語られている。「貴族たちが酒を飲み、詩を朗誦し、観光に出かけた時代であった」(『Le Tac - An Nam chi luoc』 、83ページ)。

重陽の節句は、中国、日本、ベトナム、および一部のアジア諸国で、毎年旧暦の9月9日に行われます。
阮朝時代、教育出版社『ダイ・ナム・トゥック・ルック』には次のように記されている。「明満19年(1838年)マウ・トゥアット…重陽祭。国王はグビン山へ行かれた。その前に国王は礼部省にこう告げられた。『重陽祭は古来より存在してきた。我が国の民衆は質素で、タティック祭や重陽祭を好んで祝う人はほとんどいない。今は国が平和で、楽しい時である。そこで今年はその始まりとして、9月9日にグビン山へ行き、官吏たちを宴会に出席させよう。民衆は喜びを表す旅を楽しむのだ…』何百人もの官吏たちが長寿の儀式を執り行い、儀式の後、宴会に向かった。国王は自ら菊酒を注ぎ、王子、公爵、そして文官たちに授けた。軍の高官たちにそれぞれ一杯ずつ渡してこう言った。「このワインはとてもおいしい。一杯飲んだら、飲み干すのに二回かかるだろう…」
このように、我が国のチュンクウ祭りはトラン王朝時代に最も早く知られていたことがわかります。
バヴァンパゴダは長年にわたり、国家の文化的伝統の美しさを保存し、チュックラム仏教文化のシンボルのイメージを尊重するために、2年に一度旧暦の9月9日に開催されるバヴァンパゴダ菊祭りという名前で、重陽の節句の美しさを復元してきたことが知られています。
[広告2]
ソースリンク



![[動画] 100以上の大学が2025~2026年度の授業料を発表](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/7/18/7eacdc721552429494cf919b3a65b42e)




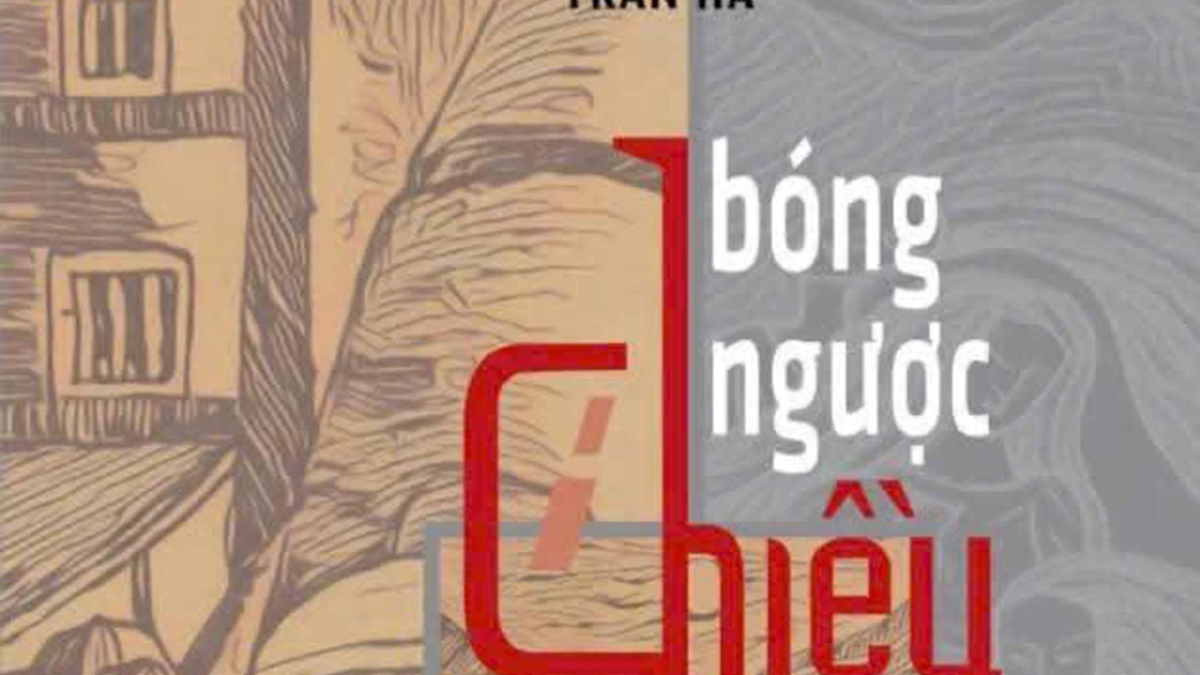
























































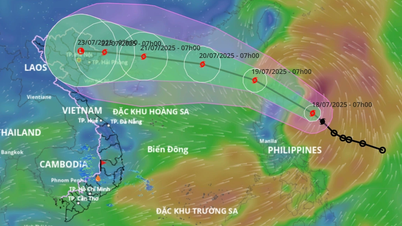



























![[インフォグラフィック] 2025年には47の製品が国家OCOPを達成する](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/402x226/vietnam/resource/IMAGE/2025/7/16/5d672398b0744db3ab920e05db8e5b7d)





コメント (0)