近年、ホーチミン市では土地資金の不足が大きなボトルネックとなっており、大型プロジェクトや外国投資資金の減少が続いています。市内の多くの工業団地は20年前に首相によって設立されましたが、用地取得の問題により未だ建設が進んでいません。
工業用地不足の問題を解決するため、ホーチミン市輸出加工工業団地公社(Hepza)はかつて、非効率的に利用されている農地を工業用地やサービス用地へ転換することを提案しました。しかし、この転換プロセスには多くの時間と複雑な手続きが必要です。こうした状況において、ホーチミン市、ビンズオン省、 バリア・ブンタウ省の合併は新たなアプローチを切り開きました。
専門家によれば、この合併は行政上の意義を持つだけでなく、国内外の投資家の高まるニーズに適した、より大規模で体系的な取り決めによる新しい工業団地を計画するための条件も作り出すという。
行政境界線の拡大は、地方自治体が産業開発区をより明確に区分するための条件を整えることにも役立ちます。従来の工業団地に留まらず、自動車、電子機器、半導体といった基幹産業への部品やスペアパーツの供給に重点を置いた、裾野産業団地や専門裾野産業といった特化型工業団地の開発を推進することが可能になります。
CBREベトナムの不動産・産業・オフィス担当部長であるレ・チョン・ヒュー氏は、行政区域の統合・調整政策は工業団地の計画・開発の方向性に変化をもたらすと述べた。ホーチミン市にとって、管理規模の拡大は、特に人材をはじめとするより多くの資源を保有することにつながる。
ヒュー氏によると、企業がベトナムへの投資を決定する際には、多くの要素を考慮するとのことです。ホーチミン市はもはや賃料競争力のある立地ではありませんが、人材、サプライチェーン、そして特に工業団地周辺のビジネスエコシステムや住宅コミュニティを考慮すると、ホーチミン市には依然として非常に明確な優位性があります。その一つが、港湾に近い地理的な立地で、輸送コストと時間の最適化に役立ちます。
「CBREは多くの企業、特に物流需要の高い企業にアドバイスを提供してきました。製造業だけでなく、自動車産業など、大規模な倉庫システムを必要とする業界にもサービスを提供しています。その理由は、大型船が特殊な荷物を輸送する場合、港に入港後、企業は集荷場所や配送センターとして機能する場所を必要とするからです。このようなセンターは、サプライチェーンを最適化するために港に近い立地が求められます。そのため、ホーチミン市エリアは、配送、集荷、そして物流センターとしての役割を担う上で、一定の優位性を持っているのです」とヒュー氏は述べました。
Hepzaの副社長であるトラン・ヴィエット・ハ氏は、合併後、ホーチミン市には66の輸出加工区と工業団地が設立され、総面積は2万7000ヘクタールを超えると述べた。計画によれば、2050年までに105の輸出加工区と工業団地が設立される予定だ。
しかし、専門家や企業は、市の産業成長の可能性を「解き放つ」ために解決すべき課題も指摘した。
まず、環状道路、高速道路、物流センターといったインフラ整備が遅れており、サプライチェーンの連続性が欠如しています。現在、バリア・ブンタウ(旧)を経由する輸出入貨物のうち、内陸水路または鉄道による輸送は約15%に過ぎず、残りは道路に依存しています。
ホーチミン市開発研究所(HIDS)所長のチュオン・ミン・フイ・ヴ博士によると、まず第一に、環状3号線、環状4号線、ホーチミン市-モックバイ高速道路、ビエンホア-ブンタウ高速道路、ベンルック-ロンタン高速道路の完成を優先すべきだという。これらは、工業団地、研究開発センター、国際港(カットライ港、ヒエップフオック港、カイメップ-チーバイ港)、そして地域のICD(国際輸送拠点)を直接結ぶ主要ルートである。
第二に、裾野産業と労働力の育成です。ベカメックス社のマーケティング担当エグゼクティブディレクター、ヴォ・ソン・ディエン氏は、多くの製造企業が輸入部品、コンポーネント、材料に依存していると述べました。そのため、基礎素材産業の発展を支援し、国内大手企業がサプライチェーンを主導するよう奨励し、裾野産業の立ち上げプロジェクトを支援するための資源を配分し、国際基準の品質検査センターを整備する必要があります。
第三に、人材育成システムを構築する。ホーチミン市繊維ファッション協会のファム・ヴァン・ヴィエット副会長は、労働力は量的には不足していないものの、自動機械の操作、生産データ処理、国際基準に従った品質管理を行う人材が不足していると述べた。そのため、デジタル化・ハイテク産業への移行という文脈において、ホーチミン市は大学、専門学校、企業、工業団地を緊密に連携させた高度な技術育成システムを構築する必要がある。
鍵となる解決策は、ハイテク職業訓練センターによる研修ネットワークを構築し、自動化工学、工業デザイン、デジタル制御、スマート物流、クリーンエネルギーといった分野の研修を拡大することです。さらに、グリーン産業と循環型産業は、2050年までのネットゼロ達成に向けたコミットメントと関連した世界的な潮流です。専門家は、ホーチミン市が、生産効率と環境責任、そしてプロセスの包括的なデジタル化を結び付けた新たな産業の発展を先導すべきだと指摘しています。
出典: https://baodautu.vn/tphcm-nhe-ganh-noi-lo-quy-dat-phat-trien-cong-nghiep-d335977.html


































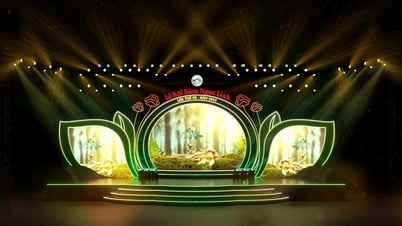

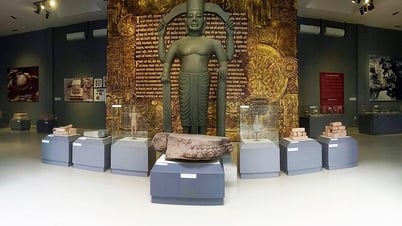




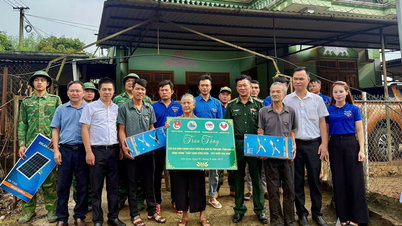





























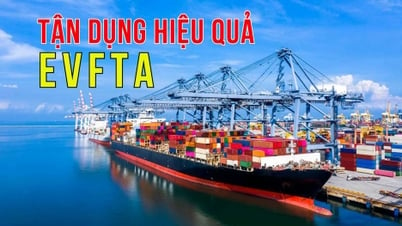




















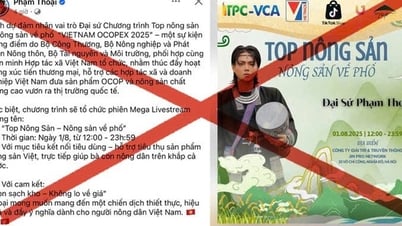






コメント (0)