挨拶さえ言いにくくなる時
中学校から高校にかけて、生徒たちは心理的発達において重要かつ複雑な時期を経験します。反抗期や引きこもりの兆候の背後には、憂慮すべき現実が隠されています。多くの子どもたちが、大人が理解し、適切なタイミングで介入することが難しい心理的トラウマを経験しているのです。
MH( ハノイの名門中学校に通う9年生)は、6年間ずっと優秀な生徒でした。しかし、9年生になった頃から、彼は変化し始めました。成績が下がり、友達との交流も減り、両親とも短い返事をする以外はほとんどコミュニケーションを取らなくなりました。
「両親に勉強の調子を聞かれるたびに、まるで尋問されているような気分になります。家の中のすべてが勉強のことばかりなのに、誰も私に『大丈夫?』と聞いてくれません。弱いと言われるのが怖くて、プレッシャーを感じていることを打ち明ける勇気がないんです」とMHさんは語った。
MHは反論したり抵抗したりすることなく、ただ徐々に黙り込んでいった。両親の目には冷酷に映ったかもしれないが、MHにとってはそれが傷つくことから自分を守る唯一の方法だった。

MHだけでなく、多くの生徒が「親に話せない」という気持ち、批判されていると感じている、信頼されていないと感じている、といった感情を共有しています。中には、仲間内で孤立したり、SNS上で巧妙な校内暴力に巻き込まれたり、あるいは単にどこにも属していないと感じたりする生徒もいます。こうした隠れた感情を解放しなければ、不安や抑うつへと蓄積し、人格形成に長期的な影響を及ぼす可能性があります。
しかし、生徒たちは自分の意見を聞いてもらい、尊重されることを切望している一方で、学校や家庭環境は規律と成績を重視しがちで、共感よりも期待が優先されてしまうことがよくあります。「規律がない」「やる気がない」「反抗的」に見える生徒の多くは、実際には行動という形で苦痛のサインを送っているのです。
ベトナム国家大学ハノイ校教育大学の副学長であるトラン・タン・ナム准教授は、若者が真剣な取り組みを避け、規律、感謝、プロ意識などの基本的な価値観を簡単に無視するケースが増えている状況において、メンターの役割がこれまで以上に重要になっているとコメントしました。
彼によると、メンターとは「灯台」のような役割を果たす人です。生徒が自分の価値観を見出し、責任感を育むのを助けるだけでなく、批判されることを恐れずに勇気を持って意見を言えるようなオープンな場を創り出すこともメンターの役割です。親や教師のような監督者の役割とは異なり、メンターは生徒に敬意と平等をもって寄り添い、自由は安楽を意味するものではなく、知性は優しさと規律が伴って初めて真に価値あるものになることを理解できるよう導きます。
メンターはスキルを教えるだけでなく、子どもたちが模範となるよう促します。メンターは親の役割に取って代わることはできませんが、子どもたちに良いロールモデルとなることで支えることができます。子どもたちに感情をコントロールする方法、責任ある意思決定の方法、そして選択には結果が伴うことを理解する方法を教えることもできます。
「メンターは子どもたちに小さな課題を計画するよう指導することで、規律と責任感の価値を理解させることができます。また、子どもたちがグループ活動に参加するよう促すことで、自分のエゴばかりに囚われることなく、他者の努力を尊重することを学ぶこともできます」とナム氏は例を挙げました。
子どもたちが指示なしに「成長」しなくて済むように
このような状況に直面して、Mentors14 (1:1 メンタリングによる個人開発コンサルティング プログラム) の創設者である Ha Minh 氏は、学生は単に「学習者」という意味ではなく、完全な人間として伴走される必要があると考えています。
「すべての生徒には前向きに成長する可能性を秘めていると信じています。しかし、彼らの話に耳を傾け、感情、恐れ、欲望、そして限界を持つ人間として捉えてもらう必要があります。信頼できる仲間がいればこそ、彼らは自分の抱える問題に真正面から向き合い、それを克服する勇気を持つことができるのです」とミンさんは語った。

ハ・ミン氏によると、解決策はスキルを追加したりコントロールを強化したりすることではなく、生徒たちの内なる理解、つまり自分自身、自分の感情、そして進みたい道について、目覚めさせることから始まります。「メンターとメンティーの関係において、信頼こそが核となります。そこから、メンターは学習を導く役割を果たすだけでなく、生徒たちの自己認識、健全な感情を表現する能力、そして自己価値感を育むのを助けます。」
ハ・ミン氏は、メンターズ14のメンタリング・プログラムは、生徒の成績向上に役立っているだけではないと述べた。さらに重要なのは、「私は何者なのか?」「何ができるのか?」「人生で本当に何を望んでいるのか?」という問いに答える方法を学ぶことだ。これは、自分自身を理解し、変化に立ち向かい、地域社会に責任を持つ自立した個人を育成するための基礎となる。
ハ・ミン氏は次のように強調しました。「真の教育とは、知識豊富な人材を育成するだけでなく、一人ひとりの生徒が個性を持ち、自分自身と社会とを繋ぐことができる人間へと成長できるよう支援することです。メンタリングは親や学校に代わるものではなく、子どもたちの成長過程において欠けている、地味ながらも不可欠な繋がりです。包括的な教育へと進むためには、思春期の生徒への心理的支援を不可欠な要素と捉える必要があります。家庭、学校、専門機関の連携が不可欠です。生徒が「迷子」の段階を乗り越えるのを助けるだけでなく、より重要なのは、彼らが人生を自ら切り開く勇気と内面の強さを育むことです。」
出典: https://vietnamnet.vn/tre-khong-noi-chuyen-duoc-voi-cha-me-phai-lam-sao-2396191.html


































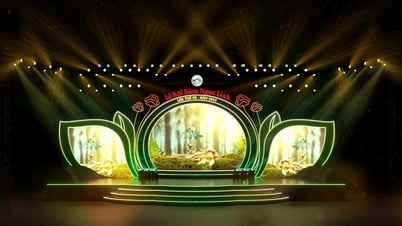

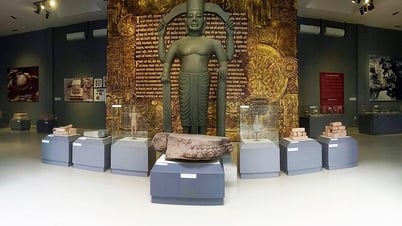




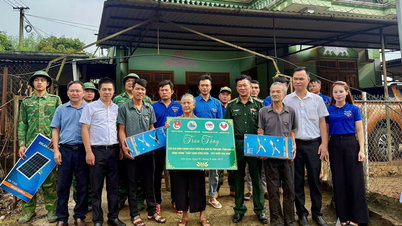




























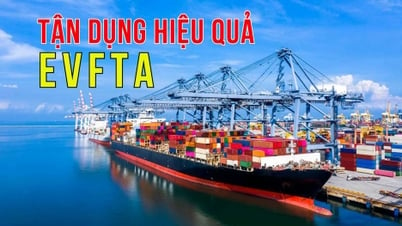




















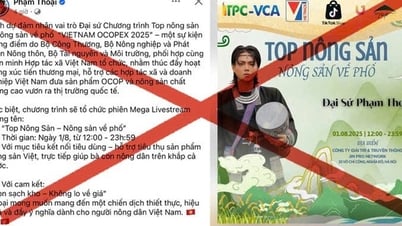






コメント (0)