この問題は単純なように思えますが、日本の世論は相反する意見が多く出ています。
日本の学校における靴の伝統の変化
日本の子供たちは何十年もの間、校門を入るとすぐに靴を履き替える習慣を保ってきました。普段履きのまま教室に入るのではなく、外履きを脱いで「上履き」と呼ばれる柔らかいプラスチック製のスリッパに履き替えます。このスリッパは教室、廊下、共用スペースを清潔に保つため、屋内でのみ履きます。各生徒の校門には、使用していない上履きを収納するための小さな収納スペースが設けられています。
この習慣は衛生上の理由から生まれただけでなく、日本の典型的な文化的特徴を反映しています。日本では、外からの汚れを持ち込まないように、家に入る際に靴を脱ぐことがよくあります。同様に、伝統的な建物、畳敷きのレストラン、オフィスなどでも、室内履きへの履き替えが求められます。これは、より清潔で整頓された空間を作ることに貢献しています。
しかし、学校における履物履き替えの習慣は劇的に変化しています。特に東京では、多くの学校で上履きを段階的に廃止し、生徒が外履きで授業に出席することを許可するようになっています。これは、現代の教育環境におけるこの伝統の必要性について多くの疑問を投げかけています。
新たなトレンド:上履きを残すか、捨てるか?
東京都港区は、公立学校における上履き廃止の先駆けとなっている。区内の19の小学校のうち、18校が登校時に生徒に靴への履き替えを義務付けないことを決定した。 「一足制」と呼ばれるこの新しい方針により、生徒は登校時に上履きに履き替える必要がなくなり、一日中外履きで登校できる。

問題は単純に思えるが、日本の世論は相反する意見を多く出している。IG.
港区教育委員会によると、この決定の主な理由は、生徒数の急増に関係しているという。20年前、この地域の5歳から14歳までの児童数はわずか約1万700人だった。しかし、2024年4月にはその数はほぼ倍増し、約2万4000人に達した。生徒数の増加は学校の過密化を意味し、学校のスペースをより効率的に活用する必要が生じている。多くの学校では、広いスペースを下駄箱に充てる代わりに、そのスペースをより重要な用途に活用することを決定している。
芝浜小学校の宮崎直人校長は、靴の履き替えをなくすことで、生徒と教師の毎朝の時間を節約できると述べた。履き替える必要がないため、校門の混雑が緩和され、生徒はより早く教室に到着できる。また、普段履きの靴は緊急時に生徒がより安全に移動するのに役立つと強調した。地震や避難の際には、生徒はより速く走ることができ、上履きが屋外を歩くのに十分ではないというリスクを回避することができる。
しかし、靴を履き替えないことは、学校における衛生面の懸念も引き起こします。これまで上履きが使われてきた主な理由の一つは、生徒が教室に土や泥などの汚れを持ち込むのを防ぐためです。特に、食堂や図書館といった場所は、生徒にとって最適な学習・生活環境を確保するために、清潔に保つ必要があります。
しかし、日本ではオフィス、店舗、レストランなど、多くの場所では、顧客や従業員が屋外で靴を履いても不衛生とみなされることはありません。都市部や郊外では、学生は非常に汚れた道路を歩く必要がないため、靴を履き替える必要性は低いのです。
港区内のほとんどの学校が方針を変更しましたが、青山小学校は上履きの履き替えを続けています。可児明子校長は、靴を履き替えることは衛生面だけでなく、生徒の心理面にも配慮していると述べています。生徒たちは、外のリラックスした状態から、より集中して学習に取り組む状態へと移行するのを感じ、それがより真剣で秩序ある学習環境の醸成につながると彼女は言います。
[広告2]
出典: https://danviet.vn/vi-sao-tre-em-nhat-ban-thay-giay-khi-vao-truong-hoc-20250219174244307.htm



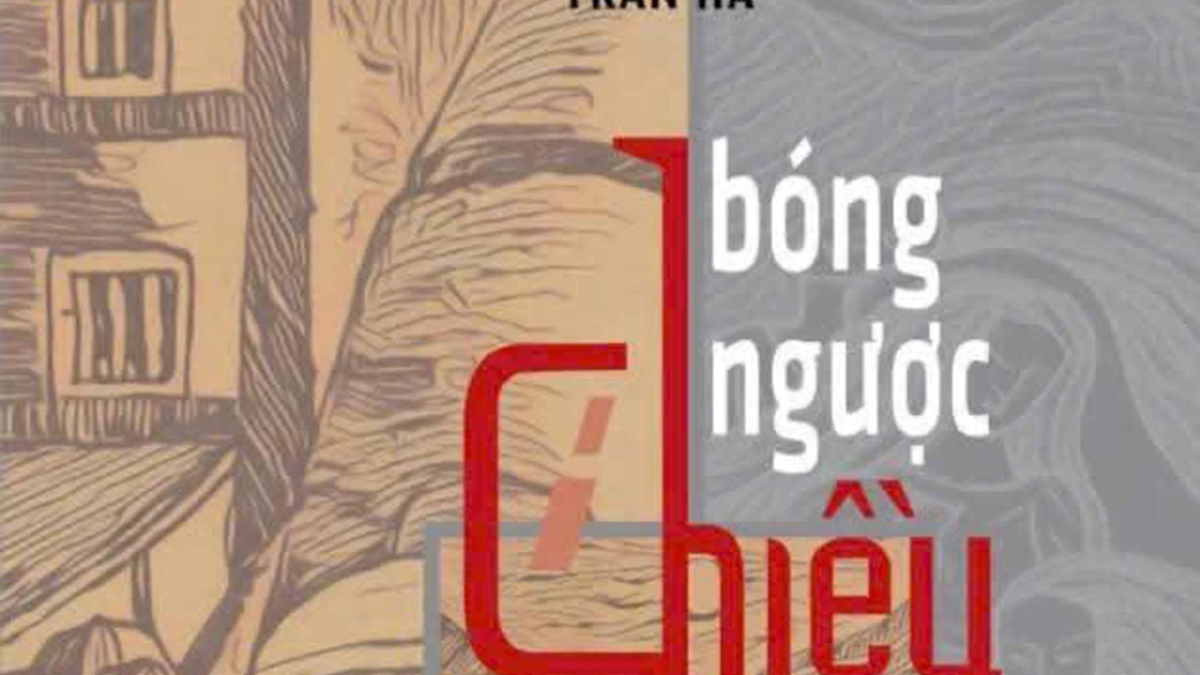

![[動画] 100以上の大学が2025~2026年度の授業料を発表](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/7/18/7eacdc721552429494cf919b3a65b42e)




























































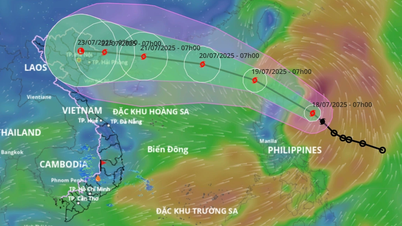



























![[インフォグラフィック] 2025年には47の製品が国家OCOPを達成する](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/402x226/vietnam/resource/IMAGE/2025/7/16/5d672398b0744db3ab920e05db8e5b7d)





コメント (0)