中央為替レートは18ドン下落し、VN指数は前週末比34.67ポイント上昇、4月の消費者物価指数(CPI)は主にガソリン価格の影響で上昇など、4月22日~26日の週の注目すべき経済情報がいくつかあります。
| 2024年4月の消費者物価指数は前年同月比4.4%上昇しました。4月25日の経済情報レビュー |
 |
| 経済ニュースレビュー |
概要
4月の消費者物価指数(CPI)は、主にガソリン価格の影響により上昇しました。専門家は、2024年のインフレ率は2023年よりも高くなる可能性が高いものの、依然として抑制されていると予測しています。
4月29日にインド統計局が発表したデータによると、世界の燃料価格の上昇に伴うガソリン価格の上昇が、2024年4月の消費者物価指数(CPI)が前月比0.07%上昇した主な要因となった。これにより、2023年12月と比較すると、4月のCPIは1.19%上昇し、前年同期と比較すると4.4%上昇した。平均すると、2024年の最初の4か月間で、CPIは前年同期比3.93%上昇した。
2024年4月の消費者物価指数(CPI)は前月比0.07%上昇し、価格指数が上昇した財・サービスは8つ、価格指数が下落した財・サービスは3つありました。価格指数が上昇した財・サービスのうち、運輸業の上昇率が1.95%と最も高く(全体のCPI上昇率は0.19ポイント)、運輸業の上昇率は主に国内ガソリン価格が4.78%上昇したこと、また、月間の価格調整の影響で軽油価格が2.01%上昇したことが大きな要因となりました。
さらに、ガソリン価格の上昇により、航空旅客輸送料金は10.42%、水運料金は0.06%、道路料金は0.13%、バス料金は0.21%、タクシー料金は0.56%それぞれ上昇しました。医薬品・医療サービスは、天候の変化、病原ウイルスの蔓延、肺炎、水痘、手足口病の患者数の急増により、免疫力を高めるための医薬品の購入ニーズが高まり、2番目に高い0.92%の増加となりました。
そのうち、鎮痛剤、解熱剤、抗炎症剤は0.19%上昇、抗アレルギー剤、過敏症治療薬は0.13%上昇、循環器系薬剤およびその他の製品は0.07%上昇しました。その他の商品・サービスは、主に身の回り品(0.6%上昇)の価格上昇により、0.27%上昇しました。
4月、価格指数が低下した3つの財・サービス群のうち、教育群が前月比2.93%減少し、総合CPIの0.18パーセントポイントの低下に寄与した点が目立った。そのうち、教育サービスは3.32%の減少となった。主な要因は、政府が2023年12月31日に、2021年8月27日付政府政令第81/2021/ND-CP号の一部条項を修正・補足する政令第97/2023/ND-CP号を発行し、地方自治体に対し、公立幼稚園および一般教育の授業料を2023-2024学年度から2021-2022学年度の授業料と同水準に維持するよう義務付けたことであり、それに応じて、多くの学校が政令第81/2021/ND-CP号に基づいて授業料を徴収した後、授業料を引き下げた。
新たに発表されたデータによると、2024年4月のコアインフレ率は前月比0.17%上昇、前年同期比2.79%上昇となった。2024年の最初の4か月平均では、コアインフレ率は前年同期比2.81%上昇となり、消費者物価指数(CPI)の平均上昇率(3.93%上昇)を下回った。これは主に、CPIの上昇に影響を与えるものの、コアインフレ率の算出対象から除外されている食品、ガソリン、医療サービスの価格によるものである。
2024年通年のインフレについて、多くの組織や専門家は、2024年のインフレ率は2023年よりも高くなる可能性が高いものの、依然として抑制されており、国会と政府が設定した目標は平均消費者物価指数(CPI)4~4.5%であると考えています。しかしながら、年初4ヶ月間のインフレ統計は、インフレリスクが依然として存在することを示しています。今年の価格管理において最も懸念されるのは、ガソリン価格、一部の建設資材価格、食料品価格など、一部の生活必需品、商品、消費者サービスの価格が変動し、上昇すると予想されることです。
それに加えて、市場価格ロードマップの実施、国が価格設定する商品およびサービスの価格におけるコストの正確かつ完全な計算は、2024年に引き続き検討する必要がある問題です。2024年7月1日からの地域最低賃金の6%引き上げにより、CPIは約0.03パーセントポイント上昇するでしょう。
しかし、依然として物価水準への圧力を緩和する要因もいくつか存在します。例えば、ベトナムは豊富な食料資源を有し、国内消費と輸出需要を満たしています。2024年も引き続き一部の税制支援政策が実施され、投入コストの削減に貢献する見込みです。さらに、世界的な物価とインフレは落ち着きを見せており、国内のマネーサプライは増加しているものの、マネー回転率は依然として低く、0.7~0.9倍程度と予測されています。これらもインフレ抑制に貢献する要因です。
4月24日に開催された、第1四半期の価格管理と運営、および2024年の残りの月の価格管理の方向性を検討する価格管理運営委員会の会議で、財務省は3つの価格管理シナリオを更新し、平均CPIが2023年と比較して約3.64%上昇(シナリオ1)、4.05%上昇(シナリオ2)、約4.5%上昇(シナリオ3)をそれぞれ予測しました。統計総局は、平均CPIが3.5%~4.5%の範囲になると予測しています(3つのシナリオ:3.5%、4.0%、4.5%)。国立銀行は、2024年の平均CPIが約4±0.5%上昇すると予測しています。
4月22日~26日の国内市場概要
外国為替市場:4月22日から26日の週、ベトナム中央銀行は週初の2セッションで中心為替レートを引き続き引き上げ、その後再び下落させた。4月26日終値時点で、中心為替レートは1米ドルあたり24,246ドンで、前週末のセッション比18ドン安となった。
ベトナム国家銀行の取引オフィスは、全セッションを通じて米ドルの買いレートを23,400 VND/USDに継続して掲載している一方、米ドルの売りレートは25,450 VND/USDに掲載されている。
インターバンク市場のUSD-VND為替レートは、4月22日から26日の週に再び下落しました。4月26日の取引終了時点で、インターバンク市場の為替レートは1米ドルあたり25,334VNDで取引を終え、前週末の取引時間と比較して116VND下落しました。
自由市場におけるドル・ドン為替レートも先週の取引を通じて下落しました。4月26日の取引終了時点では、自由市場為替レートは前週末の取引と比較して、買値で150ドン、売値で130ドン下落し、それぞれ25,530ドン/米ドル、25,630ドン/米ドルで取引されました。
4月22日から26日の週のインターバンク金融市場では、インターバンク・ドン金利は全期間で上昇傾向を示しました。4月26日の終値時点で、インターバンク・ドン金利は、翌日物4.78%(+0.82パーセントポイント)、1週間物4.82%(+0.68パーセントポイント)、2週間物4.92%(+0.56パーセントポイント)、1ヶ月物4.95%(+0.37パーセントポイント)前後で推移しました。
インターバンク米ドル金利は、全期間を通じて小幅な上昇と下落を維持しました。4月26日の終値は、翌日物5.24%(-0.01パーセントポイント)、1週間物5.31%(-0.02パーセントポイント)、2週間物5.38%(-0.02パーセントポイント)、1ヶ月物5.40%(-0.01パーセントポイント)でした。
4月22日から26日までの公開市場では、住宅ローンチャネルにおいて、中央銀行が14日物の住宅ローンを122兆ドンで入札しました。週初取引日の金利は4.0%で、その後の取引では4.25%に上昇しました。先週の落札額は117兆8,051億ドン、満期日は32兆8,651億ドンでした。
ベトナム国家銀行は、28日物ベトナム国債(SBV)を入札にかけ、全取引時間において金利入札を実施しました。週末までに落札総額は11兆4,000億ドンに達し、金利は年3.73%から3.75%に上昇し、週末には3.5%で終了しました。先週、26兆5,000億ドンが満期を迎えました。
そのため、ベトナム国家銀行は先週、公開市場チャネルを通じて純額100兆400億ドンを市場に投入し、流通中のベトナム人民元紙幣の量は51兆3500億ドンに減少し、住宅ローンチャネルでの流通量は117兆8051億ドンとなった。
4月24日の債券市場において、国庫は募集額5兆5,960億ドン/12兆ドンの国債調達に成功しました(落札率47%)。このうち、5年債と20年債は募集額の全てを調達し、それぞれ3兆ドンと2兆ドンでした。10年債は2,360億ドン/4兆ドン、15年債は3,600億ドン/3兆ドンの国債を調達しました。落札金利は、期間5年が1.61%(前回比0.11%増)、期間10年が2.50%(0.05%増)、期間15年が2.68%(0.03%増)、期間20年が2.80%(0.15%増)となった。
今週5月2日、国庫は10兆ドンの国債を発行した。そのうち5年および15年償還の債券は1期間あたり3兆ドン、7年償還の債券は5000億ドン、10年償還の債券は2兆5000億ドン、30年償還の債券は1兆ドンであった。
先週のセカンダリー市場におけるアウトライトおよびレポ取引の平均取引額は、1セッションあたり10兆5,830億ドンとなり、前週の8兆9,530億ドンから増加した。先週の国債利回りは満期ごとに異なっていた。4月26日の取引終了時点で、国債利回りは、1年債が1.85%(前セッション比+0.01パーセントポイント)、2年債が1.87%(+0.02パーセントポイント)、3年債が1.90%(+0.02パーセントポイント)、5年債が2.09%(-0.04パーセントポイント)、7年債が2.31%(-0.04パーセントポイント)、10年債が2.79%(-0.02パーセントポイント)、15年債が3.0%(-0.03パーセントポイント)、30年債が3.12%(横ばい)で推移した。
4月22日から26日の週にかけて、株式市場は回復しました。4月26日の取引終了時点で、VN指数は前週末比34.67ポイント(+2.95%)上昇の1,209.52ポイントとなりました。HNX指数は6.02ポイント(+2.73%)上昇の226.82ポイント、UPCom指数は1.60ポイント(+1.84%)上昇の88.76ポイントとなりました。
市場流動性は低下し、1セッションあたり平均で約17兆9,000億ドンとなり、前週の1セッションあたり29兆2,000億ドンから大幅に減少しました。外国人投資家は引き続き、3つの取引所すべてで1兆2,300億ドン以上の売り越しを記録しました。
国際ニュース
米国連邦準備制度理事会(FRB)は5月の会合で政策金利を変更しなかったが、米国ではここ数日、多くの重要な経済指標が記録された。5月1日に終了した会合において、連邦公開市場委員会(FOMC)は、インフレ率は過去1年間で低下したものの、依然として高水準にあると述べた。FOMCは、長期的に完全雇用と2.0%のインフレ目標の達成に向けた決意を依然として示している。
この目標を達成するため、FOMCはフェデラルファンド金利の目標レンジを5.25%から5.50%に据え置くことを決定し、今後のフェデラルファンド金利に関する決定においては、今後入手するデータを慎重に評価していきます。FOMCは、インフレ率が持続的に2.0%に向かっているという確信が強まるまでは、フェデラルファンド金利の引き下げは適切ではないと考えています。
さらに、FOMCは今年6月からバランスシート縮小のペースを月650億ドルから月250億ドルに減速させる予定です。米国経済について言えば、2024年第1四半期のGDPは前年同期比わずか1.6%増にとどまり、前四半期の3.4%増から減速し、予想の2.5%増も下回りました。
インフレ面では、米国コアPCE価格指数は3月に前月比0.3%上昇し、2月の上昇率および予想と一致しました。前年比では、コアPCEは3月に2.8%上昇し、2月から横ばいでした。
しかし、3月のPCEヘッドラインは2.7%上昇し、2月の2.5%から上昇しました。労働市場では、米国では3月に849万人の新規雇用が創出され、2月の881万人から減少し、予想の868万人も下回りました。4月には、非農業部門の新規雇用が19万2千人(ADP調べ)となり、3月の20万8千人からは減少しましたが、予想の17万9千人からは上回りました。
次に、ISM調査によると、4月の米国製造業PMI指数は49.2%にとどまり、3月の50.3%からわずかに低下し、予想の50%も下回った。最後に、コンファレンス・ボードが調査した4月の米国消費者信頼感指数は97.0ポイントとなり、3月の103.1ポイントから低下した。これは、104.0ポイントへの小幅上昇が予想されていたのに反する。
日本銀行も4月下旬の会合で政策金利を据え置きました。先週4月26日、日銀は2026年度までに日本の物価上昇率が目標の2.0%程度にとどまるとの見通しを示しました。日銀は政策金利を従来通り0.1%に据え置くことを決定しました。
1か月以上前の3月19日、日銀は政策金利をマイナス0.1%から0.1%に引き上げ、2016年以来のマイナス金利政策に終止符を打つことを決定しました。米ドルをはじめとする多くの主要通貨に対する円の相対的な下落にもかかわらず、市場では日銀が2024年に政策金利を大幅に引き上げる可能性は低いとみられています。その主な理由は、日本経済がまだ本格的な回復と安定化に至っていないことです。
日本経済について言えば、3月のコア消費者物価指数(CPI)は前年同月比2.2%上昇となり、前月の2.3%上昇からわずかに低下しました。労働市場では、失業率は2.5%への小幅低下が予想されていましたが、3月は2.6%と2月から横ばいとなりました。
次に、日本の3月の工業生産は前月比3.8%増となり、前月の0.6%減から3.4%増の予想を上回りました。2023年の同月と比較すると、3月の生産は依然として6.7%の減少となりました。最後に、日本の3月の小売売上高は前年同月比1.2%増となり、2月の4.7%増から大幅に減速し、2.5%増の予想も下回りました。
[広告2]
ソースリンク





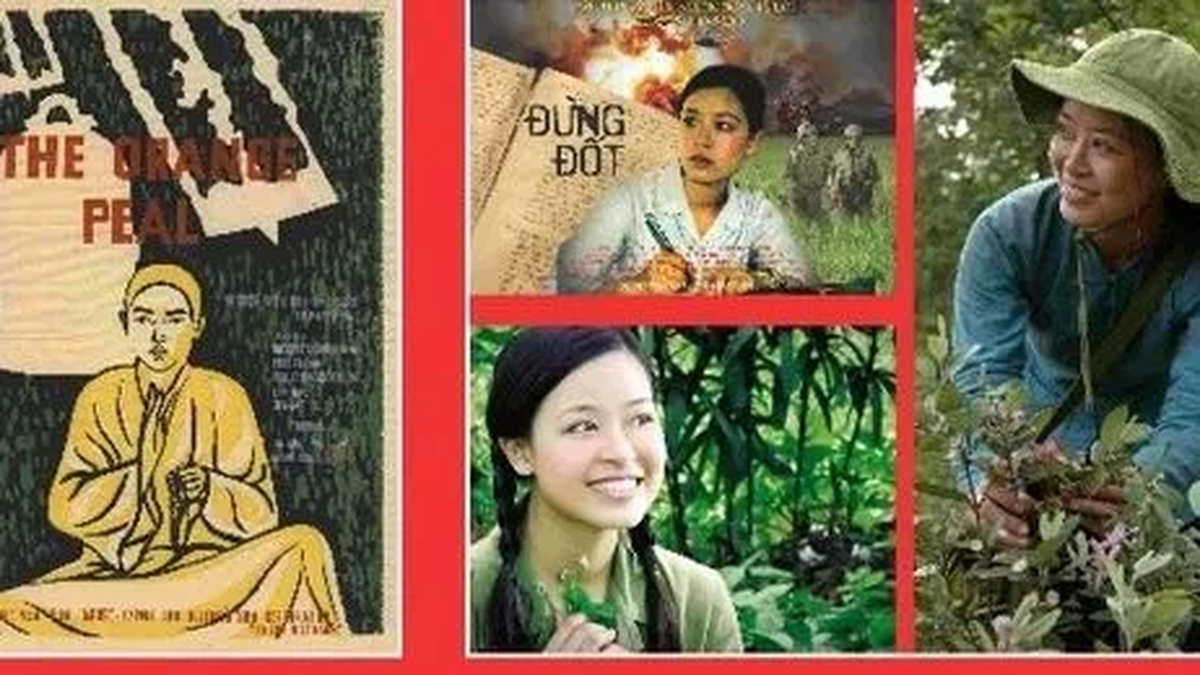





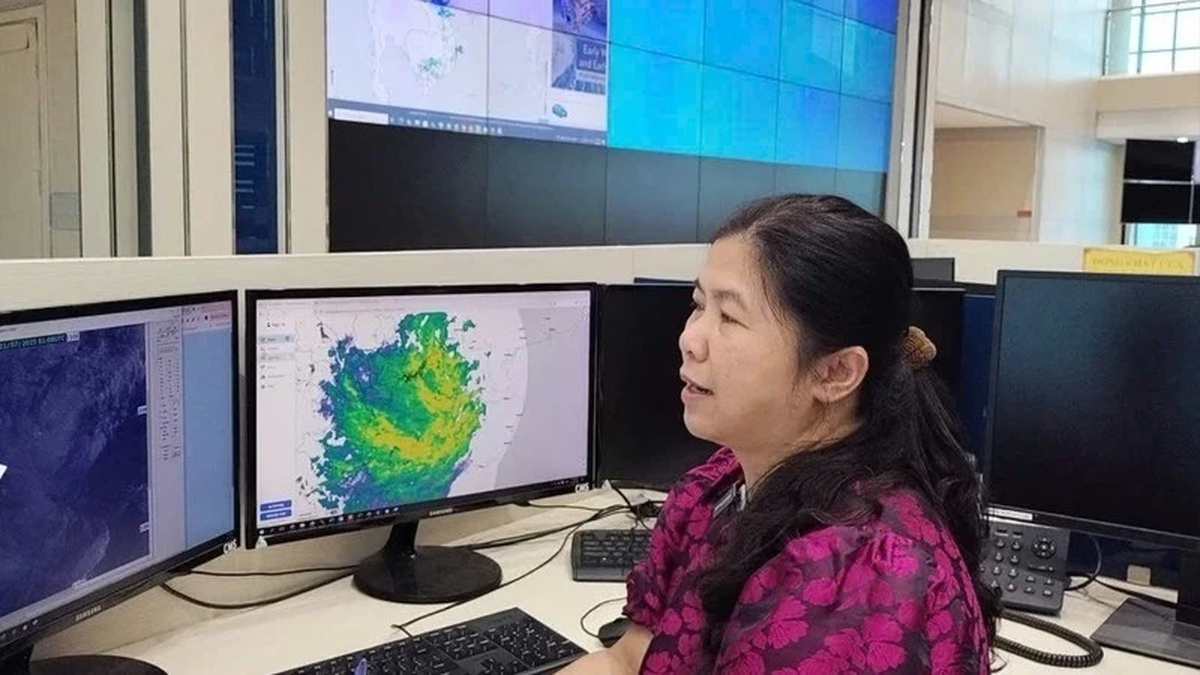
























































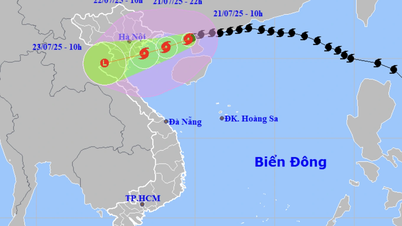



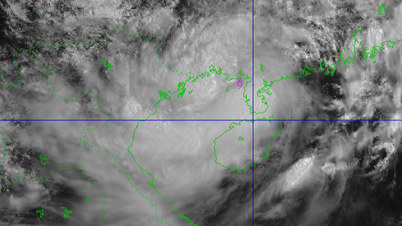




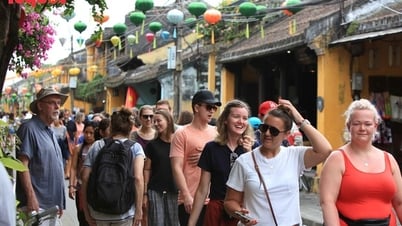

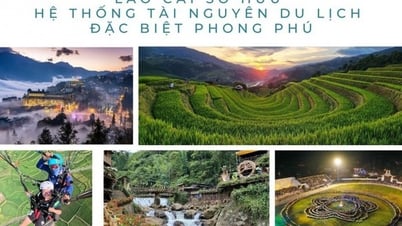




















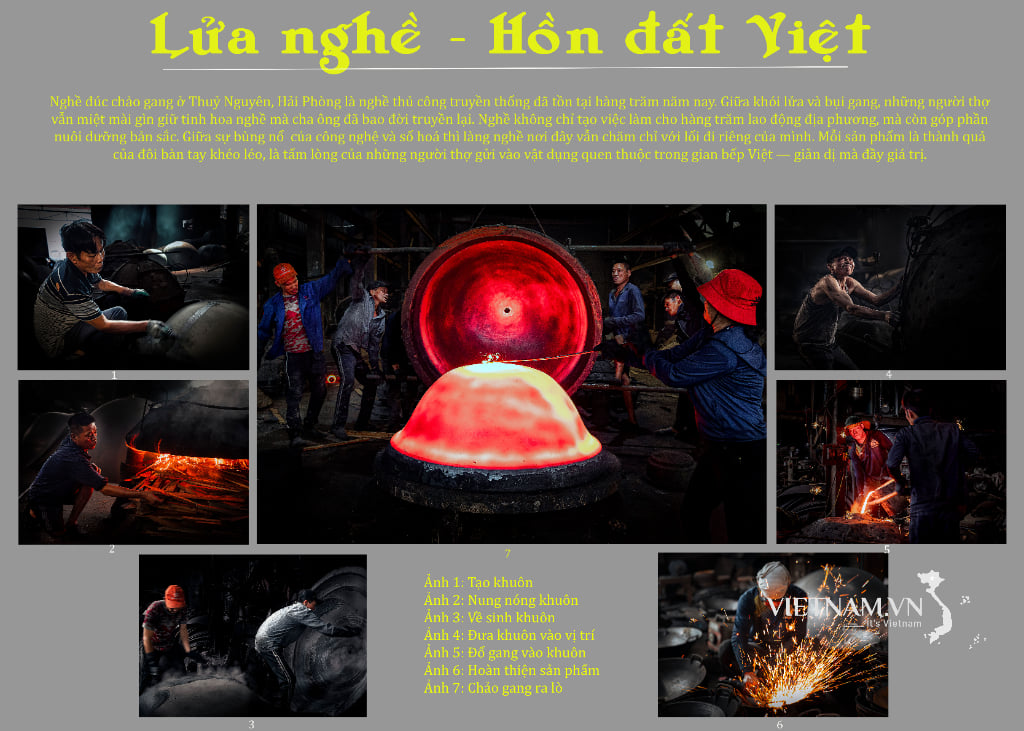


コメント (0)