
南ベトナムの言説には、川の影響が色濃く残っている。写真:DUY KHOI
様々な理由、特に地理的特徴により、日常生活におけるいくつかの言葉や音は南部住民によって新たに作り出され、共通の景観(至る所に広大な河川と水)を基盤として彼らの語彙を豊かにしています。日常生活、旅行、そして生計手段も河川と水と密接に関連しているため、南部住民は関連する比喩や隠喩を非常に豊かに用いています。
「川」を語源とする「giang」という言葉について、古代人は「co giang」は他人の水上乗り物(ボート、カヌー)にヒッチハイクするという意味だと言っていましたが、現代では一般的に乗り物(陸上乗り物)にヒッチハイクすることを意味します。誰かに歩いて同行することを冗談めかして「co giang」と言うこともあります。特に「qua giang」(川を渡る)と言うこともあります。例えば、古い歌にはこうあります。「キンマの葉一枚/お母さんに知らせて/一度か二度約束したことがある/愚かな子は渡し舟に乗って行った/幸運にも私たちは同じレストランや村にいる/そうすれば私たちの恋物語は金と石でさえ同じになるだろう」。
また、「ジャンホー」はかつて「ジャンホー侠客」のように、気ままにあちこちに暮らす人々を指す言葉として使われていました。後に「ガオチョンヌオックソン」のように、川で商売をして生計を立てる人々を指す言葉としても理解されるようになりました。そして次第に、人々は「ジャンホー」を俗語として、社会の周縁に住む悪人を指す言葉としても使うようになりました。
南部では、「水」や「水」に関連する言葉が地名に多く登場します。例えば、カイヌオック、ヌオック・チョン、ヌオック・ドゥック、ダウヌオック、ビントゥイ、ティエントゥイ、ホアトゥイ、タントゥイ、アントゥイ、タイトゥイ、トゥイトゥアンなどです。川と水があれば、行き来するための埠頭も必要です。南部にはベン・ゲ、ベン・サン、 ベン・チェなどがあります。「水」という言葉には多くの比喩的な用法があります。「トイ・ヌオック」「トイ・ベル」は、終わり、この瞬間に到達することを意味します。「レン・ヌオック」は磨かれた固体を意味します。「シュオン・ヌオック」は「頂点」にいた人が突然力を失い、声を弱めなければならないことを意味します。「ドゥオック・ヌオック」は、他人が屈服しそうになった瞬間に、もっと頑張ろうとすることを意味します。「ヌオックを与える」は、人々を奮い立たせることを意味します。

野原を駆け回るアヒルたち。写真:DUY KHOI
さらに興味深いのは、魚醤の煮込みやベジタリアン・ノンベジタリアンのスープなど、「食材と水があれば」という料理が、大きなボウルのような形をした「火鍋」に入れられることです。中央には熱した炭が置かれ、料理を温めます。炭が水とともに浮かんでいる様子が、川に浮かぶ島のように見えることから、南方の人々はこれを「島火鍋」「島料理」と名付けました。この言葉の裏には、川を中心とした生活に由来する、人々が日常的に使う無数の言葉や音が見られます。
南方では、「溺れる」という言葉は、溺れることに加え、「理性を失う」「力が尽きる」「沈む」といった意味も持ちます。「息切れする」は、水の中を歩きすぎて持ちこたえられない状態を表す言葉で、次第に、あまりにも多くの労力を必要とし、完了するのが困難になるようなことを指して使われるようになります。「導く」とは、船を操縦するだけでなく、あることを口にしながら別のことに切り替えることで、それを避けることを意味します。「カウ」は釣りをするだけでなく、「カウカッチ」とも呼ばれ、これは他人を引きつけるために様々な方法を示したり、自分の利益のために他人を欺く目的で、多く釣ったり少なく釣ったりすることを意味します。「チョダイ」は、話が途切れ途切れで、最後まで話したくないという意味です。「ボトロイ」は、問題を徹底的に処理しないことを意味します。「ランフップ」は、避けようとして、たまに不在になることを意味します。「クアイ・ムック・ヌオック」は、よくトラブルを起こす人を指します。 「サトイモの葉に水をかける」「足元まで水が来て跳ねる」「泥水がコウノトリを捕らえる」「平地は波が立つ」…など、おなじみの慣用句です。
船や船に関連する言葉、そしてそれに付随する習慣や物も、様々な意味合いで使われます。例えば、ある家族で婿となる男性は「漕ぐ兄弟」と呼ばれます(ただし、嫁でもある女性は「義理の兄弟」と呼ばれ、「漕ぐ兄弟」(妻の姉妹や友人)とは呼びません。なぜなら、ボートを漕ぐのは大変な重労働だからです)。「Già do(知らないふりをする)」は知らないふりをするという意味です。「Kèo bè kọp cánh(ケオ・ベ・コップ・カン)」は派閥や徒党を作るという意味です。「Bánh quai chèo(バイン・クアイ・チェオ)」は、足の親指ほどの大きさの生地を2つ、紐のようにねじり合わせて作った甘いケーキです。「Ghe cái tải trau(ゲ・カイ・タイ・トラウ)」は、力持ちだが軽々しく仕事を任せたり引き受けたりする人を指します。 「Xứ cầm bèo」とは、責任者が判断を誤り、故意に手を離してしまうことを指します。「網も船も失う」「舳先で矢面に立つ」「愚かな舵取りが矢面に立つ」「オールを握るために手を離す」「スムーズに漕ぐ」…これらは、ほとんど誰もが理解できる比喩表現です。
川辺での生活には物資が不足することはなく、魚やエビのイメージは様々な意味で使われています。「Sặc rần」は、不器用な作業員によって髪が傷んでしまうことを意味します。「Ngâm tôm」は、持ちかけられた問題は解決されず、いつまでもそのまま放置され、人々をうんざりと待たせることを意味します(エビは「反撃」する方法を知っている生き物なので、待てば待つほど、人々はより切羽詰まっているのです)。「Tép rong tém riu」は、取るに足らないことを意味します。「Tép di tém loi」は、早口で、聞き手を喜ばせるためなら何でも言う人を意味します。「Rông」は、一時的に監禁して後で「処理」することを意味します(魚を広げて少しずつ捕まえて食べるように)。「Vụtui's tail」は、自分の立場を明確に示さずに他人の言葉に従う行為を意味します。 「Đập nước đi cá」とは、人々を怖がらせてお金を奪うために攻撃的な行動をとることを意味します...
上記はほんの一例です。日常の民話には、文字通りの意味だけでなく、意味論的、比喩的、あるいは隠喩的な意味を持つ言葉やフレーズが数多くあります。こうした用法は今でも広く使われており、意図的か否かに関わらず、聞き手に南部の川の独特の生活を想像させます。
グエン・フー・ヒエップ
出典: https://baocantho.com.vn/doi-dieu-ve-bien-hoa-ngu-nghia-trong-cach-noi-cua-cu-dan-nam-bo-a193332.html




































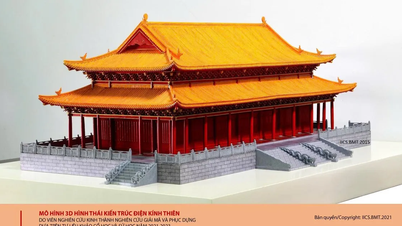






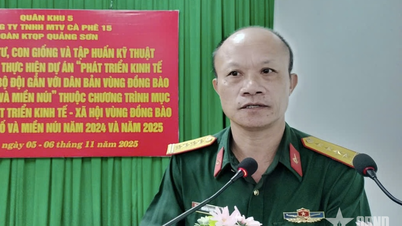









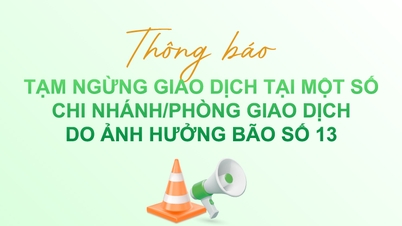




















































コメント (0)