これは、2021年から2025年の期間に国家目標プログラムを実施するために国家予算からのキャリア資金の管理、使用、決済を規制する財務省の通達55/2023/TT-BTCの規制です。
この通達は、2021年~2030年、第1期:2021年~2025年を対象とする少数民族及び山岳地帯の社会経済発展に関する国家目標プログラムを実施するためのいくつかの規定を明確に規定している。特に、住宅地、住宅、生産用地、生活用水の不足に対処するためのプロジェクト1に関しては、この通達には転職支援に関する規定が含まれている。
したがって、地方政府が生産用地を手配できない場合、土地を持たない世帯、または生産用地が不足している世帯に対し、1回限りの転業支援を実施します。民族委員会の指導に基づき、資格要件を満たした世帯については、審査の上、農具・機械の購入、 農業生産サービスの提供、他の耕作、畜産、生産、経営分野への転業に対し、1世帯あたり最大1,000万ドンを上限とした支援を実施します。支援の実施方法は民族委員会の指導に従います。または、初級レベル訓練および3か月未満の訓練を支援するための資金の管理および使用を規制する2016年10月17日付財務省通達第152/2016/TT-BTC号の第7条および第8条、通達第152/2016/TT-BTC号のいくつかの条項を修正および補足する2019年6月28日付財務省通達第40/2019/TT-BTC号の第1条第3項の規定に従って、転職のための職業訓練支援を受ける。

分散型生活用水に対する支援については、回状では、管轄機関が承認した分散型生活用水支援受給世帯リストに基づき、世帯の実施方法の登録、担当機関と予算見積もりがニーズを統合し、各実施方法(世帯が水差し、タンク、貯水槽、水容器、給水用品を受け取る、各自で水タンクを作る、井戸を掘る、または他の水源を作る)に分類し、それを県レベルの民族事務局に送り、同レベルの財務機関と調整して統合し、県レベル人民委員会に報告して、世帯当たり300万ドン(各世帯は1回のみ支援)を上限とする具体的な支援額を決定すると規定されている。世帯に提供する現物品を購入する場合、上記の支出基準には、請負業者選定の際に発生する費用も含まれる。
政策受益者への配分と支払いは次のように実施される:水差し、タンク、水槽、水容器、導水設備の支給を受けた世帯の場合:世帯登録名簿、所管官庁が指定した単位と水差し、タンク、水槽、水容器、導水設備の供給単位との間の供給契約、供給単位と各世帯との間の引渡し議事録(世帯代表者の署名入り)に基づいて世帯に実際に支給された数量、指定機関が検査を行い、国庫で予算を引き出して規定に従って水差し、タンク、水槽、水容器、導水設備の供給単位に支払う。
独自の貯水タンクを建設したり、井戸を掘ったり、その他の水源を作ったりする世帯の場合: 規定のサポート レベルと世帯登録リストに基づき、完了量の受領記録 (世帯の代表者と少なくとも 1 つの地元の社会政治組織の署名の確認付き) を取得した後、作業と予算見積を割り当てられた機関が検査を行い、国庫から予算見積を引き出して世帯に支払います。
住民の必要な場所への計画、配置、移転、定着に関するプロジェクト2については、通達は世帯を直接支援するための政策を規定しており、その中には、世帯の旧居住地から移転先への移転費用の支援が含まれる。したがって、移転費用の支援額は、実際のプロジェクトの設定に基づき、当該地域の一般的な車両の実際の距離と単価に基づいて算出される。
自給自足の交通手段、道路による自家用旅行の場合、支援額は活動実施時の行政距離とガソリン価格に応じて算出したガソリン0.2リットル/kmとする。同一車両で多数の物品、設備、資材を輸送する場合、最大支給額は上記の規定額を超えないものとする。
同時に、世帯への支援は、本通達の規定に従って実施されます。具体的には、世帯を支援するプロジェクトおよびサブプロジェクトについては、世帯の代表者、世帯主、または世帯代表者(完全な民事行為能力を有し、家族を代表して支援を受ける権限を書面で付与された者)を通じて世帯への支援が実施されます。
支援対象世帯リストの実施を支援する機関は、支援対象世帯の代表者の氏名と住所、支援金額または支援対象現物製品の名称、数量、技術仕様、記号、ラベル、生産単位、支援対象世帯の代表者の署名(指紋)または支払サービス組織の確認書(支払サービス組織を通じて支払う場合)を支払いおよび決済文書として明記します。
さらに、地元住民と同じように定住する世帯に対して、州予算の職業資金源(もしあれば)からのその他の現在の支援政策を実施します。
混住地区支援政策については、中央予算で混住地区に対し、1世帯当たり6,000万ドンの割合で支援し、新規移住世帯に割り当てられた住宅地および生産地の調整(土地の干拓、土地の干拓時に組織や個人から土地を干拓する際の規定に従った補償)の内容を実施すると通達に規定されている。
[広告2]
ソース



![[写真] ファム・ミン・チン首相が住宅政策と不動産市場に関する中央指導委員会の初会合を主宰](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/9/22/c0f42b88c6284975b4bcfcf5b17656e7)


























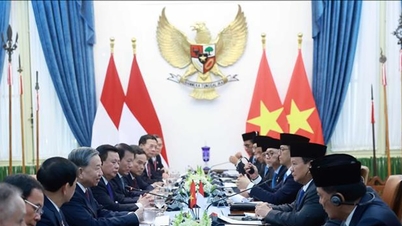




![[写真] ベトナム国家エネルギー産業グループに一級労働勲章を授与するト・ラム書記長](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/9/21/0ad2d50e1c274a55a3736500c5f262e5)



















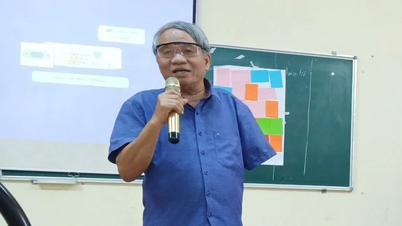














































コメント (0)