ほとんどの哺乳類は、魚類、両生類、爬虫類、または蠕虫ほど速く再生し回復する能力を持っていません…
一部の扁形動物、魚類、トカゲ類は、負傷後、体内のほぼすべての細胞を再生することができます。たとえば、メキシコのアホロートルは失った手足全体と脳の一部を再生することができ、トカゲは新しい尾を生やすことができ、ゼブラフィッシュは損傷した脊髄を再生することができます...
科学者たちは、遺伝子工学や細胞構造の進歩のおかげで、細胞レベルで人間を治療する方法を見つけるために、動物の再生能力に注目してきました…
先週香港で開催された国際幹細胞研究学会で、いくつかの研究グループが最新の研究結果を発表し、動物の再生能力に基づいた人間の病気の治療のアイデアを提案した。
ゼブラフィッシュ脊髄の再生能力
組織再生と幹細胞生物学の専門家であるメイサ・モカレド博士とミズーリ州ワシントン大学(米国)の同僚らによると、脊髄を切断されたゼブラフィッシュは、麻痺状態から8週間後にはスムーズに動けるようになり、完全に回復する可能性があるという。

ゼブラフィッシュには損傷した脊髄を再生する能力がある(写真:ブリタニカ)。
そこで、メイサ・モカレド氏とその同僚は、ゼブラフィッシュにおいて回復プロセスで重要な役割を果たす細胞群を発見した。これらの細胞はヒト胎児のアストログリア細胞に類似している。
これらのアストログリア細胞は、損傷後の人間の脳組織の修復と再生に関与している可能性があるほか、脳に入る物質を制御して有害物質から脳を守る血液脳関門の形成と維持にも重要な役割を果たしている。
研究の中で、メイサ・モカレド博士のチームは改変したヒトのアストログリア細胞をマウスに移植し、これらの細胞は脳の保護バリアを形成するのにより効果的であった。
「この成果が人間の治療法に応用されることを期待しています」とモカレド博士はコメントしたが、これはまだ初期の研究であることを認めた。
トカゲの尻尾再生能力
メイサ・モカレド博士の研究はまだ初期段階にあり、ゼブラフィッシュと人間の間の進化のギャップは非常に大きい。
南カリフォルニア大学(米国ロサンゼルス)の幹細胞生物学者アルバート・アルマダ氏とその同僚は、アノールというトカゲの尾の再生能力を研究した。
アルバート・アルマダ氏は、トカゲと人間は多くの類似した遺伝子を共有しているため、研究チームはトカゲの尾の再生過程を模倣した治療法を見つけたいと考えていると述べた。

グリーンアノールトカゲは人間と似た遺伝子を持っている(写真:iNaturalist)。
会議でアルマダ氏は、アノールトカゲの尾の再生に幹細胞がどのように関与しているかを説明した。これらの細胞はマウスやヒトの細胞と類似しているが、アノールトカゲは失われた尾を再生するために、全く新しい筋肉組織を作り出す能力を持っている。これはヒトやマウスにはできないことだ。
それでも、アルマダ氏は、尾の再生中にトカゲの細胞がどのように機能するかを解明したいと考えている。この解明は、加齢に伴う筋肉の変性など、人間の筋肉関連疾患の治療や傷の治癒を早めるのに応用できるかもしれない。
海洋剛毛虫の超高速回復能力
ウィーン大学(オーストリア)の幹細胞生物学者フロリアン・ライブル氏は、別の動物である海洋剛毛虫(学名 Platynereis dumerilii)の超回復能力を研究している。
海洋繊毛虫の特別な点は、若いときには再生能力が非常に優れているが、成体になるとホルモンの変化により徐々に再生能力を失っていくことです。
「これは、同じ生物において良好な再生と不良な再生の両方を示すモデルです」とフロリアン・ライブル氏は語った。

海の繊毛虫は、損傷した体を超高速で再生する能力を持っている(写真:CNRS)。
ライブル氏らは実験で、剛毛虫の体を切断し、傷の近くに残った細胞の一部が幹細胞に変化し、神経細胞を含む体の再生を始めることを発見した。
繊毛虫の神経系は脊椎動物の中枢神経系と類似点があり、科学者たちはそれが人間の脊髄損傷の治療の解決策を見つけるのに役立つのではないかと期待している。
科学者たちはまた、海の繊毛虫の研究が成人の人間の組織から幹細胞を再生する方法を見つけるのに役立つことを期待している。
「現在、動物の超治癒能力を研究し、その発見をどのように応用できるかを探るための大きな取り組みが行われています」とアルバート・アルマダ氏は語る。
出典: https://dantri.com.vn/khoa-hoc/kha-nang-tai-tao-cua-dong-vat-mo-ra-co-hoi-chua-benh-cho-con-nguoi-20250626025239694.htm


















































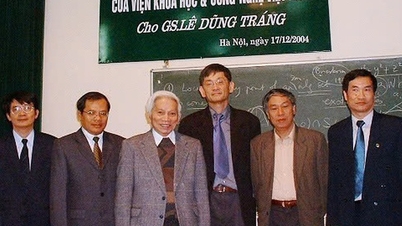



















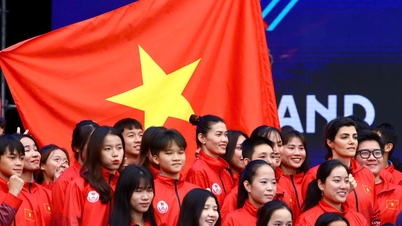

















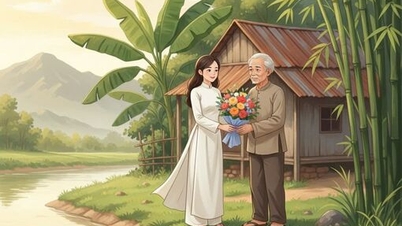





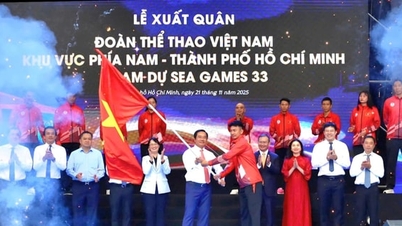
















コメント (0)