12月20日午前、ハノイ産婦人科病院は、北部各省・市の産科領域の医師数百人が参加し、2024年第12回ハノイ産婦人科科学研究指導会議を開催した。
ハノイ産婦人科病院院長のマイ・チョン・フン博士は、この年次会議はハノイ産婦人科病院とハノイおよび近隣省の病院、そして全国の代表者とのつながりを示す、包括的な専門知識を交換する場であると語った。
この方針の推進により、近年、産婦人科部門は母体と胎児の健康管理、病院での死亡率の低減から、出生前スクリーニング、胎児介入、婦人科がん、内分泌学、生殖、不妊症、不妊症などの専門分野に至るまで、重要な進歩を遂げてきました。
ハノイ産婦人科病院院長のマイ・トロン・フン博士が会議の開会演説を行った。 |
ハノイ産婦人科病院は、産婦人科領域の最終ラインとして、2018年以来、常にその役割と責任を認識し、協力し、専門知識を交換し、技術を移転することで、生殖医療における業務の質の向上と品種の品質向上に貢献したいと考えています。
胎児介入に関する知識が再び多くの産科医の注目を集めています。
会議において、胎児介入センター副所長のファン・ティ・フエン・トゥオン医師は、「先天性横隔膜ヘルニアの治療における胎児腹腔鏡手術の応用」と題した講演で、先天性横隔膜ヘルニア(CDH)は妊娠2200件につき約1件の割合で発生する先天性奇形であると述べた。
これは、9〜10週で胸膜と腹膜が完全に閉じないことによる横隔膜の欠陥であり、消化器官が胸腔内に移動し、肺低形成と肺高血圧を引き起こし、呼吸不全と高い死亡率につながります。
トゥオン医師によると、先天性横隔膜ヘルニアを持つ胎児の約30~50%は妊娠24週未満で中絶され、平均生存率は37.7%です。もし生まれた場合、この疾患は赤ちゃんに長期的な後遺症を引き起こし、酸素依存症、喘息、気管支拡張症などを引き起こします。
特に中等度から重度の横隔膜ヘルニアの場合、出生後の治療は効果がなく、子供は肺低形成や肺高血圧症による長期の後遺症を抱えることになります。
したがって、経皮経管内視鏡(FETO)による出生前介入は、重症および中等度の CDH 症例に対する有望な介入であると考えられます。
ハノイ産婦人科病院院長のマイ・チョン・フン医師によると、同病院はハノイ市内の各病院において、胎児内視鏡を用いた気管閉塞法を用いた先天性横隔膜ヘルニアに対する出生前介入法の開発と結果評価を目的とした研究プロジェクトを実施している。この研究では、先天性横隔膜ヘルニアと診断された妊婦15名が2024年7月から2027年6月までの間に参加する予定である。
「胎児腹腔鏡手術、特にFETOは、重症および中等症のCDHに対する有望な治療法として浮上しています。多くの課題はありますが、継続的な進歩により、治療成績の向上が期待されています。私たちの目標は、ハノイの病院で先天性横隔膜ヘルニアの治療に用いる胎児腹腔鏡下気管閉塞法を確立することです」と、ハノイ産科婦人科病院の院長は述べています。
会議では、子宮筋腫の低侵襲治療の結果、帝王切開傷跡欠損の診断と治療、保存的治療を優先し手術と再手術を最小限に抑えることによる子宮内膜症の治療観点の重要な変化、前置胎盤での子宮の温存、妊娠週数に応じた早期破水の治療など、産婦人科領域における多くの新しい技術的成果について医師らに最新情報が伝えられました...





















































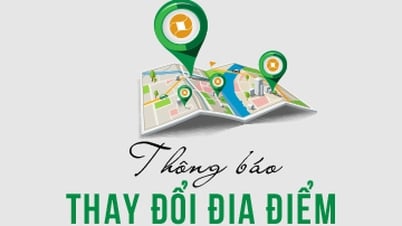
















































コメント (0)