今まで、彼女はそれが本当だと信じられなかった。昨日の午後、彼は彼女に食事を与え、世話が終わったらすぐに帰ると言った。しかし今、彼は彼女を一人残して、そそくさと出て行った。そのことを考えると、彼女の目尻から二筋の涙が流れ落ち続けた。
彼女は起き上がりたい、夫に線香をあげたいと思ったが、できなかった。危うく死にかけた脳卒中以来、ここ数ヶ月、彼女は一度も自力で起き上がることができなかった。夫はいつも彼女を支えてくれた。二人の老婦人は昼夜を問わず話し、その間、子供や孫たちは一日中忙しくしていた。
- 母がそう言っていました。両親が一番お金持ちです。
- 数えてみたけど、両親にはもっとあるよ。
- トゥアン、いくつ持っていますか?
- 彼の家族は数える必要はありません。父方の親戚は田舎に一人だけいるだけです。
それは孫たちの声だった。何を話しているのかは分からなかったが、呼び戻したいと思った。病気で寝たきりになって以来、孫たちに会うことはできなかった。部屋の中で横になり、孫たちの声に耳を傾けていた。孫たちがどれくらい太っているのか痩せているのか、分からなかった。息を切らして、彼女は呼びかけた。
- カイン、カイン! - 彼女は静かに聞いていたが、返事はなかった - ミン、ミン!
彼女はしばらく待ったが、孫たちは誰一人返事をしなかった。きっとどこかに出かけてしまったのだろう。彼女はため息をついた。ラッパは鳴り続け、途切れることなく鳴り響いていた。
しばらく横になって耳を澄ませていた老婦人は、いつの間にか眠りに落ちていた。目が覚めた時は、おそらく真夜中だった。外のトランペットの音も泣き声も聞こえなくなっていたからだ。部屋のセンサー付きナイトライトが点灯していた。口の中は苦く乾き、お腹がゴロゴロと鳴った。一日中何も食べていなかった。外の声が聞こえるようだったが、耳はまだゴロゴロと鳴り、一言も聞こえなかった。両手で体を支え、起き上がろうとしたが、細い首をドアの方に伸ばして呼びかけた。声はドアに遮られ、跳ね返って自分に当たったようで、彼女は後ろに倒れ、息を荒くした。
しばらく考えていると、また喉が渇いた。頭を上げてベッドの頭側のテーブルを見た。そこには、今朝娘が飲ませてくれた水のボトルがあった。肘掛けに寄りかかった。その足は、どうやら自分の足ではなく、彼女の足を引っ張っているようだった。もっと頑張ろう、もっと頑張ろう。ホッと一息つき、喜びに目を輝かせながらボトルに手を伸ばした。こうすれば、今度自分でやろうとするときには、だんだん慣れてきて、子供や孫に迷惑をかけずに済むだろう。夫がまだ生きていた頃、とても大切に育ててくれたので、もう何もできないと思っていたことを思い出した。ボトルの取っ手を掴んだが、弱った腕では持ち上げることができず、体重で引きずられ、ガラスにぶつかってしまった。
バン!
- それは何ですか!
彼女はパニックになり、震えました。
- お母さんは…お母さんは…お母さんは…
彼女は老眼で、目の前に立つ子供たちを見つめた。父親の葬儀を担当したのはたった二日前なのに、皆疲れ切っていた。彼女は子供たちを気の毒に思った。
- ただ一杯の水を注ぎたいだけなんです。
長女の嫁は、人差し指を鼻に当てて、気取った様子で言った。数人は顔を見合わせ、軽く眉をひそめてから、外に出て行った。長男は妹に言った。
- ホアさん、私のために掃除をしてください。それからお母さんのために着替えと洗濯をしてください。
その時になって初めて、彼女は部屋の中がカビ臭いことに気づいた。それはあまりにも退屈で、二人にとって何の助けにもならず、むしろ疲れを募らせるだけだった。
ホアは彼女の末娘で、田舎に住んでいます。夫婦ともに農家なので、兄たちほど裕福ではありません。子供たちは素直です。
- お母さん!田舎に戻って一緒に暮らして。まずは私と一緒に暮らして。
娘はそう言いながら着替えて身なりを整え、それから泣き出しました。そして小さくため息をついて、優しく言いました。
- 水をください。
娘はしばらく静かに外出し、そして戻ってきた。老婆は娘の手に握られた椀の香りを嗅ぎ、一日中じっとしていた空腹の胃がゴロゴロと鳴った。
- 一日中、弟と妹がお客様を迎えるために水を準備するのに忙しかったので…夜も遅いし、インスタントのお粥しかないので、お母さんが食べます。
子供の悲しそうな顔を見て、彼女は手を振り、うなずいた。まるで後悔と悲しみに沈んでいるようだった。家で葬儀があったので、子供や孫たちの疲れを癒すためにトランプをしていた。すると突然、リビングから大きな音が聞こえてきた。
「聞こえないでしょ!お母さんを家に連れてきて、私たち夫婦のことをみんなに笑わせて。だって、トアンは長男なんだから。」 トアンの妻の声は明瞭だった。
「ええ。それに、私は大企業の社長だし、あなたの妹さんも文化庁の長官だし、こんな家と条件で、どうして母さんを支えられないの?それに、ここにいるトアンおじさんと奥さんは、二人とも成功した実業家で、幅広い人脈を持っている。もし母さんを田舎の叔父と叔母の家に連れて行ったら、面と向かって罵倒されるわよ」とトアンは妻の言葉を続けた。
― 正直、悪気はなかったんです。田舎暮らしの夫と私はもともと自由な時間が多くて、母の世話をする時間もあるんです。でも、あなたたちはあれやこれやでいつも忙しいですよね…。
ホアの夫(老婦人の義理の息子)が言葉を言い終える前に、次男のトアンが口を挟んだ。
- つまり、ここでお母さんの世話ができないってこと?忙しいなら、誰かを雇って世話をしてもらうこともできる。家に送るのは良くないよ。
「ええ、息子はまだ元気です。どうして急に母を婿のところに住まわせる必要があるの?私たちの評判なんてどうするの?」老婦人の次女が口を挟んだ。「それに、正直に言うと、母を嫌いな人は我慢できないの。でも、母はいつまでこんな生活を続けられるの?死んだら、婿の家で幽霊のように暮らすわけにはいかないわ。ここに連れてきたら、みんな唾を吐きかけてくるわ。病気になっても看病してくれないし、死んだら組織に引き取られるわ。」
長男はうなずき、こう結論した。
要するに、母を私の家に預けておいて。忙しくて面倒を見るのが面倒なら、誰かを雇えばいい。あなたと叔父さんは貧しいから、負担する必要はない。トアンおじさん夫婦が望むなら負担してもいいし、そうでなければ無理だ。私は毎月数百万もかけて母の世話をする人を雇っているのに、そんなの割に合わない。
「あら、こっちに来てお母さんの面倒を見てあげたらどう? 誰かを雇わなくてもいいと思って。毎月給料を払えばいいのよ。娘さんがお母さんの面倒を見てくれるのが一番安心だし、副収入にもなるわ。農業ほどいい仕事じゃないけど」
「月1000万でやろうか。どう思う? ホアにお母さんの世話をさせて、君と弟のために家の掃除を頼む。毎月全額払うし、1日3食の世話もする…」
耳を澄ませば澄ませるほど、耳がざわめき、まるで何かが聞こえなくなってしまった。お粥は塩辛すぎて飲み込めなかった。彼女は手を振り、もう食べないことを知らせた。目尻にはどろっとした涙が浮かんだ。もし彼女が病気でなければ、子供たちはこんな大変な状況にはならなかっただろう。
ホアはタオルを取り、母親の口を拭いてから横になるのを手伝った。「お母さん、寝なさい」と優しく言ったが、声は詰まっていた。彼女はうなずき、眠る準備をするかのように軽く目を閉じたが、娘がボウルを持ってきてドアを閉めるのを待ってから目を開け、部屋を見回した。反対側は空っぽだった。彼が毎日寝ていたベッドは移動されていた。
彼女は一晩中意識を失っていた。子供たちが成功するまで苦労して育てた昔の日々を思い出した。脳卒中で寝たきりになった時も、幸いにも夫がそばにいてくれた。そうでなければ、子供たちや孫たちは苦しむことになっただろう。まだ元気だった頃は、家事や料理などで子供たちを手伝っていた。
夜はとても長いですね!

イラスト:HOANG DANG
*****
娘は朝7時半の葬列に備えて、夜明けから彼女にミルクを与えていた。家の外はすでに騒がしかった。ブラスバンドが再び演奏を始めていた。彼女は外に出て、彼に別れを告げたかった。二人は生涯を共にし、喜びも悲しみも分かち合った。しかし、今は彼が先に旅立つのだから、最後の旅立ちを見送ることはできないだろうか?そう思ったが、子供たちには言えなかった。たとえ言ったとしても、彼らは冷淡に受け入れるだろう。足が普通に歩けさえすればいいのに。彼女は考え続け、トランペットと太鼓の音に心を奪われた。
- あなたなの?
- 私だよ。さよならを言って行くよ。ここにいて、体に気をつけてね。考えすぎると、もっと具合が悪くなるよ。
「もう具合が悪いんです。お子さんやお孫さんに迷惑をかけないように、一緒に行けたらいいのにな」
- そんなこと言わないで。
- 出発前に私の面倒を見るって約束してくれたじゃない。私が先に行くべきだったわ。
― 一緒にいられなくて、ちゃんとお世話が出来なくてごめんね。もうすぐその時だよ。先に行っちゃうよ。あそこで君と再会できる日を待つよ。
彼がゆっくりと歩き出し、ドアの向こうに姿を消すと、彼女は身を乗り出し、腕を振り回した。彼女は地面に倒れ込み、まだ彼の姿を見つめていた。胸が痛んだ。彼は本当にいなくなってしまったのだ。
トランペットと太鼓の音が聞こえ、葬列が始まったのだと察した。彼女のいる場所から彼のいる場所まではわずか十数メートルしか離れていないのに、今は遠く感じられた。彼女は目の前の地面を掴み、扉に向かって体をよじりながら進んだが、少し動いただけでもう力が入らないようだった。銅鑼、太鼓、トランペット、フルート…の音は、どんどん遠ざかっていくようだった。
[広告2]
ソース











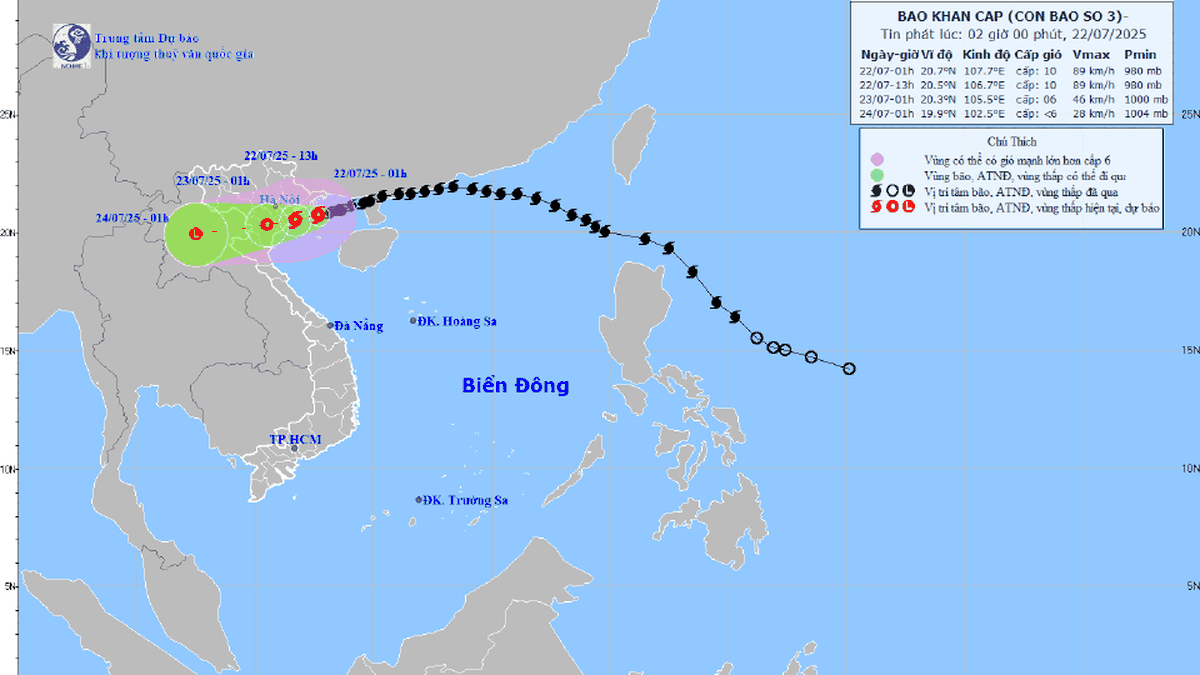












































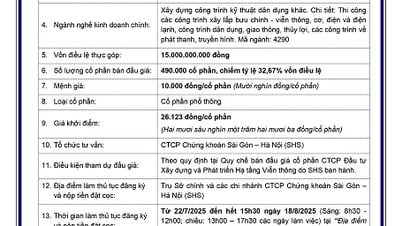








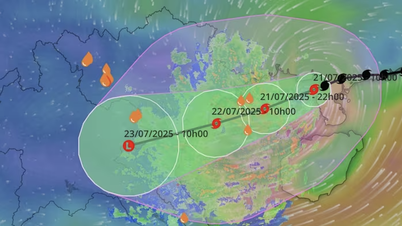











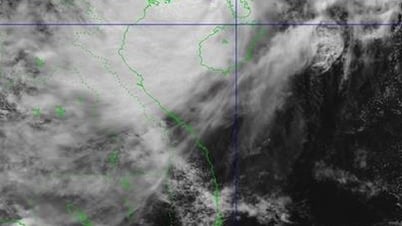























コメント (0)