トラン・ゴック・ソン准教授によると、10月初旬、インドネシアで勤務するオーストラリア人家族が、4歳の娘の便が淡色で、腹痛と嘔吐を伴っていることに気付きました。インドネシアの医師は娘に総胆管嚢胞(そうしゅうのうほう)があると診断し、開腹手術を勧めました。

家族は病気について学び、国際会議でトラン・ゴック・ソン准教授が発表した胆管嚢胞の治療のための単孔腹腔鏡手術法に関する文書を研究した後、子供をベトナムに連れてくることを決意し、手術の場所としてサンポン総合病院のハイテクセンターを選びました。
ソン医師によると、患者の胆管は長さ2センチで、ダイヤモンド型に拡張しており(通常、主な胆嚢は嚢胞状に拡張し、胆管はわずか2~3ミリ)、すぐに手術しないと合併症を起こしやすいとのこと。
ザンポン総合病院のハイテクセンターでは、診察と検査の後、ソン医師が単穴腹腔鏡手術法を使用して、へその小さな切開で患者に直接手術を行いました(4穴腹腔鏡手術を行う場合は、患者に別々の切開が必要です)。
この方法は、痛みが少なく、腹壁へのダメージが少なく、傷の治癒が早く、醜い傷跡を残さず、合併症のリスクを最大限に抑えられるという利点があります。へそのごく小さな切開は自然な傷跡なので、新たな傷跡は残りません。しかし、これは難しい手術法であり、器具を挿入する経路が非常に狭いため、手術中の操作が非常に困難であり、外科医は非常に繊細かつ正確な操作を要求されます。
上記の患者さんの手術では、ソン医師はへその15mmの切開のみを行いました。術後、患者さんは速やかに回復し、数日後には走ったりジャンプしたりできるようになりました。術後7日で退院可能となりました。
総胆管嚢胞の単孔腹腔鏡治療は特に難しい技術です。
ベトナムは現在、この技術の応用に成功したと報告している世界の2カ国のうちの1つです。
[広告2]
ソースリンク


































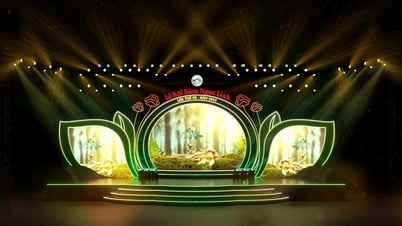

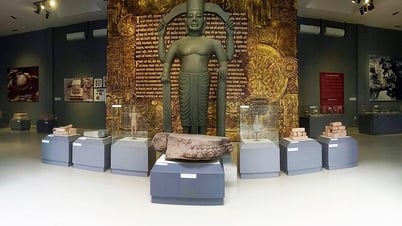




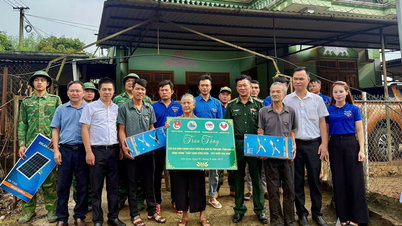




























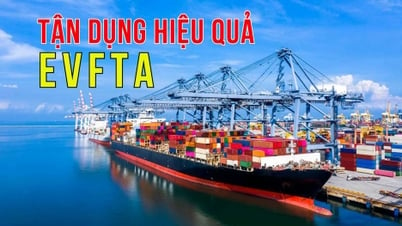




















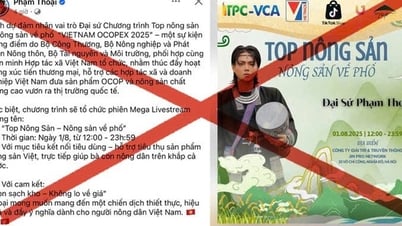






コメント (0)