
- 麺1本とスライス1枚!
- 麺類2杯とサンドイッチ2個をお願いします!
杜夫人は一人で、目の前の麺の入った丼、スープの入った鍋、そして右手には湯気の立つソーセージの鍋を操り、客に時間通りに販売できるよう手早く肉を切っており、厨房から決して離れようとしなかった。厨房の隅に近づくことは誰にも許されなかった。なぜなら、代金の徴収から客に麺の出来具合を聞くことまで、他のすべての業務は杜氏が担当していたからだ。
彼が店に入る必要がある場合、客は少し待たされるか、常連客であればテーブルに金を置いて、その上に茶碗を置くことができた。彼女は彼のために金を集めることは決してなかった。客が来ると、彼女は「待ってください。私が渡します」と言った。
おじいさんの麺屋は、名前も看板もない店だとよく言われるが、金集めから材料の準備まで、すべての工程が「プログラム」化されているため、ブランド店よりもプロフェッショナルだ。店主が痩せて背が低く、白髪混じりのハイカットヘアをしていることから、客たちはここを「おじいさんの店」と呼ぶ。
この店はシンプルながらも特別な雰囲気を醸し出しています。特筆すべきは、干しエビと干しイカを骨付きのまま煮込んだ甘辛いスープ。骨は店主自ら屠畜場で選別し、細かく刻んで柔らかく煮込んでいます。お客様は、柔らかい骨をゆっくりと噛みながら麺を味わうことができます。
レストランの大きなテーブルには、小さな椀が何段も重ねて置かれていた。大きな椀には均等にスライスされた唐辛子が、少し小さめの椀には黄金色の辛子漬けが、小さな椀には胡椒とMSGが入ったものが2つ、そして魚醤と醤油が数本ずつ入っていた。客は自分でソースを調合することができ、老人は代わりにソースを運んではくれなかった。客は食べ終わると、老人の前を通り過ぎて代金を預けたが、老人は各テーブルを回って代金を回収することはなかった。
店が混雑している時でも、彼は客には明るく接していたが、妻には不機嫌だった。妻は眉をひそめたり、夫に腹を立てたりすることは決してなかった。ただ黙々と仕事をこなし、厨房を離れることはなかった。まるで別世界から来たかのようだった。外の喧騒など気にせず、彼女は仕事に全神経を集中し、細かな作業も一つ一つ正確にこなし、満足のいく一杯の麺を作り上げていた。
* * *
朝。老人は梅の木の下のテーブルに座ってお茶を飲んでいた。今日は店が閉まっている。小さな白い黒板には「旧暦の16日まで閉店」と書かれていた。店主が病気になったのはその時だった。彼女が休むと、彼も休んだ。店主を喜ばせられるのは彼女だけだった。店のウェイターは数日ごとに入れ替わった。彼らが苦労に耐えられないからでも、店主が彼らの働きに見合うだけの給料を払わないからでもない。
彼は非常に公平な人だった。出勤前にウェイトレスと綿密な約束を交わしていた。仕事内容は、店が混雑している時だけ厨房のカウンターからテーブルまで麺を運ぶことと、客がうっかり床に落とした骨やキッチンペーパーを片付けることだけだった。日給も事前に決まっていた。しかし、彼は頑固で短気なところがあり、彼女以外にも女性に恨みを抱いているようだった。
* * *
杜夫人は、杜氏の変わった性格について誰かが文句を言うと、いつも微笑んでいた。彼を擁護することも、文句を言うこともなかった。彼女は心の底の熱さや冷たさをよく知っていたので、それをひけらかす必要はなかった。周囲を新築の立派な家々に囲まれた、小さくて古い家は、毎日二人きりで過ごすため、寂しかった。
近所の人たちは、彼らが大声で話しているのを一度も聞いたことがなかった。まるで麺を売っている時は、人生という舞台で燃え尽き、互いに、そして人生に、あらゆる側面をさらけ出しているかのようだった。しかし店が閉まると、彼らは静かな片隅に引きこもり、彼らの生活はスローモーションのフィルムのように静かだった…。そして、周りの人々も彼らについてそう思っていた。彼らが何を考え、どのように暮らしていたかは、彼らだけが知っていた。
* * *
トゥ夫人は家の前まで籠を担いで、梅を摘みに来た。風がざわめき、彼女は一つ一つ丁寧に実を摘んでいた。この木は彼女の故郷ゴーコンから持ち帰ったもので、実は実り豊かで、真っ白で、甘かった。今朝、麺を食べながらお客さんが言った言葉が、今でも私の心に響いている。
- 彼女は年をとっていますが、まだ美しく、若い頃は多くの人が彼女を愛していたに違いありません。
トゥ氏は怒っていた。
- 彼女を褒めないでください。彼女は本物だと思って、塩を入れすぎたのです。
当時の自分が美人だったかどうか、彼女は思い出せなかった。彼女の家は貧しく、自分の姿を見る鏡さえなかった。彼女は農家の娘で、毎日一日中働き詰めだった。朝の3時か4時に起きてご飯を炊き、それから畑へ急いだ。家族のために農夫として、あるいは人夫として、あるいは雇われ労働者として働いた。
種まきの季節が過ぎると、豆の種まきやジャガイモの植え付けが始まります。あっという間に収穫の季節。朝は日が昇る前に畑へ。午後、家に帰ると太陽はもう眠りについています。美しさや醜さを見つめる暇などありません。
彼女を心から愛してくれる人はたくさんいたが、彼女は気にしていなかった。娘は自分のことを大切にすべきだ。13歳で初めて自分の体に異変を感じた時から、母親はそう言い聞かせてきた。そして、自分自身を尊重しなければ、誰が自分を尊重できるというのか、と何度も繰り返した。
* * *
杜氏は静かにお茶を飲んでいた。彼は自分が他の人とは違うと感じていた。妻の美しさを褒められると、男は皆嬉しくなる。彼らは動揺するどころか、喜びと誇りに満たされる。美しい妻と出かけ、自分の誇りを持てたらと思う男も少なくない。
「お茶をどうぞ」彼女はティーポットに熱いお湯をそっと注ぎました。
「ここに座って楽しんでください」彼の声には少し憤りがあったが、彼女は一目見て理解した。
- 人の言うことに耳を傾けないで。人が醜いか美しいかなんて、問題にならないでしょ?
- 醜いとか美しいとか、どうしたの?何十年も経ってるんだから、別に気にする必要はないわ。
* * *
杜さんは疲れていました。高齢者の健康状態は天気のように変動しやすいのです。彼女は高血圧を患っており、今回の測定結果でも健康状態は変動していました。血圧は感情に左右されるため、安定しにくいのです。悲しみや不安も血圧を上昇させ、めまいを引き起こしました。
杜氏は何も言わなかったが、彼女を悲しませ、疲れさせてしまったことを悔やんでいた。二人は田舎で、彼が20歳、彼女が18歳から50年間一緒に暮らしてきたので、お互いをよく理解し合っていた。二人とも年老い、歯並びが悪くて梅を噛むのに長い時間がかかっているにもかかわらず、彼は密かに嫉妬していることを彼女は知っていた。
異性に感情を抱き始めたばかりの若い頃から彼女に気づいてはいたものの、後発者としての劣等感を抱いていることを彼女は理解していた。当時、人々は彼をバ・キエンと呼んでいた。彼女の名前ではなく、今となっては。
* * *
トゥ夫人は幼い頃、トゥ・トイと呼ばれていました。トゥ・トイは豊かで光沢のある髪をしていました。バ・キエンは、友達とキャンドルベリーの木の下で昼寝をした日から、彼女の長い髪が大好きでした。昼寝の後、午後の植毛の前に、トゥ・トイが髪を梳かして整えると、その髪は幼いバ・キエンを魅了しました。
バ・キエンはたくさんの夢を見ますが、自分とトゥ・トイがまるで不釣り合いな箸のペアのように、夢を見る権利があるのは自分だけだと分かっています。トゥ・トイは背が高くて細身で、えくぼのある魅力的な笑顔を持ち、勤勉で優しく、穏やかな口調で話します。バ・キエンは背が低く、痩せていて、ぶっきらぼうです。
* * *
午後になると、バ・キエンはトゥ・トイの家の前を通りかかり、トゥ・トイが夕食を作っている時間を見計らって立ち寄り、サトウキビや梅を少しずつ渡していました。トゥ・トイの家族は、この田舎では、少し余裕があれば野菜や魚を分け合うのが当たり前だったので、何も禁じたり、気に留めたりしませんでした。バ・キエンが白い梅の木を持ってきたとき、ようやく彼らは事情を知り始めました。トゥ・トイの父親は、バ・キエンは愚か者だとみんな言っていたが、それは事実ではないと言いました。
彼はこの家に梅の木を贈りました。それは彼がこの家に根を下ろしたいという意味です。そんな弱い男が、どうやって妻と子供を養えるというのでしょうか?
トゥ・トイさんの母親は心配しながら、娘にバ・キエンさんには気をつけるように言いました。
* * *
トゥ・トイは13歳の時に母に言われた言葉をいつも心に留めていた。他人に認められるためには、自分を律しなければならなかった。バ・キエンとの関係においては、彼が自分を高く評価してくれていると分かっていても、他のことは何も考えなかった。両親が同意した時だけ頷くようにと、いつも自分に言い聞かせていた。トゥ・トイにとって、大人は経験豊富で、一目見ただけで善人か悪人かが分かったからだ。
* * *
早朝、杜夫人は髪を梳かしていた。自分が年老いて、まるで不毛の地のように薄毛になっていることに気づいた。髪を整えようと梳かすたびに、手に持つ髪の毛が少しずつ減っていくのがわかった。数年前には大きなオレンジほどの大きさだったお団子は、今では大きなニンニクの塊ほどの大きさになっていた。
彼女は庭に出て、梅の木に水をやっている杜氏を見た。背中は丸まり、体型はどんどん小さくなっていた。おそらく彼も彼女と同じように、自分がどんどん小さくなっていることに気づき、自分の体型に対する劣等感に苛立ちを募らせているのだろう。彼は複雑な感情を抱いていた。ムオイ・トットを憎む気持ちと、嫌いなあの人のような強く健康な体を手に入れたい気持ちが半分ずつあった。
* * *
「やあ!ボラの生姜魚醤炒め。誰もシャツを持ってないけど、行くのがちょっと躊躇ってる」
ムオイ・トットはただそんなふうに淡々と歌っただけだったが、トゥ・トイの植樹グループの姉妹たちは、彼がトゥ・トイの意図を巧みに試しているのだと思い続けていた。
ムオイ・トット氏は再びこう語った。
「ほっ…ほっ…おお…おお!空を見上げて、白い雲、青い雲/みんな好きだけど、特に君が好き」。友人たちはトゥ・トイに歌い返すように促した。
「ほっ、ほっ、あ、あ、あ!私の結婚生活は大丈夫、そんなふうにふざけないで。あなたを愛しているから気をつけているの、そうしないと噂されちゃうから。」
バ・キエンは打ちのめされたように感じた。背が高く、筋肉質で、優しい農家の少年、ムオイ・トットには到底及ばないと思っていた。
午後、トゥ・トイの家を通りかかったとき、バ・キエンは勇気を振り絞って、興奮して声を震わせながら歌を歌いました。
「ホーホー…オー…オー!手を伸ばしてコリアンダーの茎を摘む/君を愛しすぎて、無視するふりをする」荒々しくぎこちない歌声は、短く嗄れた息で途切れた。トゥ・トイはそれを聞いて、理解したが、どうしたらいいのか分からず、そのまま放っておいた。すべては両親の意志にかかっていた。
* * *
杜夫人は物思いにふけり、心の中で微笑んだ。彼が嫉妬していることは分かっていた。年老いて、もうすぐ死を迎えるというのに、それでも嫉妬は消えない。彼は彼なりの方法で彼女を愛していた。彼女には自分以外の男と関わるなって思ってほしくなかった。社交界では、彼女はいつも彼に一歩を踏み出させ、自分にふさわしくないという思いを忘れさせていた。心の奥底では、彼は恩人だった。
彼はなかなか消し去れない恨みを抱えていた。男が彼女に近づくと、彼は怒り、動揺した。たとえ彼女が高潔な人であっても、彼女を一人にしておくと安心できなかった。ある時、二人でお茶を飲んでいた時、彼はまるで感情を爆発させたかのように何かを言ったが、彼女は彼がずっとそのことを考えていることを分かっていた。
- 君が先に死んでくれれば、私が君の面倒をちゃんと見ることができるのに。私たちには子供がいないんだ。
彼女は悲しそうに微笑んだ。「正直、何十年も経っているのに、あなたはまだその古い話を忘れていないのね。」
* * *
バ・キエンは野原の真ん中にある藁葺き屋根の小屋に一人で座っていた。午後なのに、太陽はまだ明るく輝いていた。悲しみが洪水のようにこみ上げてきた。トゥ・トイを心から愛しているのに、なぜ愛する人と一緒にいられないのだろう?結局のところ、彼もムオイ・トットに劣るわけではないのに。
見た目は少し劣っていたものの、ムオイ・トットは一度に二斤の米を運ぶことには引けを取りませんでした。トゥ・トイは、彼女がとても従順で、両親の言うことをいつも聞いていたので、自分の感情を誰にも表に出さないことを知っていました。両親が同意する限り、彼女は決して逆らうことはありません。
明日はトゥ・トイの結婚式。近所の人々は結婚式の準備に忙しくしている。バ・キエンはトゥ・トイの結婚式の後、遠くタイニン省まで船を漕いで行き、そこで雇われて働く計画を立てている。どこも雇われている。もし彼がそこに留まれば、ムオイ・トットとトゥ・トイが一緒にどこへでも出かける姿を見ることになるだろう。あるいは、ムオイ・トットが耕作に出かける日には、トゥ・トイが田んぼに稲を運び、一緒にご飯を食べる姿を見ることになるだろう。焼いたボラと生姜の魚醤をかけたご飯だ。
シャツを持っている人が誰もいなかったので、彼はためらい、立ち去りたくなかった。あの歌はバ・キエンに向けられたものだったに違いない。トゥ・トイには約束があったが、立ち去る決心がつかなかった。バ・キエンは気まずくなった。「あら、トゥ・トイはどうしたの?トゥ・トイはとても思いやりがあって、約束もなかったのに、どうして責めるの?トゥ・トイはとても可愛くて優しいのに、どうしてムオイ・トットは立ち去ることができたの?ムオイ・トットは放浪鳥のように水辺を追って雇われ仕事をしていたし、故郷は田舎だと聞いていたのに。」
* * *
「心配しすぎて病気になるなんて!」トゥ夫人は彼を責めた。責めたけれど、自分が何を言っても彼を安心させることはできないと分かっていた。
「愛してくれて嬉しいわ。何十年も一緒に暮らしているのに、まだ私を信用してくれないの?」と彼女は続けた。
彼は黙っていた。
「もしあなたが私より先に亡くなったら、私は自分の面倒を見る方法を知っています。でも今は老いて衰弱しています。誰が私の面倒を見てくれるでしょうか?」
彼女の言うことが的を射ていたので、彼は恥ずかしそうに微笑んだ。
* * *
トゥ・トイは部屋にこもり、雨のように泣きじゃくった。外はまるで市場が暴動を起こしたかのようだった。人々はまさかこんなことが起こるとは思ってもみなかった。この平和な村で、トゥ・トイの結婚式で起きたような恐ろしい出来事はかつてなかった。
両家族が座ってビンロウジュとビンロウジュの実を交換し、ワインを飲みながら、ムオイ・トットが結婚式の後、妻とどのように暮らすかについて話し合っていると、突然、赤ん坊を抱いた女性が泣きながらやって来た。
彼女は自分がムオイ・トットの正式な妻だと断言した。息子がムオイ・トットと瓜二つの顔をしているのに、人々がまだ自分の言葉を信じているのだから、断言する必要などなかった。皆が落ち着いた後、ムオイ・トットと両親を探し出し、事情を突き止めようとしたが、二人はもうそこにいなかった。何もないのなら、なぜ逃げなければならなかったのか?真相が明らかになった。ムオイ・トットには故郷に既に妻がいた。新郎の両親も偽者だった。ムオイ・トットは知人に頼んで身代わりを務めさせていたのだ。
* * *
結婚式が失敗に終わった1ヶ月後、トゥ・トイは家から一歩も出ませんでした。誰も彼女を説得できませんでした。トゥ・トイは泣きながら、自分の運命を責めました。デートの前日、彼女は周りの人たちに結婚を急ぐなと言いましたが、家族は焦り、よく調べず、厄介な事態になってしまいました。
* * *
その月の最後の夜、土砂降りの雨が降っていた。バ・キエンは小屋の中で寝返りを打ち、眠れずにいた。トゥ・トイはひどく哀れだった。思いやりを示そうとはしていたものの、世間の思惑に抗えなかった。こんなに優しく高潔な人こそ、愛され、尊敬されるべき人だった。バ・キエンは友人から、トゥ・トイは悲しそうで劣等感に苛まれ、誰にも会う勇気がないと聞いていたが、客観的に見れば何も悪いことはしていない、と聞かされた。
それはまるで、運命が彼女に突きつけた挫折、つまずきのようだった。バ・キエンは、トゥ・トイを本当に愛しているのか、それとも一時的な軽率さだけなのか、改めて考え直した。トゥ・トイは今や失恋した恋人となった。そんな彼女を妻に、そして後に子供たちの母親として受け入れるだろうか?
* * *
バ・キエンは家の裏手の水路から梅籠を摘み、トゥ・トイの家へ運んだ。玄関を入ると、それまで考えていた思慮深い言葉はたちまち消え去った。彼はトゥ・トイに梅籠を持っていくと言い、家族が温かく夕食に招いてくれるのを見て、彼も一緒に食事をした。
「お二人にお願いです。トゥ・トイと結婚させてください。もしよろしければ、両親に伝えます」バ・キエンの声は震えていた。
家族全員が混乱した。トゥ・キエンの突然の一言に、家族は皆どう反応すればいいのか分からなかった。正直に言うと、トゥ・トイの父であるナムおじさんは、バ・キエンの家族が反対するのではないかと恐れていた。そんな破滅的な運命の女を嫁として簡単に受け入れるはずがない。
* * *
バ・キエンは前庭に座り、この梅の木は50年も生きていると呟いた。祖父母がここに来てから、栄枯盛衰を見てきたのだ。当初は、トゥ・トイに過去を忘れさせるために、数ヶ月だけここを離れるつもりだった。しかし、この新しい土地の方がもしかしたら適しているかもしれないと気づいた。誰もこの昔話を知っていたわけではないのだ。
二人が知っていたのは、トゥ・トイが妻だということだけだった。愛する彼女を最後まで守り抜くと誓った。人生で幾多の過酷な試練を乗り越えてきた。愛し合っていた頃は、もう離れられないと思っていた。しかし、別れた途端、すべてが元に戻った。
彼はトゥ・トイをもう悲しませないようにしていた。自分のような人間が誰かの心をときめかせることは滅多にないことを知っていた。彼はいつも、周りの女性たちにはわざと皮肉っぽく、辛辣な口調で話しかけていた。彼女たちが自分のことを思い出すのを、彼は気に留めていなかった。
彼としては、安心した。
* * *
先日の約束通り、杜夫人が先に出発した。杜氏は何もできず、ぐったりと座り込んでいた。そして、かつて彼女に言った願いとは違うのだと自分に言い聞かせた。… 彼女に民族衣装を着せながら、彼は幼い頃から白髪になるまで愛し続けた女性を見つめた。
ニラのように細い髪の毛を握りしめ、彼は涙をこらえた。彼女が美しくても醜くても、老いても若くても、彼女への愛は揺るぎなかった。日々大切にされ、くすぶるその愛は、祖父母が長年かけて煮出した麺のスープのように濃厚だった。
* * *
麺屋は閉まっていた。再開日を示す白いチョークの線が引かれた看板もなかった。彼女はもういなくなり、彼はもう何も売ることができなかった。家の前の梅の木は次々と実を落としていた。彼女がいなくなったので、彼は梅を摘む気にもなれなかった。ある日、彼は市場へ供え物の食べ物を買いに行った。
ぼんやりとまたボラを買ってきて、彼女の祭壇に供えようとした時、二人が付き合ってからボラを使った料理を一度も作らなかったことを思い出した。もしかしたら、ボラというと昔の民謡を思い出すから、彼が悲しむのではないかと心配していたのかもしれない。誰もいないので、彼は涙をこぼした。閉店した蕎麦屋を眺めた。庭には梅が白く咲いていた。
TQT
ソース









































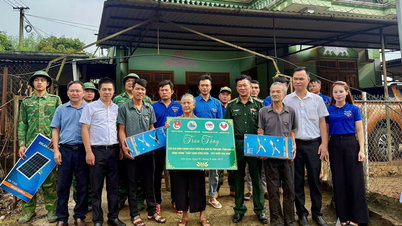
























































コメント (0)