現実には、大学は分散しており、規模も小さい。
教育訓練省は、重点的かつ的を絞った投資とより効率的な運営を目指し、大学システムの再編政策を実施しています。現状において、この政策をどのように評価されますか?
高等教育は長年にわたり、多くの国の開発戦略の中核を担ってきました。世界中の高等教育の運営と改革には、三つの大きな潮流が強い影響を与えています。それは、大学の学際性、分野横断性、機能の多様化、合併や提携によるシステムの中央集権化と再編、そして自治権の強化です。
フランス、ドイツ、オランダなど多くの国では、小規模大学や散在する大学を統合して、国際的に競争できる学際的な大学を形成する政策を実施しています。

アジアでは、韓国、中国、シンガポールがいずれも大規模な改革を実施しました。例えば、シンガポールは、より国際志向の大学を少数に絞り、より合理化したモデルを採用し、シンガポール国立大学(NUS)やシンガポール国立大学(NTU)といった大学を再編と合併によって設立しました。
私たちはこうした流れから逃れることはできないと考えています。現在、ベトナムには600以上の大学がありますが、そのほとんどは規模が小さく、活動範囲も狭く、教育や研究の質が社会経済発展の要件を満たしていません。
ベトナムの多くの大学はカレッジから昇格して設立されましたが、近代的な大学運営の基盤が欠如しています。同じ地域や同じ分野の大学では、似たような専攻科目が提供されることが多く、不健全な競争と資源の浪費につながっています。
ベトナム国家大学、ハノイ工科大学、ハノイ医科大学などのいくつかの主要大学を除いて、ほとんどのベトナムの大学は国際的にはもちろんのこと、地域でも評判がありません。
その結果、ベトナムの大学制度は真に優れた機関を生み出すのに苦労しており、一方ですべての社会資源は小さく非効率的な部分に細分化されている。
画期的な変化がなければ、ベトナムの高等教育は、質の低下、公的資源の浪費、国際競争力の機会の喪失、地域ランキングでの苦戦など、深刻な結果に直面することになるだろう。

ベトナムは、科学技術とイノベーションを基盤とした知識基盤型経済へと成長モデルを転換する必要に直面しています。そのため、2045年までに質の高い人材を育成できる強力な大学システムを構築するという目標を達成するには、小規模大学の統合が必須条件となります。
最初から正しくやろうとすべきではありません。
近年、大学の再編が大きな注目を集めています。統合プロセスが機械的で官僚的な「官僚化」となり、混乱を招くことを防ぐためには、どのようなアプローチが必要だとお考えですか。
合併が効果的であるためには、公共の利益、大学の自治の尊重、透明性、基準の原則を確保する必要がある。
この合併は、単に体裁を整えるために研修機関の数を減らすということではなく、リソースを最適化し、研修と研究の質を向上させ、学習者と社会のニーズにより良く応えることを目指しています。
グエン・キム・ソン教育訓練大臣は、今回の再編の目的は教育機関の強化であり、重点分野への投資を集中させ、より効果的なものにすることだと明言した。公立・私立を問わず、入学者数に乏しく質の基準を満たしていない小規模で分散した学校が、まず見直しと再編の対象となる。
合併プロセスは透明性が保たれ、理由、基準、ロードマップが明確に説明され、教職員と学生に混乱を引き起こす可能性のある管理上の強制が回避される必要があります。
さらに、合併は「一度きり」に行うべきではなく、ショックやリソースの浪費を避けるためにテスト、評価、調整を行う必要があります。
すべての大学が合併できるわけではありません。持続可能な学際的な大学を形成するためには、合併は厳格かつ科学的な基準に基づいて行われなければなりません。
例えば、地理的な位置を考慮し、同じ地域(市、省)にある学校の統合を優先的に行うべきです。これにより、共通のインフラを活用し、管理コストを削減することができます。これにより、学生と教職員の学習と教育に支障をきたすような、遠く離れた学校の統合を避けることができます。
研修の面では、補完的な研修プログラムを持つ大学が合併すると、多分野にわたる大学が形成され、あまりにも多くの重複する専門分野を持つ大学間の機械的な合併が避けられ、簡単に衝突や人員過剰につながりかねません。
同様の使命を持ちながらも強みが異なる大学は、統合されるべきです。例えば、工学に強い大学と、経済学・社会科学に強い大学を統合するなどです。これにより、学際的な研究能力を備えた大学が生まれ、国内外の研究プログラムへの参加が容易になります。
規模の面では、生徒数が 3,000 人未満の学校は、リソースを活用するために合併を検討する必要があります。
ハノイ、ホーチミン市、フエ、ダナンといったベトナムの経済、政治、社会の中心地には、世界クラスの研究大学を設立することが優先されるべきである。各経済圏には、地域の人材ニーズに応えつつ、徐々に国際社会に統合していくために、十分な規模を持ち、応用志向の学際的な大学が少なくとも1校は設置されるべきである。
さらに、各州には、州の直接的な労働力需要に応えるとともに、地域社会の一般的な教育レベルの向上にも貢献する、中規模の「コミュニティ大学」タイプの多分野にわたる大学が少なくとも 1 つ必要です。
新しいガバナンスメカニズムをすぐに導入する必要があります。
この大学の合併は教育と研修活動にどのような影響を与える可能性があるでしょうか。また、大学評議会が機能しなくなった場合のガバナンス モデルに向けて、教育部門はどのように準備を進めているのでしょうか。
大学評議会の廃止に伴い、合併後に新たに設立される大学には、新たなガバナンス体制が早急に必要となる。この体制においては、大学の長は政治的立場だけでなく、大学運営に関する優れた能力と学術的知識を備えている必要がある。
大学の統合は、資源利用の効率化など、プラスの効果をもたらします。大学は図書館、実験室、寮などの共通施設を共有できるようになります。特に人員が過剰または不足している分野において、教員の配置がより合理的になります。
これにより、国際ランキングに参加し、地域レベルで競争力を持つ、大規模で学際的な大学が誕生します。大規模で名声のある学際的な大学は、国内外の学生を惹きつけます。一方、政府は研究予算を、小規模でばらばらなプロジェクトに分散させるのではなく、より集中的に配分できるようになります。
外国のパートナーもまた、多数の小規模で断片化された学校よりも、大規模な機関との連携を優先しています。
しかし、ガバナンス体制の改革を伴わずに合併を進めれば、中間層が多数存在する肥大化した官僚機構に陥り、運営効率が低下するだけです。これはベトナムのいくつかの「国立大学」と「地方大学」で既に発生しており、管理体制が煩雑になり、重複が生じ、非効率的になり、各機関の強みを結集して活用できなくなっています。
したがって、教育訓練部は現代的なガバナンスメカニズムを設計し、教員、学生、卒業生の権利を保障する理由、メリット、そしてコミットメントを明確に説明する必要がある。同時に、優秀な教員の確保、公平な配置、そして合併後の「不利益」感の回避など、合理的な人事政策を策定する必要がある。
世界各国が学校の再編や統合を行ってきた方法から、ベトナムは教訓を学ぶことができる。それは、行政命令に基づいて行うべきではなく、国家の科学技術開発戦略と連携して行う必要があるということだ。
私の意見では、何よりもまず、合併プロセス全体を規制するための基本原則の枠組みを確立する必要があります。これには、オープン性と透明性を確保するための法的枠組みとメカニズム、ガバナンスモデルの定義、人材育成のための政策とインセンティブの確立、教職員の権利の保護、そして世界中のモデルからの学習が含まれます。
大学には、変化を受け入れ、地域よりも国家と学術の利益を優先する責任があります。ベトナムの大学制度の未来は、私たちがどちらの道を選ぶかにかかっています。容易ではあるものの短期的な道、つまり命令による合併によって書類上だけの「スーパー大学」を作る道。それとも、より困難ではあるものの持続可能な道、つまり透明性、自律性、そして社会的責任の原則に基づく合併か。
ありがとうございます!

文部大臣は再編が必要となる学校の概要を説明した。

大学大再編を受け、2026年には大学への入り口はさらに狭まるのか?

基準を満たさない高等教育機関は合併または解散される。

140の公立大学が大規模な再編と合併に直面している。
出典: https://tienphong.vn/sap-xep-cac-truong-dai-hoc-lam-the-nao-moi-hieu-qua-post1790873.tpo













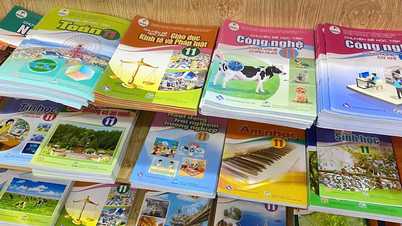












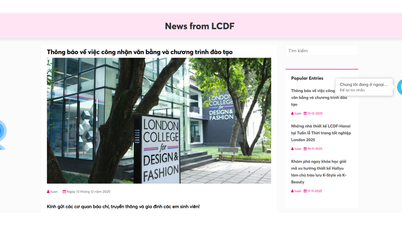



























































































コメント (0)