ファン・チャウ・チンは生まれながらの雄弁家でした。彼の「舌」は「剣や銃」よりも強力な武器となり、彼はこの優位性を国家の独立と進歩のための闘争に活かしました。

自然な雄弁さ
ファン・チャウ・チンは、その雄弁さによって、フエのチャン検閲官、 クアンナム省のヴオン・ズイ・チン総督、トンキン州知事といった「重要人物」が権力を行使して彼を論破しようとした際に、彼らを「黙らせた」こともあった。ファン・チャウ・チンは、日常生活のあらゆる場面でその雄弁さを発揮し、大衆を動員して独立、自由、そして国家の進歩のために闘争を挑んだ。
フイン・トゥック・カンは著書『ファン・タイホー史』(アン・ミン出版社、 フエ、1959年)の中で、ファン・チャウ・チンが家業の経営から世界の平和実現に至るまで、持ち前の雄弁さを発揮したことを示す数々の歴史的逸話を綴っています。以下の3つの短編がその好例です。
―「この家には妾がいて、義妹とよく口論になり、意見が合わない。ところが、ある紳士の言葉を聞くと、何もなかったかのようにすぐに同意した。」
―「人の悩みを解決する習慣は、戦国時代の学者の習慣に似ている。兄弟が解決できない問題を抱えているとき、師匠が来て一言言えば、すぐに解決する。何度も何百何千と議論しても解決しないので、師匠を呼ぶ。新しい場所に着くと、道理も人間関係もはっきりしているので、女性も子供も皆理解し、喜んで聞く。」
―「紳士は『廖寨』『涛湖』『海達』『大度』『雁全天蘇』といった古い小説から新しい小説まで、様々な小説を読むのが好きで、その多くを暗記し、巧みに語り聞かせる。同じ物語を聞かせると、人々は眠くなり、聞く気も失せてしまう。紳士が語る物語には始まりがあり、終わりがあり、重層的で、興味深いので、誰もがまるで良い芝居を見るように聞きたがる。そのため、学者から料理人、人力車の運転手まで、誰もが彼を楽しい語り手とみなしている。」(40ページ)
ファン・チャウ・チンは日常生活だけではなく、大衆を動員する際にも常に雄弁さを駆使して「説得」を行っていた。例えば、1905年に南征から戻る際にニントゥアン省知事、ビンディン省フーカット県の郡長、クアンガイ省の引退知事を「説得」して自身の政策を支持させたり、フオックキエウのフランス人司祭を「挑発」してクアンナム省領事に紹介させたりした(フイン・トゥック・カンが著書『ファン・タイ・ホー・ティエン・シン・ダット・スー』で語っており、グエン・ヴァン・スアンが『フォン・トラオ・ズイ・タン』で語っている)。
ファン・チャウ・チンの雄弁さが最も顕著に表れているのは、彼の政治的著作である『Dau Phap Chinh Quyen Thu』『Thu That Dieu』『Trung Ky Dan Bien Thi Mat Ky』『Tan Viet Nam』などです。これらの著作では、彼は時代を超えたビジョンを持った新しい独自のアイデアを、鋭く明快で簡潔な、不思議なほどわかりやすい文体で提示しています。
彼の雄弁さは、おそらく、生涯の終わりにサイゴンで行った二つの演説、「君主制と民主主義」、「東西の倫理と道徳」において最も明確に示されたと言えるでしょう。この二つの演説を通して、彼の雄弁さは、文章と口頭の両方で高く評価されました。これらは「燃えるような心」と「緊密で論理的な議論、具体的かつ確かな証拠、力強く雄弁な口調、そして明晰な思考と鋭い思考」をもって書かれた二つのエッセイでした。
グエン・スアン・ザン博士は、この二つの講義について次のように述べている。「彼は非常に教育的で、深い理解に基づいた講義をしました。(中略)ファン・チャウ・チン氏は、おそらくベトナムで初めて演説術を駆使した人物でしょう。彼の演説は非常に雄弁で、現代的で、非常に説得力がありました。この点で、ファン・チャウ・チン氏はベトナムの福沢諭吉でした。彼は啓蒙家であり、思想革命家であり、近代ベトナムの教師でした。」(『ファン・チャウ・チンとその政治著作集』、Tre Publishing House、2022年)
弁論家の舌
ファン・チャウ・チンの闘争方法は非暴力であり、ベトナム国民とフランス当局双方に対する「動員」「教育」「説得」が彼の最も重要な手段であった。「ファン・チャウ・チンは、単なる軍事的解決や一時的な外部勢力への依存ではなく、国家の近代化と国力の確立への道筋を深く見据えた改革者であった」(グエン・スアン・ザン)。彼は常に自らの「雄弁」を駆使し、それを「舌」と呼んだ。少なくとも二度、彼は自らの「舌」について語っている。
一度目は1906年。この年、ファン・チャウ・チンは日本の改革運動を「目撃」するため、海を渡って日本へ渡りました。ファン・ボイ・チャウに別れを告げる際、彼はこう言いました。「日本人の知性を見て、それを我々の知性と比較するのは、ひな鳥と老鷹を比べるようなものだ。今、君はここにいる。文学活動に専念し、同胞が聾唖にならないよう、彼らを啓蒙すべきだ。祖国の発展と指導は私が引き継ぐ。私の舌が残っている限り、フランス人は私をどうすることもできない。」
二度目は1908年です。日本から帰国後、ファン・チャウ・チンはフランス政府宛てにインドシナ総督宛ての手紙を書きました。この手紙は官僚たちから彼を憎むようになりました。1908年、減税反対運動の後、多くの学者が逮捕されました。ファン・チャウ・チンはハノイで最初に逮捕され、フエに連行されてホータンに投獄されました。裁判では、裁判所の判決に異議を唱え、激しく抵抗しました。
獄中では、彼は自分が「後で斬首」(後で斬首されるために残す)の刑に処せられ、コンダオに流刑されることを知らなかった。数日後、大尉と二人の兵士が牢に入り、足かせと手錠を調べ、彼を牢獄の扉まで連行した。彼は自分が斬首刑に処せられるために連れて行かれるのだと確信した。慣例により、重罪を犯した囚人は通常、北門からアンホア刑場へと連行される。この時、彼は自分が南門(トゥオントゥ)から連行されるのを見た。彼が尋ねると、大尉はコンロンへ流刑に処せられると答えた。彼は「Xuat do mon(後で斬首される)」という詩を詠んだ。
鉄の門が一般公開されます。
英雄的で悲劇的な歌はそのまま残ります。
国は混乱し、国民は苦境に陥っている。
男たちは崑崙を罰しない。
(重い足かせ、城門の外
悲しそうに歌っていますが、舌はまだ残っています。
国は水没し、国民は衰弱している。
崑崙で男が恐れるものは何ですか?
言葉がある限り、発言の余地は残り、非暴力闘争のチャンスも残ります!
1926年にファン・チャウ・チンが亡くなったとき、ファン・ボイ・チャウは弔辞の中で「舌」のイメージを使ってファン・チャウ・チンの雄弁さを称賛した。
「… 舌と剣と銃の三インチ、暴君は恐怖しながら風を見つめます。
太鼓や銅鑼のように鳴る羽根、民主主義の扉はランプをさらに明るく照らします...
以前も良かったし、その後もさらに良くなりました。共和国の看板は、需要に応えるよう最善を尽くしてください。
死者は神聖だが、生者はさらに神聖でなければならない。独立への梯子は、死者を掴むべく、伸びようと決意している。
[広告2]
ソース





















































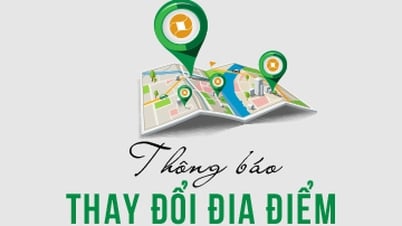
















































コメント (0)