南東部の黄金の三角地帯
政治局の決議を具体化するためにホーチミン市を主要なサービスセンターに変えるプロジェクトにおいて、市は現状を評価し、ビジョンを決定し、一連のハイエンドのサービス基準を構築し、主要な一連のソリューションを提案するという主要目標を特定しました。

これに基づき、市は9つの主要サービス分野を選定しました。それらは、貿易、金融、物流、情報技術・通信、科学技術、不動産、 教育、医療、宿泊・飲食です。これらの分野は現在、サービス構造の90%以上を占めており、2010年から2024年にかけて平均8.1%の成長率を維持すると予想されています。
ホーチミン市と比較すると、ビンズオン省とバリア・ブンタウ省のサービス比率は低い(それぞれ 87% と 78%)ものの、物流、運輸・倉庫、港湾、国際輸送、観光の分野で優れており、ホーチミン市と多層的に共鳴し合っています。
そのおかげで、付加価値サービス構造が形成され、卸売・小売業が216兆8,470億ドン(サービス部門のGRDPの約25%)でトップとなり、運輸・倉庫業が149兆5,920億ドン(約17%)に達し、ホーチミン市が国内有数のサービスセンターの地位に躍り出る「滑走路」が築かれた。
ホーチミン市物流協会の執行委員兼政策法務部長のルオン・クアン・ティ氏は、3つの省の合併によって物流と経済の完全な「黄金の三角地帯」が誕生したと語った。
具体的には、ビンズオン省は広範囲にわたる工業団地(IP)ネットワークを保有しており、2030年までにハイテク、機械、情報技術に重点を置いた10の新規IPを開発する計画です。河川港と道路をカイメップ・チーバイ港湾群およびロンタン空港と連携させる戦略は、シームレスな輸送回廊の形成に貢献しています。
ホーチミン市は、貿易、サービス、消費、流通、金融、テクノロジーの中心地として、地域の「頭脳」としての役割を果たしています。一方、バリア・ブンタウ省は、地域基準を満たすカイメップ・チーバイ深水港群を有し、国際ゲートウェイとしての役割を果たしており、輸出入において大きな優位性を生み出しています。
ベカメックスグループの貿易・サービスエコシステム開発担当ディレクターであり、ビンズオン新都市WTCのCEOであるフイン・ディン・タイ・リン氏は、複合一貫物流の役割とホーチミン市・カイメップ・バウバン・カントー高速鉄道(全長324km)の提案により、深水港がつながり、コストが削減され、効率が向上し、サプライチェーンの時間が短縮されるとコメントした。
リン氏によると、3つの経済圏の統合は単なる機械的な追加ではなく、その核心的価値は共通の運用システムにあり、地域の既存の資源を動員し、連携することに役立つという。
ルオン・クアン・ティ氏によると、「黄金の三角地帯」は大きな潜在力を持つにもかかわらず、依然として同期と深い統合が欠けている。「連携の考え方を省間のつながりから地域内の統合へと転換し、経済の拠点間で単一かつシームレスなサプライチェーンを形成する必要があります。これは、『スーパーリージョン』の巨大なスケールを解き放つための前提条件です」とティ氏は強調した。
物流企業の現状も多くの課題を抱えています。ベトナム統計局によると、2022年には国内の物流企業は3万社を超え、そのうち5,000社以上が3PLサービスを提供する見込みです。国内企業は全体の80%以上を占めているものの、市場シェアは約30%にとどまっています。これは市場の細分化を反映しており、ベトナムの物流をより高い付加価値レベルへと引き上げるためには、サービス能力の向上、プロセスの標準化、データ連携といった喫緊の課題が残されています。
インフラ面では、ベトナム全体の貨物量の45%、コンテナ量の60%以上を取り扱う南部地域は、依然として道路交通による大きな圧力にさらされています。バリア・ブンタウ省とホーチミン市を結ぶ「唯一無二」のルートである国道51号線などの主要路線は、しばしば過積載となり、輸送時間の延長、コストの上昇、そして地域の競争優位性の低下を招いています。
これは「ボトルネック」と考えられており、複合輸送(水路、鉄道、道路、航空)を開発し、データに基づいて商品の流れを再編成し、近代的でスムーズかつ持続可能な物流ネットワークに向けて早急に解決する必要があります。
他の国から何を学ぶべきか
高級サービスに向けた物流ロードマップを構築するには、ホーチミン市は成功した国際モデルを参照する必要があります。
シンガポールはスマートポートに多額の投資を行い、自動化、IoT、AI、そして港湾、倉庫、船会社、税関間の共有データプラットフォームを統合しています。これにより、この島国はサプライチェーン全体の可視性を確保し、「ファーストマイル」と「ラストマイル」の両方の効率を最適化し、運用コストを大幅に削減しています。
ロッテルダムは、2050年までに実質ゼロ排出を目指し、物流に対してより持続可能なアプローチを採用しています。その主力プロジェクトであるPorthos CCS(CO₂回収・貯留)は、物流のグリーン化は追加コストではなく、港の世界的な魅力を維持するのに役立つ長期的な競争上の優位性であることを示しています。
一方、上海は統合インフラと制度改革を組み合わせ、自由貿易区(FTZ)モデルを導入することで通関時間を半減させました。また、仕分け、梱包、ラベル貼付といった付加価値サービスの発展を奨励し、海事人材の誘致にインセンティブを提供するとともに、迅速な通関手続き、電気トラックの導入、船舶へのLNG利用などを通じて、スマートで環境に配慮したオペレーションを推進しています。

ホーチミン市経済大学のグエン・フエ・ミン講師は、国際モデルと比較した場合、物流の未来は規模ではなく、要素をシームレスで効率的かつ環境に配慮した運用エコシステムに結び付ける能力にあると述べた。
新しいホーチミン市にとって、鍵となるのは物流のデジタル変革です。重点分野は、データの標準化、港湾、倉庫、ICD(国際貨物輸送システム)、税関、船会社間の共有プラットフォーム(データレイク)の構築、アルゴリズムを用いたルート、空コンテナ、積荷の最適化、新世代のOMS/WMS/TMSシステムと国際EDI標準の導入、そして「ワンストップ・ペーパーレス」の手続き経路の構築です。
ミン氏によると、ホーチミン市は、新しい中央港、内陸コンテナデポ(ICD)システム、冷蔵倉庫、都市型物流センターへの官民連携投資を誘致しながら、港と工業団地を結ぶ主要ルートへの公共投資を優先する必要があるという。
ホーチミン市商工会のグエン・ゴック・ホア会長は、ホーチミン市は貨物物流と旅客物流を並行して発展させ、複合輸送網(航空、鉄道、水路、道路)を活用した包括的なサービスエコシステムを構築すべきだと述べた。これはホーチミン市にとって物流を再構築する「絶好の機会」であり、輸出入の玄関口から地域のサービス、データ、接続センターへと、世界のサプライチェーンにおけるベトナムの地位を強化することになる。
ホーチミン市人民委員会のグエン・ヴァン・ドゥオック委員長は、国家管理の観点から、今後、ホーチミン市は港湾、空港、水路、鉄道のネットワークに関連するスマート物流インフラの開発を優先し、環状3号線、環状4号線、カイメップ・チーバイ地域に沿って地域物流センタークラスターを形成すると述べた。
同市はビッグデータと人工知能(AI)に基づくデジタル物流管理システムを導入し、共有データプラットフォームを通じて倉庫、ICD、配送センター、輸送事業者を接続する。
さらに、ホーチミン市は、新たな中央港と国際基準の冷蔵システムと連携したトゥドゥック市、クチ市、ビンチャン市、ニャーベ市の衛星物流センターへの投資を官民連携(PPP)で推進している。
ドゥオック氏は、「物流は都市と地域の経済にとってソフトインフラとなり、新たな成長の原動力となり、ホーチミン市が2025年から2030年にかけてASEANの貿易、金融、サービスの『ハブ』としての役割を果たすことに貢献するだろう」と強調した。
最終記事:国際海事センター建設のための深水港の開発
出典: https://baotintuc.vn/thi-truong-tien-te/tp-ho-chi-minh-moi-phat-trien-logistics-thong-minh-de-nang-tam-trung-tam-dich-vu-bai-1-20251022201122703.htm




![[写真] フエの洪水の中での人間の愛](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/10/29/1761740905727_4125427122470875256-2-jpg.webp)


























































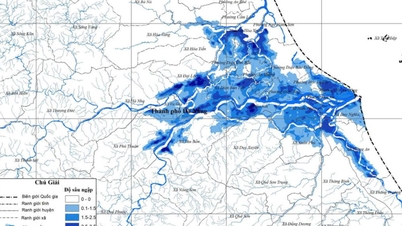

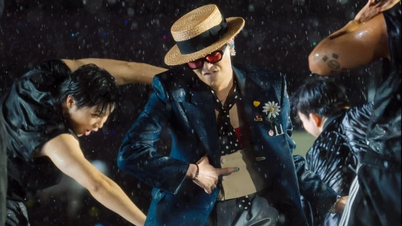






























コメント (0)